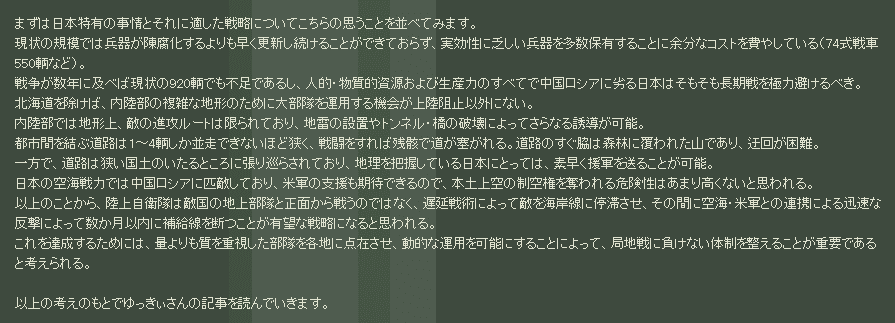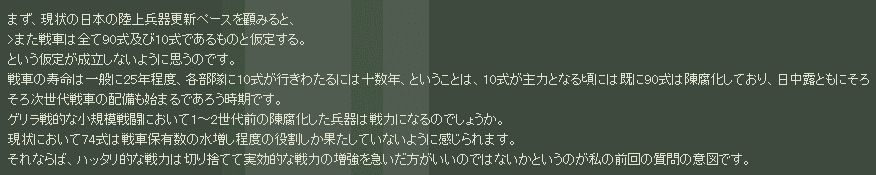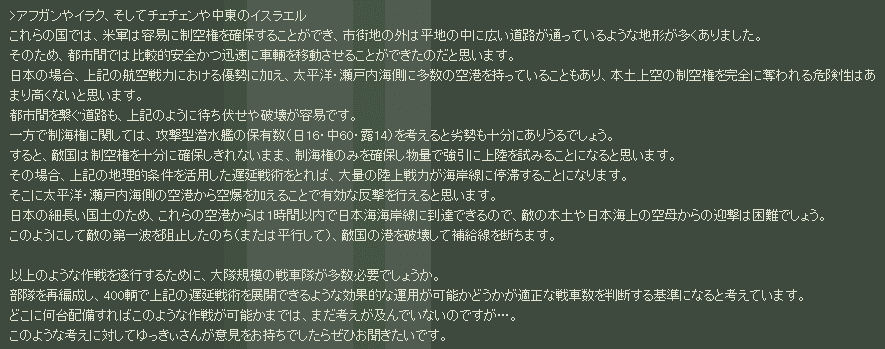元旦早々!
2日連続で、今日も文字だけの長文軍事ネタ更新です。
とても読みづらいものになると思うし、
完全に個人に宛てた更新となるので、
興味ない人は読み飛ばしてください!
昨夜の軍事ネタカテゴリの記事、
陸自に戦車400輌は少ないのか? についた質問コメントへの回答。
質問者さん、あけおめ、再度コメントありがとう。
踏み込んだ議論を期待していたとのことなので、それに応えようと思います。
前提として、質問者さんと俺とは自衛隊のドクトリンへの認識の相違を感じ、
また実際に戦争になってみない以上、何が正しい戦略かというのは証明されないので、
下記の返答は質問者さんの意見を否定するものではなく、
「ゆっきぃ的にはこう考えている」というつもりで読んで頂けると幸いです。
以下の枠線の中の文章が、質問者さんのコメント。
長いので省略してあります。
全文を読みたい方は
陸自に戦車400輌は少ないのか? 記事のコメント欄へ。
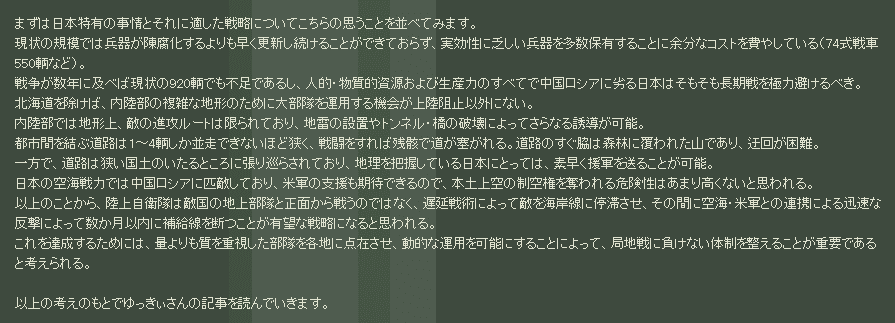
中国・ロシアとの戦いでは長期戦を避けるべきという意見は全面的に同意で、
自衛隊の戦力は縦深に欠け、そもそも長期的に戦えるようには作られていない。
量より質を重視した軍隊であり、この部分に関しては議論を必要としないだろう。
しかし一方で、質問者さんは上陸した敵部隊の補給線を洋上で遮断して、
上陸部隊を孤立させ遅滞作戦を以て消耗を待つという風に見え、
数ヶ月以内に補給線を断つという消極的な戦略は短期決戦とは矛盾している。
もちろん日本の領土は敵から見れば離島であり、
海上戦力や航空戦力による連携で補給線を洋上遮断するというのは非常に有力な戦略であり、
また敵軍にとっても恐れる事態であることに疑いはない。
しかし政治的な問題として、日本は領土が侵犯された場合、
数ヶ月と待たずに即座に反撃し奪還しなければならない世論の圧力に晒されると思う。
またトンネルや道路を破壊して敵上陸部隊の内陸部への進出を限定するという戦略だが、
本土決戦を旨とする軍隊で、このような焦土作戦じみた防衛戦略が前提とされてるだろうか。
もちろん、敵部隊の進出阻止が不可能と判断されればそれも選択肢に入ってくるだろうが、
道路を破壊すれば友軍部隊の反撃ルートも遮断されることになるので、
あくまでも最終手段の一つ程度に留めておくべきだと思う。
本土の防衛においては
"上陸阻止"が基本となるだろうが、
しかし自衛隊の重視する砲火力などの装備体系を見ると、
本土の陸上戦において
「上陸させて叩く」という戦略が適応されていると考えてる。
つまり敵が上陸してきた場合、上陸地点に橋頭堡を築き内陸部へ進出してくる前に、
早期にMLRSなどの砲撃と空自の作戦機で上陸地点を叩き、
地上の機動兵力で打撃を加え上陸地点を制圧するというような、
いわば
「上陸させて叩く」という戦略が有効に機能し得る体制にあると思う。
無論これは、空自の航空阻止作戦及び、陸自の沿岸での重MATや中距離多目的誘導弾などによる迎撃で、
敵上陸部隊を洋上で漸減させ上陸阻止を試みることは前提である。
そしてこの
「上陸させて叩く」という防衛戦略を実行する場合、
もちろん早期段階で反撃し上陸地点を制圧しなければ敵部隊の内陸部進出を招くだろうし、
その早期段階での反撃を実現するには陸自の機動戦力が必要となる。
その機動戦力とはもちろん、戦車である。
歩兵部隊や装甲車では打撃力に欠け、また上陸したばかりの敵兵力はさほど重火器を持ち込んでいないと想定され、
その局面において、戦車の制圧力は陸自の保有する兵器の中で最も確実性があり、敵上陸部隊にとっても大きな脅威であると考えられる。
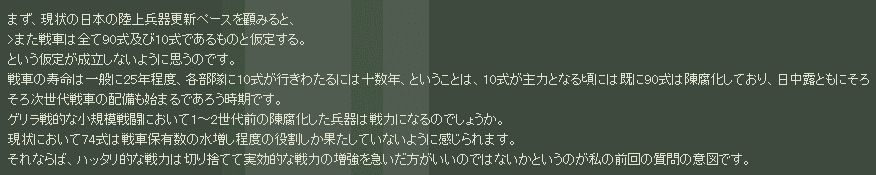
前回記事で
「>また戦車は全て90式及び10式であるものと仮定する。」と記述したのは、
前回記事の返答は日本に必要な戦車数を算出するという趣旨だったので、
算出方法を単純に、かつ現実的な数字を出す為にそう仮定した。
なぜなら74式戦車と90式&10式では部隊の編成法が異なり、
74式戦車の編成法で算出すると車輌数は90式&10式の部隊よりももっと膨れ上がってしまう。
現実的に戦車の配備数は減勢しているので、それを考慮に入れ、
また残った74式戦車の部隊内容も戦車減勢と共に改編されていくだろうという予想もこみこみで、
全ての編成法を90式&10式と仮定したのであり、つまりあの文章は、
「全て90式及び10式の編成法で考えるものとする。」と読み変えてもらって良い。
現状の年間11~15輌ベースの調達数じゃ非効率極まりないのは確かで、
実際に90式戦車は2020年以降から退役が進行する可能性があり、
日本は旧式戦車を主力に本土防衛戦を行わなければならないという危惧は、
現状のままじゃ現実となってしまうだろう。
しかしゲリラ戦的な小規模戦闘において1~2世代前の兵器で戦力になるかという質問に対しては、
俺としては
「戦力になる。」という見解も併せてここで述べておく。
何故なら74式戦車が戦うとすればこの日本本土での上陸阻止及び橋頭堡制圧、もしくはゲリラ戦じみた戦闘であり、
そのシチュエーションにおいては、敵にも十分な主力戦車があるとは考えにくい。
その場合の74式戦車の対戦相手は、敵軍の水陸両用戦車、軽戦車、装甲車、歩兵部隊となる。
そのような敵兵器に対しては74式戦車は機動戦力として、装甲・火力ともに十分に通用する戦力だと思われる。
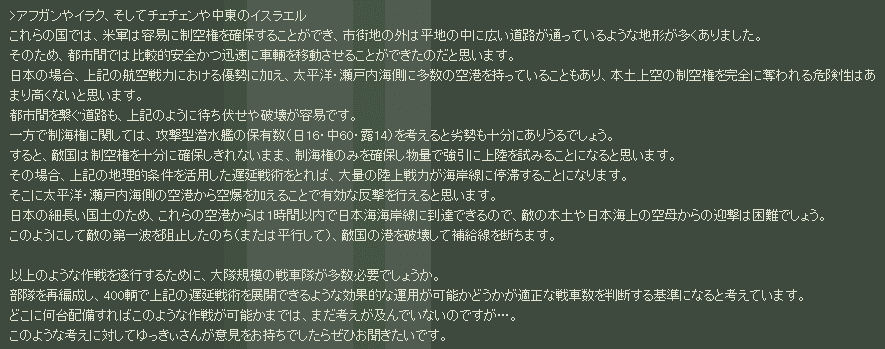
質問者さんと俺との認識で共通しているのは、
「敵上陸地点に砲爆撃を加え橋頭堡構築を阻止する。」
という部分。
意見が相違しているのがその後の対応のこと。
質問者さんの言う、橋頭堡への砲爆撃及び補給線遮断、そして地雷や交通路破壊による遅滞作戦で、
敵部隊の継戦能力を締め上げていくというのは、前述したように完全には俺は賛同しかねる。
俺の意見としては、上陸された場合は、
橋頭堡への砲爆撃、補給線遮断、その後には機動戦力による反撃が有効と考え、
故に十分な戦車兵力は陸自に必要と考えてる。
その為には質問者さんの言うような道路網の破壊は、
友軍の戦車部隊の反撃経路が失われる意味で最終手段だ。
そして質問者さんの言うように、敵が物量だけを頼みに闇雲に上陸してくるような事態になれば、戦車は尚更有効だと思われる。
何故なら、主力戦車を揚陸させるには希少な大型の揚陸艦が必要で、
しかし闇雲に物量だけでの上陸作戦でくるならそこまでの重火器は日本には持ち込めない。
強襲揚陸艦などを動員するには、完全に制空権・制海権が確保されている必要があるものと思われ、
現状の中露の空海戦力で日米相手にそこまでの優勢を確保できるとは考えにくく、
つまり前述したように、敵上陸部隊の主力は水陸両用戦車・軽戦車・装甲車・歩兵部隊となる。
その場合にこちらに十分な戦車戦力が存在するアドバンテージは、計り知れないほど大きいものと思われる。
つまり質問者さんと俺との認識の決定的な違いは、遅滞戦術を重視するか、
早期反撃により橋頭堡制圧を重視するか、であると思われる。
この早期反撃の実現の為に十分な打撃力を有する機動兵力として戦車は必要であり、
また各普通科師団に現状通り、大隊規模の戦車部隊の配備が望ましいと考えてる。
大隊以下の規模にするなら、普通科師団に戦車を何輌まで配備するのか?
それが焦点となると思うが、いずれにせよ、400輌まで削減されれば諸兵科連合を組めなくなる部隊も出てくると思われ、
陸戦を行うにあたって望ましくない戦力状況になることは間違いない。