今日のなんと暖かいこと、明日からはいよいよ師走に突入というのに…。最高気温17度と日頃と大して変らなかったのですが、全く風がなくお日様が燦々と照っていたからかも。
昨日もよく晴れて、洗濯日和だったので、午後からもう一度洗濯しました。それが今一つカラッと乾いていなかったので、今朝もう一度乾しました。それを昼前取り入れて畳む時のナント幸せなこと!私の大好きな時間です。太陽を一杯に吸い込んでフワフワ…、特に冬物はフリースや起毛素材などと、下着もフワッとしたものが多いので、畳む時の手ざわりが優しいし香りもとてもいいのです。
こんな小春日和にはウッドデッキの椅子に坐って畳むんですよ。そうするともう体中が太陽に包まれているみたい!何もかもみい~んなどこかに消えて頭の中は空っぽ…。みなさんこんなことってありません?傍には猫のテンちゃんも日向ぼこ…とてもシアワセな時間です。
午後から着付け教室へ。またまた私の大失態の結果なんです。先日お蕎麦を食べに行く約束を忘れていた話を書きましたが、あの時もう一つ忘れていたんです。前後がびっしり詰っているので、着付は日曜日の11時からという約束だったのをすっかり忘れていました。電話が入っていたのですが、お蕎麦の方へ気がいっていて、全く気がつかなかったんです。(笑)
〝忘れてた、ごめんなさ~い!〟〝いいわよ~、違う日に振り替えしてあげるから。〟と、今日にして貰ったのですが、行ってみると誰もいません。〝私ひとり?〟〝そうよ〟〝エエッ、じゃあ私ひとりのために…本当にゴメンナサ~イ!〟


こんな調子でいつもドジを踏む度みなさんに助けて貰っています。アリガタイコト!これもきっと母が見守ってくれているからなのね。お母さ~ん、ありがとう。母は誰にでもいろいろとしてあげることが大好きでした。だからいつも感謝され、誰からも好かれていました。きっとそのお陰を私が頂いているのでしょうね。ホントに感謝、感謝です!
あたゝかき十一月もすみにけり 中村草田男
人間探求派とか難解派などと言われ、難しい句が多い草田男にもこんなやさしい句があるんですね。私たちが詠んだとしたら、なんと言われるでしょう。〝当り前じゃな~い!十一月ってそんなもんよね~〟とか。
でも、こんなの~んびりした雰囲気が〝十一月〟の本意かも。十二月と比べてみるとよく分かります。何もかもが厳しくなる前のちょっと一息つける期間なのでしょう。
ところで、「十一月尽」という季語はありませんでしたし、もちろん例句もなし。この「……尽」については、以前(2017・6・30)の〝六月尽?〟で書きましたので、それを読んでみて下さい。
写真は、〝野葡萄〟、秋の季語。よく似たのに〝山葡萄〟があり、これは食用・葡萄酒などにしますが、野葡萄は食べられません。でも実の色が紫や青色などになって私の好きな植物。白い実もあるらしいのですが…見たことな~い!これもいつの間にか我家にはびこりだしたんです。しかし、もう冬も仲冬になりますよ、季節感が狂いますね~。


 またボケていますね。どうもスミマセン!
またボケていますね。どうもスミマセン!
























































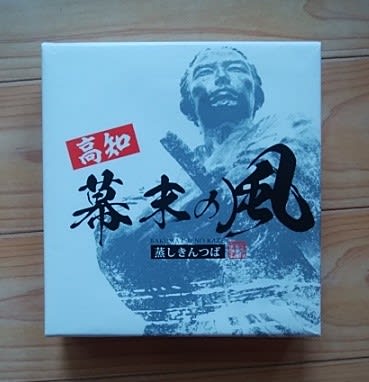


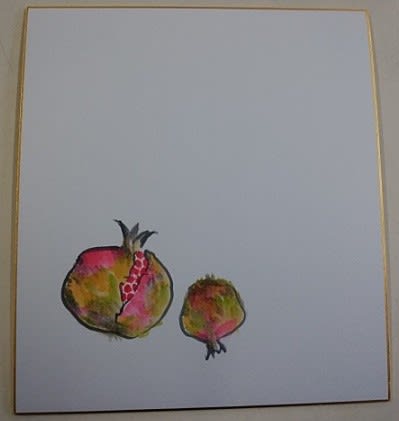








 それで、今朝はまずブログを書いています。
それで、今朝はまずブログを書いています。 では、今から市の俳句大会の選考会へ行って来ます。
では、今から市の俳句大会の選考会へ行って来ます。




















