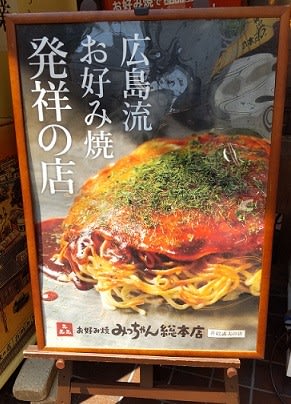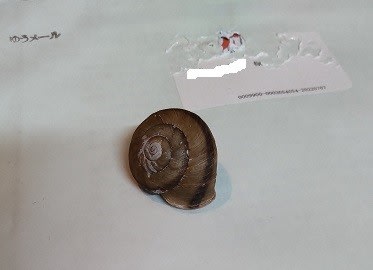今日から天気が崩れて、しばらくは雨の予報が続いているのですが…、今日の最高気温はまだ32度、おまけに最低気温も27度とは!雨は全く降りそうな気配がなく、またも蒸し暑い夜になりそうです。
今朝のラジオ体操もどんよりとして蒸し暑く、まだまだ残暑が厳しい。でも時折吹いてくる風はやっぱりあの猛暑の頃とはどこかが違いますね。今朝もラジオ体操はちょっと淋しい人数でした。
実はここをお世話して下さっている会長のNさん、そのご夫婦がコロナに罹ったんですって。どうもお孫さんから感染したようで、先週の金曜日にはお会いして一緒に帰ったのに…月曜日からお休みで罹患していたと。じゃああの金曜日にはもう感染していたのでは?だとすると私たちもアブナイ!なんて言いながら帰ったのですが、昨日は朝からダルいし、つい熱を測ってしまいました。36、4度…大丈夫のよう…でもちょっと喉が痛む…。罹った人の話では喉がとっても痛いとか。でも熱が出るんだそうですから…やっぱり?
さて、今日は8月最後の日。要するに〝八月尽〟なんですが、以前にも書いたように、私の持っている『角川俳句大歳時記』には季語として載っていません。もちろん〝葉月尽〟も。どちらにしても季節の大きな変わり目ではないからでしょうか。陽暦の8月はまだ初秋の頃、陰暦なら中秋で、その月の最後の日にそれ程の感興が湧かないからなのでしょう。
歳時記を見てたら面白い季語発見!今まで聞き知ってはいましたが、使って詠んだことはありません。それは〝八月大名〟という季語。
歳時記の説明によると〝昔は陰暦の二月と八月は農閑期である。八月は、稲作であれば作業はほとんどなく、実りを待っていればよい。この時期、農家では嫁取りや法事など客を招くことを多く行った。体を休めるだけでなく、ご馳走を食べる機会も多かった〟などというところから言われ出した季語という。
下駄履いて八月大名らしくなる 伊藤白潮
これは「鴫」(2008年10月)に掲載されたもの。もうこの頃は農業が主ではやっていけない時代になっていたでしょうから、本当の意味で〝八月大名〟にはなれないでしょう。そこで下駄でも履いたらそれらしくなったと言うことでしょうが、この〝下駄〟ということから、もしかしたらどこかの湯宿に泊まりご馳走でも食べて湯巡りなんぞしていたのでは?なんて想像していましたら…
ところが、この作者・伊藤白潮氏は「鴫」の主宰で、2008年8月12日、81歳で亡くなられているんですよ。そうすると本当に亡くなられる寸前に詠まれた句ということになるんですね。(雑誌には大体2ヶ月ぐらい前に投句しますから) だったらこれはきっと気持ちの上だけで〝八月大名〟の気分を味わって詠まれたのでしょう。まさに芭蕉が最後に詠んだ〈旅に病んで夢は枯野をかけめぐる〉というような、生涯現役の俳句人生を送られた方なのでは?…と思います。
個人的にはお名前しか知らないのですが、重厚な作品もたくさんある反面、本人も意識しておられたのか、ユーモアや諧謔精神の溢れる作品も多く、私はそちらの方が特に印象に残った作家でした。 合掌
もう一句面白い句が…
ITに闌(た)けて八月大名ぞ 能村研三
これは「沖」(2020年10月)掲載の、とても新しい現代的な句。作者・能村研三氏は、1949年市川市で能村登四郎の三男として生まれる。2001年、登四郎の死後、「沖」主宰を継承し、現在は公益社団法人俳人協会理事長、千葉俳句作家協会会長、朝日新聞千葉版俳壇選者、読売新聞千葉県版俳壇選者などを歴任され、今最も活躍中のお一人です。
この〝八月大名〟も絶滅危惧種のような季語ですが、他にも今の時代に合わずに忘れ去られてゆく季語がたくさんあります。そんな季語の本意は変えず、時代にマッチさせながら詠み残してゆきたいものだと、私は思っています。皆さんもどうぞそんな季語を見つけたら、現代的な感覚で詠んで蘇らせて下さい。是非ご協力をお願いしま~す!


写真は、芙蓉や木槿と同じアオイ科の〝矢の根梵天花〟。南アメリカが原産で、耐寒性があり、道端などに帰化しているとか。高さは1メートルくらいになり、茎は広がります。葉は鏃形で、和名の「やのねぼんてんか」はこのかたちに由来。春から秋にかけて、淡いピンク色に中心部が赤褐色の花を咲かせる常緑小低木で、学名は Pavonia。
ラジオ体操へ行く途中のお仲間さんの家に咲いていて、長い期間次々と花が咲くのでいつもいいねと言いながら、今回やっと調べてその花の名が分りました。ミニ芙蓉ともいわれ、花言葉は「慎重」「繊細美」だそうです。






































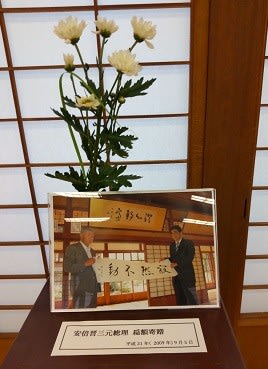












 これもしかしたら正岡子規のように自分のことを〝仏〟と詠んだのかしら?
これもしかしたら正岡子規のように自分のことを〝仏〟と詠んだのかしら?