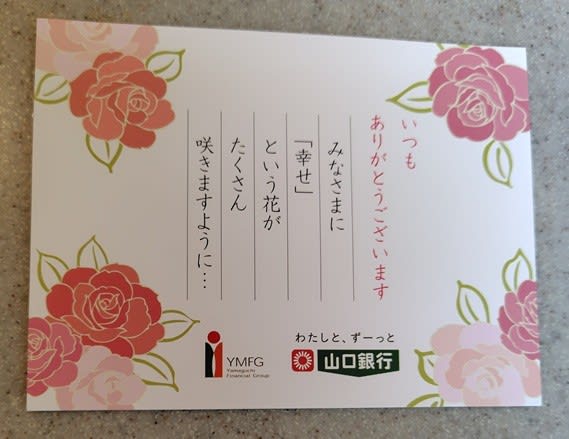今日も夏の高気圧に覆われ雲一つもなく、九州北部から関東方面まで強い日差しが照りつけて危険な暑さが続くようです。最高気温も35度超えは当たり前。せめて夕立でも来て、夜でも涼しくなってくれると有難いのですが。もう幾日も一滴の水に会わない…ああ、雨がほしい!なんともはかない望みです。
京都から帰っても休む暇なく忙しかったからかしら、23日頃から突然頭痛と寒気がして、熱を測ってみると38度5分まで上がっていました。道理で体の節々…特に京都で酷使した膝の痛いこと、痛いこと!
だって16日の宵山は16000歩、17日の山鉾巡行の日は大雨でしたが、それでも12000歩近く歩いているんですよ。おまけに金曜日は教室で3時間立ちっぱなし、土曜日は朝からきらら俳句教室と午後の宇部馬酔木句会へ…息つく暇がなかったんです。
でも、熱とだるさと食欲不振以外、喉や咳などの風邪やコロナの症状がないので、やっぱりこの暑さでの過労からかもと…病院へは行かず3日ほどの解熱剤で治りました。が、今度はあまり食べていないので体力がなく…。やっと今週からラジオ体操にも復帰できました。というわけで、続きが遅くなってしまい、すみませんでした。
では、祇園祭の最大のイベント「山鉾巡行」の巻きですよ。
あいにく当日は朝から天気予報通りの雨。でもまだ宿を出た頃はそれほど酷くはなさそうだったので淡い期待を持ったのですが、徐々に強くなるばかりでした。巡行は9時からスタート。私たちの観覧席は10時30分頃通過する予定でしたので、それまでは地下街で雨宿りして過ごそうと休憩していると…例の〝コンチキチン〟というお囃子の音がここまで聞こえてくるんです。気が急くものの観覧席では傘が差せないというので、合羽を買おうとコンビニへ…でも既に売り切れ。運よく100均にわずかに残っていたのを買って慌てて地上へ出ました。
もう何もかもびしょ濡れになるのは覚悟して、合羽を着て椅子に座ると…あッ、見えました。先頭の「長刀(なぎなた)鉾」が…。さすがに高さがスゴイ!この大雨をものともせずに…やはり〝百聞は一見に如かず〟ですね。
ところで、もう二度とは見ることもないかと思って、特別観覧席(13500円)を買ってもらっていたのですが、その席の名称がなんと「そよかぜ席」。普通ならこの暑さですもの、熱中症にならないようにと配慮された席で、席の後ろには扇風機がずらりと並んでいるのです。なのにこの土砂降りの雨…そよかぜなんかより雨除けのテントが欲しかったですね。大枚をはたいたんだからてっきりテントはあるものと思っていたんですけど…自由席の人達は傘さして見てましたね。クヤシイ!



この長刀鉾は、鉾頭に大長刀をつけているのでこの名で呼ばれています。他の山鉾はくじとりで順番が決まりますが、この鉾だけは古来より「くじとらず」で毎年必ず巡行の先頭に立ちます。生(いき)稚児が乗るのも今ではこの鉾だけです。高さ25m、重さ12トン、囃し方など鉾に乗っている人が40から50人、直径2m前後の車輪を綱で曳く人が、これも40人から50人という。一つの鉾はそれぐらいなんですが、曳山(ひきやま)になるとその半分以下になります。ですが、それでもそれらが合わせて23基も続いてくるのですから、それはそれは壮大ですよね。もちろん昨夜の宵山で見学した「月鉾」も来ました。
それでは、②占出山(うらでやま)③霰(あられ)天神山④山伏山⑤函谷鉾(かんこぼこ)⑥油天神山⑦綾傘鉾(あやがさほこ)⑧蟷螂山(とうろうやま)⑨菊水鉾⑩保昌山(ほうしょうやま)⑪伯牙山(はくがやま)⑫白楽天山⑬月鉾⑭木賊山(とくさやま)⑮四条傘鉾⑯太子山⑰鶏鉾(にわとりほこ)⑱芦刈山⑲郭巨山(かっきょやま)⑳孟宗山㉑放下鉾(ほうかほこ)㉒岩戸山の順です。が、何が何やら分からずに来る順に撮りましたし、山は上の飾り物がどれも似ていて、おまけにビニールが被せてあったりで、本番の良さが出ていなかったのでしょう。惜しいこと。鉾はどれも高さがありますし、人数も多いのでみな見ごたえがありますが、これも晴天だったらもっと凄かったんでしょうけどね。残念です。
























最後は、雨のためか予定より1時間ほど遅れていましたが、13時過ぎに「船鉾」が来ました。



雨の中無事に最期の船鉾を見送って、私たちはやっとお昼を食べに出かけ、ホッと一息ついてのんびりです。それから預けていた荷物を取りに寄り、地下鉄で京都駅まで行って、そこで解散しました。
ちなみに、宵山では月鉾の「厄除け粽」を買いました。昔から祇園祭では粽を厄除けのお守りとして、家や店舗の玄関の軒下に飾るのだそうです。 その由来は、大昔、 素戔嗚尊 すさのおのみこと が旅で一夜の宿を求めた際、貧しいながらも手厚くもてなしてくれた 蘇民将来(そみんしょうらい)へのお礼として、末代まで厄災から護ることを約束し、茅の輪を腰に付けさせたことがはじまりと言われています。この謂れは夏越の祓の「茅の輪」と同じですね。

ああ、本当に疲れました。でも念願が叶って気分は上々と…みれば、この日は雨のため新幹線が軒並み遅れていて、予定より1時間遅い帰宅になり、我が家に付いた途端にバタンキューでした。
雨は新山口駅に着く頃にはやみ…というより宇部ではたいした雨ではなかったとか…クヤシイ!
それでは最後まで下手な写真をたくさん見ていただき、心から感謝です。有難うございました。皆様お疲れさまでした。