今日もまた、俳句教室でした。今回のハイライトは、次の句、
受験子と握手してわが運渡す
原句は〈受験子に渡すお守り我の運〉でした。
季語は「受験子」、「じゅけんし」と読みます。基本季語は「入学試験」で、その傍題に「受験」「受験生」「受験子」などがあります。
「合格」もその一つですが、ここで気を付けないといけないのは「落第」という季語。
合格は、入学試験でのことで、落第は卒業試験や進級試験などで不合格になること、だから同じ春の季語であっても、意味は違ってきます。
さて、原句の作者の気持ちはとてもよく分りますね。お孫さんに合格祈願のお守りを授かってきて、さあ渡そうとしたとき、自分の運気も一緒にあげようと思ったのだと…。
ちょっと欲張りすぎかな。やはりここでは、「お守り」か「我の運」かのどちらかにした方がいいでしょうね。
「受験」に「お守り」はもう定番ですから面白くないです。ここは「我の運」を生かしましょう。
作者曰く、「渡す時がんばってねと、私の運を注入してあげるためギュウッとハグしたんですよ。」と。(笑)
中学3年生?高校かも…もし男の子だったら当惑するでしょうね。でも女の子でした。
「確かにあなたは誰もが認める強運の持ち主だから…でも、もし悪運だったらどうするの?」
それで「結果は?」と聞くと、すかさず「見事に落ちました!」と。
一同エエッ‼と開いた口がふさがらない…
すると、「大丈夫ですよ」、「これが却って福となるかもよ」と、ちゃんと励ましておきましたから…。(爆笑)
あ~なんと愉しいこと!…これが句会の面白さです。
でもやっぱりハグは俳句的でないかと思い、握手ぐらいにしておきましたが。
ところで、先日の稀勢の里の優勝、日本中の人が感動したでしょうね…勿論私もですが。
日馬富士戦で負傷したあの様子を観て、ああこれで折角の連続優勝のチャンスを逃したなあ…惜しいなあと。
でもまだ次もあるのだから欠場もやむをえない、早く怪我を治して…と思いきや、次の鶴竜戦に出て…、痛々しかったですね。もちろんあっけなく負けましたが、でも最後の照ノ富士戦で勝ち、優勝決定戦へ…すべてはあの稀勢の里の涙が語ってくれました。 やっぱり相撲は男の競技ですね。
やっぱり相撲は男の競技ですね。
早速月曜日にあった句会には、次の句が出ていました。
右腕がもぎ取る春の賜杯かな
もちろん私は特選に採りましたよ。だって、これは今でなくては詠めない句。
恐らく稀勢の里のことを知らない人や時間が過ぎて読む人には、「なぜ右腕なの?」という疑問と、春でなくてもいいのでは…などと問題にされる句でしょう。
でも、私はこういう今でしか味わえない実感を詠んだ句も残していきたいと思っています。
ちなみにこの句、蓋を開けてみれば、わが旦那様の作でした。おそまつ!












 こちらでは昨夜から〝春雷〟です。
こちらでは昨夜から〝春雷〟です。
 では登山講習会に参加していた栃木県の高校生が雪崩に巻き込まれ、6人の心肺停止と4人の行方不明を報じていました。他にも多くの負傷者がいると…(夜はもっと増えたみたい
では登山講習会に参加していた栃木県の高校生が雪崩に巻き込まれ、6人の心肺停止と4人の行方不明を報じていました。他にも多くの負傷者がいると…(夜はもっと増えたみたい )
)


 をしたのを詠んだんです」と言う。
をしたのを詠んだんです」と言う。
 そりゃあ美味しかったですよ。
そりゃあ美味しかったですよ。



 その通りでした。ご指摘心から感謝致します。有り難うございました。
その通りでした。ご指摘心から感謝致します。有り難うございました。 )
) ですよね
ですよね




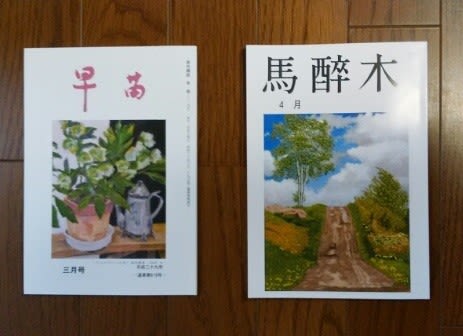


 その句は、
その句は、
 )
)









 いつの間にかわが家にはこんなに花があったのかと……ゆっくり見てあげる暇がなくてゴメンナサイね。
いつの間にかわが家にはこんなに花があったのかと……ゆっくり見てあげる暇がなくてゴメンナサイね。







 また、文字が多いから読みにくいなどの感想で、
また、文字が多いから読みにくいなどの感想で、  ???と考えてテンプレートを変えてみました。
???と考えてテンプレートを変えてみました。 〟かというのをちょっと見ていたら、最後には猫派が勝ちましたね。もちろん私も猫派です。前にも書きましたが、今は雄猫〝テン〟一匹ですが、一年半前はもう一匹、雌猫〝チャーミー〟がいました。老衰で死にましたが、最後の最後までよく食べて…それが救いでした。
〟かというのをちょっと見ていたら、最後には猫派が勝ちましたね。もちろん私も猫派です。前にも書きましたが、今は雄猫〝テン〟一匹ですが、一年半前はもう一匹、雌猫〝チャーミー〟がいました。老衰で死にましたが、最後の最後までよく食べて…それが救いでした。 驚いていましたが…懐かしい話です。
驚いていましたが…懐かしい話です。






 と。それで、少し紹介しますね。
と。それで、少し紹介しますね。 でももう少々のことでは驚かなくなっていますので、みなさまどうぞ心配しないで下さいね。私は安心するための検査だと思っていますから。まだまだ頑張りますよ!
でももう少々のことでは驚かなくなっていますので、みなさまどうぞ心配しないで下さいね。私は安心するための検査だと思っていますから。まだまだ頑張りますよ!













