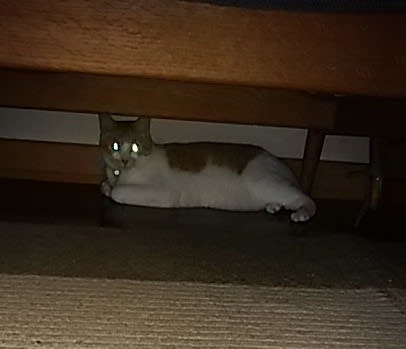とうとう明日で一月が終りますね。するとすぐに節分、立春と続きます。きっと二月もアッという間でしょう。
しろじろと一月をはる風の畦 綾部仁喜
この句の解釈の鍵は、〈しろじろと〉をどうとるかということでしょう。この語は一般的に〝夜が次第に明けてゆくさま〟という意味に用いますが、ここは夜ではなく〝一月〟が終る様子なんですから違うでしょう。とすると、色の白さを言ってるのではなく、〝はっきりしているさま〟とか、または、〝しらじらしいさま〟という意味もありますので、そういうふうにとるのも面白いかもしれません。私としては感覚的な意味にここは受止めたいですね。
ところで、今日は天気もよく最高気温13度と暖かかったのですが、明日からは雨になり最高気温もグッと下がって6度とか…まるで冬の最後のあがきのように寒波が襲ってきます。昨年の今日のブログを見ると、〝梅の蕾から白いものがのぞき始めてもう随分になります。一輪でも咲いたら写真をと思って見るのですが、最強の寒波が襲って以来未だにそのままで前には進みません。まるで凍結しているよう…。〟と書いています。やはり去年はまだ梅の花が一輪も咲いていなかったんですね。しかし、今日見ると我家の奥の方にある梅の木が気付かないうちにもう満開になっていたんですよ。まだ春ではないというのに…。
この梅の花が満開になると、私はすぐに次の句が思い浮かびます。最初はどういう意味なのかさっぱり分からずに悩んだものでした。そこで、いろいろ下手な解説を私が書くより、『増殖する俳句歳時記』に清水哲男氏が書かれたものを転載しましょう。
勇気こそ地の塩なれや梅真白 中村草田男
季語は「梅」で春。迂闊にも、この句が学徒出陣する教え子たちへの餞(はなむけ)として詠まれたことを知らなかった。つい最近、俳人協会の機関紙「俳句文学館」(2006年2月)に載っていた奈良比佐子の文章で知った。「地の塩」はマタイ伝山上の説教のなかで、イエスが弟子たちに、「あなたがたは地の塩である」と言っていることに由来している。「だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである」。このときに作者は「(きみたちの)勇気」こそが「地の塩」を塩たらしめると言ったわけだが、しかしこの「勇気」の中身については何も言及されていない。当時の時局を考えるならば、中身は「国のために死ぬ勇気」とも、あるいは逆に「犬死にを避ける勇気」とも、まだ他にもいろいろと解釈は可能だ。「とにかく死なずに戻って来い」などとはとても公言できない時代風潮のなかでは、新約聖書の匂いを持ち出すだけでも、それこそ大変な勇気が必要だったと思う。したがって、勇気の中身を問うのは酷に過ぎる。作者もまた曖昧さを承知で、そのあたりのことは受け手である学生たちの理解にまかせてしまっている。だから作者は、その曖昧な物言いに、せめて純白の梅の花を添えることで、死地に赴く若者たちへの祈りとしたのだろう。作者の本心は「地の塩」や「勇気」にではなく、凛冽と咲く「梅真白」にこそ込められている。『来し方行方』(1947)所収。(清水哲男)
ちなみに、この句には〝教え子が学徒動員として時代の渦に巻き込まれる「かどで」の際に「無言裡に書き示したもの」とあり、聖書に言う信仰する者をさす「地の塩」は「他者によって生成せしめられるものでなくて自ら生成するもの、他者によって価値づけられるものではなくて自らが価値の根源であるもの」〟と自句自注にあると。
やっぱり草田男の句は、〝人間探求派〟とか〝難解派〟とか言われるだけあって、難しいですね。
明日から一泊で近江八幡へ出かけてきます。でも寒そう!しっかり着ぶくれて行きますね。
写真は満開の梅です。ちょっとボケていますが、ゴメンナサイ!















 …と落ち着かない1日でした。でも、時々日が差してきたりするので積もるようなことはありません。もしかしたら今朝は雪が積もっているかもと期待したのですが、雨が上がったあとのようでした。11時からは着付教室へ。帰ってくると気持の良い天気になって、あちらこちらの木々に鳥たちが…キジバト、カラス、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ、スズメ…と確認できただけでもこれだけいましたよ。昨日からの寒さで餌が十分食べられなかったからでしょうか。
…と落ち着かない1日でした。でも、時々日が差してきたりするので積もるようなことはありません。もしかしたら今朝は雪が積もっているかもと期待したのですが、雨が上がったあとのようでした。11時からは着付教室へ。帰ってくると気持の良い天気になって、あちらこちらの木々に鳥たちが…キジバト、カラス、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ、スズメ…と確認できただけでもこれだけいましたよ。昨日からの寒さで餌が十分食べられなかったからでしょうか。 明日は最後のF教室の新年句会です。今から準備しますので、ではまたね。
明日は最後のF教室の新年句会です。今から準備しますので、ではまたね。