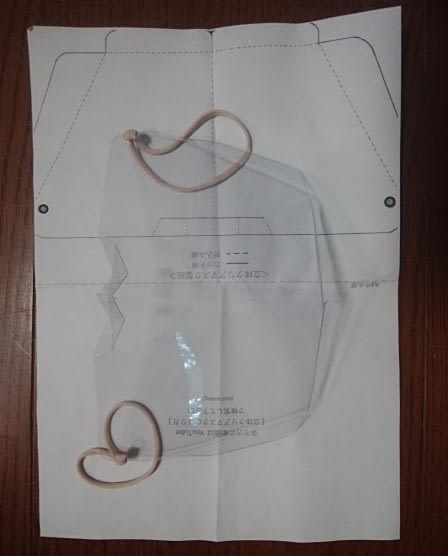昨夜のこと、我が家の気まぐれ猫〝テン〟が、私にイヤに媚びを売るようにすり寄ってきて鳴いていました。
〝どうしたんね、ご飯がないの?〟と言うと、鳴きながらえさ箱へ誘導するように先に立ちます。ドアを開けて見ると…〝なんね、餌あるやないの!〟と部屋に戻ろうとすると、また訴えるようにニャアニャーと。
〝じゃあ草がほしいの?〟…そうなんです、草が欲しいときだけは私に鳴いてせがみます。それで外へ出るのに裏口の方へ行こうと…いつもならドアまで付いてくるテンが離れたところでまた鳴いています。ウ~ン、草じゃないの?と、…もう一度えさ箱に目をやると何か黒いものが…、〝エエッ、ゴキブリがいる!〟それも何とも大きなゴキブリでした。
そうだったんです。テンの訴えは〝ゴキブリ〟〝あんたねえ~ネズミを捕る猫でしょ!トカゲもバッタもカマキリも捕ってくるんだからゴキブリも捕まえなくっちゃ!〟
結局、追いかけまわしフマキラーをかけて、私がやっと退治しました。後始末もきれいにしてえさ箱も洗って新しい餌を入れてやると、やっと安心して食べていました。主人に話すと〝まるで○○(息子の名前)のようじゃの~〟と。〝わあ、あなたも一緒じゃん!〟
とにかく主人の方は多少マシなのですが、息子といったらゴキブリがいると言っただけで、わあわあと騒いで逃げ回っているんですから。私も好きではありませんけどね…。
さてさて、今日も空は曇っていても雨は一滴も降らず、最高気温も34度と、とにかく暑いです。どなたかが〝大残暑〟と詠まれていましたが、確かにこうも暑い日が続くとそう言いたくなる気持もよく分りますよね。夏の季語の〝暑〟には〝大暑〟〝酷暑〟〝極暑〟など、いろいろあるんですから、残暑の季語にも何か違った言い方があってもいいかも。これからは地球温暖化で年々酷くなりそうですし…。
口紅の玉虫いろに残暑かな 飯田蛇笏
ここでいう〝玉虫いろ〟というのはどんな色を指しているのでしょう。〝口紅の〟とあるからには赤系統を想像してしまうのですが…。辞書には、玉虫色というのは〝玉虫の羽のような金属的光沢を帯びた美しい金緑色、金紫色〟また、〝玉虫の羽のように光線の具合によって金緑色、金紫色などに輝く染物、織物の色〟とも。ということはこの玉虫色のような口紅をつけた女性を詠んだことになるのですが、今ならいざ知らず、この句を詠んだ当時にそんな色の口紅があったとはとても思えません。では夜のネオン街などで見かけた女性の?その口紅に光があたっていろいろな色に見えたということかしら。でも私には蛇笏がそういうような夜の歓楽街に縁があったとはとても思えないんですけどね。
とするとこの句は???疑問が深まるばかりです。ここは〈玉虫いろの〉でなく〈いろに〉ですから、間違いなく口紅が玉虫色のように見えたんでしょう。そして、そこに〝残暑〟を感じたのだと…。
この句は、1932年(昭和7年)に出版された蛇笏の処女句集『山廬集(さんろしゅう)』に所収されています。蛇笏は1885年(明治18年)生まれ。1903(明治36年)年に上京し、1905年(明治38年)早稲田大学英文科に入学しますが、1909年(明治42年)に家から帰郷の命を受けて学業を断念し、早大を中退して帰郷します。それからは故郷山梨で家業の農業や養蚕に従事する一方、俳誌「雲母」を主宰し、格調の高い俳句を詠み続けます。蛇笏は伝統的俳句の立場から最後まで自然風土に根ざした俳句を提唱しました。
蛇笏の作品は、山梨の山間で創作したものが大半ですが、若い頃は小説家を志望していたということもあって、『山廬集』には小説的な発想をもつ句も多く含まれているということです。高浜虚子も「ホトトギス」に連載した「進むべき俳句の道」(1915年)において、「小説的」であることを初期の蛇笏の第一の特徴として挙げているのだとも。
そういうことを考え合わせると、句の詠み方の格調からは蛇笏らしいとは言えるものの、その内容に於ては彼のイメージからはかなり違った映像を描いてしまいました。夜の歓楽街…酒場でしょうか、そこに働く美しい女性の艶めかしい口紅。光線の加減で妖しく色が変わる…その唇から吐き出される息や言葉にじっとりとした息苦しいほどの暑さを…もう秋だというのにここだけはまだ夏のような暑さが残っているのだなあ…と。でも、やはり蛇笏ですね。口紅に玉虫を持ってくるなんて…その品格といい、雅やかさといい…、印象鮮明でドキッとさせられました。
蛇笏の句で艶めいたものを、私は知らないのですが、この句が詠まれたのは句集が発表される前でしょうから、蛇笏もまだ30代か40代でしょうか。いや、20代かも。学生時代に…また、上京した折にでも銀座のクラブに飲みに行ったのかも。アハハ…ゲスの鑑賞ですかしら。でしたら、蛇笏サマ、どうぞお許し下さいませね。
俳句も一旦作者の手を離れてしまうと、どう鑑賞されようと自由なんです。それがまた面白いところでもありますが。
写真は、〝凌霄花(のうぜんか)〟、もう1回は咲き終っていたのが、また一つだけ咲いてました。山吹も。これらを〝帰り花〟とはいわないんですから、気をつけてね。〝狂咲き〟とか〝二度咲き〟なども、全部冬の季語なんですよ。



























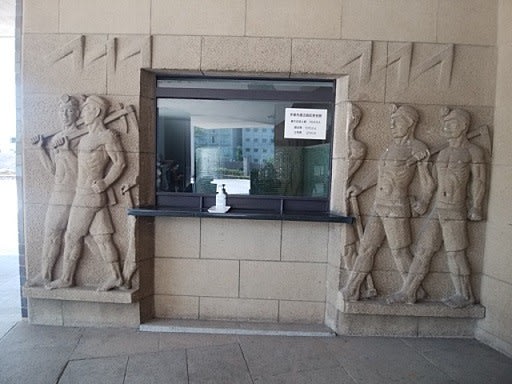











































 下の句をどうぞ。
下の句をどうぞ。 じゃあ山口県はどうなってるのかしらと見ると、あらら…いつの間にか78人にも。この田舎の宇部市でも13人と…エエッ、という感じでした。これじゃあ他の所でもどんどん増えているのでしょうね。どうも一番沖縄が大変みたい…。だって感染者の累計1,179人のうち、7月に入ってからの新規感染者数が1,037人なんだって。これ見ただけでも、病院の悲鳴が聞こえてきそうですもの。ああ、やっぱり他人事ではありませんよ。つい目を離すと…コワイですね!皆さん、もっともっと気を引き締めて、どうにかこの夏を乗り切りたいものですね。ガンバリましょう!
じゃあ山口県はどうなってるのかしらと見ると、あらら…いつの間にか78人にも。この田舎の宇部市でも13人と…エエッ、という感じでした。これじゃあ他の所でもどんどん増えているのでしょうね。どうも一番沖縄が大変みたい…。だって感染者の累計1,179人のうち、7月に入ってからの新規感染者数が1,037人なんだって。これ見ただけでも、病院の悲鳴が聞こえてきそうですもの。ああ、やっぱり他人事ではありませんよ。つい目を離すと…コワイですね!皆さん、もっともっと気を引き締めて、どうにかこの夏を乗り切りたいものですね。ガンバリましょう!