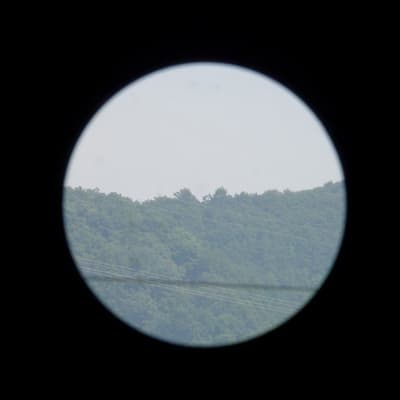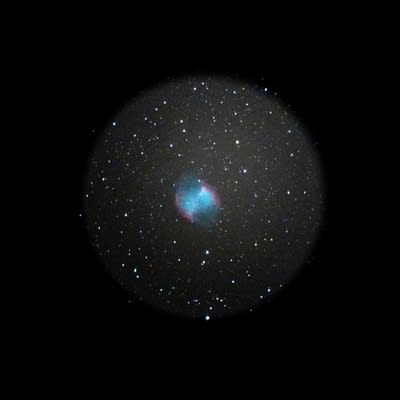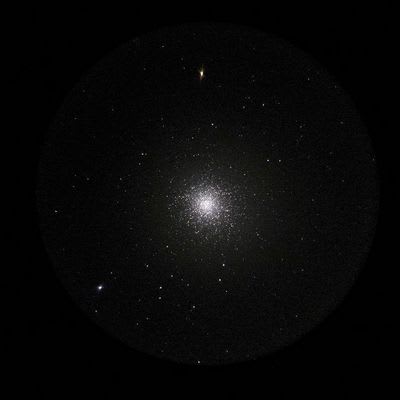こ、コリャ英和!!
LX7用フィルター・コンバージョンレンズアダプターのことです。
Kiwi Potos LA-52LX7

メーカーはココ↓
http://kiwifotos.com/index.php
Amazonで買えます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90STOK-SELECT%E3%80%91%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-LUMIX-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-52mm/dp/B00AQ1943M
LX7のフロントリングがバヨネット構造になっており、
これが外せると教えて下さった方がいらっしゃいまして、
更に上記アダプターがAmazonで売っていると言うので、早速ポチ!

向かって反時計方向に回すと外れますが、
初めて外す時は”これ以上力を入れちゃあヤバイかも?”って
くらいの力が必要です。でも、2回目以降はアッサリ外れます。
と言うことは、あまり付けたり外したりしているとバカっちゃう
と言うことですね。
バヨネット部の拡大です。
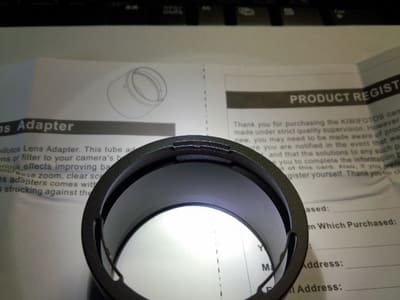
材質:アルミ
表面処理:黒梨地アルマイト
質感:良し
なんと、NCでバヨネット部を削り出している。
バリも無くキレイですが、取り扱い注意ですねコレハ。
と、言うことで付けっ放し決定。”カチッ”とハマります。

お~お~、ええど、ええどコリャ~

”構造上、広角側では四隅がケラレます。”
とAmazonには書いてありますが、全然そんなことはありません。
これで広角端ですよ。

何時も使っているフードを付けるとこんな感じです。
このフードで四隅がほんの少しケラレる程度ですから、
LA-52LX7ではまったく問題なしですね。

52mmのフィルターねじが切ってあるので、市販のフードも使えます。

うーん、かっけー。
初めからこういうカメラだと思えば、それで良し。
露避けヒーターも難なく巻けます。

-------------
で、
こっからが縮小コリメーターのお話し。
内径48.3mm。Vixenの現行NLVアイピースの外形が48mmなので
入ります。


笠井トレーディングのSV30mm_2inchはM57->M52変換リング経由で
直結出来ます。(でもこのアイピースはC-8と相性悪いのよねえ~)
この状態でLX7のレンズギリギリまで寄れますが当たりはしません。

このアイピースは視野環が無いので輪郭が不明瞭ですが、
だいたいこんな感じです。あれ?F1.6になってしまった。
F1.4だともう少し写野が狭くなります。

以上、LA-52LX7の使い勝手を一通りチェックしてみましたが、
特筆すべきは機械的強度です。
M37mmフィルターねじを利用して縮小コリメート撮影をすると、
どうしてもズームレンズのフニャフニャ感が拭えません。
更に、LX7のズーム機構はLX7本体の自重を引き上げることが
出来ず、屈折鏡筒で天頂撮影時に画像チェックしようものなら、
”ガガガガガッ”とレンズが脱調して”電源を入れ直せ!”
となってしまうのです。
画像チェックをするとレンズが勝手に引っ込むんですよね、LX7。
それだけでもイヤなのですが、
これを繰り返していると、どうも無限遠位置が狂って来るよう
なのです。買った直後は、間違いなく∞マークの右側にあった
真の無限遠位置が、最近では2m~∞の間で、かなり2m寄りに
なってしまいました。常にデータを数値化していますから、
間違いないことです。
友人の個体では、なんと無限遠が0.3m~1mの間になってしまった
と言っていました。
国士無双・・・じゃなかった、 酷使無用ですね(^^♪
つづく
LX7用フィルター・コンバージョンレンズアダプターのことです。
Kiwi Potos LA-52LX7

メーカーはココ↓
http://kiwifotos.com/index.php
Amazonで買えます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90STOK-SELECT%E3%80%91%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-LUMIX-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-52mm/dp/B00AQ1943M
LX7のフロントリングがバヨネット構造になっており、
これが外せると教えて下さった方がいらっしゃいまして、
更に上記アダプターがAmazonで売っていると言うので、早速ポチ!

向かって反時計方向に回すと外れますが、
初めて外す時は”これ以上力を入れちゃあヤバイかも?”って
くらいの力が必要です。でも、2回目以降はアッサリ外れます。
と言うことは、あまり付けたり外したりしているとバカっちゃう
と言うことですね。
バヨネット部の拡大です。
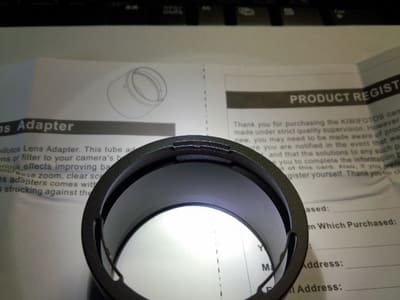
材質:アルミ
表面処理:黒梨地アルマイト
質感:良し
なんと、NCでバヨネット部を削り出している。
バリも無くキレイですが、取り扱い注意ですねコレハ。
と、言うことで付けっ放し決定。”カチッ”とハマります。

お~お~、ええど、ええどコリャ~

”構造上、広角側では四隅がケラレます。”
とAmazonには書いてありますが、全然そんなことはありません。
これで広角端ですよ。

何時も使っているフードを付けるとこんな感じです。
このフードで四隅がほんの少しケラレる程度ですから、
LA-52LX7ではまったく問題なしですね。

52mmのフィルターねじが切ってあるので、市販のフードも使えます。

うーん、かっけー。
初めからこういうカメラだと思えば、それで良し。
露避けヒーターも難なく巻けます。

-------------
で、
こっからが縮小コリメーターのお話し。
内径48.3mm。Vixenの現行NLVアイピースの外形が48mmなので
入ります。


笠井トレーディングのSV30mm_2inchはM57->M52変換リング経由で
直結出来ます。(でもこのアイピースはC-8と相性悪いのよねえ~)
この状態でLX7のレンズギリギリまで寄れますが当たりはしません。

このアイピースは視野環が無いので輪郭が不明瞭ですが、
だいたいこんな感じです。あれ?F1.6になってしまった。
F1.4だともう少し写野が狭くなります。

以上、LA-52LX7の使い勝手を一通りチェックしてみましたが、
特筆すべきは機械的強度です。
M37mmフィルターねじを利用して縮小コリメート撮影をすると、
どうしてもズームレンズのフニャフニャ感が拭えません。
更に、LX7のズーム機構はLX7本体の自重を引き上げることが
出来ず、屈折鏡筒で天頂撮影時に画像チェックしようものなら、
”ガガガガガッ”とレンズが脱調して”電源を入れ直せ!”
となってしまうのです。
画像チェックをするとレンズが勝手に引っ込むんですよね、LX7。
それだけでもイヤなのですが、
これを繰り返していると、どうも無限遠位置が狂って来るよう
なのです。買った直後は、間違いなく∞マークの右側にあった
真の無限遠位置が、最近では2m~∞の間で、かなり2m寄りに
なってしまいました。常にデータを数値化していますから、
間違いないことです。
友人の個体では、なんと無限遠が0.3m~1mの間になってしまった
と言っていました。
国士無双・・・じゃなかった、 酷使無用ですね(^^♪
つづく