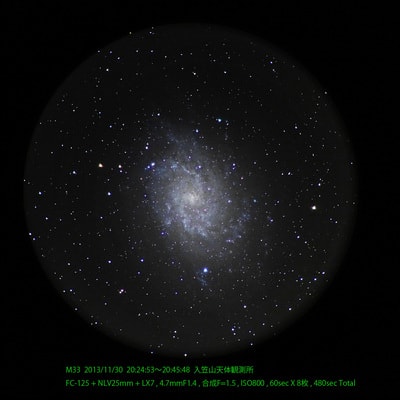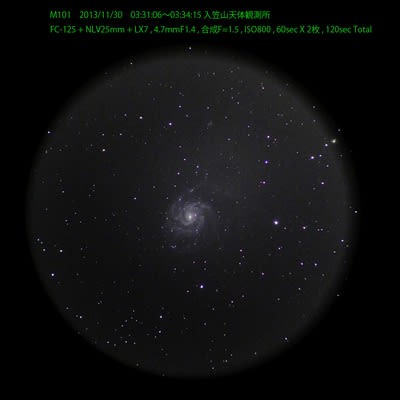年末年始があっという間に過ぎ去り、もう15日ですよ。
天気は良かったものの、さすがにこんな時にお星様の撮影なんて行かれません。
有間峠は12月~4月まで路面凍結のために通行止め林道となります。
こんな時期は何かを作るのがいつものパターンです。
今年初めのお題はコレ。

PHOTON32mm(左)とHYPERION36mm(右)です。
デカイ (V)o¥o(V)
共にM43mm_P0.75のフィルタネジ(雄)が切ってあります。
HYPERION36mmにはM54mm_P0.75(雄)も切ってあります。
これらとKiwi Potos LA-52LX7 M52mm_P0.75(雌)を接続するアダプター
を作ろうと言う訳です。
・スライドまたはネジで主点調節が出来ること。
・カメラをワンタッチで取り外せること。
・構図決定が楽に出来ること。
・剛性があること。
まあ、こんなところですね。
次の新月期までに作ってみようと思います。
天気は良かったものの、さすがにこんな時にお星様の撮影なんて行かれません。
有間峠は12月~4月まで路面凍結のために通行止め林道となります。
こんな時期は何かを作るのがいつものパターンです。
今年初めのお題はコレ。

PHOTON32mm(左)とHYPERION36mm(右)です。
デカイ (V)o¥o(V)
共にM43mm_P0.75のフィルタネジ(雄)が切ってあります。
HYPERION36mmにはM54mm_P0.75(雄)も切ってあります。
これらとKiwi Potos LA-52LX7 M52mm_P0.75(雌)を接続するアダプター
を作ろうと言う訳です。
・スライドまたはネジで主点調節が出来ること。
・カメラをワンタッチで取り外せること。
・構図決定が楽に出来ること。
・剛性があること。
まあ、こんなところですね。
次の新月期までに作ってみようと思います。