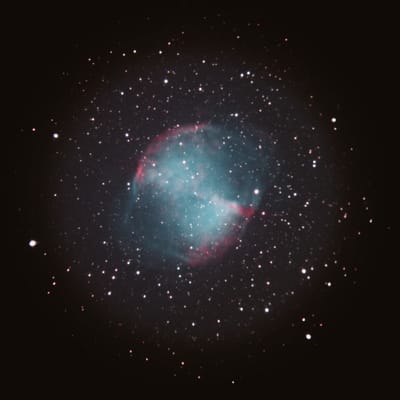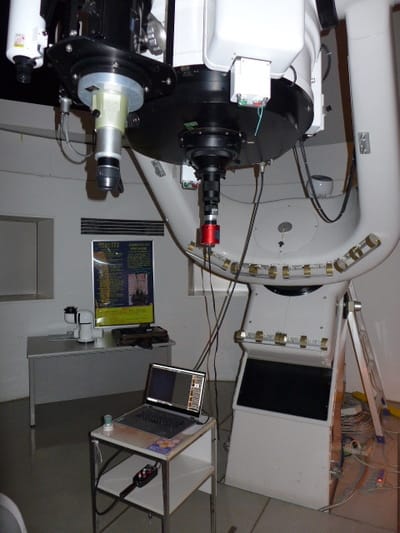沈みかけた夏物を一気にゲット!
水蒸気一杯の低空狙いでボケボケですけど、今年は夏物を
何も撮影できなかったので良しとしましょう。
本日アップした複数記事の一連画像は、全て昨日一気に撮影
したものです。縮小コリメート法と高感度裏面照射カラーCOMS
カメラを組み合わせると・・・
後処理が膨大になって大変ですね~( ̄▽ ̄)
M8
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M20
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M16
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M22(アレ?曇ったか?)
G120 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M13
G200 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M57
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

------------------------------------------------------------
撮影日時:2019/09/25
撮影場所:65cm天文台 標高870m
天候:23時までは薄雲ありの晴れ。以降曇り。
気温:12℃
星空指数:40
シーイング:高気圧前衛のため 2/5
撮像鏡筒:65cmF12クラシカルカセグレン
アイピース:TELE VUE 55mm PLoSSL
レンズ:CCTV 16mmF1.4 C MountLens
撮像カメラ:ZWO-ASI294MC
縮小率:55/16=3.4375
合成F:3.49
合成fl:2269mm
通常光学系FOV:3450 X 21mm / 7800mm = 9.29'角(m4/3対角)
縮小光学系FOV:3450 X 9mm / 2269mm = 13.68'角(円形写野直径)
*上記9mmは1/1.8インチ素子の対角、21mmはm4/3素子の対角
------------------------------------------------------------
水蒸気一杯の低空狙いでボケボケですけど、今年は夏物を
何も撮影できなかったので良しとしましょう。
本日アップした複数記事の一連画像は、全て昨日一気に撮影
したものです。縮小コリメート法と高感度裏面照射カラーCOMS
カメラを組み合わせると・・・
後処理が膨大になって大変ですね~( ̄▽ ̄)
M8
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M20
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M16
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M22(アレ?曇ったか?)
G120 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M13
G200 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

M57
G250 , 10X15s , 150s Total , NoDarkAndFlat , 2X2binning

------------------------------------------------------------
撮影日時:2019/09/25
撮影場所:65cm天文台 標高870m
天候:23時までは薄雲ありの晴れ。以降曇り。
気温:12℃
星空指数:40
シーイング:高気圧前衛のため 2/5
撮像鏡筒:65cmF12クラシカルカセグレン
アイピース:TELE VUE 55mm PLoSSL
レンズ:CCTV 16mmF1.4 C MountLens
撮像カメラ:ZWO-ASI294MC
縮小率:55/16=3.4375
合成F:3.49
合成fl:2269mm
通常光学系FOV:3450 X 21mm / 7800mm = 9.29'角(m4/3対角)
縮小光学系FOV:3450 X 9mm / 2269mm = 13.68'角(円形写野直径)
*上記9mmは1/1.8インチ素子の対角、21mmはm4/3素子の対角
------------------------------------------------------------