都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「プライベート・ユートピア」 東京ステーションギャラリー
東京ステーションギャラリー
「プライベート・ユートピア ここだけの場所 ブリティッシュ・カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在」
1/18-3/9

東京ステーションギャラリーで開催中の「プライベート・ユートピア」を見て来ました。
イギリスの公的な国際交流機関の「ブリティッシュ・カウンシル」。これまでに同国の若い世代のアーティストの作品を収集。その数は現在9000点にも及びます。うち選ばれた120点が日本へ。東京駅のステーションギャラリーで公開されています。

ジョージ・ショウ「灰の水曜日:午後3時」2004-2005年
出品は30名です。半数以上がターナー賞を受賞、もしくはノミネートされた作家。大掛かりなインスタレーションは少なく、小さなものが目立ちます。ジャンルは絵画に写真に映像に立体。ともかくは多様な作品が紹介されていました。
ではいくつか印象深い作品を。まずはコーネリア・パーカー。何やらフレームに入れられた英語の地図。ロンドンです。ただよく見ると一部が焦げている。実はこれ、本物の隕石を焦がして地図帖の上に置いたのだとか。まるで隕石が衝突したかのような姿。実際に起きたらどれほどの被害が起きてしまうのか。それをただ傍観者の如く眺める自分。何とも言い難い居心地の悪さを感じます。
サイモン・スターリングはどうでしょうか。「シャクナゲを救う」と題された写真作品。確かに写るのはシャクナゲの木。何でも作家自らスコットランドからスペインへ移送した時の様子を収めたもの。そもそもシャクナゲはスペインの植物。それをスウェーデン人がスコットランドにもたらした。今度は送り返す。移民の問題などにも目を向けているのかもしれません。

マーカス・コーツ「エビガラスズメ蛾、エビガラスズメ蛾の幼虫、シェービング・フォームによる自画像」2013年
目立つのはマーカス・コーツです。そして何が目立つかと言えば白い泡で覆われた人体像。その名も「エビガラススズメ蛾、エビガラススズメ蛾の幼虫、シェービング・フォームによる自画像」です。まるで繭。得体の知れない動物に変身しています。その他にはカゲロウや蝶の幼虫を取り込んだ作品もありました。
デジタルで処理された画像を加工してカンヴァスへと写すのがトビー・ジーグラーです。連作は「巨大遺跡のようなもの」。トーテムポールのようなモチーフが象られている。しかしながら見方を変えればテーカップのようにも映る。遺跡なのか身近な素材なのか。スケール感も曖昧になっています。

ギャリー・ヒューム「シスター・トゥループから無題」2009年
グロスペイントを用いているのだそうです。アメリカのチアリーダーをモチーフとしたのはギャリー・ヒューム。チアと言えどもそれを全身像で捉えるのではない。トリミングと言って良いのでしょうか。動く手足をクローズアップして描く。グラフィカルな印象も与えられます。
出品作家の中でも特に知られるのはライアン・ガンダーにマーティン・クリードです。ガンダーは2011年に銀座のメゾン・エルメスでも個展を開催。かの空間を大きく変容させるようなインスタレーションを展開していました。今回は小さな作品です。チラシ表紙にも掲げられた「四代目エジャートン男爵の16枚の羽毛がついた極楽鳥」。基本は鳥の剥製。しかしながらその姿はこの世の存在ではないかのような奇異な出立ちをしている。そして新種の鳥を発見したという新聞記事も。一つの物語を作り上げています。
マーティン・クリードはお馴染みのメトロノームを用いた作品です。3つのメトロノームが異なる時を刻む。シンプルな仕掛けながらも時の感覚を乱す音。それがひたすらズレて反復していく。しばし耳を傾けました。

マイク・ネイソン「ブラック・アート・バーベキュー、サン・アントニオ、1961年8月」1998年
多面的な視点で社会の問題を見つめる。ユーモア、時にアイロニカルでもある。批評的という言葉で宜しいのでしょうか。そうした作品も目立ちました。
90年代以降のイギリス美術の動向。総勢30名、全120点と盛りだくさんです。企画には感謝したいところですが、私の理解力の問題もあったかもしれません。ともかく頭の切り替えが大変でした。少し人数を絞った上、何名かの作家をより深く追うような形の方が良かった気もします。

ウッド&ハリソン「テーブルと椅子」2001年
時間の都合により参加出来ませんでしたが、過日行われたブリテッシュ・カウンシルアーツ(@jpBritishArts)によるツイッター上のギャラリーツアーは面白い試みだと感心しました。
『プライベート・ユートピア ここだけの場所』ツイッター・ギャラリーツアー
出品リストは会場内で係の方に申し出るといただけます。3月9日まで開催されています。
「プライベート・ユートピア ここだけの場所 ブリティッシュ・カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在」 東京ステーションギャラリー
会期:1月18日(土)~3月9日(日)
休館:月曜日。
料金:一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生400円。
*20名以上の団体は100円引。
時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。
住所:千代田区丸の内1-9-1
交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)
「プライベート・ユートピア ここだけの場所 ブリティッシュ・カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在」
1/18-3/9

東京ステーションギャラリーで開催中の「プライベート・ユートピア」を見て来ました。
イギリスの公的な国際交流機関の「ブリティッシュ・カウンシル」。これまでに同国の若い世代のアーティストの作品を収集。その数は現在9000点にも及びます。うち選ばれた120点が日本へ。東京駅のステーションギャラリーで公開されています。

ジョージ・ショウ「灰の水曜日:午後3時」2004-2005年
出品は30名です。半数以上がターナー賞を受賞、もしくはノミネートされた作家。大掛かりなインスタレーションは少なく、小さなものが目立ちます。ジャンルは絵画に写真に映像に立体。ともかくは多様な作品が紹介されていました。
ではいくつか印象深い作品を。まずはコーネリア・パーカー。何やらフレームに入れられた英語の地図。ロンドンです。ただよく見ると一部が焦げている。実はこれ、本物の隕石を焦がして地図帖の上に置いたのだとか。まるで隕石が衝突したかのような姿。実際に起きたらどれほどの被害が起きてしまうのか。それをただ傍観者の如く眺める自分。何とも言い難い居心地の悪さを感じます。
サイモン・スターリングはどうでしょうか。「シャクナゲを救う」と題された写真作品。確かに写るのはシャクナゲの木。何でも作家自らスコットランドからスペインへ移送した時の様子を収めたもの。そもそもシャクナゲはスペインの植物。それをスウェーデン人がスコットランドにもたらした。今度は送り返す。移民の問題などにも目を向けているのかもしれません。

マーカス・コーツ「エビガラスズメ蛾、エビガラスズメ蛾の幼虫、シェービング・フォームによる自画像」2013年
目立つのはマーカス・コーツです。そして何が目立つかと言えば白い泡で覆われた人体像。その名も「エビガラススズメ蛾、エビガラススズメ蛾の幼虫、シェービング・フォームによる自画像」です。まるで繭。得体の知れない動物に変身しています。その他にはカゲロウや蝶の幼虫を取り込んだ作品もありました。
デジタルで処理された画像を加工してカンヴァスへと写すのがトビー・ジーグラーです。連作は「巨大遺跡のようなもの」。トーテムポールのようなモチーフが象られている。しかしながら見方を変えればテーカップのようにも映る。遺跡なのか身近な素材なのか。スケール感も曖昧になっています。

ギャリー・ヒューム「シスター・トゥループから無題」2009年
グロスペイントを用いているのだそうです。アメリカのチアリーダーをモチーフとしたのはギャリー・ヒューム。チアと言えどもそれを全身像で捉えるのではない。トリミングと言って良いのでしょうか。動く手足をクローズアップして描く。グラフィカルな印象も与えられます。
出品作家の中でも特に知られるのはライアン・ガンダーにマーティン・クリードです。ガンダーは2011年に銀座のメゾン・エルメスでも個展を開催。かの空間を大きく変容させるようなインスタレーションを展開していました。今回は小さな作品です。チラシ表紙にも掲げられた「四代目エジャートン男爵の16枚の羽毛がついた極楽鳥」。基本は鳥の剥製。しかしながらその姿はこの世の存在ではないかのような奇異な出立ちをしている。そして新種の鳥を発見したという新聞記事も。一つの物語を作り上げています。
マーティン・クリードはお馴染みのメトロノームを用いた作品です。3つのメトロノームが異なる時を刻む。シンプルな仕掛けながらも時の感覚を乱す音。それがひたすらズレて反復していく。しばし耳を傾けました。

マイク・ネイソン「ブラック・アート・バーベキュー、サン・アントニオ、1961年8月」1998年
多面的な視点で社会の問題を見つめる。ユーモア、時にアイロニカルでもある。批評的という言葉で宜しいのでしょうか。そうした作品も目立ちました。
90年代以降のイギリス美術の動向。総勢30名、全120点と盛りだくさんです。企画には感謝したいところですが、私の理解力の問題もあったかもしれません。ともかく頭の切り替えが大変でした。少し人数を絞った上、何名かの作家をより深く追うような形の方が良かった気もします。

ウッド&ハリソン「テーブルと椅子」2001年
時間の都合により参加出来ませんでしたが、過日行われたブリテッシュ・カウンシルアーツ(@jpBritishArts)によるツイッター上のギャラリーツアーは面白い試みだと感心しました。
『プライベート・ユートピア ここだけの場所』ツイッター・ギャラリーツアー
出品リストは会場内で係の方に申し出るといただけます。3月9日まで開催されています。
「プライベート・ユートピア ここだけの場所 ブリティッシュ・カウンシル・コレクションにみる英国美術の現在」 東京ステーションギャラリー
会期:1月18日(土)~3月9日(日)
休館:月曜日。
料金:一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生400円。
*20名以上の団体は100円引。
時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。
住所:千代田区丸の内1-9-1
交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
「ラファエル前派展」 森アーツセンターギャラリー
森アーツセンターギャラリー
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」
1/25-4/6

森アーツセンターギャラリーで開催中の「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」を見て来ました。
1848年、7名の若い芸術家によって結成された「ラファエル前派兄弟団」。ラファエロを規範とする当時のアカデミズムに反発。それ以前の初期ルネサンスに理想を掲げての芸術活動。紆余曲折、時に社会の批判を浴びながらも、結果的にはイギリスの近代美術に大きな足跡を残した。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「見よ、我は主のはしためなり(受胎告知)」1849-50年 油彩・カンヴァス テート美術館
具体的にはミレイにロセッティにハント。さらに第二世代としてのモリスにバーン=ジョーンズ。今でも人気の画家たちです。ここにテート美術館所蔵のラファエル前派コレクションがやって来ました。
展示の構成は描かれたテーマ別。歴史に宗教に風景に近代生活。そして後半はラファエル前派の変容、言わば純然たる美を表現しようとした試みから象徴主義への流れを辿る。全72点です。またテートにはじまり、ワシントン・ナショナル・ギャラリー、プーシキン美術館と廻って来た国際巡回展でもあります。
それではいくつかの作品を挙げてみます。まずはアーサー・ヒューズの「4月の恋」。兄弟団のメンバーではなかったものの、その周囲にいたという画家。美しいのは紫色を帯びた青いロングドレス。それが鬱蒼としたヒルガオの緑と呼応する。モデルは妻であるトライフィーナ。作品は当時、学生であったモリスが買い上げたそうです。

ジョン・エヴァレット・ミレイ「オフィーリア」1851-52年 油彩・カンヴァス テート美術館
「オフィーリア」もお出ましです。東京では2008年の文化村のミレイ展以来のことでしょうか。お馴染みのハムレットにおけるヒロインの入水の場面。何度見ても美しい作品は美しいわけですが、今回改めて感心したのは彼女を取り巻く草花の表現。よく指摘されるようにミレイは一時、ロンドンを離れてまでして草花の写生に勤しみます。詩的霊感と自然への眼差し。また左上には彼女を見つめるコマドリの姿も。受難の象徴なのでしょうか。
ウォリスの「チャタートン」も目を引きます。僅か17歳で息を引き取ったという詩人。だらりと手を垂らしてベットに横たわる。ブロンズの髪はまだ若々しい。鑑賞者はそれこそ死の第一発見者となる。まるで舞台を前にしたかのようにドラマテックですらあります。
ミレイでは「両親の家のキリスト(大工の仕事場)」も興味深いもの。当然ながら描かれているのは聖書の主題。しかしながら聖家族をあまりにも風俗的に表したことから、大変な非難を浴びたとか。ラファエル前派の半ば革新性を伺える作品と言えるかもしれません。
最も惹かれたのがジョン・ロッダム・スペンサー・スタンホープの「過去の追想」です。何と言っても印象深いのはどこか物憂げな表情で佇む女性。長い髪を右手で引っ張るように透く。窓からは小舟の停泊するテムズ。よく見ると空には黒い雲も。工場の煙でしょうか。女性は娼婦です。割れたガラスに破れたカーテン。それにしても狭そうな室内。貧困から抜け出せるのか。枯れかけの鉢植えに床へ散る花が彼女の行方を暗示するかのようです。
ミレイの「安息の谷間」はどうでしょうか。夕焼けにそまる墓場の景色。一人の尼が墓を掘り、もう一人が両手を前にして墓石に座る。「死」の気配が全体を支配する作品ではありますが、不思議と風俗的でかつリアル、どこか身近な光景に映るのも興味深いところ。こちらを向く尼の目線にも引込まれます。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「ベアタ・ベアトリクス」1864-70年 油彩・カンヴァス テート美術館
それにしても美しき女性ばかり。いずれも実在のモデル。リジーにジェインにアニー。画家と深い関係を持ち、時に複雑な人間ドラマを展開した女性たちです。その辺りについては会場内の「人間相関図」で知ることが出来ます。ただ展示自体は先にも触れたようにテーマ、モチーフ別での構成です。いわゆる画家の個性や生き様云々よりも、作品自体を見比べることに重点の置かれた展示と言えるかもしれません。

ウィリアム・ダイス「ペグウェル・ベイ、ケント州」1858-60年 油彩・カンヴァス テート美術館
ラファエロ前派のグループとしての活動は僅か数年で終えてしまいます。短い期間に画家たちがどのような表現を志向したのか。結成期から60年代頃までの約20年間にスポットを当てての企画。そういう意味では密度の濃い展示という印象を受けました。

ウィリアム・ホルマン・ハント「良心の目覚め」1853-54年 油彩・カンヴァス テート美術館
要所には大作が構えていますが、小品も目立ちます。もちろん個人差はあるかもしれませんが、私は意外と早く見終えました。しかしながら考えれば本展は2つに1つと言って良いもの。「ザ・ビューティフル」です。ラファエル前派に引き続き、三菱一号館では英国の唯美主義に関する展覧会が行われています。

「ザ・ビューティフルー英国の唯美主義1860~1900」@三菱一号館美術館(1/30~5/6)
そもそも唯美主義はロセッティやバーン=ジョーンズらも参加した芸術運動。時代もラファエル前派から僅かに下った頃です。深い関係があるのは言うまでもありません。
六本木から丸の内へ。一号館の「ザ・ビューティフル」もあわせて見に行きたいと思います。

ウィリアム・モリス「麗しのイズー」1856-58年 油彩・カンヴァス テート美術館
会期一週目の日曜だったからでしょうか。館内はまだ余裕がありました。ただ追って混雑してくるのではないでしょうか。なお公式のツイッターアカウント(@prb_konzatsu)では混雑情報をリアルタイムで更新しています。そちらも参考になりそうです。
 「美術手帖3月号増刊 ラファエル前派 19世紀イギリスの美術革命/美術出版社」
「美術手帖3月号増刊 ラファエル前派 19世紀イギリスの美術革命/美術出版社」
4月6日まで開催されています。
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」 森アーツセンターギャラリー
会期:1月25日(土)~4月6日(日)
休館:会期中無休
時間:10:00~20:00(1月、2月の火曜日は17時まで。)入館は閉館時間の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、4歳~中学生500(400)円。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」
1/25-4/6

森アーツセンターギャラリーで開催中の「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」を見て来ました。
1848年、7名の若い芸術家によって結成された「ラファエル前派兄弟団」。ラファエロを規範とする当時のアカデミズムに反発。それ以前の初期ルネサンスに理想を掲げての芸術活動。紆余曲折、時に社会の批判を浴びながらも、結果的にはイギリスの近代美術に大きな足跡を残した。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「見よ、我は主のはしためなり(受胎告知)」1849-50年 油彩・カンヴァス テート美術館
具体的にはミレイにロセッティにハント。さらに第二世代としてのモリスにバーン=ジョーンズ。今でも人気の画家たちです。ここにテート美術館所蔵のラファエル前派コレクションがやって来ました。
展示の構成は描かれたテーマ別。歴史に宗教に風景に近代生活。そして後半はラファエル前派の変容、言わば純然たる美を表現しようとした試みから象徴主義への流れを辿る。全72点です。またテートにはじまり、ワシントン・ナショナル・ギャラリー、プーシキン美術館と廻って来た国際巡回展でもあります。
それではいくつかの作品を挙げてみます。まずはアーサー・ヒューズの「4月の恋」。兄弟団のメンバーではなかったものの、その周囲にいたという画家。美しいのは紫色を帯びた青いロングドレス。それが鬱蒼としたヒルガオの緑と呼応する。モデルは妻であるトライフィーナ。作品は当時、学生であったモリスが買い上げたそうです。

ジョン・エヴァレット・ミレイ「オフィーリア」1851-52年 油彩・カンヴァス テート美術館
「オフィーリア」もお出ましです。東京では2008年の文化村のミレイ展以来のことでしょうか。お馴染みのハムレットにおけるヒロインの入水の場面。何度見ても美しい作品は美しいわけですが、今回改めて感心したのは彼女を取り巻く草花の表現。よく指摘されるようにミレイは一時、ロンドンを離れてまでして草花の写生に勤しみます。詩的霊感と自然への眼差し。また左上には彼女を見つめるコマドリの姿も。受難の象徴なのでしょうか。
ウォリスの「チャタートン」も目を引きます。僅か17歳で息を引き取ったという詩人。だらりと手を垂らしてベットに横たわる。ブロンズの髪はまだ若々しい。鑑賞者はそれこそ死の第一発見者となる。まるで舞台を前にしたかのようにドラマテックですらあります。
ミレイでは「両親の家のキリスト(大工の仕事場)」も興味深いもの。当然ながら描かれているのは聖書の主題。しかしながら聖家族をあまりにも風俗的に表したことから、大変な非難を浴びたとか。ラファエル前派の半ば革新性を伺える作品と言えるかもしれません。
最も惹かれたのがジョン・ロッダム・スペンサー・スタンホープの「過去の追想」です。何と言っても印象深いのはどこか物憂げな表情で佇む女性。長い髪を右手で引っ張るように透く。窓からは小舟の停泊するテムズ。よく見ると空には黒い雲も。工場の煙でしょうか。女性は娼婦です。割れたガラスに破れたカーテン。それにしても狭そうな室内。貧困から抜け出せるのか。枯れかけの鉢植えに床へ散る花が彼女の行方を暗示するかのようです。
ミレイの「安息の谷間」はどうでしょうか。夕焼けにそまる墓場の景色。一人の尼が墓を掘り、もう一人が両手を前にして墓石に座る。「死」の気配が全体を支配する作品ではありますが、不思議と風俗的でかつリアル、どこか身近な光景に映るのも興味深いところ。こちらを向く尼の目線にも引込まれます。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ「ベアタ・ベアトリクス」1864-70年 油彩・カンヴァス テート美術館
それにしても美しき女性ばかり。いずれも実在のモデル。リジーにジェインにアニー。画家と深い関係を持ち、時に複雑な人間ドラマを展開した女性たちです。その辺りについては会場内の「人間相関図」で知ることが出来ます。ただ展示自体は先にも触れたようにテーマ、モチーフ別での構成です。いわゆる画家の個性や生き様云々よりも、作品自体を見比べることに重点の置かれた展示と言えるかもしれません。

ウィリアム・ダイス「ペグウェル・ベイ、ケント州」1858-60年 油彩・カンヴァス テート美術館
ラファエロ前派のグループとしての活動は僅か数年で終えてしまいます。短い期間に画家たちがどのような表現を志向したのか。結成期から60年代頃までの約20年間にスポットを当てての企画。そういう意味では密度の濃い展示という印象を受けました。

ウィリアム・ホルマン・ハント「良心の目覚め」1853-54年 油彩・カンヴァス テート美術館
要所には大作が構えていますが、小品も目立ちます。もちろん個人差はあるかもしれませんが、私は意外と早く見終えました。しかしながら考えれば本展は2つに1つと言って良いもの。「ザ・ビューティフル」です。ラファエル前派に引き続き、三菱一号館では英国の唯美主義に関する展覧会が行われています。

「ザ・ビューティフルー英国の唯美主義1860~1900」@三菱一号館美術館(1/30~5/6)
そもそも唯美主義はロセッティやバーン=ジョーンズらも参加した芸術運動。時代もラファエル前派から僅かに下った頃です。深い関係があるのは言うまでもありません。
六本木から丸の内へ。一号館の「ザ・ビューティフル」もあわせて見に行きたいと思います。

ウィリアム・モリス「麗しのイズー」1856-58年 油彩・カンヴァス テート美術館
会期一週目の日曜だったからでしょうか。館内はまだ余裕がありました。ただ追って混雑してくるのではないでしょうか。なお公式のツイッターアカウント(@prb_konzatsu)では混雑情報をリアルタイムで更新しています。そちらも参考になりそうです。
 「美術手帖3月号増刊 ラファエル前派 19世紀イギリスの美術革命/美術出版社」
「美術手帖3月号増刊 ラファエル前派 19世紀イギリスの美術革命/美術出版社」4月6日まで開催されています。
「ラファエル前派展 英国ヴィクトリア朝絵画の夢」 森アーツセンターギャラリー
会期:1月25日(土)~4月6日(日)
休館:会期中無休
時間:10:00~20:00(1月、2月の火曜日は17時まで。)入館は閉館時間の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学生1200(1000)円、4歳~中学生500(400)円。
*( )内は15名以上の団体料金
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「野見山暁治展 いつかは会える」 ニューオータニ美術館
ニューオータニ美術館
「野見山暁治展 いつかは会える」
1/25-3/23
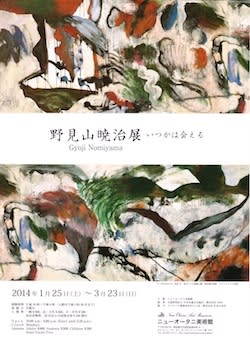
1920年に福岡で生まれた画家、野見山暁治。近年には2011年にブリヂストン美術館で一大個展を開催。長きにわたる画業の変遷と展開。その多様な絵画世界に感銘したものでした。
首都圏ではそれ以来となる美術館での個展です。そして今回の中心はステンドグラスの原画。都内では副都心線の明治神宮前駅に飾られた「いつかは会える」が知られているのではないでしょうか。他にもJR博多駅の「海の向こうから」(2011年)、また福岡空港国際線ターミナルの「そらの港」(2013)の原画を交える。主に野見山の近年の制作を紹介する内容でした。

野見山暁治「いつかは会える」2007年 東京メトロ副都心線・明治神宮前駅 ステンドグラス原画(部分)
さてまずは「いつかは会える」から。何やら物の怪の如くに跋扈する絵具の塊。飛び交いながら上下左右へと広がる。しかしながらそれらの合間にはどこか静けさに満ちた地平が奥へと伸びている。また黒い太線。鳥が羽を広げる姿のようにも見えます。心象風景でしょうか。様々な景色が混在していました。
なお本作ではステンドグラスの一部も展示されています。鮮やかに輝くステンドグラス。絵画と見比べてみる。当然ながら質感はまるで異なります。その辺も展示の見どころの一つかもしれません。
原画で最も新しいのが福岡空港の「そらの港」です。「いつかは会える」と参照してどうでしょうか。地におけるグレーとも白ともいえる色彩は強く塗りこめられる。より物質感の際立つ平面。赤や黄色、また紫の塊は、複雑怪奇、自ら意志をもって動くかのように形を作る。黄色に黒の太線もより激しく絡み合っている。絵画はより大胆にかつ自由に展開しています。
それにしても改めて作品を間近で見ると、表面に絵具を削り取ったような一種の傷があることが分かります。また塗り残し、さらには絵具を垂らしたような部分も。筆致は驚くほどに変幻自在です。
会場では最初期の「自画像」(芸大の卒業制作です。)や大戦前の静物画などもあわせて紹介されています。戦後、留学生として渡欧、その頃に描いた作品でしょうか。一枚の風景画「パンテオン」に惹かれました。細い線で幾何学状に組み立てられた建物群。中央にはドームも。空がピリピリと割れ始めています。
ニューオータニの手狭なスペース。出品は40点弱です。それでも年齢など感じさせない迫力の絵画群。思いの外に長居して見入りました。
 「目に見えるものー野見山暁治画文集/求龍堂」
「目に見えるものー野見山暁治画文集/求龍堂」
3月23日まで開催されています。
「野見山暁治展 いつかは会える」 ニューオータニ美術館
会期:1月25日(土)~3月23日(日)
休館:月曜日。
料金:一般800円、高・大生500円、小・中生300円。
*宿泊者無料、20名以上の団体は各100円割引。
時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで
住所:千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンコート6階
交通:東京メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅D出口より徒歩5分。東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線永田町駅7番出口より徒歩5分。
「野見山暁治展 いつかは会える」
1/25-3/23
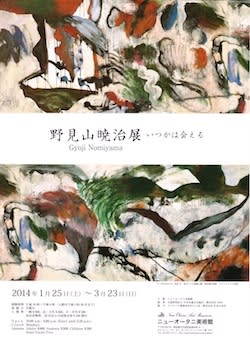
1920年に福岡で生まれた画家、野見山暁治。近年には2011年にブリヂストン美術館で一大個展を開催。長きにわたる画業の変遷と展開。その多様な絵画世界に感銘したものでした。
首都圏ではそれ以来となる美術館での個展です。そして今回の中心はステンドグラスの原画。都内では副都心線の明治神宮前駅に飾られた「いつかは会える」が知られているのではないでしょうか。他にもJR博多駅の「海の向こうから」(2011年)、また福岡空港国際線ターミナルの「そらの港」(2013)の原画を交える。主に野見山の近年の制作を紹介する内容でした。

野見山暁治「いつかは会える」2007年 東京メトロ副都心線・明治神宮前駅 ステンドグラス原画(部分)
さてまずは「いつかは会える」から。何やら物の怪の如くに跋扈する絵具の塊。飛び交いながら上下左右へと広がる。しかしながらそれらの合間にはどこか静けさに満ちた地平が奥へと伸びている。また黒い太線。鳥が羽を広げる姿のようにも見えます。心象風景でしょうか。様々な景色が混在していました。
なお本作ではステンドグラスの一部も展示されています。鮮やかに輝くステンドグラス。絵画と見比べてみる。当然ながら質感はまるで異なります。その辺も展示の見どころの一つかもしれません。
原画で最も新しいのが福岡空港の「そらの港」です。「いつかは会える」と参照してどうでしょうか。地におけるグレーとも白ともいえる色彩は強く塗りこめられる。より物質感の際立つ平面。赤や黄色、また紫の塊は、複雑怪奇、自ら意志をもって動くかのように形を作る。黄色に黒の太線もより激しく絡み合っている。絵画はより大胆にかつ自由に展開しています。
それにしても改めて作品を間近で見ると、表面に絵具を削り取ったような一種の傷があることが分かります。また塗り残し、さらには絵具を垂らしたような部分も。筆致は驚くほどに変幻自在です。
会場では最初期の「自画像」(芸大の卒業制作です。)や大戦前の静物画などもあわせて紹介されています。戦後、留学生として渡欧、その頃に描いた作品でしょうか。一枚の風景画「パンテオン」に惹かれました。細い線で幾何学状に組み立てられた建物群。中央にはドームも。空がピリピリと割れ始めています。
ニューオータニの手狭なスペース。出品は40点弱です。それでも年齢など感じさせない迫力の絵画群。思いの外に長居して見入りました。
 「目に見えるものー野見山暁治画文集/求龍堂」
「目に見えるものー野見山暁治画文集/求龍堂」3月23日まで開催されています。
「野見山暁治展 いつかは会える」 ニューオータニ美術館
会期:1月25日(土)~3月23日(日)
休館:月曜日。
料金:一般800円、高・大生500円、小・中生300円。
*宿泊者無料、20名以上の団体は各100円割引。
時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで
住所:千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンコート6階
交通:東京メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅D出口より徒歩5分。東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線永田町駅7番出口より徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 千葉市美術館
千葉市美術館
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」
1/25-3/2

千葉市美術館で開催中の「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」を見て来ました。
江戸の文化を象徴する浮世絵。もちろん描かれているのは当時の人々の生活。浮世絵をひも解くことで、彼の時代の風俗なり流行を知ることも出来ます。
ずばり本展のテーマは浮世絵が表したものです。盛り場や花見での宴席に夕涼み、または歌舞伎役者に看板娘。さらには子どもたちの遊ぶ姿から一転して彼方に望む富士の景色まで。主に8つのセクションから江戸の人々の美意識なり文化を探っていきます。

歌川広重「名所江戸百景 両国花火」 安政5(1858)年頃 東京芸術大学 *展示期間:1/25~2/6
まずはプロローグから。名所です。冒頭の師宣の「江戸雀」は最古の地誌書。江戸の名所が34箇所記されている。鍬形恵斎の「東都繁昌図巻」はどうでしょうか。飛鳥山の花見から日本橋まで。特に面白いのは日本橋の魚河岸です。行き来する商売人。そこには魚図鑑かと思うほどたくさんの魚が描かれています。

鳥文斎栄之「三幅神吉原通い図巻」(部分) 文化期(1804-1818)年頃 千葉市美術館
吉原へ進みましょう。鳥文斎栄之の「三幅神吉原通い図巻」は、恵比寿、大黒、福禄寿の三福神が吉原へ通うという物語を描いたもの。隅田川で小舟に乗り、しばらくして河をあがって吉原大門へ。その後はガラリと場面が変わっての大宴会。全長5~6mほどでしょうか。長い絵巻です。
メインストリートの仲之町の花見を描いたのは国貞、「桜下吉原仲之町賑之図」です。艶やかな着物に身を包んだ遊女が集う。桜は毎年植え替えていたというから驚きです。まさに享楽。吉原の賑わいを感じ取ることが出来ます。
さて江戸の盛り場、何も吉原だけではありません。例えば隅田川西岸の橘町に東岸の深川、さらには南の品川へ。そしてここで面白いのが盛り場によって遊女のファッションなり様式が異なっていることです。
例えば橘町、何と踊り子たちは芸がないことで有名だったとか。また目立つために二人連れで歩くという風習も。それに足元は低い履物が基本。少しだけ三味線を習ったような若い子が多かったそうです。

鳥居清長「当世遊里美人合 多通美」 天明(1781-89)前期 個人蔵
一方の深川は大人の女性です。下駄は厚底で黒地立てのスタイリッシュな羽織。例えば清長の「当世遊里美人合 多通美」。確かに渋い。ちなみに多通美とは江戸から見て辰巳の方角、つまり深川を表しています。
なおこの盛り場毎の遊女の様相、最新の千葉市美術館ニュース(69号)の「双子コーデ」というテキストに詳しく載っています。吉原でもよく描かれる二人連れの遊女の画、花魁や禿との関係。まさかそこに一定の様式なり傾向があったとは思いませんでした。

歌川国貞「七代目市川団十郎の矢の根五郎」 文政8(1825)年 成田山霊光館
歌舞伎も江戸の人々の楽しみの一つ。役者絵です。「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」は写楽のデビューとしても知られる名作。そして七代目の団十郎を描いた絵馬もお目見え。成田山の所蔵です。さらには八代目団十郎の有名なファンであったという老婆を描いた珍品も。また興味深いのは死絵です。ようは役者の死の追善のための作品ですが、うち国芳の「八代目市川団十郎の死絵」が異彩を放つ。横たわるのは巨大な団十郎。その周囲を女性たちが泣いて囲んでいる。言わば見立役者涅槃図です。ユーモアのある表現ではないでしょうか。
役者の姿を貼った団扇も展示されていました。ちなみにこれらは日用品であることから、団扇の状態で残っているのが珍しいとのこと。好きな役者の団扇を持って楽しんだという江戸の人々。現代人の感覚とそう変わらないのかもしれません。

喜多川歌麿「鞠と扇を持つ美人」 寛政8-9(1796-97)年頃 千葉市美術館
その他には評判の町娘を描いた美人大首絵なども展観。ラストは清親で明治に残る江戸の情緒を探る。また外国人の日本旅行紀の言葉が引用されているのもポイントです。彼らの見た日本の景色。そこから振り返って江戸を見知る。展示の視座は多角的でした。
またあえて触れておきたいのがキャプションです。千葉市美、いつもながらではありますが、今回も一点一点の作品に丁寧な解説がついています。浮世絵の背後や情景。より深く絵を味わうことが出来ました。

石井林響「霊泉ノ図」 明治38(1905)年頃 千葉市美術館
さて本展に続く所蔵作品展、「画人たちの1万時間~写生、下絵、粉本類を中心に」も驚くほどに充実。またある意味でマニアックです。こちらは新収蔵品から写生帖や下絵類を公開。幕府の御用絵師である麻布一本松狩野家の描いた下絵類から、千葉ゆかりの近代日本画家の石井林響のスケッチなど。そして何と言っても興味深いのは田中抱二に関する資料が出ていたことです。

「田中抱二関係資料」 江戸時代後期~明治時代前期 個人蔵(千葉市美術館寄託)
田中抱二とは抱一最晩年の弟子で同門の四天王とも称された人物。花鳥画などに秀作を残しています。資料は入門時の10代の作から晩年までの画史や縮図。いずれも抱二を先生と呼ぶ人物が整理したものだそうです。目を引くのは虫や花を描いた画冊や抱一の「絵手鑑」を写した画帖など。ちなみに抱一の画塾の雨華庵では一と六の付く日が稽古日だったとか。画人の制作や暮らしが垣間見えます。抱一ファンには嬉しい展示でした。
最後に展示替えの情報です。一部作品において入れ替えがあります。
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」出品リスト(PDF)
リピーター向けの割引制度もあります。その名も「ごひいき割引」。有料チケットを提示すると、会期中、2回目以降の観覧料が2割引となります。
それにしても偶然なのか江戸博では「大浮世絵」展(~3/2)が開催中。そちらは王道。浮世絵を通史で追うのに対し、ここ千葉では江戸の人々の具体的な生活を事細かに浮かび上がらせていく。確かに名品が揃うのは両国かもしれませんが、企画や構成では千葉の方が面白い。出品は200点超。絵馬、肉筆と盛りだくさんです。楽しめました。

鈴木春信「風流江戸八景 真乳山の暮雪」 明和5(1768)年頃 個人蔵
両国から小一時間ほど足を伸ばして千葉へ。あわせてご覧になっては如何でしょうか。
 「浮世絵図鑑:江戸文化の万華鏡/別冊太陽/平凡社」
「浮世絵図鑑:江戸文化の万華鏡/別冊太陽/平凡社」
3月2日まで開催されています。
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 千葉市美術館
会期:1月25日(土)~3月2日(日)
休館:2/3、2/10。
時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。
料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*ごひいき割引:本展チケット(有料)半券の提示で、会期中2回目以降の観覧料2割引。
住所:千葉市中央区中央3-10-8
交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」
1/25-3/2

千葉市美術館で開催中の「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」を見て来ました。
江戸の文化を象徴する浮世絵。もちろん描かれているのは当時の人々の生活。浮世絵をひも解くことで、彼の時代の風俗なり流行を知ることも出来ます。
ずばり本展のテーマは浮世絵が表したものです。盛り場や花見での宴席に夕涼み、または歌舞伎役者に看板娘。さらには子どもたちの遊ぶ姿から一転して彼方に望む富士の景色まで。主に8つのセクションから江戸の人々の美意識なり文化を探っていきます。

歌川広重「名所江戸百景 両国花火」 安政5(1858)年頃 東京芸術大学 *展示期間:1/25~2/6
まずはプロローグから。名所です。冒頭の師宣の「江戸雀」は最古の地誌書。江戸の名所が34箇所記されている。鍬形恵斎の「東都繁昌図巻」はどうでしょうか。飛鳥山の花見から日本橋まで。特に面白いのは日本橋の魚河岸です。行き来する商売人。そこには魚図鑑かと思うほどたくさんの魚が描かれています。

鳥文斎栄之「三幅神吉原通い図巻」(部分) 文化期(1804-1818)年頃 千葉市美術館
吉原へ進みましょう。鳥文斎栄之の「三幅神吉原通い図巻」は、恵比寿、大黒、福禄寿の三福神が吉原へ通うという物語を描いたもの。隅田川で小舟に乗り、しばらくして河をあがって吉原大門へ。その後はガラリと場面が変わっての大宴会。全長5~6mほどでしょうか。長い絵巻です。
メインストリートの仲之町の花見を描いたのは国貞、「桜下吉原仲之町賑之図」です。艶やかな着物に身を包んだ遊女が集う。桜は毎年植え替えていたというから驚きです。まさに享楽。吉原の賑わいを感じ取ることが出来ます。
さて江戸の盛り場、何も吉原だけではありません。例えば隅田川西岸の橘町に東岸の深川、さらには南の品川へ。そしてここで面白いのが盛り場によって遊女のファッションなり様式が異なっていることです。
例えば橘町、何と踊り子たちは芸がないことで有名だったとか。また目立つために二人連れで歩くという風習も。それに足元は低い履物が基本。少しだけ三味線を習ったような若い子が多かったそうです。

鳥居清長「当世遊里美人合 多通美」 天明(1781-89)前期 個人蔵
一方の深川は大人の女性です。下駄は厚底で黒地立てのスタイリッシュな羽織。例えば清長の「当世遊里美人合 多通美」。確かに渋い。ちなみに多通美とは江戸から見て辰巳の方角、つまり深川を表しています。
なおこの盛り場毎の遊女の様相、最新の千葉市美術館ニュース(69号)の「双子コーデ」というテキストに詳しく載っています。吉原でもよく描かれる二人連れの遊女の画、花魁や禿との関係。まさかそこに一定の様式なり傾向があったとは思いませんでした。

歌川国貞「七代目市川団十郎の矢の根五郎」 文政8(1825)年 成田山霊光館
歌舞伎も江戸の人々の楽しみの一つ。役者絵です。「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」は写楽のデビューとしても知られる名作。そして七代目の団十郎を描いた絵馬もお目見え。成田山の所蔵です。さらには八代目団十郎の有名なファンであったという老婆を描いた珍品も。また興味深いのは死絵です。ようは役者の死の追善のための作品ですが、うち国芳の「八代目市川団十郎の死絵」が異彩を放つ。横たわるのは巨大な団十郎。その周囲を女性たちが泣いて囲んでいる。言わば見立役者涅槃図です。ユーモアのある表現ではないでしょうか。
役者の姿を貼った団扇も展示されていました。ちなみにこれらは日用品であることから、団扇の状態で残っているのが珍しいとのこと。好きな役者の団扇を持って楽しんだという江戸の人々。現代人の感覚とそう変わらないのかもしれません。

喜多川歌麿「鞠と扇を持つ美人」 寛政8-9(1796-97)年頃 千葉市美術館
その他には評判の町娘を描いた美人大首絵なども展観。ラストは清親で明治に残る江戸の情緒を探る。また外国人の日本旅行紀の言葉が引用されているのもポイントです。彼らの見た日本の景色。そこから振り返って江戸を見知る。展示の視座は多角的でした。
またあえて触れておきたいのがキャプションです。千葉市美、いつもながらではありますが、今回も一点一点の作品に丁寧な解説がついています。浮世絵の背後や情景。より深く絵を味わうことが出来ました。

石井林響「霊泉ノ図」 明治38(1905)年頃 千葉市美術館
さて本展に続く所蔵作品展、「画人たちの1万時間~写生、下絵、粉本類を中心に」も驚くほどに充実。またある意味でマニアックです。こちらは新収蔵品から写生帖や下絵類を公開。幕府の御用絵師である麻布一本松狩野家の描いた下絵類から、千葉ゆかりの近代日本画家の石井林響のスケッチなど。そして何と言っても興味深いのは田中抱二に関する資料が出ていたことです。

「田中抱二関係資料」 江戸時代後期~明治時代前期 個人蔵(千葉市美術館寄託)
田中抱二とは抱一最晩年の弟子で同門の四天王とも称された人物。花鳥画などに秀作を残しています。資料は入門時の10代の作から晩年までの画史や縮図。いずれも抱二を先生と呼ぶ人物が整理したものだそうです。目を引くのは虫や花を描いた画冊や抱一の「絵手鑑」を写した画帖など。ちなみに抱一の画塾の雨華庵では一と六の付く日が稽古日だったとか。画人の制作や暮らしが垣間見えます。抱一ファンには嬉しい展示でした。
最後に展示替えの情報です。一部作品において入れ替えがあります。
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」出品リスト(PDF)
リピーター向けの割引制度もあります。その名も「ごひいき割引」。有料チケットを提示すると、会期中、2回目以降の観覧料が2割引となります。
それにしても偶然なのか江戸博では「大浮世絵」展(~3/2)が開催中。そちらは王道。浮世絵を通史で追うのに対し、ここ千葉では江戸の人々の具体的な生活を事細かに浮かび上がらせていく。確かに名品が揃うのは両国かもしれませんが、企画や構成では千葉の方が面白い。出品は200点超。絵馬、肉筆と盛りだくさんです。楽しめました。

鈴木春信「風流江戸八景 真乳山の暮雪」 明和5(1768)年頃 個人蔵
両国から小一時間ほど足を伸ばして千葉へ。あわせてご覧になっては如何でしょうか。
 「浮世絵図鑑:江戸文化の万華鏡/別冊太陽/平凡社」
「浮世絵図鑑:江戸文化の万華鏡/別冊太陽/平凡社」3月2日まで開催されています。
「江戸の面影 浮世絵は何を描いてきたのか」 千葉市美術館
会期:1月25日(土)~3月2日(日)
休館:2/3、2/10。
時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。
料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*ごひいき割引:本展チケット(有料)半券の提示で、会期中2回目以降の観覧料2割引。
住所:千葉市中央区中央3-10-8
交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」 原美術館
原美術館
「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」
1/11-3/30

原美術館で開催中のミヒャエル・ボレマンス個展、「アドバンテージ」のプレスプレビューに参加してきました。
1963年にベルギーに生まれたミヒャエル・ボレマンス。当初は写真表現を手がけながらも、90年代半ばに絵画に転向。以来、同国を代表する美術作家として活動し続けている。
ベラスケスやマネなどに倣った画風はクラシカル。一方でシュールな側面も持ちえています。静けさと謎めき。不思議に惹き付けるものがあります。

「The Trick」(トリック)他 カンヴァスに油彩 2002年 個人蔵
そのボレマンス、制作数に対して完成作が少ないことなどから、なかなかまとまって展示をする機会がなかったとのこと。かつて日本では横浜トリエンナーレ(2011年)に出品があったものの、美術館での個展は一度もありませんでした。
ここに実現。舞台は原美術館です。作品は38点。2点は国立国際美術館の所蔵作品、他は全て個人蔵。また近年取り組み始めた映像も含みます。作品は寡黙。さらには大きさが5号ほどと比較的小さめ。必ずしも空間を埋め尽くすような展示でありません。しかしながら小さな箱との相性は良い。作家の世界観を知るには遜色のない内容となっていました。
さてその箱との関係。そもそも本展は作家が以前、原美術館を訪ねたことからはじまります。建物に強く惹かれたというボレマンス、自ら希望、構想して今回の個展の開催にこぎ着けました。

「Dragonplant」(ドラゴンプラント) カンヴァスに油彩 2003年
「作品は多すぎず、少な過ぎてもいけない。」(ボレマンス)確かに余白も多い会場。作品同士の距離感がまた意味ありげでもある。ボレマンスの主に描くポートレート。ただ何か俯いていたり、何かを手にとって見ていたり、また何かを持って作業している。そしてその何かは明示されない。具象的でありながら、作品の背景なり物語は曖昧になっている。あくまでも解釈は観る側の一人一人に投げかけられています。

「Red Hand, Green Hand(2)」(赤い手、緑の手 2) カンヴァスに油彩 2010年 個人蔵
かつての絵画の役割は見たことを再現することだった。しかし今、それは例えば写真がやっている。つまり絵画は解放され、ある意味で自由になった。世界に溢れたイマジネーションを具現化する試み。それを絵画は瞬時に出来ない。あくまでも絵画はスローである。時間がかかる。だからこその面白さがある。そうしたことをボレマンスは述べています。

「The Trees」(木々) カンヴァスに油彩 2008年 国立国際美術館
それにしてもボレマンスの筆致、思いの外に軽やかです。キャンバス地は白ではなくベージュ。そこに油絵具を薄く伸ばしてモチーフを象る。確かに人物は静止してますが、流れるようなストロークの由縁でしょうか。映像的とも言える動きがある。先に挙げたベラスケスかマネと言えば後者。そしてシュールというのは時に腕なりが消えているような描写があること。また作業している手の先も同じく見えなくなる。地とモチーフとが上下に行き来しています。

「The Marvel」(驚異) カンヴァスに油彩 2001年 個人蔵
「たちの悪い幽霊のようにあなたに付きまとうもの。それが作品である。」(ボレマンス)。一見、美しき絵画に潜んだ不穏な気配。神秘的でもある。ベルギーの象徴派も思い起こしました。

「The Bread」(パン) 19インチLCDスクリーン、HDヴィデオ(ループ)、AP 2012年
なおボレマンス、現在、東京・京橋のギャラリー小柳でも個展を開催中です。こちらは全て新作での展示です。(原美術館のボレマンス展は2001年~2013年の作品で構成。)

「ミヒャエル・ボレマンス展」@ギャラリー小柳(1/11~3/1)
まずは一度、小柳にてボレマンス画の雰囲気を味わい、その上で改めて原美術館でまとめて見るのも良いかもしれません。

「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」会場風景
3月30日までの開催です。おすすめします。
「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」 原美術館(@haramuseum)
会期:1月11日(土)~3月30日(日)
休館:月曜日。(但し祝日にあたる1月13日は開館)、1月14日。
時間:11:00~17:00。*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで
料金: 一般1000円、大高生700円、小中生500円
*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。
*20名以上の団体は1人100円引。
住所:品川区北品川4-7-25
交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」
1/11-3/30

原美術館で開催中のミヒャエル・ボレマンス個展、「アドバンテージ」のプレスプレビューに参加してきました。
1963年にベルギーに生まれたミヒャエル・ボレマンス。当初は写真表現を手がけながらも、90年代半ばに絵画に転向。以来、同国を代表する美術作家として活動し続けている。
ベラスケスやマネなどに倣った画風はクラシカル。一方でシュールな側面も持ちえています。静けさと謎めき。不思議に惹き付けるものがあります。

「The Trick」(トリック)他 カンヴァスに油彩 2002年 個人蔵
そのボレマンス、制作数に対して完成作が少ないことなどから、なかなかまとまって展示をする機会がなかったとのこと。かつて日本では横浜トリエンナーレ(2011年)に出品があったものの、美術館での個展は一度もありませんでした。
ここに実現。舞台は原美術館です。作品は38点。2点は国立国際美術館の所蔵作品、他は全て個人蔵。また近年取り組み始めた映像も含みます。作品は寡黙。さらには大きさが5号ほどと比較的小さめ。必ずしも空間を埋め尽くすような展示でありません。しかしながら小さな箱との相性は良い。作家の世界観を知るには遜色のない内容となっていました。
さてその箱との関係。そもそも本展は作家が以前、原美術館を訪ねたことからはじまります。建物に強く惹かれたというボレマンス、自ら希望、構想して今回の個展の開催にこぎ着けました。

「Dragonplant」(ドラゴンプラント) カンヴァスに油彩 2003年
「作品は多すぎず、少な過ぎてもいけない。」(ボレマンス)確かに余白も多い会場。作品同士の距離感がまた意味ありげでもある。ボレマンスの主に描くポートレート。ただ何か俯いていたり、何かを手にとって見ていたり、また何かを持って作業している。そしてその何かは明示されない。具象的でありながら、作品の背景なり物語は曖昧になっている。あくまでも解釈は観る側の一人一人に投げかけられています。

「Red Hand, Green Hand(2)」(赤い手、緑の手 2) カンヴァスに油彩 2010年 個人蔵
かつての絵画の役割は見たことを再現することだった。しかし今、それは例えば写真がやっている。つまり絵画は解放され、ある意味で自由になった。世界に溢れたイマジネーションを具現化する試み。それを絵画は瞬時に出来ない。あくまでも絵画はスローである。時間がかかる。だからこその面白さがある。そうしたことをボレマンスは述べています。

「The Trees」(木々) カンヴァスに油彩 2008年 国立国際美術館
それにしてもボレマンスの筆致、思いの外に軽やかです。キャンバス地は白ではなくベージュ。そこに油絵具を薄く伸ばしてモチーフを象る。確かに人物は静止してますが、流れるようなストロークの由縁でしょうか。映像的とも言える動きがある。先に挙げたベラスケスかマネと言えば後者。そしてシュールというのは時に腕なりが消えているような描写があること。また作業している手の先も同じく見えなくなる。地とモチーフとが上下に行き来しています。

「The Marvel」(驚異) カンヴァスに油彩 2001年 個人蔵
「たちの悪い幽霊のようにあなたに付きまとうもの。それが作品である。」(ボレマンス)。一見、美しき絵画に潜んだ不穏な気配。神秘的でもある。ベルギーの象徴派も思い起こしました。

「The Bread」(パン) 19インチLCDスクリーン、HDヴィデオ(ループ)、AP 2012年
なおボレマンス、現在、東京・京橋のギャラリー小柳でも個展を開催中です。こちらは全て新作での展示です。(原美術館のボレマンス展は2001年~2013年の作品で構成。)

「ミヒャエル・ボレマンス展」@ギャラリー小柳(1/11~3/1)
まずは一度、小柳にてボレマンス画の雰囲気を味わい、その上で改めて原美術館でまとめて見るのも良いかもしれません。

「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」会場風景
3月30日までの開催です。おすすめします。
「ミヒャエル・ボレマンス:アドバンテージ」 原美術館(@haramuseum)
会期:1月11日(土)~3月30日(日)
休館:月曜日。(但し祝日にあたる1月13日は開館)、1月14日。
時間:11:00~17:00。*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで
料金: 一般1000円、大高生700円、小中生500円
*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。
*20名以上の団体は1人100円引。
住所:品川区北品川4-7-25
交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |









