都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術
加島美術
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」
3/18〜4/9
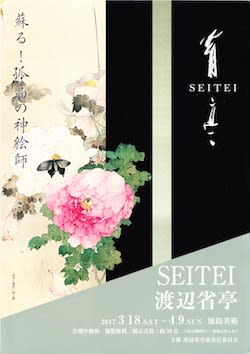
幕末の江戸に生まれ、パリ万国博覧会では銀牌も獲得した日本画家、渡辺省亭(1851〜1918)。「わたなべせいてい」の呼び方しかり、必ずしも現代では良く知られているとは言えません。
それもそのはずです。今までの回顧展はゼロ。まとめて画業を俯瞰する機会すら一度もありませんでした。
今年で没後100年。まさに省亭再発見です。初めての回顧展が京橋の加島美術にて開催されています。
省亭は幼い頃から絵が好きでした。まず学んだのは菊池容斎です。そして柴田是真にも私淑。19歳でイギリスのエディンバラ公に贈呈された画帖の一部を描きました。22歳で独立します。その後、「日本最初の貿易会社である起立工商会社に就職」(解説より)し、主に七宝の工芸図案を制作しました。さらに第一回内国勧業博覧会では三等を受賞。若い頃から画才を発揮しました。
明治11年、起立工商会社の社員として渡欧します。日本画家として初めてフランスの地を踏みました。約2年から3年間ほど滞在します。パリでは印象派関連のサークルに参加し、ドガやマネらの前で日本画の制作も実演しました。鳥の絵をドガに謹呈した逸話も残っているそうです。西洋のジャポニスムにも影響を与えました。
赤坂離宮迎賓館の「花鳥の間」の七宝の下絵を手がけたのも省亭です。七宝は大家の涛川惣助が制作。今でも同広間に飾られています。

「雪月花図」 個人蔵
省亭の画風を捉える言葉として挙げられるのが「洒脱」(解説より)でしたが。「雪月花図」はどうでしょうか。三幅対の掛け軸です。右に桜。鳥がとまっています。中央が月です。上には満月が照り、下方には菖蒲が花をつけています。そして左が雪。冬の光景でしょう。雀が群れていました。構図に無駄もありません。

「秋草図」
「秋草図」からは琳派を連想しました。大きな満月を背景に草が縦方向に伸びています。茎や葉は幾分絡み合っています。線は素早い。抱一のようです。流麗とも言えるかもしれません。

「あざみ図」 個人蔵
「あざみ図」も美しい。刺々しいあざみが紅色の花を咲かせています。大きな蜂が飛んでいました。あざみの周囲に刷毛でなぞったような筆触があることに気がつきました。影、ないし茂みを表しているのでしょうか。写実性の高いあざみとは対比的です。かなり大胆でした。

「萩にうさぎの図」
写実といえば「萩にうさぎの図」も忘れられません。見るべきはうさぎです。とりわけその毛並みと目に要注目です。絵具を滲ませては立体感を出す一方、細い筆を重ねては毛を表現しています。そして目です。潤んでいて光があります。視線も強い。まるで意思を持っているかのようでした。省亭は動物画の名手でもあります。

右:「牡丹に蝶の図」 個人蔵
傑作と呼んで過言ではありません。「牡丹に蝶の図」に魅せられました。白と紅の牡丹です。蜜を吸いに蝶がとまっています。色は極めて瑞々しい。ニュアンスに富んでいます。

「牡丹に蝶の図」(拡大) 個人蔵
花びらは湿り気を帯びているのでしょうか。柔らかな質感さえ伝わってきました。省亭はパリ滞在経験もあり、西洋の技法にも通じていました。立体感、ないし光の表現は西洋由来と言えるのかもしれません。それを日本画に落とし込むことに成功しています。

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭展」会場風景
出展は約30点。全て個人のコレクションです。会場はギャラリーのスペースですが、1階と2階の全フロアを利用。思いの外に数もあります。また露出での展示でした。ガラスケースはありません。
なお現在、「渡辺省亭展」にあわせ、都内各地の博物館、美術館でも省亭の作品が公開中です。
[都内で公開中の省亭(関連)作品]
・東京国立博物館(本館18室):3月7日(火)〜4月16日(日)
「雪中群鶏」、「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」(12枚)
・迎賓館赤坂離宮(花鳥の間):一般公開開催日
「渡辺省亭下絵による濤川惣助の七宝焼」(30枚)
・山種美術館:2月16日(木)〜4月16日(日)
「葡萄」、「月に千鳥」
・松岡美術館:3月22日(水)〜5月14日(日)
「藤花游鯉之図」他4点
・根津美術館:4月12日(水)〜5月14日(日)
「不忍蓮」、「枯野牧童図」
私も早速、東京国立博物館の展示を見てきました。会場は本館の1階18室です。「雪中群鶏」、及び「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」が展示されていました。

「雪中群鶏」 明治26(1893)年 東京国立博物館
「雪中群鶏」はシカゴ万国博覧会への出品作です。車の上で鶏が群れています。いわゆる「洋風表現」(解説より)ということでしょうか。まるで印象派を思わせるような色遣いが目を引きます。

「赤坂離宮花鳥図画帖」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
そしてもう1つが迎賓館の七宝下絵こと「赤坂離宮花鳥図画帖」です。かの「花鳥の間」の装飾です。これがまた極めて写実的でした。

「赤坂離宮花鳥図画帖(鷦鷯に紫陽花)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
例えば「鷦鷯に紫陽花」です。紫陽花は二輪。日本古来のガクアジサイでしょうか。がくの部分も一枚一枚、丁寧に塗り分けています。葉の所々が茶色に変色していました。鋭い観察眼です。鳥の毛並みも細かい。陰影もあります。

「赤坂離宮花鳥図画帖(駒鳥に藤)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
「駒鳥に藤」も魅惑的です。房はやや立体的です。駒鳥は反り返るように枝にとまっています。蔓の部分の線や色にも澱みがありません。高い画力を伺い知ることが出来ました。

「赤坂離宮花鳥図画帖(黒鶫に木瓜・山桜)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
ほか雉が見を屈めて歩く「雉に蕨」や白い桜に紅色の木瓜をあわせた「黒鶫に木瓜・山桜」も美しい。かの離宮に飾るための下絵です。よほど力が入っていたのでしょうか。いずれも質が高い。どの作品も隙がありませんでした。
さて最後に加島美術での展示替えの情報です。前後期で作品の入れ替えがあります。
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」
前期:3月18日(土)〜3月29日(水)
後期:3月30日(木)〜4月9日(日)
省亭自身、いわゆる画壇に属さず、弟子も取らなかったそうです。また晩年は展覧会の出品もやめてしまいます。それ故に歴史に埋もれてしまったのかもしれません。
 「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」
「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」
「わたなべせいてい」の名、しかと覚えました。「神」とするには議論あるやもしれませんが、また一人、惹かれる絵師と出会うことが出来ました。
1点を除いて撮影が可能でした。但し事前に受付の方に断っておくのが良さそうです。

4月9日までの開催です。まずはおすすめします。
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術(@Kashima_Arts)
会期:3月18日(土)〜4月9日(日)
休館:会期中無休。
時間:10:00~18:00
料金:無料。
住所:中央区京橋3-3-2
交通:東京メトロ銀座線京橋駅出口3より徒歩1分。地下鉄有楽町線銀座一丁目駅出口7より徒歩2分。JR線東京駅八重洲南口より徒歩6分。
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」
3/18〜4/9
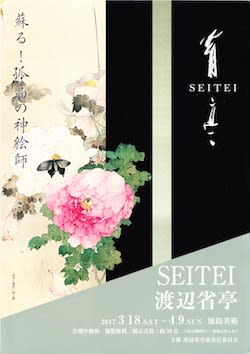
幕末の江戸に生まれ、パリ万国博覧会では銀牌も獲得した日本画家、渡辺省亭(1851〜1918)。「わたなべせいてい」の呼び方しかり、必ずしも現代では良く知られているとは言えません。
それもそのはずです。今までの回顧展はゼロ。まとめて画業を俯瞰する機会すら一度もありませんでした。
今年で没後100年。まさに省亭再発見です。初めての回顧展が京橋の加島美術にて開催されています。
省亭は幼い頃から絵が好きでした。まず学んだのは菊池容斎です。そして柴田是真にも私淑。19歳でイギリスのエディンバラ公に贈呈された画帖の一部を描きました。22歳で独立します。その後、「日本最初の貿易会社である起立工商会社に就職」(解説より)し、主に七宝の工芸図案を制作しました。さらに第一回内国勧業博覧会では三等を受賞。若い頃から画才を発揮しました。
明治11年、起立工商会社の社員として渡欧します。日本画家として初めてフランスの地を踏みました。約2年から3年間ほど滞在します。パリでは印象派関連のサークルに参加し、ドガやマネらの前で日本画の制作も実演しました。鳥の絵をドガに謹呈した逸話も残っているそうです。西洋のジャポニスムにも影響を与えました。
赤坂離宮迎賓館の「花鳥の間」の七宝の下絵を手がけたのも省亭です。七宝は大家の涛川惣助が制作。今でも同広間に飾られています。

「雪月花図」 個人蔵
省亭の画風を捉える言葉として挙げられるのが「洒脱」(解説より)でしたが。「雪月花図」はどうでしょうか。三幅対の掛け軸です。右に桜。鳥がとまっています。中央が月です。上には満月が照り、下方には菖蒲が花をつけています。そして左が雪。冬の光景でしょう。雀が群れていました。構図に無駄もありません。

「秋草図」
「秋草図」からは琳派を連想しました。大きな満月を背景に草が縦方向に伸びています。茎や葉は幾分絡み合っています。線は素早い。抱一のようです。流麗とも言えるかもしれません。

「あざみ図」 個人蔵
「あざみ図」も美しい。刺々しいあざみが紅色の花を咲かせています。大きな蜂が飛んでいました。あざみの周囲に刷毛でなぞったような筆触があることに気がつきました。影、ないし茂みを表しているのでしょうか。写実性の高いあざみとは対比的です。かなり大胆でした。

「萩にうさぎの図」
写実といえば「萩にうさぎの図」も忘れられません。見るべきはうさぎです。とりわけその毛並みと目に要注目です。絵具を滲ませては立体感を出す一方、細い筆を重ねては毛を表現しています。そして目です。潤んでいて光があります。視線も強い。まるで意思を持っているかのようでした。省亭は動物画の名手でもあります。

右:「牡丹に蝶の図」 個人蔵
傑作と呼んで過言ではありません。「牡丹に蝶の図」に魅せられました。白と紅の牡丹です。蜜を吸いに蝶がとまっています。色は極めて瑞々しい。ニュアンスに富んでいます。

「牡丹に蝶の図」(拡大) 個人蔵
花びらは湿り気を帯びているのでしょうか。柔らかな質感さえ伝わってきました。省亭はパリ滞在経験もあり、西洋の技法にも通じていました。立体感、ないし光の表現は西洋由来と言えるのかもしれません。それを日本画に落とし込むことに成功しています。

「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭展」会場風景
出展は約30点。全て個人のコレクションです。会場はギャラリーのスペースですが、1階と2階の全フロアを利用。思いの外に数もあります。また露出での展示でした。ガラスケースはありません。
本日から「美しい人びと」後期の展示が始まりました。同じ展示室5に渡辺省亭5点も並びました。皆さまのご来館をお待ちしております。#松岡美術館 #渡辺省亭 https://t.co/TBglybaPYD pic.twitter.com/p4J6QMHRcz
— 松岡美術館 (@matsu_bi) 2017年3月22日
なお現在、「渡辺省亭展」にあわせ、都内各地の博物館、美術館でも省亭の作品が公開中です。
[都内で公開中の省亭(関連)作品]
・東京国立博物館(本館18室):3月7日(火)〜4月16日(日)
「雪中群鶏」、「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」(12枚)
・迎賓館赤坂離宮(花鳥の間):一般公開開催日
「渡辺省亭下絵による濤川惣助の七宝焼」(30枚)
・山種美術館:2月16日(木)〜4月16日(日)
「葡萄」、「月に千鳥」
・松岡美術館:3月22日(水)〜5月14日(日)
「藤花游鯉之図」他4点
・根津美術館:4月12日(水)〜5月14日(日)
「不忍蓮」、「枯野牧童図」
私も早速、東京国立博物館の展示を見てきました。会場は本館の1階18室です。「雪中群鶏」、及び「迎賓館赤坂離宮七宝下絵」が展示されていました。

「雪中群鶏」 明治26(1893)年 東京国立博物館
「雪中群鶏」はシカゴ万国博覧会への出品作です。車の上で鶏が群れています。いわゆる「洋風表現」(解説より)ということでしょうか。まるで印象派を思わせるような色遣いが目を引きます。

「赤坂離宮花鳥図画帖」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
そしてもう1つが迎賓館の七宝下絵こと「赤坂離宮花鳥図画帖」です。かの「花鳥の間」の装飾です。これがまた極めて写実的でした。

「赤坂離宮花鳥図画帖(鷦鷯に紫陽花)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
例えば「鷦鷯に紫陽花」です。紫陽花は二輪。日本古来のガクアジサイでしょうか。がくの部分も一枚一枚、丁寧に塗り分けています。葉の所々が茶色に変色していました。鋭い観察眼です。鳥の毛並みも細かい。陰影もあります。

「赤坂離宮花鳥図画帖(駒鳥に藤)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
「駒鳥に藤」も魅惑的です。房はやや立体的です。駒鳥は反り返るように枝にとまっています。蔓の部分の線や色にも澱みがありません。高い画力を伺い知ることが出来ました。

「赤坂離宮花鳥図画帖(黒鶫に木瓜・山桜)」 明治39(1906)年頃 東京国立博物館
ほか雉が見を屈めて歩く「雉に蕨」や白い桜に紅色の木瓜をあわせた「黒鶫に木瓜・山桜」も美しい。かの離宮に飾るための下絵です。よほど力が入っていたのでしょうか。いずれも質が高い。どの作品も隙がありませんでした。
さて最後に加島美術での展示替えの情報です。前後期で作品の入れ替えがあります。
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」
前期:3月18日(土)〜3月29日(水)
後期:3月30日(木)〜4月9日(日)
省亭自身、いわゆる画壇に属さず、弟子も取らなかったそうです。また晩年は展覧会の出品もやめてしまいます。それ故に歴史に埋もれてしまったのかもしれません。
 「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」
「渡辺省亭:花鳥画の孤高なる輝き/東京美術」「わたなべせいてい」の名、しかと覚えました。「神」とするには議論あるやもしれませんが、また一人、惹かれる絵師と出会うことが出来ました。
1点を除いて撮影が可能でした。但し事前に受付の方に断っておくのが良さそうです。

4月9日までの開催です。まずはおすすめします。
「蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」 加島美術(@Kashima_Arts)
会期:3月18日(土)〜4月9日(日)
休館:会期中無休。
時間:10:00~18:00
料金:無料。
住所:中央区京橋3-3-2
交通:東京メトロ銀座線京橋駅出口3より徒歩1分。地下鉄有楽町線銀座一丁目駅出口7より徒歩2分。JR線東京駅八重洲南口より徒歩6分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









