都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「動物絵画の250年」 府中市美術館
府中市美術館
「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」
3/7-5/6
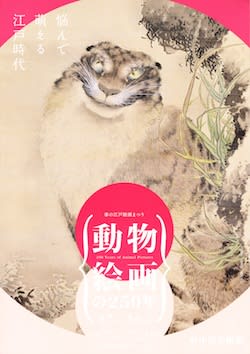
府中市美術館で開催中の「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」を見てきました。
毎年春、府中恒例の「江戸絵画まつり」。今回のテーマは「動物絵画」です。
ところでこの「動物絵画」、府中市美の展覧会を常にチェックされている方にとっては、「一度見た。」と思われるかもしれません。
実際、同美術館では2007年に「動物絵画の100年」展を開催。その時は年代を1751年から1850年の100年間に絞り、江戸絵画における動物モチーフの作品を紹介していました。

島田元旦「玉兎図」 鳥取・景福寺 *前期展示
今回は続編、250年間拡大バージョンです。ほぼ江戸時代の大半を網羅しています。

黒田稲皐「群鯉図」 鳥取県立博物館 *後期展示
出品は166点。ただし会期中に一度、全て入れ替わります。
[動物絵画の250年 展示構成]
1.想像を具現する
2.動物の姿や動きと、「絵」の面白さ
3.心と動物
さて動物を描いた絵といえども、モチーフからして多様。一言で括れるものでもありません。
トップバッターは鳥でした。森徹山の「群鳥図」です。山を望む水辺の鳥たち、一体何羽いるのでしょうか。雁が飛来し、鶴が舞い降り、鴨が集う。もはや数えられないくらいに無数に群れています。
現実にこのような光景が起こり得るのでしょうか。狩野元信印の「鷲猿図」です。鷲と猿、上に乗るのが鷲です。大きな脚で猿の頭を押さえつけています。猿はもう降参したと言わんばかりにへばっていました。絵師の逞しい想像力あってからこその作品と言えるかもしれません。
こうした絵師の想像力を喚起させる作品として挙げられるのが虎のモチーフです。というのも当時、実物の虎を見る機会はなく、中国絵画などの粉本を手本にして描いたものが殆ど。よって忠実に写そうとしたものあり、一方で半ばデフォルメ、好き勝手に描いたものと多様です。その意味では各絵師の個性を見比べることが出来ます。
伊年印の「虎図」はどうでしょうか。真ん丸顔の虎がスクっと立ち上がってこちらを見ています。どことなく飄々としていて親しみやすくもある。何度か見たことのある作品ですが、その度にどうしてもドラえもんを思い出してしまいます。

片山楊谷「竹虎図屏風」 個人蔵 *後期展示
片山楊谷の「竹虎図屏風」が強烈です。六曲一双の大画面、左には一頭、右には二頭の虎が描かれています。喧嘩をしているのでしょうか。互いに身を竦めては隙を伺っています。そして何よりも目に付くのは虎の毛、これがフサフサというよりもトゲトゲしい。まるで針山のような線が連なっています。
さらに構図も大胆です。よく見ると一頭の虎の尾が画面を一度飛び出して、再び戻っていることが分かります。ど迫力の虎図。見知らぬ絵師でしたが、思いがけないほど印象に残りました。
動物の擬人化もポイントの一つです。分かりやすいのが上田公長の「狐の嫁入り図屏風」ではないでしょうか。ずばり狐の嫁入りのモチーフですが、狐がそのまま袴羽織を着て婚礼の列を作っています。また擬人化ならぬ、動物を文字化した国芳の「猫の当字 ふぐ」も面白いもの。ふぐのふの字の一部に実際のフグを当てています。国芳の才知が伺えました。
対象を的確に見定めようとする写実性、真に迫った動物絵画も少なくありません。
例えば応挙の「粟鶉図」です。ともかく二羽の鶉の描写が精緻極まりない。羽の一枚一枚が肉眼では確認出来ないほど細かく描かれています。
また迫真の変則バージョンと言えるのが司馬江漢の「猫と蝶図」です。と言うのも蝶こそ写実、本物と見間違うほど丁寧に表していますが、猫だけは何故か太く大雑把な描線で捉えています。別の絵師の手によるのではないかと思ってしまうほどでした。
面白い絵とは、絵師のアイデアによるところが大きいのかもしれません。柴田是真の「滝図」です。いわゆる描表装、枠をはみ出し、青い地の表具のてっぺんから滝が落ちています。そして滝壺も画面の外、水を跳ねては渦を巻いています。また滝の中央には鯉が上を向いて泳いでいました。
とすると思い付くのが鯉の滝登りです。ただここでは必ずしもそうではないのかもしれません。なぜなら鯉の先に何やら虫が飛んでいるからです。つまり鯉の餌とりの様子なのでしょうか。実際にこれほど鯉が垂直に跳ねるとは思えませんが、滝登りの主題とかけた鯉の躍動感のある姿、さすがに一捻りあると感心しました。
こうした水の生き物を捉えた作品としては建部凌岱の「海錯図屏風」もインパクトがあります。

建部凌岱「海錯図屏風」 青森県立図書館 *後期展示
海とあるように、海中の魚たちを描いた屏風絵です。エイやタコ、サメにアンコウらしき深海魚まで描かれていますが、ともかく方向もモチーフもバラバラ。妙なほど統一感がありません。
蘆雪の「遠望松鶴図」にも目を奪われました。中央には松が一本、ぽつんとあるだけです。右から小さな鶴が飛んで来ていますが、それがキャプションにもあるようにまるでハンググライダーです。簡素な描線で最低限のモチーフのみを描いていますが、言わば余白の芸術ならぬ深い味わいが感じられます。
若冲も数点出ていました。中でも面白いのが「河豚と蛙の相撲図」、文字通り河豚と蛙が取っ組み合っている作品です。

伊藤若冲「河豚と蛙の相撲図」 個人蔵 *後期展示
手前が河豚、奥が蛙。蛙がちょうど河豚を掴んでいる姿が描かれていますが、よく見ると河豚は擬人化されることなく、手も足もない。というよりも鰭が手の代わりになっています。これこそ手も足も出ない状態ではないでしょうか。何ともユーモラス。もはや勝負になりません。

長沢蘆雪「紅葉狗子図」 敦賀市立博物館 *後期展示
ラストは小さき動物を愛でる慈しみの精神。かの可愛らしい応挙犬が3点、そしてさらに緩く、もはやゆるキャラと化した蘆雪の子犬で幕を閉じます。

円山応挙「麦穂子犬図」 個人蔵 *前期展示
府中市美の江戸絵画展、一概に言えないかもしれませんが、他の美術館に比べて個人蔵が多いのも特徴です。ゆえにいわゆる名作云々というよりも、見慣れないような珍品にこそ見るべき点があるのではないでしょうか。知らない絵師がわんさか出てきます。その意味でも発見の少なくない展覧会でした。
なお作品は前後期を区切っての完全入れ替え制です。(出品リスト)出遅れた私はついうっかり前期を見逃してしまいました。
前期:3月7日(土)~4月5日(日)
後期:4月7日(火)~5月6日(水)
既に会期は後期です。以降の展示替えはありません。

長沢蘆雪「亀図」 個人蔵 *後期展示
また展覧会のレクチャーがいずれも会期末に行われます。そちらにあわせて出かけるのも良いのではないでしょうか。
[展覧会講座]
5月2日(土)「江戸の動物絵画 その多彩さを生んだもの」 講師:金子信久(当館学芸員)
5月4日(月)「動物絵画 外国と日本」 講師:音ゆみ子(当館学芸員)
*いずれも午後2時から。講座室にて無料。
 「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」
「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」
5月6日まで開催されています。
「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」 府中市美術館
会期:3月7日(土)~5月6日(水)
*前期:3月7日(土)~4月5日(日)、後期:4月7日(火)~5月6日(水)
休館:月曜(但し5/4を除く)。
時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)
料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。
*( )内は20名以上の団体料金。
*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。
*有料チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。
場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内
交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。
「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」
3/7-5/6
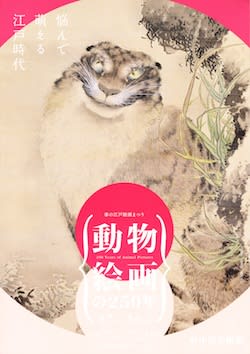
府中市美術館で開催中の「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」を見てきました。
毎年春、府中恒例の「江戸絵画まつり」。今回のテーマは「動物絵画」です。
ところでこの「動物絵画」、府中市美の展覧会を常にチェックされている方にとっては、「一度見た。」と思われるかもしれません。
実際、同美術館では2007年に「動物絵画の100年」展を開催。その時は年代を1751年から1850年の100年間に絞り、江戸絵画における動物モチーフの作品を紹介していました。

島田元旦「玉兎図」 鳥取・景福寺 *前期展示
今回は続編、250年間拡大バージョンです。ほぼ江戸時代の大半を網羅しています。

黒田稲皐「群鯉図」 鳥取県立博物館 *後期展示
出品は166点。ただし会期中に一度、全て入れ替わります。
[動物絵画の250年 展示構成]
1.想像を具現する
2.動物の姿や動きと、「絵」の面白さ
3.心と動物
さて動物を描いた絵といえども、モチーフからして多様。一言で括れるものでもありません。
トップバッターは鳥でした。森徹山の「群鳥図」です。山を望む水辺の鳥たち、一体何羽いるのでしょうか。雁が飛来し、鶴が舞い降り、鴨が集う。もはや数えられないくらいに無数に群れています。
現実にこのような光景が起こり得るのでしょうか。狩野元信印の「鷲猿図」です。鷲と猿、上に乗るのが鷲です。大きな脚で猿の頭を押さえつけています。猿はもう降参したと言わんばかりにへばっていました。絵師の逞しい想像力あってからこその作品と言えるかもしれません。
こうした絵師の想像力を喚起させる作品として挙げられるのが虎のモチーフです。というのも当時、実物の虎を見る機会はなく、中国絵画などの粉本を手本にして描いたものが殆ど。よって忠実に写そうとしたものあり、一方で半ばデフォルメ、好き勝手に描いたものと多様です。その意味では各絵師の個性を見比べることが出来ます。
伊年印の「虎図」はどうでしょうか。真ん丸顔の虎がスクっと立ち上がってこちらを見ています。どことなく飄々としていて親しみやすくもある。何度か見たことのある作品ですが、その度にどうしてもドラえもんを思い出してしまいます。

片山楊谷「竹虎図屏風」 個人蔵 *後期展示
片山楊谷の「竹虎図屏風」が強烈です。六曲一双の大画面、左には一頭、右には二頭の虎が描かれています。喧嘩をしているのでしょうか。互いに身を竦めては隙を伺っています。そして何よりも目に付くのは虎の毛、これがフサフサというよりもトゲトゲしい。まるで針山のような線が連なっています。
さらに構図も大胆です。よく見ると一頭の虎の尾が画面を一度飛び出して、再び戻っていることが分かります。ど迫力の虎図。見知らぬ絵師でしたが、思いがけないほど印象に残りました。
動物の擬人化もポイントの一つです。分かりやすいのが上田公長の「狐の嫁入り図屏風」ではないでしょうか。ずばり狐の嫁入りのモチーフですが、狐がそのまま袴羽織を着て婚礼の列を作っています。また擬人化ならぬ、動物を文字化した国芳の「猫の当字 ふぐ」も面白いもの。ふぐのふの字の一部に実際のフグを当てています。国芳の才知が伺えました。
対象を的確に見定めようとする写実性、真に迫った動物絵画も少なくありません。
例えば応挙の「粟鶉図」です。ともかく二羽の鶉の描写が精緻極まりない。羽の一枚一枚が肉眼では確認出来ないほど細かく描かれています。
また迫真の変則バージョンと言えるのが司馬江漢の「猫と蝶図」です。と言うのも蝶こそ写実、本物と見間違うほど丁寧に表していますが、猫だけは何故か太く大雑把な描線で捉えています。別の絵師の手によるのではないかと思ってしまうほどでした。
面白い絵とは、絵師のアイデアによるところが大きいのかもしれません。柴田是真の「滝図」です。いわゆる描表装、枠をはみ出し、青い地の表具のてっぺんから滝が落ちています。そして滝壺も画面の外、水を跳ねては渦を巻いています。また滝の中央には鯉が上を向いて泳いでいました。
とすると思い付くのが鯉の滝登りです。ただここでは必ずしもそうではないのかもしれません。なぜなら鯉の先に何やら虫が飛んでいるからです。つまり鯉の餌とりの様子なのでしょうか。実際にこれほど鯉が垂直に跳ねるとは思えませんが、滝登りの主題とかけた鯉の躍動感のある姿、さすがに一捻りあると感心しました。
こうした水の生き物を捉えた作品としては建部凌岱の「海錯図屏風」もインパクトがあります。

建部凌岱「海錯図屏風」 青森県立図書館 *後期展示
海とあるように、海中の魚たちを描いた屏風絵です。エイやタコ、サメにアンコウらしき深海魚まで描かれていますが、ともかく方向もモチーフもバラバラ。妙なほど統一感がありません。
蘆雪の「遠望松鶴図」にも目を奪われました。中央には松が一本、ぽつんとあるだけです。右から小さな鶴が飛んで来ていますが、それがキャプションにもあるようにまるでハンググライダーです。簡素な描線で最低限のモチーフのみを描いていますが、言わば余白の芸術ならぬ深い味わいが感じられます。
若冲も数点出ていました。中でも面白いのが「河豚と蛙の相撲図」、文字通り河豚と蛙が取っ組み合っている作品です。

伊藤若冲「河豚と蛙の相撲図」 個人蔵 *後期展示
手前が河豚、奥が蛙。蛙がちょうど河豚を掴んでいる姿が描かれていますが、よく見ると河豚は擬人化されることなく、手も足もない。というよりも鰭が手の代わりになっています。これこそ手も足も出ない状態ではないでしょうか。何ともユーモラス。もはや勝負になりません。

長沢蘆雪「紅葉狗子図」 敦賀市立博物館 *後期展示
ラストは小さき動物を愛でる慈しみの精神。かの可愛らしい応挙犬が3点、そしてさらに緩く、もはやゆるキャラと化した蘆雪の子犬で幕を閉じます。

円山応挙「麦穂子犬図」 個人蔵 *前期展示
府中市美の江戸絵画展、一概に言えないかもしれませんが、他の美術館に比べて個人蔵が多いのも特徴です。ゆえにいわゆる名作云々というよりも、見慣れないような珍品にこそ見るべき点があるのではないでしょうか。知らない絵師がわんさか出てきます。その意味でも発見の少なくない展覧会でした。
なお作品は前後期を区切っての完全入れ替え制です。(出品リスト)出遅れた私はついうっかり前期を見逃してしまいました。
前期:3月7日(土)~4月5日(日)
後期:4月7日(火)~5月6日(水)
既に会期は後期です。以降の展示替えはありません。

長沢蘆雪「亀図」 個人蔵 *後期展示
また展覧会のレクチャーがいずれも会期末に行われます。そちらにあわせて出かけるのも良いのではないでしょうか。
[展覧会講座]
5月2日(土)「江戸の動物絵画 その多彩さを生んだもの」 講師:金子信久(当館学芸員)
5月4日(月)「動物絵画 外国と日本」 講師:音ゆみ子(当館学芸員)
*いずれも午後2時から。講座室にて無料。
 「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」
「江戸かわいい動物 たのしい日本美術/講談社」5月6日まで開催されています。
「春の江戸絵画まつり 動物絵画の250年」 府中市美術館
会期:3月7日(土)~5月6日(水)
*前期:3月7日(土)~4月5日(日)、後期:4月7日(火)~5月6日(水)
休館:月曜(但し5/4を除く)。
時間:10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)
料金:一般700(560)円、大学・高校生350(280)円、中学・小学生150(120)円。
*( )内は20名以上の団体料金。
*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。
*有料チケットには2度目の観覧料が半額になる割引券付き。
場所:府中市浅間町1-3 都立府中の森公園内
交通:京王線東府中駅から徒歩15分。京王線府中駅からちゅうバス(多磨町行き)「府中市美術館」下車。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









