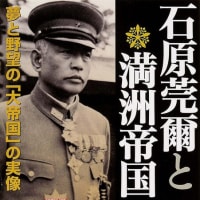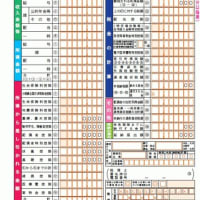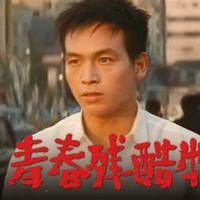1960年代の日本映画全盛時代には、正月映画があった。
昔は、サラリーマン以外、頻繁に休暇は取れなかったので、正月とゴールデンウィークは、映画界のかき入れ時だった。
映画各社は、スター総動員の大作を公開したものだった。
松竹の1962年の『今年の恋』など典型で、岡田茉莉子と吉田輝雄が主役で、除夜の鐘を突いて新年の幸福を祈るという正月らしいベストの作品だった。

この年、東宝は、黒澤明、三船敏郎の『椿三十郎』、大映は山本富士子の『女と三悪人』、日活は小林旭の『渡り鳥北に帰る』、東映は『ひばり・チエミの弥次喜多道中』と中村錦之助の『若き日の次郎長』といった具合だった。
このように賑やかな作品が並んだが、新東宝のみは、『赤と黒の花びら』という地味な作品だった。前年には、『狂熱の果て』と意欲的な作品が公開されていたのだが。
こうした正月映画のあり方は、1970年代以降なくなったと思う。
その原因は、日本映画のあり方が変化したこともあるが、洋画封切りで、『タワーリング・インフルノ』に始まる、一斉公開・ブロック・バスター方式公開の普及もあったと思う。
これを邦画で応用したのは、角川映画で、短期にテレビ広告をはじめ広告を集中的にやって一斉に公開してヒットを狙うものだった。
最後まで、「正月映画」を維持していたのは、松竹の渥美清、山田洋次の『男はつらいよ』シリーズだったが、これも渥美清の死で、終了になってしまった。