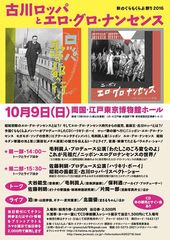私は、2007年9月30日に彼女が、阿佐ヶ谷ラピュタに出た時、つぎのように書いた。

『まり子自叙伝・花咲く星座』
おそらく今の50代以下の人は、女優の宮城まり子を見たことがないに違いない。だが、昭和20から30年代、彼女は、日本の映画、テレビ、舞台、歌謡曲で最も有名な女性の一人だった。レコードでは『毒消しゃいらんかねぇ』が最大のヒット曲だが、『ガード下の靴磨き』も有名である。
彼女の歌の特徴としては、音程が正確で大変パンチがありながら、一種独特の哀愁味があるところにある。その魅力、人を引き付ける力は、美空ひばりに匹敵するものがあった。ただ、ひばりと違うのは、宮城まり子にはクールな知的な味わいがあったことで、これは彼女の弟が作曲家で(映画では池部良の兄に変えられている)、音楽監督だったことによるのだろう。そして、言うまでもなく彼女の生涯の伴侶だったのは、作家吉行淳之介である。吉行は、勿論妻がありながら、宮城に会い「私の人生感のすべてが変わってしまった」と書いている。今日映画を見て、宮城が人を引き込む物凄い能力があることが分かった。
戦前、貧困の中で大阪で養女に出されたまり子は、女学校進学が叶わぬと、歌手になることを夢見る。父の坂本武は、事業に失敗するとまり子を中心に兄池部と旅回りの一座を作り、戦時下の九州を巡業する。 戸畑での公演中、一座の中心夫婦が逃げ、仕方なくまり子は、すべての演目を一人でこなし、観客の圧倒的声援を受ける。ここから、まり子の独演公演が大成功する。戦後、上京して、浅草、日劇、さらにはビクターの専属、ついには『極楽島物語』で東京宝塚劇場のミュージカルに主演する。その間に、近所の中学生久保明との淡い恋と戦後の失恋など、大分フィクションが挟まれているらしいが、宮城まり子の一代記を菊田一夫が大変ドラマチックに、そして上品にまとめている。元は菊田の作・演出でヒットした舞台劇である。 宮城まり子の芸質は、現在の女優で言えば吉田日出子に似ていると思う。本質的に一人芸であり、一種とぼけたスットンキョウなところが。現在で言えば、「天然ボケ」と言うのだろうが、本当に彼女は演技ではなく天性として嫌味なくぼけられるのである。
雨の中ラピュタには、監督松林宗恵氏と共に宮城まり子もきていた。少し太られたようだが、その童女のような容姿と話し方は全く変わらず。
終了後のトークでは、映画は舞台の合間の夜間撮影で、完成するとすぐに次の舞台だったので、映画は一度も見たことがなく、今日初めて見た、とは驚いた。そのくらい当時の大スターは忙しかったのである。彼女が、すべての芸能活動をやめ、障害児施設「ねむの木学園」に専心するようになったのは、弟が交通事故で亡くなったことが大きな理由で、当初は「姉弟学園(きょうだい学園)」と名付けたかったのだそうだ。
戦後の芸能に多大な足跡を残された女優のご冥福をお祈りする。