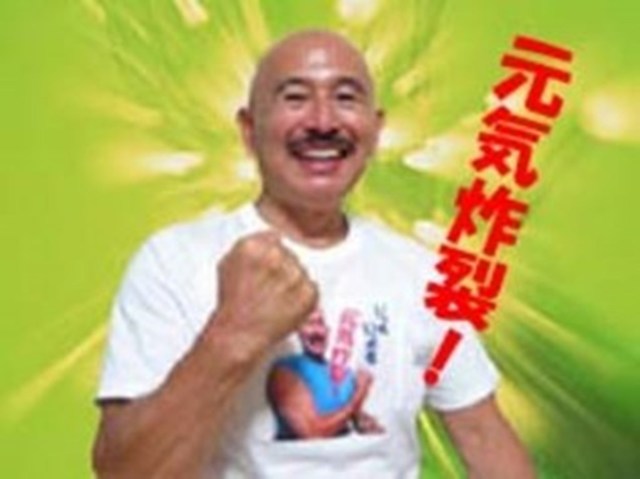朝ドラ「らんまん」を観て思うこと、感じることなどがたくさんあるが、
登場人物たちの言葉や行動からその思いや感情が伝わってくる
シーンもも多く、それを想像させる仕草などにも関心が高く、連日
興味を惹かれる。
[らんまん]には関心を持って注意注目するシーンも多いが
万太郎や田辺教授の手紙を見たり書いたりするシーンで
ふと気づいた(思いだした)ことがある。
それは・・・あのローマ字で書かれた手紙が私たちが慣れ親しんだ
「筆記体」であることなのだ。(あの時代なら当然なのかもしれないが)
私たちはあのドラマの中の文章と同じようにノートに自分の名前を
書く時なども筆記体だったし、活字体を使うよりは筆記体が
多かったと思う。
私たちが若いころは街中の喫茶店や宣伝等の文字の英語もそうだったし、
映画(洋画)のラストの「THE END」「END」や「FIN」も活字体よりは
筆記体が圧倒的に多かったと思う。(エンドロールのキャストなども・・・)
いま、テレビのクイズ番組などで自分も解答しようとする時に
活字体も分かってはいるのだが速く書こうとするとつい、筆記体に
なってしまうことがある。
速さだけではなく、ローマ字の筆記体を見たり書いたりすると何故か
心が落ち着くような気持になるのだ。
・・と言ってももちろん活字体を否定したりするわけではない。
私たちが中学生の頃は筆記体を学び、よく練習した記憶があるので
懐かしく親近感のようなものを感じるのだ。
そういう懐かしい思い出も含めて「らんまん」の中の綺麗な筆記体の
文字を見る度に、現在の子供たちが使わないことに寂しさ(?)も感じ、
その懐かしい筆記体を学校では学ばなくなったのはなぜか?・・・・
そしてそれはいつの頃からか?・・・と関心を持ったのだ。
今から20年以上も前・・・
「学習指導要領」とやらで「生徒の学習負担に配慮」したうえで
教えるものとされ、「必ず習うもの」から「余裕があったら習う」に
変わったという。
とかく問題が多かったとされる「ゆとり教育」で授業数が減り、
筆記体を教える公立中学校は激減したそうで、その後「脱ゆとり」への
方向転換で授業数は増加した後も筆記体教育の方針は変わらず、
現在でも習わない子どもが多いとのこと。
簡単に表すと「中学校で筆記体を習ったのは昭和生まれ」
「習っていないのは平成生まれ」という図式になるようだ。
そしてそれはこんなところにも・・・
リットル、メートルなどの表記に現在は活字体が使われるように
なったようだ。
平成でも早いうちに生まれた人は「リットルなどの単位で筆記体に
触れた世代」、それ以降は「筆記体を習わず、リットルも活字体で
書く世代」ということに。
小文字のアルファベットの筆記体を習わず知らないため筆記体の
小文字のエルを文字として認識せず「リットル専用の特殊な記号」と
思っている人も多いようだ。
こうして「らんまん」のシーンは思わぬ思い出を呼び覚ましてくれたり、
疑問に関するヒントを与えてくれたりもしていると思うと
ドラマ以外の楽しさにも繋がっているのだ。
筆記体でアルファベットの大文字・小文字を書いてみた
AからZまで筆記体で書いてみた