トマス・ピンチョン『スロー・ラーナー』(ちくま文庫、志村正雄訳)
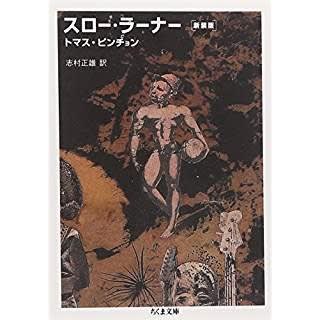
『重力の虹』など、現代アメリカ文学史上に聳える3つの傑作長編を発表後、十余年の沈黙の後に、天才作家自身がまとめた初期短篇集。「謎の巨匠」と呼ばれてきたピンチョンが自らの作家生活を回顧する序文を付した話題作。ポップ・カルチャーと熱力学、情報理論とスパイ小説が交錯する、楽しく驚異にみちた世界。(内容案内より)
◎ちょっと難解だけれど
トマス・ピンチョンは、謎につつまれたアメリカの小説家です。1937年生まれですから、もうすぐ80歳になろうとしています。
処女作「小雨(スモール・レイン)」を発表したのは大学生のときです。ピンチョンのくわしい経歴は不明です。写真も撮らせませんし、文学賞の授賞式にも姿を見せません。したがって半世紀以上も、正体不明のままなのです。彼の履歴でわかっていることは、コーネル大学物理学部に入学し、途中海軍に入り、ふたたび今度は英文学科に戻っていることくらいです。
ピンチョンは世界中で非常に高い評価をうけ、日本にも根強いファンがいます。かくいう私も脳みそを撹拌されながら、好んでピンチョン作品を読んでいます。最近、新潮社から「トマス・ピンチョン全小説」という全集が刊行されました。
ピンチョンは、日本に何度かきているようです。来日するなり、山手線を5周したなどというエピソードが残されています(出典は忘れました)。ピンチョンを最初に読んだのは、『競売ナンバー49の叫び』(筑摩書房)でした。いまはちくま文庫になっていますが、当時はサンリオ文庫(絶版)しかなく、図書館で借りて読みました。
『スロー・ラーナー』というタイトルは、「のろまな子」という意味です。ピンチョンは1962年(25歳)のときに、実質的な文壇デビューともいえる、『V』(全2巻、図書刊行会)を発表しています。『スロー・ラーナー』には『V』発表前後に書かれた、処女作「小雨」をふくめた5つの短編が収載されています。
『スロー・ラーナー』をはじめて読んだときは、とにかく難解で何度も立ち往生しました。ところが、ちくま文庫で読んだときは、すんなりと作品に入れました。訳者は志村正雄と同じなのですが、黄ばんだ本と新刊のちがいが影響しているのでしょうか。
ピンチョンの作品は、さまざなま形容詞で評価されています。「破戒的」「不条理」「混沌」「野放図」「脱線」「博学」「繊細」「ユーモア」……。
ピンチョンの作品には、骨格がありません。ピンチョンの気まぐれな運転につき合う、くらいの軽い気持ちでページをくくらなければなりません。ちくま文庫の再読で、やっとピンチョンのクセが飲みこめました。頑固で移り気な著者の運転に、慣れてきたのです。現在、昨日、15年前、現在、明日……。時空間を遊泳しながら、こんな作家は日本にいないよなと思いました。舞台もコロコロ変化します。考えごとをしながら活字を追っていると、いつの間にかとんでもない場所にいたりします。船酔いに似た感覚になります。
◎『スロー・ラーナー』は初の短編集
『スロー・ラーナー』は有名な大作『重力の虹』(初出1973年、「トマス・ピンチョン全小説集」上下巻)が発表されてから、11年ぶりの新刊として話題になりました。ピンチョン作品には他の短編がないので、本書は格好のドアオープナーとなるでしょう。ただし本書もやや難解です。
『スロー・ラーナー』の冒頭には、「スロー・ラーナー(のろまな子)序」が掲載されています。若いころの自作を自虐的に語る掌篇ですが、私は腹を抱えて笑いました。どんな作家も自分のデビュー作や初期作に遭遇すると、赤面するか目を背けてしまいます。ピンチョンは堂々と辛らつな口調で、ののしりつづけたのです。
読者はまず「序」で驚かされます。こんなふうに書かれています。
――以下の短篇を再読してのぼくの最初の反応はイヤコイツハ参ッタで、詳説すべからざる肉体的徴候がそれにともなった。考えなおして、何とか全面的に書きなおせないものかと思った。(中略)いまやぼくは、その当時のぼくであった青年作家に関して、ある次元の明晰さに到達したふりをしている。というのが、この男をぼくの人生から締め出してすましているわけにも行かないのだ。しかし何らかの、今のところは未開発の科学技術を通じて、彼に今日出会うとしたら、何と安らいだ気持で彼に金を貸してやったり、それどころではない、通りへ出て行ってビールを飲みながら昔の話をしたりもすることだろう。(「序」より)
つづいて、こんな文章が展開されます。
――どんなに思いやりの深い読者に対しても、以下の作品にはどこかにそうとう退屈な部分があり、少年っぽくもあり不良っぽくもあると警告しておのが公正というものだろう。同時に、ぼくの望むぎりぎりのところは、以下の作品がときどき、うねぼれの強い、間抜けな、思慮の足りないものになるにしても、そうした欠点をそのままにしておいてなお、駆け出しの小説が当然含んでいる諸問題の例として、また年少の作家にとって避けたほうがよい実際例への戒めとして、役には立つだろう。(「序」より)
「序」の引用だけで、本稿は埋まってしまいました。すこしテンポをあげます。
片岡義男が以前ブログに書いていました。彼はデビュー作のころの自分を、主題にして書いてみたかったとのことです。片岡義男は、大のピンチョン崇拝者です。ピンチョンに『神曲』(ダンテ作)を書かせてみたいと思うほどですから、ピンチョンにたいしては相当いれこんでいます。
収載作について、簡単に紹介しておきます。ストーリーをたどる意味はあまりないのですが、流れだけは示しておきたいと思います。
「小雨」
ピンチョンの処女作。主人公・リヴィアンは陸軍の通信兵。大学を卒業し、みずから志願したのです。彼は気力というものが欠落している若者です。彼の唯一の楽しみは、休暇のことだけです。ある日彼は、ハリケーンに襲われた村へと、救助活動に出向かなければならなくなります。
この作品には当初、「少量の雨」というタイトルがついていました。それを「小雨」と改めた経緯については、文庫の「訳者あとがき」に詳しく書かれています。
「低地」
主人公・デニスは、妻とともにロング・アイランドで暮らしています。ロング・アイランドは、ピンチョンが生まれ育ったところです。フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(新潮文庫)にもこの舞台は登場しています。
ゴミ屋とドロボウをしている友人が訪ねてきます。激昂した妻はデニスを追い出し、彼は友人とともにゴミ集積所で寝泊りをすることになります。寓話的なこの作品のキーワードは「ゴミ」「見捨てられた人間」など、いわゆる落ちこぼれです。いきなり六本木のライブハウスに、連れこまれたような混乱におちいりました。
「エントロピー」
「広辞苑」の意味を転記しようと思いましたが、エントロピーは難しすぎます。またこの作品は「低地」よりもっと難しいものでした。文庫本「訳者のあとがき」を読んでも、頭のなかに点灯したハテナマークが消えません。紹介するのはパスさせてください。
「秘密裡に」
時代背景はよくわかりませんでした。でもこの作品は好きです。主人公・ポーペンタインは英国のスパイです。彼は友人のグッドフェロウといっしょに列車に乗りこみます。テロを防ぐためです。ドイツ側のスパイとくりひろげられる展開は、ピンチョンの長編作品と通じるところがあります。この作品はのちに、『V』の第3章に組みこまれることとなります。
「秘密のインテグレーション」
この作品は、『V』上梓後に書かれています。だから厳密にいうと、初期作品にはなりません。私はピンチョン『スロー・ラーナー』を読むときは、最初にこの作品を選ぶべきだと思っています。もっともわかりやすい作品です。
主人公は天才少年グローヴァ。自宅の地下で、不思議な実験をくりかえしています。ほかの登場人物は4人のこども、1匹の犬、イボをもった隣りのこども、黒人、アルコール中毒だったこども……。彼らはとんでもない計画を進行中です。
『スロー・ラーナー』の「秘密のインテグレーション」のなか(P202)に、「ドラえもん」を連想させられる記述があります。主人公のグローヴァが、作品のなかで読んでいる本がそれです。
――グローヴァは『トム・スウィフトと魔法のカメラ』を読んでいた。ヴィクター・アプルトンの書いたものだ。アプルトンが『トム・スウィフト』を書いたのは、1910年から1941年にかけて。シリーズ作品の主人公・トムは次々と社会のため、国のために発明品を生み出す。(本文と注釈の一部を引用)
残念ながら、この作品は見あたりません。したがって断言はできませんが、「ドラえもん」の著者が、原文で読んでいた可能性は否定できません。
◎『競売ナンバー49の叫び』も魅力的なのですが
『競売ナンバー49の叫び』がちくま文庫になりましたので、こちらを紹介しようかなとも思いました。しかしピンチョンへの入口としては、短篇集の方がふさわしいと判断しました。
応援演説を紹介させていただきます。
――ピンチョンにも若くて生意気で、カッコつけたがる時期があって、憧れている作家がいて、そりゃあピンチョンだからまだ学部生の頃に書いた作品だって驚くくらい巧みなんだけど、でも、やっぱり背伸びしている姿は丸見えで、処女長篇『V』に圧倒され、『競売ナンバー49の叫び』はそれと比べれば愉しく読めたとはいうものの、自分には一生ピンチョンを十全に堪能することはできないのかもしれないと怯えていたわたしは、初期作品ばかり収めた『スロー・ラーナー』を読むことで、気を取り直すことができたのだ。(豊崎由美『ガタスタ屋の矜恃・場外乱闘篇』(本の雑誌社)
『競売ナンバー49の叫び』には本文とは別に、約50ページの「競売ナンバー49の叫び・解注」がつけられています。本文にちりばめられた、天文学、歴史学、民俗学などたくさんの「○○学」の知識が、そこで解説されているわけです。ただし本文には「注釈あり」の記号がつけられておらず、「競売ナンバー49の叫び・解注」は独立した作品としても読まなければなりません。
青木淳悟のデビュー作『四十日と四十夜のメルヘン』(新潮文庫)は話題になりました。朝日新聞2012年5月16日の「顔」欄(実際には三島由紀夫賞を受賞した『私のいない高校』を伝える記事なのですが)に、こんな文章がありました。
――「ピンチョンが現れた!」早大在学中の2003年、「四十日と四十夜のメルヘン」でデビューし、米国の作家になぞらえ高く評価された。あれから9年。気鋭の小説家に贈られる賞を射止めた。(新聞より)
青木淳悟『私のいない高校』(講談社)は、文庫化されたら「山本藤光の文庫で読む500+α」で紹介させていただくつもりです。それにしても「ピンチョン現れた!」は、書き過ぎではないでしょうか。もっともピンチョンの初期短篇よりは、ずっとわかりやすいのですが。
(山本藤光:2010.03.11初稿、2018.02.21改稿)
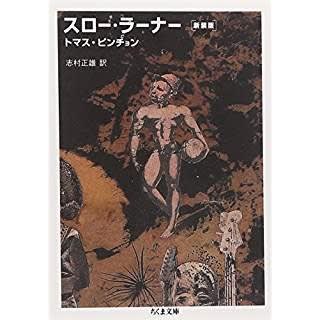
『重力の虹』など、現代アメリカ文学史上に聳える3つの傑作長編を発表後、十余年の沈黙の後に、天才作家自身がまとめた初期短篇集。「謎の巨匠」と呼ばれてきたピンチョンが自らの作家生活を回顧する序文を付した話題作。ポップ・カルチャーと熱力学、情報理論とスパイ小説が交錯する、楽しく驚異にみちた世界。(内容案内より)
◎ちょっと難解だけれど
トマス・ピンチョンは、謎につつまれたアメリカの小説家です。1937年生まれですから、もうすぐ80歳になろうとしています。
処女作「小雨(スモール・レイン)」を発表したのは大学生のときです。ピンチョンのくわしい経歴は不明です。写真も撮らせませんし、文学賞の授賞式にも姿を見せません。したがって半世紀以上も、正体不明のままなのです。彼の履歴でわかっていることは、コーネル大学物理学部に入学し、途中海軍に入り、ふたたび今度は英文学科に戻っていることくらいです。
ピンチョンは世界中で非常に高い評価をうけ、日本にも根強いファンがいます。かくいう私も脳みそを撹拌されながら、好んでピンチョン作品を読んでいます。最近、新潮社から「トマス・ピンチョン全小説」という全集が刊行されました。
ピンチョンは、日本に何度かきているようです。来日するなり、山手線を5周したなどというエピソードが残されています(出典は忘れました)。ピンチョンを最初に読んだのは、『競売ナンバー49の叫び』(筑摩書房)でした。いまはちくま文庫になっていますが、当時はサンリオ文庫(絶版)しかなく、図書館で借りて読みました。
『スロー・ラーナー』というタイトルは、「のろまな子」という意味です。ピンチョンは1962年(25歳)のときに、実質的な文壇デビューともいえる、『V』(全2巻、図書刊行会)を発表しています。『スロー・ラーナー』には『V』発表前後に書かれた、処女作「小雨」をふくめた5つの短編が収載されています。
『スロー・ラーナー』をはじめて読んだときは、とにかく難解で何度も立ち往生しました。ところが、ちくま文庫で読んだときは、すんなりと作品に入れました。訳者は志村正雄と同じなのですが、黄ばんだ本と新刊のちがいが影響しているのでしょうか。
ピンチョンの作品は、さまざなま形容詞で評価されています。「破戒的」「不条理」「混沌」「野放図」「脱線」「博学」「繊細」「ユーモア」……。
ピンチョンの作品には、骨格がありません。ピンチョンの気まぐれな運転につき合う、くらいの軽い気持ちでページをくくらなければなりません。ちくま文庫の再読で、やっとピンチョンのクセが飲みこめました。頑固で移り気な著者の運転に、慣れてきたのです。現在、昨日、15年前、現在、明日……。時空間を遊泳しながら、こんな作家は日本にいないよなと思いました。舞台もコロコロ変化します。考えごとをしながら活字を追っていると、いつの間にかとんでもない場所にいたりします。船酔いに似た感覚になります。
◎『スロー・ラーナー』は初の短編集
『スロー・ラーナー』は有名な大作『重力の虹』(初出1973年、「トマス・ピンチョン全小説集」上下巻)が発表されてから、11年ぶりの新刊として話題になりました。ピンチョン作品には他の短編がないので、本書は格好のドアオープナーとなるでしょう。ただし本書もやや難解です。
『スロー・ラーナー』の冒頭には、「スロー・ラーナー(のろまな子)序」が掲載されています。若いころの自作を自虐的に語る掌篇ですが、私は腹を抱えて笑いました。どんな作家も自分のデビュー作や初期作に遭遇すると、赤面するか目を背けてしまいます。ピンチョンは堂々と辛らつな口調で、ののしりつづけたのです。
読者はまず「序」で驚かされます。こんなふうに書かれています。
――以下の短篇を再読してのぼくの最初の反応はイヤコイツハ参ッタで、詳説すべからざる肉体的徴候がそれにともなった。考えなおして、何とか全面的に書きなおせないものかと思った。(中略)いまやぼくは、その当時のぼくであった青年作家に関して、ある次元の明晰さに到達したふりをしている。というのが、この男をぼくの人生から締め出してすましているわけにも行かないのだ。しかし何らかの、今のところは未開発の科学技術を通じて、彼に今日出会うとしたら、何と安らいだ気持で彼に金を貸してやったり、それどころではない、通りへ出て行ってビールを飲みながら昔の話をしたりもすることだろう。(「序」より)
つづいて、こんな文章が展開されます。
――どんなに思いやりの深い読者に対しても、以下の作品にはどこかにそうとう退屈な部分があり、少年っぽくもあり不良っぽくもあると警告しておのが公正というものだろう。同時に、ぼくの望むぎりぎりのところは、以下の作品がときどき、うねぼれの強い、間抜けな、思慮の足りないものになるにしても、そうした欠点をそのままにしておいてなお、駆け出しの小説が当然含んでいる諸問題の例として、また年少の作家にとって避けたほうがよい実際例への戒めとして、役には立つだろう。(「序」より)
「序」の引用だけで、本稿は埋まってしまいました。すこしテンポをあげます。
片岡義男が以前ブログに書いていました。彼はデビュー作のころの自分を、主題にして書いてみたかったとのことです。片岡義男は、大のピンチョン崇拝者です。ピンチョンに『神曲』(ダンテ作)を書かせてみたいと思うほどですから、ピンチョンにたいしては相当いれこんでいます。
収載作について、簡単に紹介しておきます。ストーリーをたどる意味はあまりないのですが、流れだけは示しておきたいと思います。
「小雨」
ピンチョンの処女作。主人公・リヴィアンは陸軍の通信兵。大学を卒業し、みずから志願したのです。彼は気力というものが欠落している若者です。彼の唯一の楽しみは、休暇のことだけです。ある日彼は、ハリケーンに襲われた村へと、救助活動に出向かなければならなくなります。
この作品には当初、「少量の雨」というタイトルがついていました。それを「小雨」と改めた経緯については、文庫の「訳者あとがき」に詳しく書かれています。
「低地」
主人公・デニスは、妻とともにロング・アイランドで暮らしています。ロング・アイランドは、ピンチョンが生まれ育ったところです。フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(新潮文庫)にもこの舞台は登場しています。
ゴミ屋とドロボウをしている友人が訪ねてきます。激昂した妻はデニスを追い出し、彼は友人とともにゴミ集積所で寝泊りをすることになります。寓話的なこの作品のキーワードは「ゴミ」「見捨てられた人間」など、いわゆる落ちこぼれです。いきなり六本木のライブハウスに、連れこまれたような混乱におちいりました。
「エントロピー」
「広辞苑」の意味を転記しようと思いましたが、エントロピーは難しすぎます。またこの作品は「低地」よりもっと難しいものでした。文庫本「訳者のあとがき」を読んでも、頭のなかに点灯したハテナマークが消えません。紹介するのはパスさせてください。
「秘密裡に」
時代背景はよくわかりませんでした。でもこの作品は好きです。主人公・ポーペンタインは英国のスパイです。彼は友人のグッドフェロウといっしょに列車に乗りこみます。テロを防ぐためです。ドイツ側のスパイとくりひろげられる展開は、ピンチョンの長編作品と通じるところがあります。この作品はのちに、『V』の第3章に組みこまれることとなります。
「秘密のインテグレーション」
この作品は、『V』上梓後に書かれています。だから厳密にいうと、初期作品にはなりません。私はピンチョン『スロー・ラーナー』を読むときは、最初にこの作品を選ぶべきだと思っています。もっともわかりやすい作品です。
主人公は天才少年グローヴァ。自宅の地下で、不思議な実験をくりかえしています。ほかの登場人物は4人のこども、1匹の犬、イボをもった隣りのこども、黒人、アルコール中毒だったこども……。彼らはとんでもない計画を進行中です。
『スロー・ラーナー』の「秘密のインテグレーション」のなか(P202)に、「ドラえもん」を連想させられる記述があります。主人公のグローヴァが、作品のなかで読んでいる本がそれです。
――グローヴァは『トム・スウィフトと魔法のカメラ』を読んでいた。ヴィクター・アプルトンの書いたものだ。アプルトンが『トム・スウィフト』を書いたのは、1910年から1941年にかけて。シリーズ作品の主人公・トムは次々と社会のため、国のために発明品を生み出す。(本文と注釈の一部を引用)
残念ながら、この作品は見あたりません。したがって断言はできませんが、「ドラえもん」の著者が、原文で読んでいた可能性は否定できません。
◎『競売ナンバー49の叫び』も魅力的なのですが
『競売ナンバー49の叫び』がちくま文庫になりましたので、こちらを紹介しようかなとも思いました。しかしピンチョンへの入口としては、短篇集の方がふさわしいと判断しました。
応援演説を紹介させていただきます。
――ピンチョンにも若くて生意気で、カッコつけたがる時期があって、憧れている作家がいて、そりゃあピンチョンだからまだ学部生の頃に書いた作品だって驚くくらい巧みなんだけど、でも、やっぱり背伸びしている姿は丸見えで、処女長篇『V』に圧倒され、『競売ナンバー49の叫び』はそれと比べれば愉しく読めたとはいうものの、自分には一生ピンチョンを十全に堪能することはできないのかもしれないと怯えていたわたしは、初期作品ばかり収めた『スロー・ラーナー』を読むことで、気を取り直すことができたのだ。(豊崎由美『ガタスタ屋の矜恃・場外乱闘篇』(本の雑誌社)
『競売ナンバー49の叫び』には本文とは別に、約50ページの「競売ナンバー49の叫び・解注」がつけられています。本文にちりばめられた、天文学、歴史学、民俗学などたくさんの「○○学」の知識が、そこで解説されているわけです。ただし本文には「注釈あり」の記号がつけられておらず、「競売ナンバー49の叫び・解注」は独立した作品としても読まなければなりません。
青木淳悟のデビュー作『四十日と四十夜のメルヘン』(新潮文庫)は話題になりました。朝日新聞2012年5月16日の「顔」欄(実際には三島由紀夫賞を受賞した『私のいない高校』を伝える記事なのですが)に、こんな文章がありました。
――「ピンチョンが現れた!」早大在学中の2003年、「四十日と四十夜のメルヘン」でデビューし、米国の作家になぞらえ高く評価された。あれから9年。気鋭の小説家に贈られる賞を射止めた。(新聞より)
青木淳悟『私のいない高校』(講談社)は、文庫化されたら「山本藤光の文庫で読む500+α」で紹介させていただくつもりです。それにしても「ピンチョン現れた!」は、書き過ぎではないでしょうか。もっともピンチョンの初期短篇よりは、ずっとわかりやすいのですが。
(山本藤光:2010.03.11初稿、2018.02.21改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます