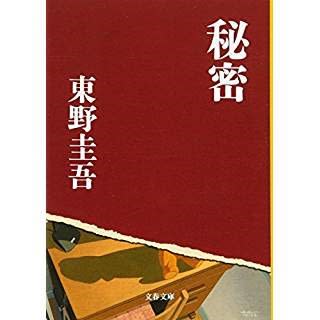久間十義『刑事たちの夏』(上下巻、中公文庫)

新宿歌舞伎町裏のホテルで大蔵省キャリア官僚が墜落死した。自殺か、他殺か―。「特命」で捜査に加わる強行犯六係の松浦洋右は、他殺の証拠を手にする。しかし、大蔵省と取引した上層部が自殺と断定し、捜査は中止に。組織と対峙し私的な捜査を続ける松浦は、政官財癒着を象徴する陰謀にたどり着くが…。ブームの先駆となった傑作警察小説。(「BOOK」データベースより)
◎ルポ的純文学
久間十義とは、デビュー作『マネーゲーム』(河出文庫、初出1987年)からのおつきあいです。本書は文芸賞佳作となりました。当時社会的なニュースになった、豊田商事事件をテーマにした作品です。このときに久間十義が道産子作家であることを知り、以来ずっと読み続けています。
その後発表された『世紀末鯨鯢記』(河出文庫、初出1990年、三島由紀夫賞受賞)に代表されるように、現代社会を鋭くえぐる作品を書き続けています。そしてデビューから約10年後、『刑事たちの夏』(初出1998年、日経新聞社)を読んで、久間十義が高みに登ったと感激させられました。このとき書評はPHP研究所メルマガ「ブックチェイス」で発表しています。
そして2017年1月に、新装版『刑事たちの夏』(上下巻、中公文庫)が出たのを機会に再読しました。ほとんどストーリーを忘れていましたが、腐敗した権力機構と闘う男たちの姿は、現在に通じるとその先見性に驚かされました。
『刑事たちの夏』は、1997年2月から1年以上に渡って、日本経済新聞社夕刊に連載されていました。本書は現代の病める事件を、虚構の世界に再現したものです。事件は、灰色と評されていた、大蔵省審議官の墜落死からはじまります。
久間十義は、社会現象を取り入れたこの手法を好んで用います。前記の豊田商事事件やイエスの方舟などを彷彿させる作品に続いて、今度は大蔵省です。
審議官の墜落死を他殺とみた刑事に対して、様々な妨害が入ります。政府や警察組織の弾圧が見え隠れします。
主人公の松浦洋右は警視庁捜査一課、強行犯捜査六係主任です。彼には別居している妻と息子がいます。仕事に熱中するあげく、家族をかえりみなかったのが原因というお決まりのパターンなのです。
洋右には銀座のクラブに勤めるヒロコという恋人がおり、彼に憧れている東京地検の美由紀がいます。物語りはこの三人を基軸に進められます。
ストーリーは意外に単調です。また文章は平易であり読みやすいものです。最後に予想外のどんでん返しはありません。したがって本格的な推理小説として読んだら、何か損をした感じになってしまいます。
単行本購入時の本書は、推理小説の棚にありました。当時の書店はジャンル別に棚分けされていたのです。したがって私は推理小説の前提で読んでしまいました。妻子に見放されたが、二人の女性から心を寄せられている反体制派の刑事の物語。こんな帯なら、失望することもありませんでした。
しかし本書は、ルポルタージュに近い純文学と呼べるものです。そのあたりを踏まえた評論があります。引用してみます。
――「現実をいかに描くか」という問題にかなりこだわっているせいか、久間さんの作品は一見ルポルタージュ的な印象を受けるのですが、久間さん自身はむしろルポにこそ虚偽が入り込むという思いがあって、小説というかたちの中で現実を描く方がより一層現実を追求することができるのではないか、と考えておられるんじゃないかと思います。(女性文学会編『たとえば純文学はこんなふうにして書く』同文書院P124)
◎バルザック的な視線
タイトルは、「刑事たち」と複数形になっています。筆者は複数の刑事を描きたかったのでしょうが、残念ながら主人公以外は影が薄い感は否めません。
気になったのは「目をしばたたいた」の表現が、何回となく出てくることです。単行本10ページ「洋右は目をしばたたいた」、14ページ「彼は目をしばたたいた」、105ページ「彼はしばたたき……」、154ページ「羽田は目をしばたたいた」、166ページ「洋右は目をしばたたいた」、278ページ「彼女は目をしばたたいた」……キリがないので探すのはやめます。
違う表現はないものなのでしょうか。私は目をしばたたいて、考えこんでしまいました。最後は茶化しになりましたが、私は久間十義は骨太な作家だと思っています。そして本書は、大蔵省改め財務省の現在を描いているように思えました。
久間十義について、秋山駿は次のように書いています。
――社会の変化の運動をぎゅっと掴み、その運動に操られる人間の生態を、ときおりモデル人形をいじくるように自分の指で揺すぶっては観察する――そんなバルザック的な視線がある。(秋山駿『作家と作品』小沢書店P349-350)
中公文庫下巻は、大蔵省の不正について書かれた「白鳥メモ」が登場します。そしてそのメモの争奪戦が展開されます。このあたりの描写は繊細で、まるで現在の財務書の不正を彷彿とさせます。現実にあった社会問題を、独自の視点で小説化し続ける久間十義。私は、佐木隆三『復讐するは我にあり』(文春文庫、500+α紹介作)とともに、新たなジャンルが確立されたと評価しています。
山本藤光1998.09.12初稿。2018.10.06改稿

新宿歌舞伎町裏のホテルで大蔵省キャリア官僚が墜落死した。自殺か、他殺か―。「特命」で捜査に加わる強行犯六係の松浦洋右は、他殺の証拠を手にする。しかし、大蔵省と取引した上層部が自殺と断定し、捜査は中止に。組織と対峙し私的な捜査を続ける松浦は、政官財癒着を象徴する陰謀にたどり着くが…。ブームの先駆となった傑作警察小説。(「BOOK」データベースより)
◎ルポ的純文学
久間十義とは、デビュー作『マネーゲーム』(河出文庫、初出1987年)からのおつきあいです。本書は文芸賞佳作となりました。当時社会的なニュースになった、豊田商事事件をテーマにした作品です。このときに久間十義が道産子作家であることを知り、以来ずっと読み続けています。
その後発表された『世紀末鯨鯢記』(河出文庫、初出1990年、三島由紀夫賞受賞)に代表されるように、現代社会を鋭くえぐる作品を書き続けています。そしてデビューから約10年後、『刑事たちの夏』(初出1998年、日経新聞社)を読んで、久間十義が高みに登ったと感激させられました。このとき書評はPHP研究所メルマガ「ブックチェイス」で発表しています。
そして2017年1月に、新装版『刑事たちの夏』(上下巻、中公文庫)が出たのを機会に再読しました。ほとんどストーリーを忘れていましたが、腐敗した権力機構と闘う男たちの姿は、現在に通じるとその先見性に驚かされました。
『刑事たちの夏』は、1997年2月から1年以上に渡って、日本経済新聞社夕刊に連載されていました。本書は現代の病める事件を、虚構の世界に再現したものです。事件は、灰色と評されていた、大蔵省審議官の墜落死からはじまります。
久間十義は、社会現象を取り入れたこの手法を好んで用います。前記の豊田商事事件やイエスの方舟などを彷彿させる作品に続いて、今度は大蔵省です。
審議官の墜落死を他殺とみた刑事に対して、様々な妨害が入ります。政府や警察組織の弾圧が見え隠れします。
主人公の松浦洋右は警視庁捜査一課、強行犯捜査六係主任です。彼には別居している妻と息子がいます。仕事に熱中するあげく、家族をかえりみなかったのが原因というお決まりのパターンなのです。
洋右には銀座のクラブに勤めるヒロコという恋人がおり、彼に憧れている東京地検の美由紀がいます。物語りはこの三人を基軸に進められます。
ストーリーは意外に単調です。また文章は平易であり読みやすいものです。最後に予想外のどんでん返しはありません。したがって本格的な推理小説として読んだら、何か損をした感じになってしまいます。
単行本購入時の本書は、推理小説の棚にありました。当時の書店はジャンル別に棚分けされていたのです。したがって私は推理小説の前提で読んでしまいました。妻子に見放されたが、二人の女性から心を寄せられている反体制派の刑事の物語。こんな帯なら、失望することもありませんでした。
しかし本書は、ルポルタージュに近い純文学と呼べるものです。そのあたりを踏まえた評論があります。引用してみます。
――「現実をいかに描くか」という問題にかなりこだわっているせいか、久間さんの作品は一見ルポルタージュ的な印象を受けるのですが、久間さん自身はむしろルポにこそ虚偽が入り込むという思いがあって、小説というかたちの中で現実を描く方がより一層現実を追求することができるのではないか、と考えておられるんじゃないかと思います。(女性文学会編『たとえば純文学はこんなふうにして書く』同文書院P124)
◎バルザック的な視線
タイトルは、「刑事たち」と複数形になっています。筆者は複数の刑事を描きたかったのでしょうが、残念ながら主人公以外は影が薄い感は否めません。
気になったのは「目をしばたたいた」の表現が、何回となく出てくることです。単行本10ページ「洋右は目をしばたたいた」、14ページ「彼は目をしばたたいた」、105ページ「彼はしばたたき……」、154ページ「羽田は目をしばたたいた」、166ページ「洋右は目をしばたたいた」、278ページ「彼女は目をしばたたいた」……キリがないので探すのはやめます。
違う表現はないものなのでしょうか。私は目をしばたたいて、考えこんでしまいました。最後は茶化しになりましたが、私は久間十義は骨太な作家だと思っています。そして本書は、大蔵省改め財務省の現在を描いているように思えました。
久間十義について、秋山駿は次のように書いています。
――社会の変化の運動をぎゅっと掴み、その運動に操られる人間の生態を、ときおりモデル人形をいじくるように自分の指で揺すぶっては観察する――そんなバルザック的な視線がある。(秋山駿『作家と作品』小沢書店P349-350)
中公文庫下巻は、大蔵省の不正について書かれた「白鳥メモ」が登場します。そしてそのメモの争奪戦が展開されます。このあたりの描写は繊細で、まるで現在の財務書の不正を彷彿とさせます。現実にあった社会問題を、独自の視点で小説化し続ける久間十義。私は、佐木隆三『復讐するは我にあり』(文春文庫、500+α紹介作)とともに、新たなジャンルが確立されたと評価しています。
山本藤光1998.09.12初稿。2018.10.06改稿