A・C・クラーク『幼年期の終わり』(ハヤカワ文庫、福島正実訳)
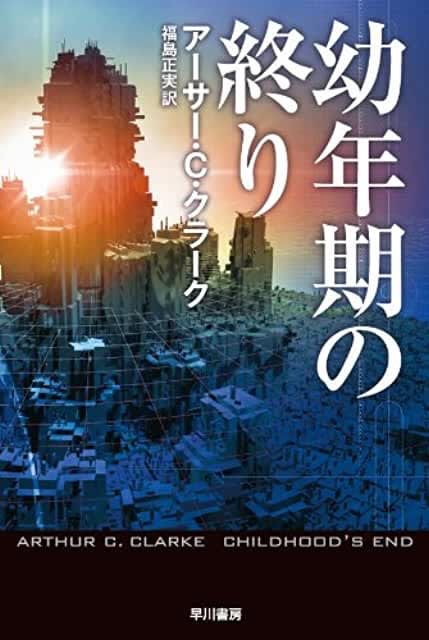
異星人の宇宙船が地球の主要都市上空に停滞してから五十年。その間、
異星人は人類にその姿を見せることなく、見事に地球管理を行なった。
だが、多くの謎があった。宇宙人の真の目的は? 人類の未来は?
――巨匠が異星人とのファースト・コンタクトによって新たな道を歩みはじめる
人類の姿を描きあげた傑作!(内容紹介)
◎巨大な宇宙船の来襲
アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』(ハヤカワ文庫)は、
1952年に刊行されたSF史上の最高傑作と評価されています。
発表から半世紀以上たった今も、
その斬新さはまったく色あせていません。
ミステリー風SF小説しか知らなかった私は、
本格的な科学を駆使した
本書に打ちのめされました。
本書の時代は20世紀後半。全世界の上空に
巨大な円盤状の宇宙船が鎮座しています。
米ソが宇宙開発競争を展開しているさなか、
人々が「オーバーロード」と呼んでいる宇宙船はなんら動きを
みせません。地球人たちは気がつかないのですが、
「オーバーロード」の出現で
地球上から少しずつ戦争や飢餓が減ってゆきます。
「オーバーロード」に立ち入ることが許されているのは、
国際連合事務総長のストルムグレンだけです。
彼は自称カレルレンという宇宙人とのみ、電波を介して
会話ができます。しかしその姿はみることができません。
カレルレンは、地球は自分たちに支配されており、
国も国境もない世界を構築すると伝えます。
ストルムグレンは「オーバーロード」の真の目的と
宇宙人の正体を探ろうと努力します。
しかしそれが実現しないまま、彼は退官の日を迎えます。
――彼らの動機は誰一人知らなかった。誰一人、
オーバーロードが人類を導いていこうとしている未来を、
知らなかったのである。(本文P47)
カレルレンは姿を見たいと画策するストルムグレンに、
「正体は50年後にさらす」と伝えます。
ここまでが第1部のあらすじとなります。
第2部は、それから50年後が舞台となります。
世界の首都の上空にあった宇宙船は、
ニューヨークのものだけを残して消えています。
◎ゴーン容疑者のように
ニューヨーク郊外に着陸したオーバーロードは、ついに人類のまえに
姿をあらわします。
――皮に似た強靱な翼、短い角、さかとげのある尻尾――
すべてがそこにあった。ありとあらゆる伝説に巣食うもっとも
怖ろしい存在が――知られざる過去の暗闇から、明るい日光
のもとにその巨体をぬめぬめとひからせ、(中略)黒檀さながらの
威厳をもってそこに立っているのであった。(本文P123)
参考のために同じ箇所について、光文社古典新訳文庫(池田真紀子訳)
を並べてみます。
――硬い革でできたような翼、小さな角、矢印の形をした尾――
すべて揃っていた。あらゆる伝説のなかでももっとも怖ろしい一つが、
未知の過去から命を持って現れたのだ。ただし、それはいま、
微笑をたたえて立っていた――黒檀を思わせる厳かさを
放ち、巨体をまばゆい陽射しにつやつやと輝かせ(後略)(P132)
こうして姿を明らかにした宇宙人たちは、人類と共生して平和を
目指すことになります。人類の多くは彼らが自分たちに牙を
むいてこないことを悟っています。
しかし彼らを受け入れない人たちも存在します。
その代表格が、天文学者のジャン・ロドリックスで、
第2部では彼が主人公となります。彼はオーバーロードの出現で、
宇宙探険の夢を削がれたことを怨みに思っています。
彼はオーバーロードが地球を離れるときをねらって、
密かに密航をくわだてます。ゴーン容疑者が日本を脱出したとき
のように、鯨の剥製にもぐりこむのです。
第2部まではあいまいにされていた「オーバーロード」の
上部機関である「オーバーマインド」の存在は第3部で知る
ことになります。謎であった「オーバーロード」は、
この「オーバーマインド」の指示を受けていました。
読者は第3部で、「オーバーロード」の地球上での怖ろしい
役割を知らされます。
密航を企てたジャン・ロドリックスは、80年後に地球への
帰還を果たします。彼は浦島太郎のように、
若いままの姿です。地球にはすでに「オーバーロード」の
姿はありません。役割を終えた宇宙人は、地球を去ってゆきます。
そしてジャン・ロドリックスが戻った地球は……。
これ以上ストーリーは追いません。とにかく驚愕のラストシーンを
味わっていただきたいと思います。本書は『SFマガジン』の特集
「この20人、この5冊」(2012年9月号)で、次のようにラストシーン
の美しさを称えられています。
――黙示録的想像力の比類なき結晶というべき
ラストシーンの美しさは、いまなお色褪せないSF文学の
至高の到達点である。
『幼年期の終わり』は、2007年に光文社古典新訳文庫(池田真紀子訳)
になっています。新訳で久しぶりに本書を読んだ大森望も
ラストに触れています。
――こんな話だったのか。意外と面白いじゃん。でもやっぱり
世の中が単純だった時代のSFだよな……などと思いつつ
読み進めていたところ、結末でふい打ちを食らい、不覚にも
ちょっと感動。お見それしました。オールタイムベストSF投票で
『ソラリス』(補:スタニスワフ・レム作)に次いで2位に入るだけある。
(大森望『21世紀のSF1000』ハヤカワ文庫)
◎未来の記憶
A・C・クラークは1917年生まれのイギリスのSF作家です。
ロバート・A・ハインライン(500+α紹介予定作『夏への扉』ハヤカワ文庫)、
アイザック・アシモフ(500+α紹介作『ミクロの決死圏』ハヤカワ文庫)
と並びSF御三家と称されています。
――クラーク作品の特徴は、少年時代に彼を虜にした英国と米国の
ふたつのSFの系譜を統合する、文明論的な思弁と冒険小説的な
ストーリィテリングを兼ね備えた明快かつ壮大なイメージの豊饒さである。
(『SFマガジン』2012年9月号)
『10代のうちに本当に読んでほしい「この一冊」』(河出文庫)という
本があります。そのなかで森達也は、10代の若者に向けて本書を
紹介しています。呼びかけの一部を引用しておきます。
――ロードには神という意味もある。つまり彼らは人類にとっての
新しい神なのだ。オーバーロードたちは優しく、根気強く、そして
的確な指示を下し続けた。戦争や紛争は終わり、飢餓や差別や経済格差
などの問題も解消された。(同書P20)
最後に本書の読みどころを紹介している文章があります。引用しておきます。
――宇宙人である「上空」と、人々のあいだで何世代にもわたって
語り継がれてきた悪魔の姿が一致するのは、人類の過去の記憶に
よるのではなく、未来の記憶であったというプロットは極めて
効果的といえる。(『たのしく読めるイギリス文学』ミネルヴァ書房)
この文章の意味を、ずっとわからずにいました。本書を読み終わったあとに、
『100分de名著・アーサー・C・クラーク・スペシャル』のテキストを
購読しました。番組はみていませんが、テキストのなかで「未来の記憶」
の解説がなされていました。
――人類の守護神だと思っていた存在が、実は悪魔だった。そして、
人類の歴史で悪魔として語り継がれ、記憶されてきた存在が、
実は宇宙からの知的生命体だった。――『守護天使』は「未来の
記憶」というオチで終焉します。(同書)
この引用文の前段に、『幼年期の終わり』の種明かしがなされています。
A・C・クラークは、以前に書いた中編『守護天使』がもとに『幼年期の終わり』
を執筆していました。
カレルレンの登場で、『守護天使』は終わっているようです。翻訳本が
ないので証明することはできません。
つまり旧作の終わったところからはじめたのが、本書だったわけです。
しかし現状の私には「未来の記憶」がイメージできません。近いうちに、
新訳で再挑戦してみます。
いずれにせよ、本書は傑作でした。未読のかたには、「もったいない」
とつたえさせていただきます。
山本藤光2020.04.17
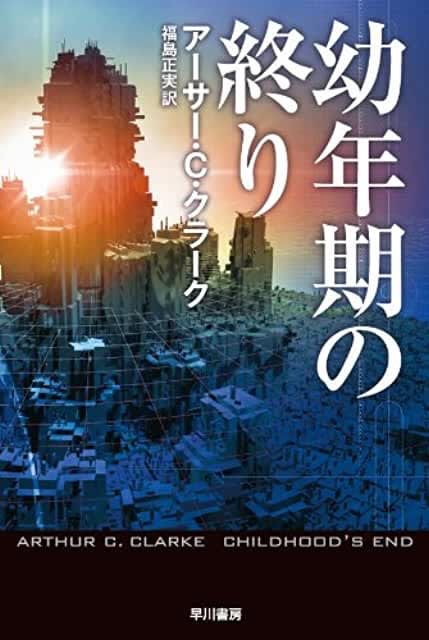
異星人の宇宙船が地球の主要都市上空に停滞してから五十年。その間、
異星人は人類にその姿を見せることなく、見事に地球管理を行なった。
だが、多くの謎があった。宇宙人の真の目的は? 人類の未来は?
――巨匠が異星人とのファースト・コンタクトによって新たな道を歩みはじめる
人類の姿を描きあげた傑作!(内容紹介)
◎巨大な宇宙船の来襲
アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』(ハヤカワ文庫)は、
1952年に刊行されたSF史上の最高傑作と評価されています。
発表から半世紀以上たった今も、
その斬新さはまったく色あせていません。
ミステリー風SF小説しか知らなかった私は、
本格的な科学を駆使した
本書に打ちのめされました。
本書の時代は20世紀後半。全世界の上空に
巨大な円盤状の宇宙船が鎮座しています。
米ソが宇宙開発競争を展開しているさなか、
人々が「オーバーロード」と呼んでいる宇宙船はなんら動きを
みせません。地球人たちは気がつかないのですが、
「オーバーロード」の出現で
地球上から少しずつ戦争や飢餓が減ってゆきます。
「オーバーロード」に立ち入ることが許されているのは、
国際連合事務総長のストルムグレンだけです。
彼は自称カレルレンという宇宙人とのみ、電波を介して
会話ができます。しかしその姿はみることができません。
カレルレンは、地球は自分たちに支配されており、
国も国境もない世界を構築すると伝えます。
ストルムグレンは「オーバーロード」の真の目的と
宇宙人の正体を探ろうと努力します。
しかしそれが実現しないまま、彼は退官の日を迎えます。
――彼らの動機は誰一人知らなかった。誰一人、
オーバーロードが人類を導いていこうとしている未来を、
知らなかったのである。(本文P47)
カレルレンは姿を見たいと画策するストルムグレンに、
「正体は50年後にさらす」と伝えます。
ここまでが第1部のあらすじとなります。
第2部は、それから50年後が舞台となります。
世界の首都の上空にあった宇宙船は、
ニューヨークのものだけを残して消えています。
◎ゴーン容疑者のように
ニューヨーク郊外に着陸したオーバーロードは、ついに人類のまえに
姿をあらわします。
――皮に似た強靱な翼、短い角、さかとげのある尻尾――
すべてがそこにあった。ありとあらゆる伝説に巣食うもっとも
怖ろしい存在が――知られざる過去の暗闇から、明るい日光
のもとにその巨体をぬめぬめとひからせ、(中略)黒檀さながらの
威厳をもってそこに立っているのであった。(本文P123)
参考のために同じ箇所について、光文社古典新訳文庫(池田真紀子訳)
を並べてみます。
――硬い革でできたような翼、小さな角、矢印の形をした尾――
すべて揃っていた。あらゆる伝説のなかでももっとも怖ろしい一つが、
未知の過去から命を持って現れたのだ。ただし、それはいま、
微笑をたたえて立っていた――黒檀を思わせる厳かさを
放ち、巨体をまばゆい陽射しにつやつやと輝かせ(後略)(P132)
こうして姿を明らかにした宇宙人たちは、人類と共生して平和を
目指すことになります。人類の多くは彼らが自分たちに牙を
むいてこないことを悟っています。
しかし彼らを受け入れない人たちも存在します。
その代表格が、天文学者のジャン・ロドリックスで、
第2部では彼が主人公となります。彼はオーバーロードの出現で、
宇宙探険の夢を削がれたことを怨みに思っています。
彼はオーバーロードが地球を離れるときをねらって、
密かに密航をくわだてます。ゴーン容疑者が日本を脱出したとき
のように、鯨の剥製にもぐりこむのです。
第2部まではあいまいにされていた「オーバーロード」の
上部機関である「オーバーマインド」の存在は第3部で知る
ことになります。謎であった「オーバーロード」は、
この「オーバーマインド」の指示を受けていました。
読者は第3部で、「オーバーロード」の地球上での怖ろしい
役割を知らされます。
密航を企てたジャン・ロドリックスは、80年後に地球への
帰還を果たします。彼は浦島太郎のように、
若いままの姿です。地球にはすでに「オーバーロード」の
姿はありません。役割を終えた宇宙人は、地球を去ってゆきます。
そしてジャン・ロドリックスが戻った地球は……。
これ以上ストーリーは追いません。とにかく驚愕のラストシーンを
味わっていただきたいと思います。本書は『SFマガジン』の特集
「この20人、この5冊」(2012年9月号)で、次のようにラストシーン
の美しさを称えられています。
――黙示録的想像力の比類なき結晶というべき
ラストシーンの美しさは、いまなお色褪せないSF文学の
至高の到達点である。
『幼年期の終わり』は、2007年に光文社古典新訳文庫(池田真紀子訳)
になっています。新訳で久しぶりに本書を読んだ大森望も
ラストに触れています。
――こんな話だったのか。意外と面白いじゃん。でもやっぱり
世の中が単純だった時代のSFだよな……などと思いつつ
読み進めていたところ、結末でふい打ちを食らい、不覚にも
ちょっと感動。お見それしました。オールタイムベストSF投票で
『ソラリス』(補:スタニスワフ・レム作)に次いで2位に入るだけある。
(大森望『21世紀のSF1000』ハヤカワ文庫)
◎未来の記憶
A・C・クラークは1917年生まれのイギリスのSF作家です。
ロバート・A・ハインライン(500+α紹介予定作『夏への扉』ハヤカワ文庫)、
アイザック・アシモフ(500+α紹介作『ミクロの決死圏』ハヤカワ文庫)
と並びSF御三家と称されています。
――クラーク作品の特徴は、少年時代に彼を虜にした英国と米国の
ふたつのSFの系譜を統合する、文明論的な思弁と冒険小説的な
ストーリィテリングを兼ね備えた明快かつ壮大なイメージの豊饒さである。
(『SFマガジン』2012年9月号)
『10代のうちに本当に読んでほしい「この一冊」』(河出文庫)という
本があります。そのなかで森達也は、10代の若者に向けて本書を
紹介しています。呼びかけの一部を引用しておきます。
――ロードには神という意味もある。つまり彼らは人類にとっての
新しい神なのだ。オーバーロードたちは優しく、根気強く、そして
的確な指示を下し続けた。戦争や紛争は終わり、飢餓や差別や経済格差
などの問題も解消された。(同書P20)
最後に本書の読みどころを紹介している文章があります。引用しておきます。
――宇宙人である「上空」と、人々のあいだで何世代にもわたって
語り継がれてきた悪魔の姿が一致するのは、人類の過去の記憶に
よるのではなく、未来の記憶であったというプロットは極めて
効果的といえる。(『たのしく読めるイギリス文学』ミネルヴァ書房)
この文章の意味を、ずっとわからずにいました。本書を読み終わったあとに、
『100分de名著・アーサー・C・クラーク・スペシャル』のテキストを
購読しました。番組はみていませんが、テキストのなかで「未来の記憶」
の解説がなされていました。
――人類の守護神だと思っていた存在が、実は悪魔だった。そして、
人類の歴史で悪魔として語り継がれ、記憶されてきた存在が、
実は宇宙からの知的生命体だった。――『守護天使』は「未来の
記憶」というオチで終焉します。(同書)
この引用文の前段に、『幼年期の終わり』の種明かしがなされています。
A・C・クラークは、以前に書いた中編『守護天使』がもとに『幼年期の終わり』
を執筆していました。
カレルレンの登場で、『守護天使』は終わっているようです。翻訳本が
ないので証明することはできません。
つまり旧作の終わったところからはじめたのが、本書だったわけです。
しかし現状の私には「未来の記憶」がイメージできません。近いうちに、
新訳で再挑戦してみます。
いずれにせよ、本書は傑作でした。未読のかたには、「もったいない」
とつたえさせていただきます。
山本藤光2020.04.17


















