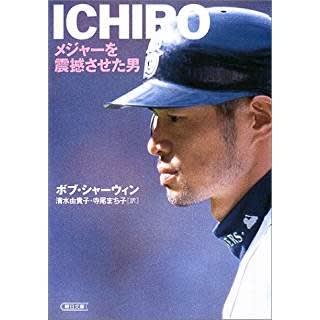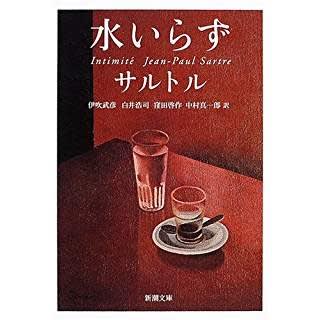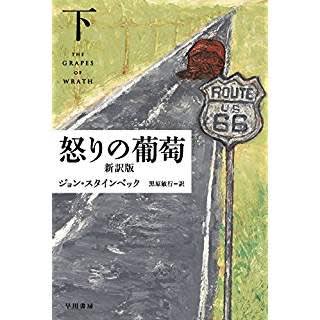シェイクスピア『ハムレット』(角川文庫、河合祥一郎訳)

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。―」王子ハムレットは父王を毒殺された。犯人である叔父は、現在王位につき、殺人を共謀した母は、その妻におさまった。ハムレットは父の亡霊に導かれ、復讐をとげるため、気の触れたふりをしてその時をうかがうが…。四大悲劇のひとつである、シェイクスピアの不朽の名作。ハムレット研究の若き気鋭が、古典の持つリズムと日本語にこだわり抜いた、読み易く、かつ格調高い、画期的新訳完全版。(「BOOK」データベースより)
◎7つの訳文のどれを選ぶか
これまでにたくさんの訳者による『ハムレット』を読んできました。そのなかで一番古い訳文は、坪内逍遥のものだと思います。
国立国会図書館の常設案内(平成8年8月27日から9月21日)によると、初めて翻訳劇「ハムレット」が上演されたのは坪内逍遥訳のようです。これはkindleで読むことができます。ただし本の写真版なので文字を拡大できず、ひどく読みにくいものでした。
――明治40年11月22日、坪内逍遥訳・指導によって初めて翻訳劇『ハムレット』が上演された(それまでは翻案のみ)。逍遥はシェイクスピアの中に歌舞伎との同質性を見て、シェイクスピアをモデルに歌舞伎を改良しようとした。そのため七五調の古風な文体になっている。(「国立国会図書館」の第73回常設案内より)
私の手元にある『ハムレット』のなかから、有名なセリフ(第3幕第1場)「To be, or not to be, that is the question」の訳文を比べてみたいと思います。
■kindle本(坪内逍遥訳)
――存(ながら)ふるか……存へぬか……それが疑問ぢゃ、残忍な運命の矢石と只管堪(ひたさらた)へ忍ふでをるが大丈夫の志か、或は海なす艱難を逆(むか)へ撃って、戦うて根を絶つが大丈夫か? 死は……ねむり……に過ぎぬ。
■新潮文庫(福田恒存訳)
――生か、死か、それが疑問だ、どちらが男らしい生きかたか、じっと身を伏せ、不法な運命の矢弾を堪えるのと、それとも剣をとって、押しよせる苦難に立ち向かい、とどめを刺すまであとには引かぬのと、いったいどちらが。いっそ死んでしまったほうが。(本文P84)
■角川文庫(河合祥一郎訳)
――生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。/どちらが気高い心にふさわしいのか。非道な運命の矢弾をじっと耐え忍ぶか、それとも/怒濤の苦難に斬りかかり、/戦って相果てるか。死ぬことは――眠ること、それだけだ。(本文P98)
■岩波文庫(野島秀勝訳)
――生きるか、死ぬか、それが問題だ。/どちらが立派な生き方か、/気まぐれな運命が放つ矢弾にじっと耐え忍ぶのと、/怒濤のように打ち寄せる苦難に刃向い/勇敢に戦って相共に果てるのと。死ぬとは……眠ること、それだけだ。(本文P142)
■ちくま文庫(松岡和子訳)
――生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ。/どちらが雄々しい態度だろう、/やみくもな運命の矢弾を心の内でひたすら耐え忍ぶか、/艱難の海に刃を向け/それにとどめを刺すか。死ぬ、眠る――/それだけのことだ。(本文P128-129)
■光文社古典新訳文庫(安西徹雄訳)
――生か死か、問題はそれだ。死ぬ、眠る。それで終わりか? そう、それで終わり。いや、眠れば夢を見る。(本文P60)。
■白水Uブックス(小田島雄志訳)
――このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ。/どちらがりっぱな生き方か、このまま心のうちに/暴虐な運命の矢弾をじっと耐えしのぶことか、/それとも寄せくる怒濤の苦難に敢然と立ちむかい、/闘ってそれに終止符をうつことか。死ぬ、眠る、/それだけだ。(本文P110)
どの訳文を選ぶかは、好みの問題です。私の場合は、大好きな番組「NHK100分de名著」の『ハムレット』(4回シリーズ)を観たので、角川文庫を選びました。。訳者の河合祥一郎が、コメンテイターとして出演していたのです。すばらしい解説でした。
シェイクスピアの訳文を選ぶとき、時代背景について理解しておかなければなりません。井上ひさしは次のように語っています。
――先生(補:シェイクスピア)ご活躍のころのエリザベス朝の劇場は本邦における能舞台のようなもの、舞台装置はないにも等しく、豪華な衣装を別にすれば、作品の効果は戯曲の台詞の迫力と役者の演技力にまつよりほかはありませんでした。おまけに女優はおらず、女の役は少年が勤めておりました。(中略)一にも言葉、二にも言葉、ひたすら言葉を練り上げて、泣かせる台詞、いい台詞、おかしな台詞で、観客を唸らせることに命を懸けておいでになった。(井上ひさしのベスト3。丸谷才一編『私の選んだ文庫ベスト3』ハヤカワ文庫P28-29)
◎熱情と知性のはざまで
ハムレットは、将来を嘱望された王子でした。父の急死とあわただしい母の再婚に、心を痛めます。ハムレットは王である父を愛し、尊敬をしていました。しかし母が再婚した父の弟は、受け入れられる存在ではありませんでした。
そんなとき、父の幽霊が出現します。幽霊は自分を殺害したのは弟であることを告げ、復讐せよと命じます。しかしハムレットは幽霊の本性が見抜けず、逡巡してしまいます。そして父の死の真相を調べようと思います。
ハムレットを優柔不断な若者と思っている方は多いと思います。しかし「100分de名著」のなかで、河合祥一郎は次のように語っています。ハムレットは熱情と理性の人。気高く生きるためにどうしたらよいかを追求している人。この解説に触れて、私は新たなハムレット像を見つめなおしました。
河合祥一郎は、シェイクスピアがハムレットの分身を登場させているとも語っていました。その部分を意識して再読しますと、なるほど合点がいきました。詳細についてはあとから触れます。
・ホレイシオ(ハムレットの腹心の友):「理性」の象徴。
・レアーティーズ(ポローニアスの息子):「熱情」の象徴。
・フォーティンブラス(ノルウェー王子):「理性と熱情」を兼ね備えた人の象徴。
『ハムレット』の物語構造については、木下順二の著書から引かせていただきます。ハムレットが優柔不断に見えてしまうのは、。次の引用文で理解できます。
――ハムレットにとっては、自分の願望――叔父が犯人であることを確かめること――その願望へ着々と近づいて行く行為は、同時に最も願わしくないこと――復讐――へ着々と近づいて行くという行為だった。つまり願望を持てば持つほど願望から遠ざかるという、劇『オイディップス王』にわれわれが見たあの構造は、このようにして劇『ハムレット』に当てはまるわけです。(木下順二『劇的とは』岩波新書P68)
ソポクレス『オイディプス王』(岩波文庫、藤沢令夫訳)については、「山本藤光の文庫で読む500+α」で紹介済みです。そちらをご覧ください。ハムレットの心の葛藤について、もうひとつの論評を引かせていただきます。
――これ以上に、人間が生きて行く為に経験する苦しみとか、その終りを意味している筈の死とかいうものの性質が、実は我々に少しも解っていないということを的確に描写したものはない。それ故に、ハムレットは迷っているのではなくて、我々人間が置かれている立場を自分に確認させ、そして自分が発した問に対して答はないから、答えずにいるのである。(吉田健一『文学人生案内』講談社文芸文庫P107)
悩むハムレット以外に、ハムレットの行動に着目している文章もあります。
――ハムレットは確かに迷い、悩む。同時に、果敢に行動する。愛するオフィーリアに対して、「尼寺へゆきやがれ」と絶縁の言葉を突きつけ、その父親の侍従長ポローニアスを、間違えたとはいえ瞬時に刺殺し、己の母親を鋭い言葉でずたずたに切り裂く。(轡田隆史『名著の読み方・人生の見かたを変える』中経文庫P30)
このあたりは優柔不断どころか、直情径行のハムレットになっています。もうひとつ引用させていただきます。
――ハムレットの最大の行動は演技をすることである。周囲は敵ばかり。常に誰かに見張られている。見るものを観客だと考えれば、そのただなかに立つハムレットは彼らの視線を意識して演技をせざるをえない。(松岡和子『「もの」で読む入門シェイクスピア』ちくま文庫P39)
◎意味深な結末
2014年は、シェイクスピア生誕450年でした。この年は日本の永禄7年にあたり、5回目の川中島の戦いをしていました。シェイクスピアが『ハムレット』を書いたのは1600年ころといわれています。、40歳の手前あたりに、今なお色あせることのない戯曲を発表したのです。
『ハムレット』の結末(第5幕第2場)について、斉藤美奈子がユニークな文章を書いています。
――劇中に二度しか登場しない(なんだか上手くやったように見える)もうひとりの王子(補:フォーティンブラス)。非業の死をとげた王子(補:ハムレット)との差をどう考えるべきか。それが問題だ。(斎藤美奈子『名作うしろ読み』中央公論新社P47)
フォーティンブラス(ノルウェー王子)については、先に「理性の熱情」を兼ね備えた人の象徴と紹介しました。斉藤美奈子の文章を読んで、物語の完結にふさわしい人だったのだと認識させられました。
ホレイシオ(ハムレットの腹心の友。「理性」の象徴)の役割についても、引用しておきたいと思います。河合隼雄と松岡和子との対談のなかで、河合は次のように語っています。
――ハムレットは初めからまっしぐらに死の世界に向かって行く主人公ですね。まわりもほとんど全員が死ぬ。その中で、ホレイショーだけは非常に大事な役だと思いました。最初から最後まで見届け、それを語る役目、言ってみればシェイクスピア自身ですよ。(河合隼雄×松岡和子『シェイクスピア』新潮文庫P173)
最後に私がなぜ数ある訳書のなかから、角川文庫を選んだのかについて、その理由をもうひとつだけ書かせていただきます。それは角川文庫の巻末の野村萬斉(狂言師)の「後口上」に書かれたことに感動したからです。野村萬斉は自らが演ずるために、河合祥一郎に新訳を依頼したのです。
――私は口承の日本語文化を受け継ぐ狂言師ということに起因しますが、英文学翻訳読物劇ではなく、聞いて実感が持てる日本語戯曲音読劇としてのシェイクスピアを上演したかったのです。(野村萬斉)
そんなわけで、私は角川文庫を再読して、この原稿の改稿作業をしました。何度読んでも、『ハムレット』は新しく感じます。私の蔵書のなかには、まだまだ数多い『ハムレット』の書評があります。おそらく本書の数十倍のボリュームだと思います。
(山本藤光:2012.09.25初稿、2018.03.12改稿)

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。―」王子ハムレットは父王を毒殺された。犯人である叔父は、現在王位につき、殺人を共謀した母は、その妻におさまった。ハムレットは父の亡霊に導かれ、復讐をとげるため、気の触れたふりをしてその時をうかがうが…。四大悲劇のひとつである、シェイクスピアの不朽の名作。ハムレット研究の若き気鋭が、古典の持つリズムと日本語にこだわり抜いた、読み易く、かつ格調高い、画期的新訳完全版。(「BOOK」データベースより)
◎7つの訳文のどれを選ぶか
これまでにたくさんの訳者による『ハムレット』を読んできました。そのなかで一番古い訳文は、坪内逍遥のものだと思います。
国立国会図書館の常設案内(平成8年8月27日から9月21日)によると、初めて翻訳劇「ハムレット」が上演されたのは坪内逍遥訳のようです。これはkindleで読むことができます。ただし本の写真版なので文字を拡大できず、ひどく読みにくいものでした。
――明治40年11月22日、坪内逍遥訳・指導によって初めて翻訳劇『ハムレット』が上演された(それまでは翻案のみ)。逍遥はシェイクスピアの中に歌舞伎との同質性を見て、シェイクスピアをモデルに歌舞伎を改良しようとした。そのため七五調の古風な文体になっている。(「国立国会図書館」の第73回常設案内より)
私の手元にある『ハムレット』のなかから、有名なセリフ(第3幕第1場)「To be, or not to be, that is the question」の訳文を比べてみたいと思います。
■kindle本(坪内逍遥訳)
――存(ながら)ふるか……存へぬか……それが疑問ぢゃ、残忍な運命の矢石と只管堪(ひたさらた)へ忍ふでをるが大丈夫の志か、或は海なす艱難を逆(むか)へ撃って、戦うて根を絶つが大丈夫か? 死は……ねむり……に過ぎぬ。
■新潮文庫(福田恒存訳)
――生か、死か、それが疑問だ、どちらが男らしい生きかたか、じっと身を伏せ、不法な運命の矢弾を堪えるのと、それとも剣をとって、押しよせる苦難に立ち向かい、とどめを刺すまであとには引かぬのと、いったいどちらが。いっそ死んでしまったほうが。(本文P84)
■角川文庫(河合祥一郎訳)
――生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。/どちらが気高い心にふさわしいのか。非道な運命の矢弾をじっと耐え忍ぶか、それとも/怒濤の苦難に斬りかかり、/戦って相果てるか。死ぬことは――眠ること、それだけだ。(本文P98)
■岩波文庫(野島秀勝訳)
――生きるか、死ぬか、それが問題だ。/どちらが立派な生き方か、/気まぐれな運命が放つ矢弾にじっと耐え忍ぶのと、/怒濤のように打ち寄せる苦難に刃向い/勇敢に戦って相共に果てるのと。死ぬとは……眠ること、それだけだ。(本文P142)
■ちくま文庫(松岡和子訳)
――生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ。/どちらが雄々しい態度だろう、/やみくもな運命の矢弾を心の内でひたすら耐え忍ぶか、/艱難の海に刃を向け/それにとどめを刺すか。死ぬ、眠る――/それだけのことだ。(本文P128-129)
■光文社古典新訳文庫(安西徹雄訳)
――生か死か、問題はそれだ。死ぬ、眠る。それで終わりか? そう、それで終わり。いや、眠れば夢を見る。(本文P60)。
■白水Uブックス(小田島雄志訳)
――このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ。/どちらがりっぱな生き方か、このまま心のうちに/暴虐な運命の矢弾をじっと耐えしのぶことか、/それとも寄せくる怒濤の苦難に敢然と立ちむかい、/闘ってそれに終止符をうつことか。死ぬ、眠る、/それだけだ。(本文P110)
どの訳文を選ぶかは、好みの問題です。私の場合は、大好きな番組「NHK100分de名著」の『ハムレット』(4回シリーズ)を観たので、角川文庫を選びました。。訳者の河合祥一郎が、コメンテイターとして出演していたのです。すばらしい解説でした。
シェイクスピアの訳文を選ぶとき、時代背景について理解しておかなければなりません。井上ひさしは次のように語っています。
――先生(補:シェイクスピア)ご活躍のころのエリザベス朝の劇場は本邦における能舞台のようなもの、舞台装置はないにも等しく、豪華な衣装を別にすれば、作品の効果は戯曲の台詞の迫力と役者の演技力にまつよりほかはありませんでした。おまけに女優はおらず、女の役は少年が勤めておりました。(中略)一にも言葉、二にも言葉、ひたすら言葉を練り上げて、泣かせる台詞、いい台詞、おかしな台詞で、観客を唸らせることに命を懸けておいでになった。(井上ひさしのベスト3。丸谷才一編『私の選んだ文庫ベスト3』ハヤカワ文庫P28-29)
◎熱情と知性のはざまで
ハムレットは、将来を嘱望された王子でした。父の急死とあわただしい母の再婚に、心を痛めます。ハムレットは王である父を愛し、尊敬をしていました。しかし母が再婚した父の弟は、受け入れられる存在ではありませんでした。
そんなとき、父の幽霊が出現します。幽霊は自分を殺害したのは弟であることを告げ、復讐せよと命じます。しかしハムレットは幽霊の本性が見抜けず、逡巡してしまいます。そして父の死の真相を調べようと思います。
ハムレットを優柔不断な若者と思っている方は多いと思います。しかし「100分de名著」のなかで、河合祥一郎は次のように語っています。ハムレットは熱情と理性の人。気高く生きるためにどうしたらよいかを追求している人。この解説に触れて、私は新たなハムレット像を見つめなおしました。
河合祥一郎は、シェイクスピアがハムレットの分身を登場させているとも語っていました。その部分を意識して再読しますと、なるほど合点がいきました。詳細についてはあとから触れます。
・ホレイシオ(ハムレットの腹心の友):「理性」の象徴。
・レアーティーズ(ポローニアスの息子):「熱情」の象徴。
・フォーティンブラス(ノルウェー王子):「理性と熱情」を兼ね備えた人の象徴。
『ハムレット』の物語構造については、木下順二の著書から引かせていただきます。ハムレットが優柔不断に見えてしまうのは、。次の引用文で理解できます。
――ハムレットにとっては、自分の願望――叔父が犯人であることを確かめること――その願望へ着々と近づいて行く行為は、同時に最も願わしくないこと――復讐――へ着々と近づいて行くという行為だった。つまり願望を持てば持つほど願望から遠ざかるという、劇『オイディップス王』にわれわれが見たあの構造は、このようにして劇『ハムレット』に当てはまるわけです。(木下順二『劇的とは』岩波新書P68)
ソポクレス『オイディプス王』(岩波文庫、藤沢令夫訳)については、「山本藤光の文庫で読む500+α」で紹介済みです。そちらをご覧ください。ハムレットの心の葛藤について、もうひとつの論評を引かせていただきます。
――これ以上に、人間が生きて行く為に経験する苦しみとか、その終りを意味している筈の死とかいうものの性質が、実は我々に少しも解っていないということを的確に描写したものはない。それ故に、ハムレットは迷っているのではなくて、我々人間が置かれている立場を自分に確認させ、そして自分が発した問に対して答はないから、答えずにいるのである。(吉田健一『文学人生案内』講談社文芸文庫P107)
悩むハムレット以外に、ハムレットの行動に着目している文章もあります。
――ハムレットは確かに迷い、悩む。同時に、果敢に行動する。愛するオフィーリアに対して、「尼寺へゆきやがれ」と絶縁の言葉を突きつけ、その父親の侍従長ポローニアスを、間違えたとはいえ瞬時に刺殺し、己の母親を鋭い言葉でずたずたに切り裂く。(轡田隆史『名著の読み方・人生の見かたを変える』中経文庫P30)
このあたりは優柔不断どころか、直情径行のハムレットになっています。もうひとつ引用させていただきます。
――ハムレットの最大の行動は演技をすることである。周囲は敵ばかり。常に誰かに見張られている。見るものを観客だと考えれば、そのただなかに立つハムレットは彼らの視線を意識して演技をせざるをえない。(松岡和子『「もの」で読む入門シェイクスピア』ちくま文庫P39)
◎意味深な結末
2014年は、シェイクスピア生誕450年でした。この年は日本の永禄7年にあたり、5回目の川中島の戦いをしていました。シェイクスピアが『ハムレット』を書いたのは1600年ころといわれています。、40歳の手前あたりに、今なお色あせることのない戯曲を発表したのです。
『ハムレット』の結末(第5幕第2場)について、斉藤美奈子がユニークな文章を書いています。
――劇中に二度しか登場しない(なんだか上手くやったように見える)もうひとりの王子(補:フォーティンブラス)。非業の死をとげた王子(補:ハムレット)との差をどう考えるべきか。それが問題だ。(斎藤美奈子『名作うしろ読み』中央公論新社P47)
フォーティンブラス(ノルウェー王子)については、先に「理性の熱情」を兼ね備えた人の象徴と紹介しました。斉藤美奈子の文章を読んで、物語の完結にふさわしい人だったのだと認識させられました。
ホレイシオ(ハムレットの腹心の友。「理性」の象徴)の役割についても、引用しておきたいと思います。河合隼雄と松岡和子との対談のなかで、河合は次のように語っています。
――ハムレットは初めからまっしぐらに死の世界に向かって行く主人公ですね。まわりもほとんど全員が死ぬ。その中で、ホレイショーだけは非常に大事な役だと思いました。最初から最後まで見届け、それを語る役目、言ってみればシェイクスピア自身ですよ。(河合隼雄×松岡和子『シェイクスピア』新潮文庫P173)
最後に私がなぜ数ある訳書のなかから、角川文庫を選んだのかについて、その理由をもうひとつだけ書かせていただきます。それは角川文庫の巻末の野村萬斉(狂言師)の「後口上」に書かれたことに感動したからです。野村萬斉は自らが演ずるために、河合祥一郎に新訳を依頼したのです。
――私は口承の日本語文化を受け継ぐ狂言師ということに起因しますが、英文学翻訳読物劇ではなく、聞いて実感が持てる日本語戯曲音読劇としてのシェイクスピアを上演したかったのです。(野村萬斉)
そんなわけで、私は角川文庫を再読して、この原稿の改稿作業をしました。何度読んでも、『ハムレット』は新しく感じます。私の蔵書のなかには、まだまだ数多い『ハムレット』の書評があります。おそらく本書の数十倍のボリュームだと思います。
(山本藤光:2012.09.25初稿、2018.03.12改稿)