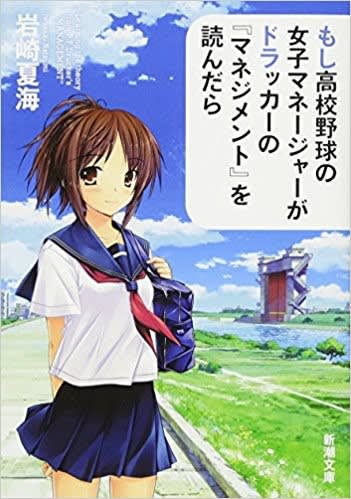石原慎太郎『太陽の季節』(新潮文庫)

石川達三、井上靖、中村光夫、舟橋聖一は〇、佐藤春夫、宇野浩二、丹羽文雄、滝井孝作は×、芥川賞選考会でも評価は真っ二つ! 女とは肉体の歓び以外のものではない。友とは取引の相手でしかない……。退屈で窮屈な既成の価値や倫理にのびやかに反逆し、若き戦後世代の肉体と性を真正面から描いた「太陽の季節」。最年少で芥川賞を受賞したデビュー作は戦後社会に新鮮な衝撃を与えた。(Amazon)
◎日本のために
石原慎太郎氏が89歳で世を去りました。作家、政治家、東京都知事と積極的に人生を突き進んだ、偉大な先達に敬意を表したいと思います。
石原慎太郎氏への哀悼で、胸を打たれたものがあります。紹介させていただきます。
――国家を奪われ、経済を失い、そして今や人間すら消失しかかっている、この国の長い長い「戦後」に対する最後の反逆者、その果敢なる表現者の死を今は悼むだけである。(富岡幸一郎。産経新聞2022年2月10日朝刊)
石原慎太郎は1932年生まれですから、終戦を迎えたときは中学生でした。まさに進駐軍が肩をきって闊歩している姿が、トラウマになっていたのだと思います。
政治家・石原慎太郎に仕えた、江崎道朗氏のコメントを引用しておきます。以下、石原慎太郎の言葉です。(虎の門ニュース2022年2月2日放送)
――日本は自分の足で立てる国にならなければいけない、
――国家あっての文学である。
つまり晩年の石原は、軸足を日本のために、と大きく動かしています。才能豊かな文学の土壌を離れて。
◎評価は真っ二つ
石原慎太郎の文壇デビューは、センセーショナルなものでした。処女作『太陽の季節』(新潮文庫)の選評は真っ二つだったものの、史上最年少(当時)で芥川賞を射止めました。
この原稿はずっと以前、PHPメルマガ「ブックチェイス」に掲載したものに加筆修正しています。訃報に接し、「山本藤光の文庫で読む500+α」に転載することにしました。これまで発表を控えていたのは、『太陽の季節』を肯定していなかったからです。このたび再読してみました。
やはり貧乏学生だった私には、ぼんぼん学生の世界は理解できません。したがって、できるだけ多くの『太陽の季節』論を紹介することにしました。
まずは芥川賞の選評から、いくつか引用しておきます。
――井上靖:その力倆と新鮮なみずみずしさに於て抜群だと思った。問題になるものを沢山含みながら、やはりその達者さと新鮮さには眼を瞑ることはできないといった作品であった。戦後の若い男女の生態を描いた風俗小説ではあるが、ともかく一人の―こんな青年が現代沢山いるに違いない―青年を理窟なしに無造作に投げ出してみせた作品は他にないであろう。
――吉田健一:体格は立派だが頭は痴呆の青年の生態を胸くそが悪くなるほど克明に描写した作品。ハード・ボイルド小説の下地がこの作品にはある。
――佐藤春夫:反倫理的なのは必ずも排撃はしないが、こういう風俗小説一般を文芸として最も低級なものと見ている上、この作者の鋭敏げな時代感覚もジャナリストや興行者の域を出ず、決して文学者のものではないと思ったし、またこの作品から作者の美的節度の欠如を見て最も嫌悪を禁じ得なかった。
いかがでしょうか。あなたはどの選評を支持しますか。選評は割れたものの、『太陽の季節』は一大ブームとなりました。無軌道な若者を指す「太陽族」という言葉が生まれ、「慎太郎刈り」という高くかりあげた頭髪まで流行しました。また本書はのちに映画化され、慎太郎の弟・裕次郎がデビューしています。
◎素直に愛することができない男女
石原慎太郎『太陽の季節』のすべては、冒頭の文章で表現されています。
――竜哉が強く英子に魅かれたのは、彼が拳闘に魅かれた気持ちと同じようなものがあった。/それには、リングで叩きのめされる瞬間、抵抗される人間だけが感じる、あの一種驚愕の入り混じった快感に通じるものが確かにあった。(本文冒頭より)
主人公の津川竜哉は、N学園の拳闘部に所属しています。私はずっと大学生と勘違いしていました。安藤宏・編『日本の小説101』(新書館)では、N学園を高校と書いてあります。再読してみると、正確には高校三年生でした。
しかし常識的に考えると、主人公が高校生であるのにはムリがあります。主人公たちは週末になったら、銀座で女給遊びをしています。公然とタバコをすったり、酒を飲んだりしています。私の勘違いは、そんな描写の連続によるものでした。
石原慎太郎は倫理を無視した、快楽至上主義の主人公をこれでもかと硬質な文章で描きまくります。ある日、竜哉は友人達と若い女をナンパします。そのなかのひとりが英子でした。竜哉は自分にまとわりつく英子を、煩わしく感じるようになります。そこで英子を金銭で兄に譲ったりもします。
竜哉は単なる遊びの範ちゅうだった女関係から、英子に魅かれだす衝動に揺さぶられる自分を感じます。この心の変化は、主人公を微妙に変えてゆきます。竜哉の心の中に固有名詞を持たない女ではない、英子の存在が鮮明になっていくのです。
林真理子は主人公について、次のように書いています。
――女を愛したり、溺れたりすることは自尊心が許さないのだ。恋することに照れ、羞恥し、やがては相手の女性を憎むようになる。これは思春期独特の感情である。(『林真理子の名作読本』文春文庫)
つまり竜哉に、大人の感情が芽生えてくるわけです。このあたりの転換は、本書の読みどころのひとつです。そして物語は、一気にエンディングへと向かいます。詳細には触れません。
樋口久仁は本書を次のようにまとめています。
――素直に愛することができない男女の逆説的な「恋愛」の形が描かれているのである。(安藤宏・編『日本の小説101』新書館)
この視点で本書を読むと、わかりやすくなります。裕福な家庭に生まれ育った男女の、思春期の物語。現在の世の中では絶対に生まれない、一握りの若者の群像が描かれた作品。『太陽の季節』は、「終戦」の落とし物なのです。
最後に、江藤淳の言葉を引いておきます。江藤淳は石原慎太郎を、読者にこびない作風と書いています。そして『太陽の季節』については、次のように論評しています。
――もし『太陽の季節』の主人公が、ヨットの陶酔のあとで、恋人の尻に敷かれて恐妻家にでもなっていけば、この作品は見事な小説になるかも知れない。(江藤淳『石原慎太郎・大江健三郎』中公文庫)
江藤淳が指摘するとおり、そうなればありきたりな普通の小説です。『太陽の季節』には「戦後」の混沌とした社会の匂いが、いたるところから立ちこめています。そんな時代に一石を投じ、社会現象としたのですから、本書は日本文学史上には残りつづける作品だと思います。
山本藤光2022.04.02

石川達三、井上靖、中村光夫、舟橋聖一は〇、佐藤春夫、宇野浩二、丹羽文雄、滝井孝作は×、芥川賞選考会でも評価は真っ二つ! 女とは肉体の歓び以外のものではない。友とは取引の相手でしかない……。退屈で窮屈な既成の価値や倫理にのびやかに反逆し、若き戦後世代の肉体と性を真正面から描いた「太陽の季節」。最年少で芥川賞を受賞したデビュー作は戦後社会に新鮮な衝撃を与えた。(Amazon)
◎日本のために
石原慎太郎氏が89歳で世を去りました。作家、政治家、東京都知事と積極的に人生を突き進んだ、偉大な先達に敬意を表したいと思います。
石原慎太郎氏への哀悼で、胸を打たれたものがあります。紹介させていただきます。
――国家を奪われ、経済を失い、そして今や人間すら消失しかかっている、この国の長い長い「戦後」に対する最後の反逆者、その果敢なる表現者の死を今は悼むだけである。(富岡幸一郎。産経新聞2022年2月10日朝刊)
石原慎太郎は1932年生まれですから、終戦を迎えたときは中学生でした。まさに進駐軍が肩をきって闊歩している姿が、トラウマになっていたのだと思います。
政治家・石原慎太郎に仕えた、江崎道朗氏のコメントを引用しておきます。以下、石原慎太郎の言葉です。(虎の門ニュース2022年2月2日放送)
――日本は自分の足で立てる国にならなければいけない、
――国家あっての文学である。
つまり晩年の石原は、軸足を日本のために、と大きく動かしています。才能豊かな文学の土壌を離れて。
◎評価は真っ二つ
石原慎太郎の文壇デビューは、センセーショナルなものでした。処女作『太陽の季節』(新潮文庫)の選評は真っ二つだったものの、史上最年少(当時)で芥川賞を射止めました。
この原稿はずっと以前、PHPメルマガ「ブックチェイス」に掲載したものに加筆修正しています。訃報に接し、「山本藤光の文庫で読む500+α」に転載することにしました。これまで発表を控えていたのは、『太陽の季節』を肯定していなかったからです。このたび再読してみました。
やはり貧乏学生だった私には、ぼんぼん学生の世界は理解できません。したがって、できるだけ多くの『太陽の季節』論を紹介することにしました。
まずは芥川賞の選評から、いくつか引用しておきます。
――井上靖:その力倆と新鮮なみずみずしさに於て抜群だと思った。問題になるものを沢山含みながら、やはりその達者さと新鮮さには眼を瞑ることはできないといった作品であった。戦後の若い男女の生態を描いた風俗小説ではあるが、ともかく一人の―こんな青年が現代沢山いるに違いない―青年を理窟なしに無造作に投げ出してみせた作品は他にないであろう。
――吉田健一:体格は立派だが頭は痴呆の青年の生態を胸くそが悪くなるほど克明に描写した作品。ハード・ボイルド小説の下地がこの作品にはある。
――佐藤春夫:反倫理的なのは必ずも排撃はしないが、こういう風俗小説一般を文芸として最も低級なものと見ている上、この作者の鋭敏げな時代感覚もジャナリストや興行者の域を出ず、決して文学者のものではないと思ったし、またこの作品から作者の美的節度の欠如を見て最も嫌悪を禁じ得なかった。
いかがでしょうか。あなたはどの選評を支持しますか。選評は割れたものの、『太陽の季節』は一大ブームとなりました。無軌道な若者を指す「太陽族」という言葉が生まれ、「慎太郎刈り」という高くかりあげた頭髪まで流行しました。また本書はのちに映画化され、慎太郎の弟・裕次郎がデビューしています。
◎素直に愛することができない男女
石原慎太郎『太陽の季節』のすべては、冒頭の文章で表現されています。
――竜哉が強く英子に魅かれたのは、彼が拳闘に魅かれた気持ちと同じようなものがあった。/それには、リングで叩きのめされる瞬間、抵抗される人間だけが感じる、あの一種驚愕の入り混じった快感に通じるものが確かにあった。(本文冒頭より)
主人公の津川竜哉は、N学園の拳闘部に所属しています。私はずっと大学生と勘違いしていました。安藤宏・編『日本の小説101』(新書館)では、N学園を高校と書いてあります。再読してみると、正確には高校三年生でした。
しかし常識的に考えると、主人公が高校生であるのにはムリがあります。主人公たちは週末になったら、銀座で女給遊びをしています。公然とタバコをすったり、酒を飲んだりしています。私の勘違いは、そんな描写の連続によるものでした。
石原慎太郎は倫理を無視した、快楽至上主義の主人公をこれでもかと硬質な文章で描きまくります。ある日、竜哉は友人達と若い女をナンパします。そのなかのひとりが英子でした。竜哉は自分にまとわりつく英子を、煩わしく感じるようになります。そこで英子を金銭で兄に譲ったりもします。
竜哉は単なる遊びの範ちゅうだった女関係から、英子に魅かれだす衝動に揺さぶられる自分を感じます。この心の変化は、主人公を微妙に変えてゆきます。竜哉の心の中に固有名詞を持たない女ではない、英子の存在が鮮明になっていくのです。
林真理子は主人公について、次のように書いています。
――女を愛したり、溺れたりすることは自尊心が許さないのだ。恋することに照れ、羞恥し、やがては相手の女性を憎むようになる。これは思春期独特の感情である。(『林真理子の名作読本』文春文庫)
つまり竜哉に、大人の感情が芽生えてくるわけです。このあたりの転換は、本書の読みどころのひとつです。そして物語は、一気にエンディングへと向かいます。詳細には触れません。
樋口久仁は本書を次のようにまとめています。
――素直に愛することができない男女の逆説的な「恋愛」の形が描かれているのである。(安藤宏・編『日本の小説101』新書館)
この視点で本書を読むと、わかりやすくなります。裕福な家庭に生まれ育った男女の、思春期の物語。現在の世の中では絶対に生まれない、一握りの若者の群像が描かれた作品。『太陽の季節』は、「終戦」の落とし物なのです。
最後に、江藤淳の言葉を引いておきます。江藤淳は石原慎太郎を、読者にこびない作風と書いています。そして『太陽の季節』については、次のように論評しています。
――もし『太陽の季節』の主人公が、ヨットの陶酔のあとで、恋人の尻に敷かれて恐妻家にでもなっていけば、この作品は見事な小説になるかも知れない。(江藤淳『石原慎太郎・大江健三郎』中公文庫)
江藤淳が指摘するとおり、そうなればありきたりな普通の小説です。『太陽の季節』には「戦後」の混沌とした社会の匂いが、いたるところから立ちこめています。そんな時代に一石を投じ、社会現象としたのですから、本書は日本文学史上には残りつづける作品だと思います。
山本藤光2022.04.02