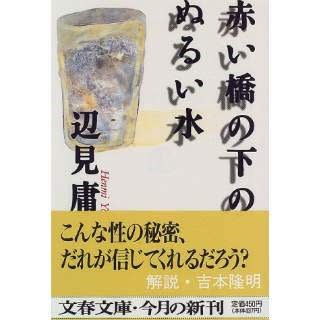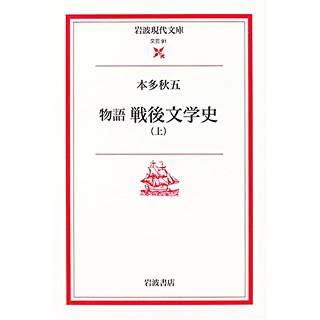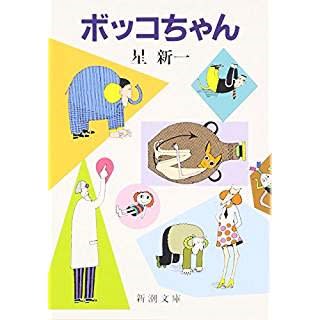本多孝好『真夜中の五分前』(2冊セット、新潮文庫)

![]()
◎『MISSING』から『ALONE TOGETHER』へ
本多孝好のデビュー作『MISSING』(双葉文庫、初出1999年)を読んだときの衝撃を忘れていません。小説推理新人賞受賞「眠りの海」に、4本の短篇を加えた作品集でした。つぎに読んだ作品は、『ALONE TOGETHER』(双葉文庫)でした。PHPメルマガ「ブックチェイス」に掲載したものを引用してみたいと思います。
(引用はじめ)
『ALONE TOGETHER』は、呪いをあつかった不思議な作品です。主人公の柳瀬は元医大生。入学した夏には退学しています。今は塾の先生をしています。この塾が変っています。不登校生を集めた塾でさえ、対応できない生徒ばかりの面倒をみているのです。
柳瀬は医大のとき、脳神経科の教授・笠原にこんな質問をしています。
――「(脳に)呪いの入り込む余地はあるとお考えですか?」
「他者の意思により無意識の領域に情報としてインプットされ、その脳を持つ個体そのものを操る可能性です。」(本文より)
3年後、柳瀬は笠井教授に呼び出され、立花サクラ(14歳)を守ってやってほしいとの依頼受けます。そのころから柳瀬は、フリーライターにつきまとわれます。笠井教授が患者を故意に殺したというのです。
最終処分場と呼ばれる塾の生徒と先生。立花サクラの通う女子中学校の仲間たち。殺人を犯したかもしれない教授と事件を追う人たち。そして2つの波長が共鳴したときの恐怖。
本多孝好は、まだすべての機能が明らかにされていない脳から、恐ろしいテーマを発見しました。呪い殺す。脳にはそんな機能があるのでしょうか。遺伝。この作品の本当の恐怖は、それが下敷きとなっていることです。
本多孝好はとんでもない素材を、巧みな会話と文章で迫力ある作品に仕上げました。目が離せない新人なのです。
(引用おわり、PHP研究所メルマガ「ブックチェイス」2000年11月22日号より)
本多孝好は自分の小説家としてのスタンスを、つぎのように語っています。ちょっと長くなりますが、この微妙な立ち位置が本多作品のおもしろさなのだと思います。
―― 一連の作品を書いていく中で、「本多さんのテーマは癒しですね」「救いですね」とか言われるようになったんですよ。ちょうどそのころの世間でもそういう言葉がはやっていて、それに対する反発がありました。個人の抱えている、社会の中で解消されない部分の中には、表に出すと出した側が社会から攻撃を受けてしまうので出さないものもあれば、出すと出した相手側が社会を攻撃してしまうから出せないというのがあると思うんですよね。その後者の部分というのを書いてみたかったんです。善なる部分というよりは、悪なる部分ですね。(『小説推理新人賞受賞作アンソロジー』双葉文庫、巻末ロングインタビューより)
◎そして本多孝好ワールドの完成
『真夜中の五分前』(2冊セット、新潮文庫)を、本多孝好の代表作として紹介したいと思います。本書はside-Aとside-Bに分かれており、前者は一卵性姉妹との恋の話、後者はその2年後の話です。本多孝好はこれまで自死、喪失というテーマから離れられませんでした。それが前記インタビューの言葉のとおり、本書にて新天地をひらいたといえます。
北上次郎は著作『エンターテインメント作家ファイル』(本の雑誌社)のなかで、本多孝好を盛田隆二や佐藤正午とならぶ「油断のできない作家」と書いています。確かにこれまではそうだったのですが、本書を機に「安定感のある作家」になっていくことと思います。
『真夜中の五分前』では2つの物語が、交互に描かれています。仕事と日常。主人公の「僕」は、いずれにも深くのめりこんではいません。主人公は小さな広告代理店に勤めています。職場には、部下に厳しい女性の上司がいます。職場のみんなが嫌っているのに、「僕」にとっては煙たい存在ではありません。
主人公は大学時代につきあっていた恋人を、交通事故で亡くしています。彼女には、目覚し時計を5分間だけ遅らせておく習慣がありました。主人公の部屋の目覚し時計は、まだそのままになっています。
「5分間のズレ」は、主人公の生きざまの象徴として描かれています。主人公はほかの人とくらべて、仕事も日常も少しだけズレているのです。そんな主人公は、新しい女性と出会います。一卵性双生児の彼女との出会いで、主人公の日常が変化しはじめます。
本多孝好は、また意外なストーリーを展開してくれました。ひさしぶりで、不思議な世界を堪能させてもらいました。作品の性格上、これ以上深入りはしませんが、自信をもってお薦めできる作品です。本多孝好ワールドを、楽しんでもらいたいと思います。
直木賞に最も近い作家の初期作品を、ぜひお読みください。
(山本藤光:2010.11.22初稿、2018.10.03改稿)

◎『MISSING』から『ALONE TOGETHER』へ
本多孝好のデビュー作『MISSING』(双葉文庫、初出1999年)を読んだときの衝撃を忘れていません。小説推理新人賞受賞「眠りの海」に、4本の短篇を加えた作品集でした。つぎに読んだ作品は、『ALONE TOGETHER』(双葉文庫)でした。PHPメルマガ「ブックチェイス」に掲載したものを引用してみたいと思います。
(引用はじめ)
『ALONE TOGETHER』は、呪いをあつかった不思議な作品です。主人公の柳瀬は元医大生。入学した夏には退学しています。今は塾の先生をしています。この塾が変っています。不登校生を集めた塾でさえ、対応できない生徒ばかりの面倒をみているのです。
柳瀬は医大のとき、脳神経科の教授・笠原にこんな質問をしています。
――「(脳に)呪いの入り込む余地はあるとお考えですか?」
「他者の意思により無意識の領域に情報としてインプットされ、その脳を持つ個体そのものを操る可能性です。」(本文より)
3年後、柳瀬は笠井教授に呼び出され、立花サクラ(14歳)を守ってやってほしいとの依頼受けます。そのころから柳瀬は、フリーライターにつきまとわれます。笠井教授が患者を故意に殺したというのです。
最終処分場と呼ばれる塾の生徒と先生。立花サクラの通う女子中学校の仲間たち。殺人を犯したかもしれない教授と事件を追う人たち。そして2つの波長が共鳴したときの恐怖。
本多孝好は、まだすべての機能が明らかにされていない脳から、恐ろしいテーマを発見しました。呪い殺す。脳にはそんな機能があるのでしょうか。遺伝。この作品の本当の恐怖は、それが下敷きとなっていることです。
本多孝好はとんでもない素材を、巧みな会話と文章で迫力ある作品に仕上げました。目が離せない新人なのです。
(引用おわり、PHP研究所メルマガ「ブックチェイス」2000年11月22日号より)
本多孝好は自分の小説家としてのスタンスを、つぎのように語っています。ちょっと長くなりますが、この微妙な立ち位置が本多作品のおもしろさなのだと思います。
―― 一連の作品を書いていく中で、「本多さんのテーマは癒しですね」「救いですね」とか言われるようになったんですよ。ちょうどそのころの世間でもそういう言葉がはやっていて、それに対する反発がありました。個人の抱えている、社会の中で解消されない部分の中には、表に出すと出した側が社会から攻撃を受けてしまうので出さないものもあれば、出すと出した相手側が社会を攻撃してしまうから出せないというのがあると思うんですよね。その後者の部分というのを書いてみたかったんです。善なる部分というよりは、悪なる部分ですね。(『小説推理新人賞受賞作アンソロジー』双葉文庫、巻末ロングインタビューより)
◎そして本多孝好ワールドの完成
『真夜中の五分前』(2冊セット、新潮文庫)を、本多孝好の代表作として紹介したいと思います。本書はside-Aとside-Bに分かれており、前者は一卵性姉妹との恋の話、後者はその2年後の話です。本多孝好はこれまで自死、喪失というテーマから離れられませんでした。それが前記インタビューの言葉のとおり、本書にて新天地をひらいたといえます。
北上次郎は著作『エンターテインメント作家ファイル』(本の雑誌社)のなかで、本多孝好を盛田隆二や佐藤正午とならぶ「油断のできない作家」と書いています。確かにこれまではそうだったのですが、本書を機に「安定感のある作家」になっていくことと思います。
『真夜中の五分前』では2つの物語が、交互に描かれています。仕事と日常。主人公の「僕」は、いずれにも深くのめりこんではいません。主人公は小さな広告代理店に勤めています。職場には、部下に厳しい女性の上司がいます。職場のみんなが嫌っているのに、「僕」にとっては煙たい存在ではありません。
主人公は大学時代につきあっていた恋人を、交通事故で亡くしています。彼女には、目覚し時計を5分間だけ遅らせておく習慣がありました。主人公の部屋の目覚し時計は、まだそのままになっています。
「5分間のズレ」は、主人公の生きざまの象徴として描かれています。主人公はほかの人とくらべて、仕事も日常も少しだけズレているのです。そんな主人公は、新しい女性と出会います。一卵性双生児の彼女との出会いで、主人公の日常が変化しはじめます。
本多孝好は、また意外なストーリーを展開してくれました。ひさしぶりで、不思議な世界を堪能させてもらいました。作品の性格上、これ以上深入りはしませんが、自信をもってお薦めできる作品です。本多孝好ワールドを、楽しんでもらいたいと思います。
直木賞に最も近い作家の初期作品を、ぜひお読みください。
(山本藤光:2010.11.22初稿、2018.10.03改稿)