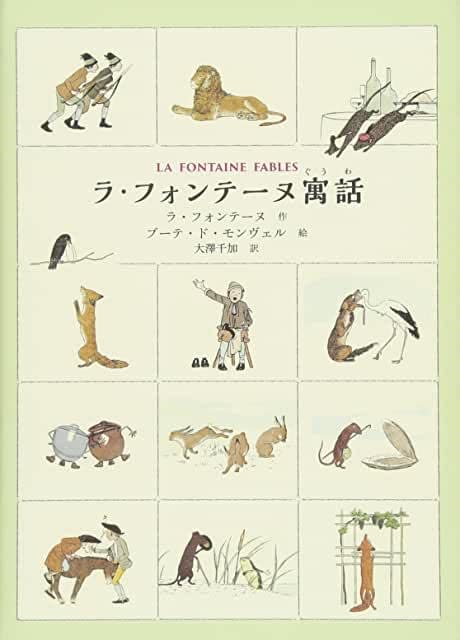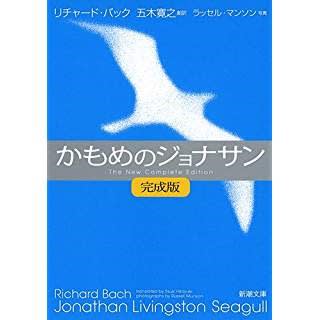クリスチアナ・ブランド『ジェミニー・クリケット事件』(『招かれざる客たちのビュッフェ』創元推理文庫所収)

英国ミステリ界の重鎮ブランド。本書にはその独特の調理法にもとづく16の逸品を収めた。コックリル警部登場の重厚な本格物「婚姻飛翔」、スリルに満ちた謎解きゲームの顛末を描く名作「ジェミニー・クリケット事件」、あまりにもブラックなクリスマス・ストーリー「この家に祝福あれ」など、ミステリの真髄を示す傑作短編集(Amazon)
◎アメリカ版とイギリス版
実は当初、『招かれざる客たちのビュッフェ』(創元推理文庫)の全16作品について書評を書くつもりでいました。ところが『北村薫の本格ミステり・ライブラリー』(角川文庫)を読んでいて私の知らない、もうひとつの『ジェミニー・クリケット事件』の存在を知りました。
北村薫は「アメリカ版」と明記して、同作品を『北村薫の本格ミステリ・ライブラリー』に所収したのです。北村薫は本作をアンソロジーの1作品として入れてくれる条件で、編集を引き受けたと書いています。
――これ(補:『ジェミニー・クリケット事件』)を入れてもらえるなら、アンソロジーをやりましょう。(『北村薫の本格ミステリ・ライブラリー』P331より)
というわけで、私が読んだ作品は「イギリス版」だったようです。さっそく「アメリカ版」も読んでみました。大筋は変わりませんが、結末部分に明かな違いがありました。どっちが優れているかの評価はネット民におまかせして、入手しやしい「イギリス版」を紹介することにします。
本作は、『短編ミステリの二百年6』(創元推理文庫)と『51番目の密室・世界短篇傑作集』(ハヤカワポケットミステリ)にも所収されています。
最初に明記しておきたいのは、本書は密室ミステリとして世界的に評価が高いという点です。老人と青年が語り合いながら、謎解きを行うという風変わりな仕掛になっています。舞台はほとんど動きません。紹介しようと思っていた他の15作品を傍らにおいて、『ジェミニー・クリケット事件』にのみ集中して紹介させていただきます。
これまでに、たくさんの密室殺人事件を読んできました。高評価してきた作品を押しのけて、本書を密室殺人事件のナンバーワンとして、推挙させていただきます。
◎クリスチアナ・ブランドについて
クリスチアナ・ブランドのプロフィールを、紹介しておきます。
――マレーシア生まれの英国作家で、こども時代はインドに滞在していた。帰国後、十七歳のときに父親が破産したため、進学を諦めて就職することを余儀なくされる。モデルや販売業などさまざまな職業に就いたが、その経験がデビュー長編『ハイヒールの死』(ハヤカワ・ミステリ文庫)には活かされた。(杉江松恋・編『ミステリマガジン700海外篇』ハヤカワ文庫P176)
『ハイヒールの死』は調理器具の売り子として働きながら書き始めたもので、嫌な同僚と接する中からアイデアが生まれたといわれています。
クリスチアナ・ブランドは、クリスティやクイーンとならんで世界的に評価の高い女流作家です。ただし日本での評価は最近のものです。
――1990年に短篇集『招かれざる客たちのビュッフェ』(1983)が深町真理子訳(創元推理文庫)で紹介されると一躍脚光を浴び、それ以前に出ていた旧訳作品も見直されることになった。「いい作品はいつか評価される」という見本のようなケースである。(郷原宏『このミステリーを読め・海外篇』王様文庫P98)
ブランドには他に、『緑は危険』(ハヤカワ文庫)や『ジェゼベルの死』(ハヤカワ文庫)などの優れた作品があります。しかし、いずれも入手困難本になっています。
◎「なんでここへきたんだね?」
ジェイルズ青年は20年ぶりに、謎解きの大好きな老人を訪ねます。彼が老人に語り始めたのは、弁護士トマス・ジェミニーが殺害された密室殺人のてんまつでした。トマス・ジェミニーには、三人の養子がいました。ジェイルズ青年はそのなかの一人です。他の二人は、ルーパート青年とヘレンという若い女性です。この三人は、いずれも死んだトマス・ジェミニーの近くで生活しています。したがって、当然容疑者として扱われます。
ジェイルズは、当時を思い出しながら語り出します。死の直前にトマス・ジェミニーは、警察に助けを求める電話をしています。しかしその言葉は、不可解なものでした。「どこへともなく消えていく」「長い腕が……」
この電話を受けて、警察はトマス・ジェミニーの事務所に駆けつけます。
――ドアには内側からかんぬきがかってあり、窓が割れていた。割れたガラスのふちが、いまだに小刻みにふるえていましたよ。ところが部屋は四階なんです。被害者は首を絞められ、そのうえ椅子に縛り付けられて、刺されていた。(本文P199)
完全な密室殺人事件。老人はジェイルズの話に耳を傾け、ときには質問したり考えこんだりします。ところがこの事件は、まったく別の展開をみせます。パトロールに出ていた巡査から、本署に電話が入ります。電話口で巡査は、「どこへともなく消えていく」「長い腕が……」と、恐怖の叫びをあげます。巡査が電話をかけてきた、公衆電話がつきとめられます。そして工場跡地の水槽のなかから、巡査の死体が発見されます。二つの殺人事件は、当然同一犯によるものと断定されます。
本書を読むときに、心に留めておいてもらいたいことがあります。老人とジェイルズのやりとりが間延びする場面では、活字から目をあげて考えてみてください。もうひとつは、二人が会話をしている場所の正体です。細心の注意を払って、活字を拾わなければなりません。ここを一刻も早く発見したら、一挙にエンディングの謎が解けます。
私は一回目の読書では最終ページになって、やっと謎が解けました。匍匐前進の再読で、二人のやりとりの裂け目を発見しました。二人がやりとりしている場所に、もっと早く気づくべきだったと恥じ入りました。エンディングの謎がわからなかった人は、答えは『短編ミステリの二百年6』(創元推理文庫)の576ページにあります。書店で立ち読みでもして、確認してください。
ヒントは『招かれざる客たちのビュッフェ』所収『ジェミニー・クリケット事件』の冒頭ページにあります。立ち働いている男たちの存在。老人が青年に尋ねる言葉の意味。この箇所で本書の構図をつかまえていたら、と悔しい思いをしました。
――かなたの色とりどりの花壇では、鍬や鋤を手にした男たちが立ち働いている。「ところでなんでここへきたんだね?」(本文P198)
私はこの描写で、老人は豪邸に住んでいると思いこんでしまいました。とんだ早とちりでした。
最後にミステリ界の重鎮たちの、本書に対する評価をご紹介しておきます。
――森英俊は『世界ミステリ作家事典(本格派篇)』(補:図書刊行会)のブランドの項で、本作を「古今の密室テーマの短編で三本の指にはいる傑作」としているが、わたしも同感だ。トリックがよくできているだけでなく、その演出が抜群にうまい。
(『有栖川有栖の密室大図鑑』(創元推理文庫、P157)
本書を知らずして、ミステリを、ましてや密室殺人事件を語るなかれ。
山本藤光2022.04.05

英国ミステリ界の重鎮ブランド。本書にはその独特の調理法にもとづく16の逸品を収めた。コックリル警部登場の重厚な本格物「婚姻飛翔」、スリルに満ちた謎解きゲームの顛末を描く名作「ジェミニー・クリケット事件」、あまりにもブラックなクリスマス・ストーリー「この家に祝福あれ」など、ミステリの真髄を示す傑作短編集(Amazon)
◎アメリカ版とイギリス版
実は当初、『招かれざる客たちのビュッフェ』(創元推理文庫)の全16作品について書評を書くつもりでいました。ところが『北村薫の本格ミステり・ライブラリー』(角川文庫)を読んでいて私の知らない、もうひとつの『ジェミニー・クリケット事件』の存在を知りました。
北村薫は「アメリカ版」と明記して、同作品を『北村薫の本格ミステリ・ライブラリー』に所収したのです。北村薫は本作をアンソロジーの1作品として入れてくれる条件で、編集を引き受けたと書いています。
――これ(補:『ジェミニー・クリケット事件』)を入れてもらえるなら、アンソロジーをやりましょう。(『北村薫の本格ミステリ・ライブラリー』P331より)
というわけで、私が読んだ作品は「イギリス版」だったようです。さっそく「アメリカ版」も読んでみました。大筋は変わりませんが、結末部分に明かな違いがありました。どっちが優れているかの評価はネット民におまかせして、入手しやしい「イギリス版」を紹介することにします。
本作は、『短編ミステリの二百年6』(創元推理文庫)と『51番目の密室・世界短篇傑作集』(ハヤカワポケットミステリ)にも所収されています。
最初に明記しておきたいのは、本書は密室ミステリとして世界的に評価が高いという点です。老人と青年が語り合いながら、謎解きを行うという風変わりな仕掛になっています。舞台はほとんど動きません。紹介しようと思っていた他の15作品を傍らにおいて、『ジェミニー・クリケット事件』にのみ集中して紹介させていただきます。
これまでに、たくさんの密室殺人事件を読んできました。高評価してきた作品を押しのけて、本書を密室殺人事件のナンバーワンとして、推挙させていただきます。
◎クリスチアナ・ブランドについて
クリスチアナ・ブランドのプロフィールを、紹介しておきます。
――マレーシア生まれの英国作家で、こども時代はインドに滞在していた。帰国後、十七歳のときに父親が破産したため、進学を諦めて就職することを余儀なくされる。モデルや販売業などさまざまな職業に就いたが、その経験がデビュー長編『ハイヒールの死』(ハヤカワ・ミステリ文庫)には活かされた。(杉江松恋・編『ミステリマガジン700海外篇』ハヤカワ文庫P176)
『ハイヒールの死』は調理器具の売り子として働きながら書き始めたもので、嫌な同僚と接する中からアイデアが生まれたといわれています。
クリスチアナ・ブランドは、クリスティやクイーンとならんで世界的に評価の高い女流作家です。ただし日本での評価は最近のものです。
――1990年に短篇集『招かれざる客たちのビュッフェ』(1983)が深町真理子訳(創元推理文庫)で紹介されると一躍脚光を浴び、それ以前に出ていた旧訳作品も見直されることになった。「いい作品はいつか評価される」という見本のようなケースである。(郷原宏『このミステリーを読め・海外篇』王様文庫P98)
ブランドには他に、『緑は危険』(ハヤカワ文庫)や『ジェゼベルの死』(ハヤカワ文庫)などの優れた作品があります。しかし、いずれも入手困難本になっています。
◎「なんでここへきたんだね?」
ジェイルズ青年は20年ぶりに、謎解きの大好きな老人を訪ねます。彼が老人に語り始めたのは、弁護士トマス・ジェミニーが殺害された密室殺人のてんまつでした。トマス・ジェミニーには、三人の養子がいました。ジェイルズ青年はそのなかの一人です。他の二人は、ルーパート青年とヘレンという若い女性です。この三人は、いずれも死んだトマス・ジェミニーの近くで生活しています。したがって、当然容疑者として扱われます。
ジェイルズは、当時を思い出しながら語り出します。死の直前にトマス・ジェミニーは、警察に助けを求める電話をしています。しかしその言葉は、不可解なものでした。「どこへともなく消えていく」「長い腕が……」
この電話を受けて、警察はトマス・ジェミニーの事務所に駆けつけます。
――ドアには内側からかんぬきがかってあり、窓が割れていた。割れたガラスのふちが、いまだに小刻みにふるえていましたよ。ところが部屋は四階なんです。被害者は首を絞められ、そのうえ椅子に縛り付けられて、刺されていた。(本文P199)
完全な密室殺人事件。老人はジェイルズの話に耳を傾け、ときには質問したり考えこんだりします。ところがこの事件は、まったく別の展開をみせます。パトロールに出ていた巡査から、本署に電話が入ります。電話口で巡査は、「どこへともなく消えていく」「長い腕が……」と、恐怖の叫びをあげます。巡査が電話をかけてきた、公衆電話がつきとめられます。そして工場跡地の水槽のなかから、巡査の死体が発見されます。二つの殺人事件は、当然同一犯によるものと断定されます。
本書を読むときに、心に留めておいてもらいたいことがあります。老人とジェイルズのやりとりが間延びする場面では、活字から目をあげて考えてみてください。もうひとつは、二人が会話をしている場所の正体です。細心の注意を払って、活字を拾わなければなりません。ここを一刻も早く発見したら、一挙にエンディングの謎が解けます。
私は一回目の読書では最終ページになって、やっと謎が解けました。匍匐前進の再読で、二人のやりとりの裂け目を発見しました。二人がやりとりしている場所に、もっと早く気づくべきだったと恥じ入りました。エンディングの謎がわからなかった人は、答えは『短編ミステリの二百年6』(創元推理文庫)の576ページにあります。書店で立ち読みでもして、確認してください。
ヒントは『招かれざる客たちのビュッフェ』所収『ジェミニー・クリケット事件』の冒頭ページにあります。立ち働いている男たちの存在。老人が青年に尋ねる言葉の意味。この箇所で本書の構図をつかまえていたら、と悔しい思いをしました。
――かなたの色とりどりの花壇では、鍬や鋤を手にした男たちが立ち働いている。「ところでなんでここへきたんだね?」(本文P198)
私はこの描写で、老人は豪邸に住んでいると思いこんでしまいました。とんだ早とちりでした。
最後にミステリ界の重鎮たちの、本書に対する評価をご紹介しておきます。
――森英俊は『世界ミステリ作家事典(本格派篇)』(補:図書刊行会)のブランドの項で、本作を「古今の密室テーマの短編で三本の指にはいる傑作」としているが、わたしも同感だ。トリックがよくできているだけでなく、その演出が抜群にうまい。
(『有栖川有栖の密室大図鑑』(創元推理文庫、P157)
本書を知らずして、ミステリを、ましてや密室殺人事件を語るなかれ。
山本藤光2022.04.05