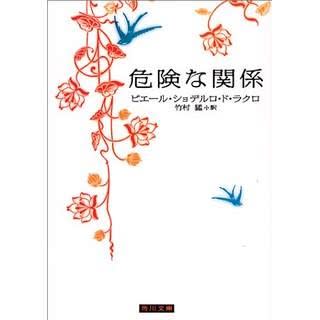リルケ『マルテの手記』(新潮文庫、大山定一訳)

青年作家マルテをパリの町の厳しい孤独と貧しさのどん底におき、生と死の不安に苦しむその精神体験を綴る詩人リルケの魂の告白。(内容紹介より)
◎純粋な空間しか映らない
卒論に安部公房を選んだ関係で、彼が影響を受けた作家はほとんど読んでいました。リルケもそのなかの一人ですが、あまり深く影響されていないと安部公房本人が書いています。ずっと安部公房が書いている、次の文章が気になっていました。
――リルケの世界は、時間の停止だったのである。停止というよりも、遮断といったほうが、もっと正確かもしれない。リルケはほとんど時間を歌わない。彼の眼には、純粋な空間しか映らないかのようだ。彼にとって、存在とは、「もの」の形のことだったらしいのだ。(『安部公房全集第21巻』新潮社P437。註:本文中の「もの」は傍点です)
そして今回再読してみて、『マルテの手記』(新潮文庫、大山定一訳)は安部公房の指摘どおりであることを実感しました。
掘辰雄に『マルテの手記』と題する短文があります。青空文庫で読むことができます。そのなかでリルケ自身が友人に語ったとするエピソードが紹介されています。
――リルケは「生」の問題を最後まで考へ、最後まで見究めんとして彼の分身マルテをその「生」の最もぎりぎりのところ――殆ど「死」の傍――に終始立たしめた。あまりに弱い神經の持主マルテにはこれ以上殆ど生きがたいやうにさへ見える。しかしリルケは「生きることの不可能なことを殆ど證明するに了つたかに見えるこの本は、この本自身の流れに逆ひつつ讀まれなければならない」と友人への手紙にいふ。(青空文庫)
◎セザンヌの絵画のよう
リルケ『マルテの手記』(新潮文庫、大山定一訳)は、日記を連ねただけの断片で物語性はありません。主人公の「僕」は28歳で、詩や戯曲を書いています。ただし、満足できるものは書けません。僕は孤独と死の恐怖にさいなまれています。
ぼくが移り住んできたパリには、あらゆる種類の刺激があります。さまざまな人が暮らしています。僕はまずしっかりとそれらを見据えようと考えます。少しだけ僕が出会った人群れを引いてみます。
――僕は一人の男がよろめいて、ぶっ倒れたのを見た。(本文P8)
――僕はしばらくして一人の妊婦と出会った。(本文P8)
――今日、このほかに僕が見たのは、置きっぱなしの乳母車に乗せてあった子供である。(本文P8)
引用のような事物のスケッチの後、僕は幼年期の回想をします。死を目前にした祖父の人格の変化。幽霊を見たこと。壁から手が突きでてきたこと。回想は際限なくつづきます。こんな具合です。
――どんな不思議なことが起こっても驚かないつもりだった。しかも、突然壁の中から別なもう一つの手が出て来ようとは、僕は夢にも思わなかった。それは僕の見たこともない、大きな、ひどく痩せ細った手だった。(本文P114)
僕は「見ることを学んでいる」はずなのですが、実際にみているのは引用例のように彼にとって不可思議なものです。僕は質感のないものを見て、瞬時にそれをイメージとして構築します。そしてすぐにそれを壊してしまいます。僕はみているものには形がありますが、壊されたあとには何も残りません。
ふたたび孤独や死にかんする、エピソードが語られます。そして詩人たちが描いた女性の愛についての所感が述べられます。
僕の孤独な心のなかには、神が同居しています。僕は何度も神に問いかけます。リルケは心象風景を、抽象画のようにつまみだします。大学時代に難儀しながら読んだのは、岩波文庫(望月市恵訳)でした。今回新潮文庫で再読してみて、すらすらと読めることに驚きました。私は「抽象画のように」とたとえました。しかし、石光泰夫の文章を読んで、なるほどと思いました。引用させていただきます。
――イメージの輪郭はみえすぎるくらい鮮明にみえているのに、そのイメージがいわば音楽のようにざわめきたって、揺らぐ水面の映像のようにもなってしまうのは、あの動的にせめぎ合いながらそれでも一定の輪郭へと納まってゆくセザンヌの絵画のタッチと同じ現象であろうか。(『世界文学101物語』高橋康也・編、石光泰夫・文、新書館P141)
◎視覚。聴覚・嗅覚を総動員
主人公マルテは「見ることを学ぶ」決心をしたのですが、彼は「味覚」以外の五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚)を総動員させています。妊婦に出会ってからの、文章で検証してみます。妊婦は市立参院へと行くのですが。僕は今度は陸軍病院にたどりつきます。
――街路がいっせいに匂いはじめた。ヨードホルムと馬鈴薯をいためる油脂と精神的な不安と、僕はどうやらこの三種の匂いをかぎ分けることが出来た。(本文P8)
パリを彷徨したのち、僕は部屋へ戻ります。今度は匂いから音の世界が描写されます。
――窓をあけたまま眠るのが、僕にはどうしてもやめられぬ。電車がベルをならして僕の部屋を走りぬける。自動車が僕を轢いて疾駆する。どこかでドアの締まる音がする。(本文P9)
12歳のときの回想場面では。触覚が登場します。僕は食事の席の不気味さに耐えられず、向いの席の父の膝に自分の足を乗せます。
――長い食事時間をよく我慢できたのは、このかすかな接触が与えてくれた力づけのお陰であった。(本文P35)
リルケは感性豊かな詩人です。私は「味覚」の描写を3度も探しました。しかし発見できませんでした。また「触覚」に触れたのも1か所だけでした。つまり主人公マルテは、「視覚」をベースに、外部から感じられる「聴覚」と「嗅覚」を重んじたのだと思います。パッチワークのような詩片を、織りなしてシュールな散文に仕上げた手腕は、まさに天才のなせる技なのでしょう。
(山本藤光:2014.04.23初稿、2018.03.07改稿)

青年作家マルテをパリの町の厳しい孤独と貧しさのどん底におき、生と死の不安に苦しむその精神体験を綴る詩人リルケの魂の告白。(内容紹介より)
◎純粋な空間しか映らない
卒論に安部公房を選んだ関係で、彼が影響を受けた作家はほとんど読んでいました。リルケもそのなかの一人ですが、あまり深く影響されていないと安部公房本人が書いています。ずっと安部公房が書いている、次の文章が気になっていました。
――リルケの世界は、時間の停止だったのである。停止というよりも、遮断といったほうが、もっと正確かもしれない。リルケはほとんど時間を歌わない。彼の眼には、純粋な空間しか映らないかのようだ。彼にとって、存在とは、「もの」の形のことだったらしいのだ。(『安部公房全集第21巻』新潮社P437。註:本文中の「もの」は傍点です)
そして今回再読してみて、『マルテの手記』(新潮文庫、大山定一訳)は安部公房の指摘どおりであることを実感しました。
掘辰雄に『マルテの手記』と題する短文があります。青空文庫で読むことができます。そのなかでリルケ自身が友人に語ったとするエピソードが紹介されています。
――リルケは「生」の問題を最後まで考へ、最後まで見究めんとして彼の分身マルテをその「生」の最もぎりぎりのところ――殆ど「死」の傍――に終始立たしめた。あまりに弱い神經の持主マルテにはこれ以上殆ど生きがたいやうにさへ見える。しかしリルケは「生きることの不可能なことを殆ど證明するに了つたかに見えるこの本は、この本自身の流れに逆ひつつ讀まれなければならない」と友人への手紙にいふ。(青空文庫)
◎セザンヌの絵画のよう
リルケ『マルテの手記』(新潮文庫、大山定一訳)は、日記を連ねただけの断片で物語性はありません。主人公の「僕」は28歳で、詩や戯曲を書いています。ただし、満足できるものは書けません。僕は孤独と死の恐怖にさいなまれています。
ぼくが移り住んできたパリには、あらゆる種類の刺激があります。さまざまな人が暮らしています。僕はまずしっかりとそれらを見据えようと考えます。少しだけ僕が出会った人群れを引いてみます。
――僕は一人の男がよろめいて、ぶっ倒れたのを見た。(本文P8)
――僕はしばらくして一人の妊婦と出会った。(本文P8)
――今日、このほかに僕が見たのは、置きっぱなしの乳母車に乗せてあった子供である。(本文P8)
引用のような事物のスケッチの後、僕は幼年期の回想をします。死を目前にした祖父の人格の変化。幽霊を見たこと。壁から手が突きでてきたこと。回想は際限なくつづきます。こんな具合です。
――どんな不思議なことが起こっても驚かないつもりだった。しかも、突然壁の中から別なもう一つの手が出て来ようとは、僕は夢にも思わなかった。それは僕の見たこともない、大きな、ひどく痩せ細った手だった。(本文P114)
僕は「見ることを学んでいる」はずなのですが、実際にみているのは引用例のように彼にとって不可思議なものです。僕は質感のないものを見て、瞬時にそれをイメージとして構築します。そしてすぐにそれを壊してしまいます。僕はみているものには形がありますが、壊されたあとには何も残りません。
ふたたび孤独や死にかんする、エピソードが語られます。そして詩人たちが描いた女性の愛についての所感が述べられます。
僕の孤独な心のなかには、神が同居しています。僕は何度も神に問いかけます。リルケは心象風景を、抽象画のようにつまみだします。大学時代に難儀しながら読んだのは、岩波文庫(望月市恵訳)でした。今回新潮文庫で再読してみて、すらすらと読めることに驚きました。私は「抽象画のように」とたとえました。しかし、石光泰夫の文章を読んで、なるほどと思いました。引用させていただきます。
――イメージの輪郭はみえすぎるくらい鮮明にみえているのに、そのイメージがいわば音楽のようにざわめきたって、揺らぐ水面の映像のようにもなってしまうのは、あの動的にせめぎ合いながらそれでも一定の輪郭へと納まってゆくセザンヌの絵画のタッチと同じ現象であろうか。(『世界文学101物語』高橋康也・編、石光泰夫・文、新書館P141)
◎視覚。聴覚・嗅覚を総動員
主人公マルテは「見ることを学ぶ」決心をしたのですが、彼は「味覚」以外の五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚)を総動員させています。妊婦に出会ってからの、文章で検証してみます。妊婦は市立参院へと行くのですが。僕は今度は陸軍病院にたどりつきます。
――街路がいっせいに匂いはじめた。ヨードホルムと馬鈴薯をいためる油脂と精神的な不安と、僕はどうやらこの三種の匂いをかぎ分けることが出来た。(本文P8)
パリを彷徨したのち、僕は部屋へ戻ります。今度は匂いから音の世界が描写されます。
――窓をあけたまま眠るのが、僕にはどうしてもやめられぬ。電車がベルをならして僕の部屋を走りぬける。自動車が僕を轢いて疾駆する。どこかでドアの締まる音がする。(本文P9)
12歳のときの回想場面では。触覚が登場します。僕は食事の席の不気味さに耐えられず、向いの席の父の膝に自分の足を乗せます。
――長い食事時間をよく我慢できたのは、このかすかな接触が与えてくれた力づけのお陰であった。(本文P35)
リルケは感性豊かな詩人です。私は「味覚」の描写を3度も探しました。しかし発見できませんでした。また「触覚」に触れたのも1か所だけでした。つまり主人公マルテは、「視覚」をベースに、外部から感じられる「聴覚」と「嗅覚」を重んじたのだと思います。パッチワークのような詩片を、織りなしてシュールな散文に仕上げた手腕は、まさに天才のなせる技なのでしょう。
(山本藤光:2014.04.23初稿、2018.03.07改稿)