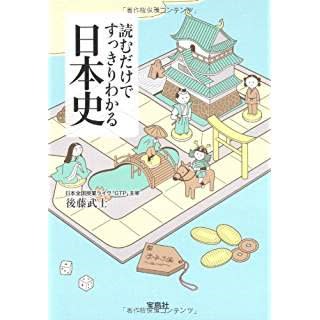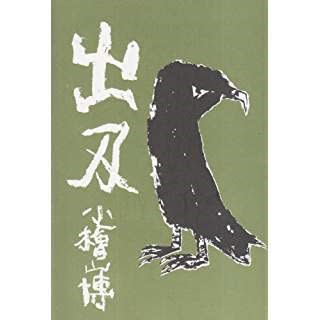小林信彦『東京少年』(新潮文庫)

東京都日本橋区にある老舗の跡取り息子。昭和十九年八月、中学進学を控えた国民学校六年生の彼は、級友たちとともに山奥の寒村の寺に学童疎開することになった。閉鎖生活での級友との軋轢、横暴な教師、飢え、東京への望郷の念、友人の死、そして昭和二十年三月十日の大空襲による実家の消失、雪国への再疎開…。多感な少年期を、戦中・戦後に過ごした小林信彦が描く、自伝的作品。(「BOOK」データベースより)
◎小林信彦は奥行きの深い作家
小林信彦は懐の深い作家です。井上ひさし(推薦作『吉里吉里人』上中下巻、新潮文庫)、橋本治(推薦作『これで古典がよくわかる』ちくま文庫)とならんで、著作の多様性はぬきんでています。小林信彦を有名にしたのは、『オヨヨ島の冒険』(角川文庫)に代表される「オヨヨ・シリーズ」でしょう。この作品は井上ひさし『ひょっこりひょうたん島』(全13巻、ちくま文庫)に匹敵するほどの人気シリーズでした。その後小林信彦は、ヤクザの株式会社シリーズ『唐獅子株式会社』(新潮文庫)などを発表します。
そして『ちはやふる奥の細道』(新潮文庫)へと、ジャンルを拡大してみせます。この作品は私の大のお気に入りです。日本文化研究科のアメリカ人・W.C.フラナガンなる人物が、松尾芭蕉の生涯を研究した翻訳本というスタイルになっています。読みながら、腹を抱えて笑ってしまいました。誤訳だらけなのです。このあたりの芸風は、最近では清水義範(推薦作『蕎麦ときしめん』講談社文庫)の十八番になっています。
小林信彦は、脚本家であり、児童文学作家であり、小説家であり、昭和の語り部であり、日本文学の研究者であり、喜劇役者の伝記作家でもあります。小林信彦には、『現代<死語>ノート』(全2巻、岩波新書、「山本藤光の文庫で読む500+α」推薦作)という著作もあります。消えてしまった言葉を拾い集めた著作で、なかなか味があります。
さらに『おかしな渥美清』(新潮文庫)や『天才伝説・横山やすし』(文春文庫)などという芸人を素材にした著作もあります。また中原弓彦というペンネームで、映画評や喜劇評を手がけています。1972年には『日本の喜劇人』(新潮文庫)で、芸術選奨励新人賞も受賞しています。
それらの著作のなかから、なにを紹介すべきかずいぶん迷いました。捨てがたいのは、『ちはやふる奥の細道』と『現代<死語>ノート』でした。いずれ紹介したいと思っていますが、1人1作品の紹介を原則にしています。どちらかを「知・教養。古典ジャンル」で取り上げたいと思います。今回は「日本現代小説125+α」として、『東京少年』(新潮文庫)を紹介させていただきます。
◎文学とサブカルチャーの融合
『東京少年』は、新潮社の情報誌「波」に連載されていました。連載開始は、2003年6月号からでした。毎回楽しみにして読んでいました。
本書は2部構成になっています。第1部は東京日本橋の老舗の跡取り息子「ぼく」が弟とともに、山村へ疎開する話です。
――「ねえ、どっちにするの?」/黒い遮光紙に包まれた電球の下で、問いつめるように母が言う。/「あさって、学校に返事をしなければならないのよ。急ぎすぎる話だから、答えにくいだろうけど」/七月半ばの夜である。みぞおちのあたりを汗が流れるのが、ぼくにはわかった。<ソカイ>というものは、ぼくからかなり遠い所にあるはずだった。(本文冒頭より)
疎開先で「ぼく」は、さまざまな辛苦を味わいます。いじめ、教師の鉄拳制裁、飢え、友人の死。『東京少年』は疎開生活でみた、人間の醜さを描いています。そして終戦を迎えます。
著者は「ひとつの国が負けるということを、少年の目にどううつるかを、書き残しておきたかった」(「波」2005年11月号より)と書いています。
第1部では国が負け、疎開先で自分自身が傷つく様子を、克明に描いています。中学進学を間近に控えた少年の、揺れる心が痛々しく伝わってきます。
第2部は、敗戦後の帰郷を描いています。優柔不断な父親にふりまわされる母子。東京への帰郷というよりは、再疎開の様子に胸が締めつけられます。戦時下の少年を、小林信彦はみごとに描いて見せました。
辛口の書評家・福田和也『作家の値うち』(飛鳥新社)の一文を引いておきます。彼がこれほど賞賛することはあまりありません。
――おそらく、一世紀後には、小林信彦は戦後日本を代表する作家とみなされ、佐藤春夫、横光利一の系譜に立ちつつ、東京の言語・文化空間を大胆に小説に取り込み、文学の有り様自体を変化させた、つまり文学とサブカルチャーの橋渡しをした人物として記憶されることだろう。
私の蔵書には小林信彦の著作が、文庫だけで78冊あります。書棚にはいりきれなくなって、一部は倉庫に<疎開>させてしまいました。大好きな著作だけを残して。
(山本藤光:2010.10.09初稿、2018.03.14改稿)

東京都日本橋区にある老舗の跡取り息子。昭和十九年八月、中学進学を控えた国民学校六年生の彼は、級友たちとともに山奥の寒村の寺に学童疎開することになった。閉鎖生活での級友との軋轢、横暴な教師、飢え、東京への望郷の念、友人の死、そして昭和二十年三月十日の大空襲による実家の消失、雪国への再疎開…。多感な少年期を、戦中・戦後に過ごした小林信彦が描く、自伝的作品。(「BOOK」データベースより)
◎小林信彦は奥行きの深い作家
小林信彦は懐の深い作家です。井上ひさし(推薦作『吉里吉里人』上中下巻、新潮文庫)、橋本治(推薦作『これで古典がよくわかる』ちくま文庫)とならんで、著作の多様性はぬきんでています。小林信彦を有名にしたのは、『オヨヨ島の冒険』(角川文庫)に代表される「オヨヨ・シリーズ」でしょう。この作品は井上ひさし『ひょっこりひょうたん島』(全13巻、ちくま文庫)に匹敵するほどの人気シリーズでした。その後小林信彦は、ヤクザの株式会社シリーズ『唐獅子株式会社』(新潮文庫)などを発表します。
そして『ちはやふる奥の細道』(新潮文庫)へと、ジャンルを拡大してみせます。この作品は私の大のお気に入りです。日本文化研究科のアメリカ人・W.C.フラナガンなる人物が、松尾芭蕉の生涯を研究した翻訳本というスタイルになっています。読みながら、腹を抱えて笑ってしまいました。誤訳だらけなのです。このあたりの芸風は、最近では清水義範(推薦作『蕎麦ときしめん』講談社文庫)の十八番になっています。
小林信彦は、脚本家であり、児童文学作家であり、小説家であり、昭和の語り部であり、日本文学の研究者であり、喜劇役者の伝記作家でもあります。小林信彦には、『現代<死語>ノート』(全2巻、岩波新書、「山本藤光の文庫で読む500+α」推薦作)という著作もあります。消えてしまった言葉を拾い集めた著作で、なかなか味があります。
さらに『おかしな渥美清』(新潮文庫)や『天才伝説・横山やすし』(文春文庫)などという芸人を素材にした著作もあります。また中原弓彦というペンネームで、映画評や喜劇評を手がけています。1972年には『日本の喜劇人』(新潮文庫)で、芸術選奨励新人賞も受賞しています。
それらの著作のなかから、なにを紹介すべきかずいぶん迷いました。捨てがたいのは、『ちはやふる奥の細道』と『現代<死語>ノート』でした。いずれ紹介したいと思っていますが、1人1作品の紹介を原則にしています。どちらかを「知・教養。古典ジャンル」で取り上げたいと思います。今回は「日本現代小説125+α」として、『東京少年』(新潮文庫)を紹介させていただきます。
◎文学とサブカルチャーの融合
『東京少年』は、新潮社の情報誌「波」に連載されていました。連載開始は、2003年6月号からでした。毎回楽しみにして読んでいました。
本書は2部構成になっています。第1部は東京日本橋の老舗の跡取り息子「ぼく」が弟とともに、山村へ疎開する話です。
――「ねえ、どっちにするの?」/黒い遮光紙に包まれた電球の下で、問いつめるように母が言う。/「あさって、学校に返事をしなければならないのよ。急ぎすぎる話だから、答えにくいだろうけど」/七月半ばの夜である。みぞおちのあたりを汗が流れるのが、ぼくにはわかった。<ソカイ>というものは、ぼくからかなり遠い所にあるはずだった。(本文冒頭より)
疎開先で「ぼく」は、さまざまな辛苦を味わいます。いじめ、教師の鉄拳制裁、飢え、友人の死。『東京少年』は疎開生活でみた、人間の醜さを描いています。そして終戦を迎えます。
著者は「ひとつの国が負けるということを、少年の目にどううつるかを、書き残しておきたかった」(「波」2005年11月号より)と書いています。
第1部では国が負け、疎開先で自分自身が傷つく様子を、克明に描いています。中学進学を間近に控えた少年の、揺れる心が痛々しく伝わってきます。
第2部は、敗戦後の帰郷を描いています。優柔不断な父親にふりまわされる母子。東京への帰郷というよりは、再疎開の様子に胸が締めつけられます。戦時下の少年を、小林信彦はみごとに描いて見せました。
辛口の書評家・福田和也『作家の値うち』(飛鳥新社)の一文を引いておきます。彼がこれほど賞賛することはあまりありません。
――おそらく、一世紀後には、小林信彦は戦後日本を代表する作家とみなされ、佐藤春夫、横光利一の系譜に立ちつつ、東京の言語・文化空間を大胆に小説に取り込み、文学の有り様自体を変化させた、つまり文学とサブカルチャーの橋渡しをした人物として記憶されることだろう。
私の蔵書には小林信彦の著作が、文庫だけで78冊あります。書棚にはいりきれなくなって、一部は倉庫に<疎開>させてしまいました。大好きな著作だけを残して。
(山本藤光:2010.10.09初稿、2018.03.14改稿)