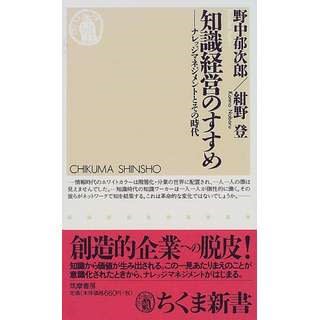野呂邦暢『草のつるぎ』(講談社文芸文庫ワイド)

「言葉の風景画家」と称される著者が、硬質な透明感と静謐さの漂う筆致で描く青春の焦燥。生の実感を求め自衛隊に入隊した青年の、大地と草と照りつける太陽に溶け合う訓練の日々を淡々と綴った芥川賞受賞作「草のつるぎ」、除隊後ふるさとに帰り、友人と過ごすやるせない日常を追う「一滴の夏」―長崎・諫早の地に根を下ろし、四十二歳で急逝した野呂邦暢の、初期短篇を含む五篇を収録。(「BOOK」データベースより)
◎野呂邦暢と佐藤正午
野呂邦暢(くにのぶ)は1937年に生まれ、42歳の若さで心筋梗塞のために、長崎県諫早市の自宅でなくなりました。彼が京大文学部受験に失敗し一浪中に、父親が事業でつまずいてしまいます。彼は受験を断念し、上京して職業を転々とします。そのうちに体調を壊し、故郷に戻ってきます。そして佐世保の自衛隊に入隊します。
28歳のとき「ある男の故郷」が、「文学界」新人賞の佳作となります。この作品から8年後の1973年、『草のつるぎ』で芥川賞を受賞します。
佐藤正午は2017年、『月の満ち欠け』(岩波書店)で直木賞を受賞しています。作家になる以前の彼は同郷の野呂邦暢の『諫早菖蒲日記』に感銘して、ファンレターを送っています。返信はありました。その返信が直木賞作家・佐藤正午誕生のきっかけとなりました。この返信に発憤して、彼は小説を書きはじめたのです。
佐藤正午は著作のなかで、野呂邦暢の早過ぎる死について、次のように書いています。
――僕は最初の小説を書き始めた。書き続けながら常に頭の片隅にあったのは、四十二歳で死んだ小説家のことである。それがどんなに早すぎる、どれほど惜しまれる死であるか、まだ若い僕には判っていない。二十五歳の青年はただ、去った者から残った者へ、一つの仕事をやり終えた小説家から自分へ、次はきみの番だと指名されたように思って、そう信じて自分を勇気づけることしかできなかった。(『ありのすさび』岩波書店P345-346)
◎五感に訴える
野呂邦暢『草のつるぎ』が、講談社文芸文庫のワイド版として登場しました。小さな活字が見えにくくなっている私には、何よりのプレゼントです。迷うことなく再読しました。
野呂邦暢は、文章修行の手本にさせていただいた名文家です。とにかく単文をリズミカルにつなぐ、希有な作家だと思っています。没後30年になりましたが、こうしてめぐりあった幸せに感謝しつつ、再読いたしました。文章の一部を引いておきます。
――雨は去った。草原は新鮮になった。赤ん坊の肌のようにみずみずしい草になった。水で清められた葉身はかぐわしかった。(P147)
――夕食後、ぼくらは草原のはずれへ歩いた。わが中隊だけのようである。日は海に沈もうとしていた。ぼくらは赤っぽい夕日に浸かった。四、五人ずつ固まってあちこちに座った。(P178)
主人公「ぼく」は、九州の海辺の駐屯地にある自衛隊に入隊します。入隊の目的は、次のように説明されています。
――物質に化学変化を起こさせるには高い熱と圧力が必要だ。そういう条件で物は変質し前とは似ても似つかぬ物に変わる。ぼくは自分の顔が体つきがいやそれに限らず自分自身の全てがイヤだ。ぼくは別人に変わりたい。ぼく以外の他人になりたい。(P147)
入隊して三週間目に、ぼくは初めて外出日を迎えます。ぼくはナイフと岩塩を買い求めます。「ぼく」は食堂で出されるご飯が石油のような味がするために食べられません。したがって岩塩入りの水で、飢えを補うしかありません。
空腹なうえに、単純で過酷な新兵訓練が続きます。「ぼく」はそのなかに身を置き、自分の内部の変化を待ちます。隊内にはさまざまな出自の人たちがいました。「ぼく」はそれらの人と距離を置き、ひたすら自らを孤立させます。周囲から嫌われ、自分が阻害される道を選びます。
これらの展開を野呂邦暢は、読者の五感をフル稼働させるような文章でたたみかけます。そして長い教育期間が終わります。読者は過酷な抑圧から解放された、「ぼく」の変化を感じ取ることになります。
◎草のつるぎとは
「草のつるぎ」というタイトルについては、著者自身が次のように書いています。文庫版には「あとがき」がありませんので、単行本のものを紹介させていただきます。
――「草のつるぎ」という題名はすでに決まっていた。自衛隊を書くとすればそういう題名でなければならなかった。「草のつるぎ」とは営庭にしげっていた萱(かや)科の硬い葉身を指しもするし、九州各地から集まった少年達の肉体をも意味する。小銃をかかえて草原を這い回れば、草はさながらナイフのようにわたし達を刺し、時には優しく肌を愛撫するかとも思われた。(単行本あとがき)
『草のつるぎ』で芥川賞を受賞する以前に、野呂作品は何度も候補になっていました。『草のつるぎ』執筆にあたり、野呂は安岡章太郎のアドバイスを意識していました。
――つまらない正義感をすててそこで見た物事を自由奔放に書けばいい。(野呂邦暢『失われた兵士たち』文春学芸ライブラリーの解説より)
安岡章太郎のアドバイスを受けて、『草のつるぎ』は芥川賞を受賞しました。選評をいくつか紹介させていただきます。
――自衛隊の新隊員の手記で、自衛隊の初期訓練、演習なども克明に書いて、班員の性格も描き分けて、地面に喰いついたようなひたむきな粘りがみえた。(瀧井孝作)
――自衛隊員の生活が、正面から書かれている。訓練、演習、営内外の生活などが、これまで旧軍隊を書いた多くの小説よりも、現実性を持って書かれている。長篇小説の書き出しのような印象を与えるくらい、延び延びと書かれているのに感心した。(大岡昇平)
―きらきらした才能を押えて、深刻がるふうもなく、思わせぶりなところもなく、百五十枚を一気に読ませて、さわやかな感銘をあたえた。(丹羽文雄)
これらの選評を見ると、安岡章太郎の助言に忠実だったことがわかります。野呂邦暢の著作は入手が難しいのですが、なんとか探し出してぜひお読みください。
山本藤光2017.09.15初稿、2018.03.04改稿

「言葉の風景画家」と称される著者が、硬質な透明感と静謐さの漂う筆致で描く青春の焦燥。生の実感を求め自衛隊に入隊した青年の、大地と草と照りつける太陽に溶け合う訓練の日々を淡々と綴った芥川賞受賞作「草のつるぎ」、除隊後ふるさとに帰り、友人と過ごすやるせない日常を追う「一滴の夏」―長崎・諫早の地に根を下ろし、四十二歳で急逝した野呂邦暢の、初期短篇を含む五篇を収録。(「BOOK」データベースより)
◎野呂邦暢と佐藤正午
野呂邦暢(くにのぶ)は1937年に生まれ、42歳の若さで心筋梗塞のために、長崎県諫早市の自宅でなくなりました。彼が京大文学部受験に失敗し一浪中に、父親が事業でつまずいてしまいます。彼は受験を断念し、上京して職業を転々とします。そのうちに体調を壊し、故郷に戻ってきます。そして佐世保の自衛隊に入隊します。
28歳のとき「ある男の故郷」が、「文学界」新人賞の佳作となります。この作品から8年後の1973年、『草のつるぎ』で芥川賞を受賞します。
佐藤正午は2017年、『月の満ち欠け』(岩波書店)で直木賞を受賞しています。作家になる以前の彼は同郷の野呂邦暢の『諫早菖蒲日記』に感銘して、ファンレターを送っています。返信はありました。その返信が直木賞作家・佐藤正午誕生のきっかけとなりました。この返信に発憤して、彼は小説を書きはじめたのです。
佐藤正午は著作のなかで、野呂邦暢の早過ぎる死について、次のように書いています。
――僕は最初の小説を書き始めた。書き続けながら常に頭の片隅にあったのは、四十二歳で死んだ小説家のことである。それがどんなに早すぎる、どれほど惜しまれる死であるか、まだ若い僕には判っていない。二十五歳の青年はただ、去った者から残った者へ、一つの仕事をやり終えた小説家から自分へ、次はきみの番だと指名されたように思って、そう信じて自分を勇気づけることしかできなかった。(『ありのすさび』岩波書店P345-346)
◎五感に訴える
野呂邦暢『草のつるぎ』が、講談社文芸文庫のワイド版として登場しました。小さな活字が見えにくくなっている私には、何よりのプレゼントです。迷うことなく再読しました。
野呂邦暢は、文章修行の手本にさせていただいた名文家です。とにかく単文をリズミカルにつなぐ、希有な作家だと思っています。没後30年になりましたが、こうしてめぐりあった幸せに感謝しつつ、再読いたしました。文章の一部を引いておきます。
――雨は去った。草原は新鮮になった。赤ん坊の肌のようにみずみずしい草になった。水で清められた葉身はかぐわしかった。(P147)
――夕食後、ぼくらは草原のはずれへ歩いた。わが中隊だけのようである。日は海に沈もうとしていた。ぼくらは赤っぽい夕日に浸かった。四、五人ずつ固まってあちこちに座った。(P178)
主人公「ぼく」は、九州の海辺の駐屯地にある自衛隊に入隊します。入隊の目的は、次のように説明されています。
――物質に化学変化を起こさせるには高い熱と圧力が必要だ。そういう条件で物は変質し前とは似ても似つかぬ物に変わる。ぼくは自分の顔が体つきがいやそれに限らず自分自身の全てがイヤだ。ぼくは別人に変わりたい。ぼく以外の他人になりたい。(P147)
入隊して三週間目に、ぼくは初めて外出日を迎えます。ぼくはナイフと岩塩を買い求めます。「ぼく」は食堂で出されるご飯が石油のような味がするために食べられません。したがって岩塩入りの水で、飢えを補うしかありません。
空腹なうえに、単純で過酷な新兵訓練が続きます。「ぼく」はそのなかに身を置き、自分の内部の変化を待ちます。隊内にはさまざまな出自の人たちがいました。「ぼく」はそれらの人と距離を置き、ひたすら自らを孤立させます。周囲から嫌われ、自分が阻害される道を選びます。
これらの展開を野呂邦暢は、読者の五感をフル稼働させるような文章でたたみかけます。そして長い教育期間が終わります。読者は過酷な抑圧から解放された、「ぼく」の変化を感じ取ることになります。
◎草のつるぎとは
「草のつるぎ」というタイトルについては、著者自身が次のように書いています。文庫版には「あとがき」がありませんので、単行本のものを紹介させていただきます。
――「草のつるぎ」という題名はすでに決まっていた。自衛隊を書くとすればそういう題名でなければならなかった。「草のつるぎ」とは営庭にしげっていた萱(かや)科の硬い葉身を指しもするし、九州各地から集まった少年達の肉体をも意味する。小銃をかかえて草原を這い回れば、草はさながらナイフのようにわたし達を刺し、時には優しく肌を愛撫するかとも思われた。(単行本あとがき)
『草のつるぎ』で芥川賞を受賞する以前に、野呂作品は何度も候補になっていました。『草のつるぎ』執筆にあたり、野呂は安岡章太郎のアドバイスを意識していました。
――つまらない正義感をすててそこで見た物事を自由奔放に書けばいい。(野呂邦暢『失われた兵士たち』文春学芸ライブラリーの解説より)
安岡章太郎のアドバイスを受けて、『草のつるぎ』は芥川賞を受賞しました。選評をいくつか紹介させていただきます。
――自衛隊の新隊員の手記で、自衛隊の初期訓練、演習なども克明に書いて、班員の性格も描き分けて、地面に喰いついたようなひたむきな粘りがみえた。(瀧井孝作)
――自衛隊員の生活が、正面から書かれている。訓練、演習、営内外の生活などが、これまで旧軍隊を書いた多くの小説よりも、現実性を持って書かれている。長篇小説の書き出しのような印象を与えるくらい、延び延びと書かれているのに感心した。(大岡昇平)
―きらきらした才能を押えて、深刻がるふうもなく、思わせぶりなところもなく、百五十枚を一気に読ませて、さわやかな感銘をあたえた。(丹羽文雄)
これらの選評を見ると、安岡章太郎の助言に忠実だったことがわかります。野呂邦暢の著作は入手が難しいのですが、なんとか探し出してぜひお読みください。
山本藤光2017.09.15初稿、2018.03.04改稿