
満月下の浅草六区
時間が押してきたので「牛探し」を中止して、地下鉄銀座線に乗りこみ、大正7年の浅草六区に移動しました。とはいっても、残念ながら、タイムマシンはまだ実用化されていませんし、杉浦日向子さんが18才で取得した時間旅行検定の四級すらも受かっていないニワトリです。ジオラマ作家の山本高樹さんが再現してくれた「浅草六区」にトリップしに行ったのでした。
目的地はテプコ浅草館。秋葉原から最新鋭の筑波エクスプレスに乗って浅草駅で降りれば徒歩1分で到着しますが、最古の地下鉄銀座線に乗って浅草に向かうことにしました(銀座線浅草駅からだと徒歩10分)。
ところで、銀座線の開業は昭和2年です。名物だった凌雲閣(浅草十二階)は関東大震災で崩落、その手前に見える浅草国技館は大正9年に焼失しており、当時最新鋭の地下鉄で浅草に遊びに行っても、これらの建物はすでに失われていました。大正浪漫が華やかな頃、人々は路面電車を乗り継いで浅草へ遊びにいったのでしょう。
(東京の路面電車は明治36年に開業、数年で主要路線が完成、震災や戦災を乗り越え、昭和37年に最大41路線まで拡大されたが、昭和40年代に次々廃止になり、荒川線と世田谷線のみ生き残った)


まずは、有楽町ガード下をくぐって、気分を高めます。飲み屋の店先に「デンキブランあります」の張り紙を見つけ、大正時代の浅草に浪漫飛行してしまいました。その当時、六区で活動写真を観た後、雷門通りにある「神谷バー」で、文明開化の明治15年に生み出された名物カクテル〈デンキブラン〉を飲むのが、ハイカラな東京っ子の定番だったとか・・・電車賃以外のお金を持ち合わせていなかったのが悔やまれます。

山本高樹さんが再現してくれた浅草六区。明治6年(1873)の太政官布告により、浅草寺の境内が浅草公園と命名され、明治17年に一区~六区まで区分けされました。六区の突き当りには、明治39年に開業した凌雲閣が威容を誇っています。設計したのはイギリス人のウィリアム・バルトン。10階まで煉瓦造、11~12階が木造という建物で、日本初のエレベータを備え、8階まで世界各国の物品店が入っていました。9~12階は展望室になっていて、東洋一の高さ(52m)を誇っていましたが、大正時代には客足が衰えてしまったそうです。関東大震災で、8階より上の部分が崩落してしまい、爆破解体されました(跡地には現在パチンコ店が建っているらしい)。
昭和7年、森下仁丹が同社の宣伝のため田原町交差点に凌雲閣を模した塔を建設、戦争中の昭和17年に金属回収の対象となり一端撤去されましたが、戦後になって再建されました。このタワーは仁丹塔と呼ばれて、地元のシンボル的存在になったのですが、昭和61年(1986)に忽然と姿を消してしまいます。
(「老朽化が進んだため」とのことですが??)
個人的には、幼い頃、浅草寺や花やしきを何度も訪れており、仁丹塔も目撃しているはずですが、ほんの少ししか覚えていません。今、浅草はとても活気に溢れているので、仁丹塔も復活してくれないかしら?


浅草国技館(左)と芝居小屋(右)。浅草六区は、見世物小屋、演劇場、活動写真館、オペラ、寄席などが集まる日本一の歓楽街でした。明治45年(1912)2月に完成した浅草国技館を設計したのは、東京駅も手がけた辰野金吾でしたが、同氏設計による両国国技館がすでに存在していたことから、相撲の興業はたった一回しか行われなかったそうです。その後、活動写真館になりますが、建物の構造が映画館には不向きで、芝居小屋としてようやく成功した暁の大正9年に全焼してしまいます。
浅草には、明治43年(1910)9月に開業したものの、約半年後の4月に火事で焼失!という幻のテーマパーク=〈ルナパーク〉もありました。アメリカのコニーアイランドを模して作った娯楽施設だそうですが、南極飛行館、天文館、海底旅行館、自動機械館、汽車活動館、木馬館、植物温室といったパビリオンがあり、メリーゴーランドやバーチャル旅行を楽しめたとか。中でも汽車活動館は、スクリーンに実際の走行風景を映し出し座席が振動するという、最も新しい娯楽施設で大変好評だったそうです。山本さん、次は「ルナパーク」を作ってくださいな~♪ すみません、ここで一度切ります。お休みなさい・・・
すみません、ここで一度切ります。お休みなさい・・・














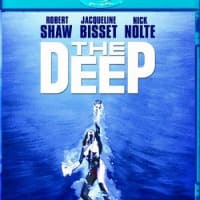





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます