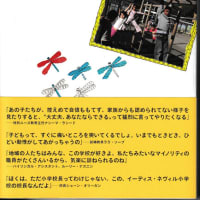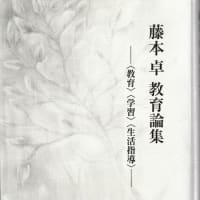■福田三津夫様
2023年2月ごろ、NHKのテレビ番組で「100分de名著」で北條民雄が取り上げられて、
みなさんにお勧めした記憶があります。
その頃、福田三津夫さんがブログで紹介していたことに、刺激を受けて、昔のことを
思い出して小生が書いたもの「北條民雄と友人の光岡良二」をお送りしました。
その時も、北條民雄は知っていても光岡良二はご存じなかったでしょう。
朝日新聞(阪神版?)で光岡良二氏に関する連載が4月から始まり、6月末まで
11回の連載が終わりました。
8回目には、私たちFIWC(フレンズ国際労働キャンプ)が建設した交流(むすび)の家に
いかに多大な貢献をしてくださったかが詳しく記述されています。
添付してお送りします。
記者の雨宮徹氏とは、彼が朝日新聞岡山総局の時に知り合いました。
愛生園や光明園をかなり積極的に報道していました。
岡山から徳島支局に転勤になったときは、ハンセン病問題の報道が
できなくなったことを残念がっていました。
ところが、北條民雄の故郷が徳島のお隣の阿南市とわかって、がぜん
取材意欲が湧いて、北條民雄に関するすばらしい連載を残しました。
今度は、姫路支局に転勤し、姫路のお隣のたつの市が光岡良二氏
の故郷らしいことをつきとめ、それはそれは熱意をもって取材をしたのです。
まるで研究者のようでした。
朝日新聞の記者はこんなに優秀なのか、と思いました。
北條民雄の故郷の近くの徳島支局に転勤命令が出たのは偶然のことですが、
北條民雄の親友の光岡良二の故郷の近くの姫路支局への転勤も、まったくの
偶然なのですが、なにか宿命的なものを感じます。
北條民雄は故郷でもひろく認知されていましたが、光岡良二の場合は
生まれ故郷がたつの市と本人も明かすことなく、親類縁者もほとんど
知らない状態だと聞きました。
はたして、そのような事実を新聞で知らしめていいのかどうか、記者
としてずいぶん悩んだようです。
新聞に連載が始まったということは、光岡さんに連なる係累の方々の
承諾を得たのだろうと思います。
ついでに、2023年2月ごろでしたかNHKの番組「100分de名著」で
北條民雄が取り上げられた頃に小生が書いた「北條民雄と光岡良二」
を再度添付します。
矢部 顕
●福田三津夫さんへの手紙
北條民雄と光岡良二
福田三津夫さんは彼のブログ(2023.2.8.)で、北條民雄の『すみれ』について取り上げていらっしゃいました。
つい最近のNHKのテレビ番組「100分de名著」で、北條民雄の『いのちの初夜』の関する放映がきっかけで、福田さんが書かれた文章が掲載されています。
これを読んで思い出したことを記しておきたいと思い、北條民雄と友人の光岡良二について書きます。
●『いのちの初夜』(北條民雄著)
ハンセン病をテーマにした小説や随筆を数多く残した北條民雄は、20歳のとき1934年(昭和9年)に全生病院(現・国立療養所多磨全生園)に入院しました。ハンセン病の症状が表れる中、何度も自殺を図ろうとしました。入院後の体験は、のちの彼の作品からうかがえます。
ある時、作品を見てほしいと川端康成に手紙を書き、「拝見いたします」と返事をもらった。それから90通の手紙のやりとりが続いたといいます。いくつかの作品が文芸誌「文学界」に載るようになりました。芥川賞候補にもなった「いのちの初夜」は、「最初の一夜」と題したものを川端が「いのちの初夜」と改題したそうです。
●『寒風』(川端康成著)
川端康成が北條民雄の死について書いた『寒風』という短編があります。この作品は1937年の北條民雄の死から約10年経った終戦後に発表されました。主に、北條民雄という作家について、全生病院について、北條民雄の父親(作品上は母親)の来訪について書かれています。この作品には、川端康成から見た北條民雄(作品上は谷沢)と光岡良二(作品上は倉木)の友情に触れています。
川端康成と光岡良二さんはずっと交流を保っていたようなので、北條民雄とその死を通してお互いに影響があったのでしょう。
●『すみれ』(北條民雄著)
北條民雄が『すみれ』を書いたのは20歳の時です。1934年(昭和9年)の5月に全生病院に入院した彼は12月に書いているそうです。この童話は、全生病院の中にあった全生学舎の子どもたちのために、教師であった光岡良二の依頼によって書かれたと言われています。
全生病院は国立療養所多磨全生園となり、全生学舎は東村山市立青葉小学校全生園分教室となりましたが、本校からの教師一人以外は光岡さんたちが教師を務めていらっしゃいました。(東京帝大文学部中退の小学校教師もめずらしい?)。私が学生時代、1960年代後半も、子どものハンセン病患者が療養所にいる時代で、私が訪問した時はソフトボールなどをして一緒に遊んだ記憶があります。(全生園分教室は1975年3月、子どもが卒業して閉鎖)
また、私たちが建設した交流(むすび)の家が完成したことによって、その小学校の子どもたちが奈良への修学旅行が可能になり、奈良の寺院を案内したり、夜は寝る前に修学旅行の定番(?)枕投げ遊びをした記憶があります。
●『古代微笑 光岡良二歌集』(光岡良二著)(風林文庫 1968年)
私たちフレンズ国際労働キャンプ(FIWC)が取り組んでいたライ(当時の呼称)快復者社会復帰セミナーセンター・交流(むすび)家の建設では、建設初期に地元住民の反対運動があり、そして奈良市長の建設反対声明があったりしたなかで、光岡さんは当時の全患協(全国ハンセン病患者協議会)事務局長として東京から奈良まで駆けつけていただいて、たいへんなご協力をいただいた同志であります。
光岡さんは、もともとは歌人として何冊かの歌集を出版されています。歌集『古代微笑』の出版記念会は、完成したばかりの奈良の交流(むすび)の家で行われました。
●『いのちの火影―北條民雄覚書』(光岡良二著)(新潮社1970年)
同じ病で入院した時期が1年違いで、同じように文学青年だった光岡さんが、北條民雄が亡くなってから30数年後に上梓された本です。小説を読むだけではわからない北條民雄という稀有な作家の人物像が詳細に描かれています。
●文学講演会「虚妄のライ」(講師・光岡良二、高橋和巳 於・同志社記念会館)
交流(むすび)の家開所記念文学講演会として、1968年6月に私たちフレンズ国際労働キャンプ(FIWC)関西委員会は、光岡さんと高橋和巳を講師として招いて京都で開催しました。
演題の「虚妄のライ」に込められた想いは、ライという言葉が差別用語となってハンセン病と言い換えられた現在では、想像力を掻き立てられない言葉となってしまいました。
高橋和巳は、当時もっとも人気のあった小説家で代表作『悲の器』『邪宗門』など。中国文学者でもあり、大学闘争の最中1969年京大文学部助教授辞任、1971年39歳で夭折しました。
2023.2.11.
矢部 顕