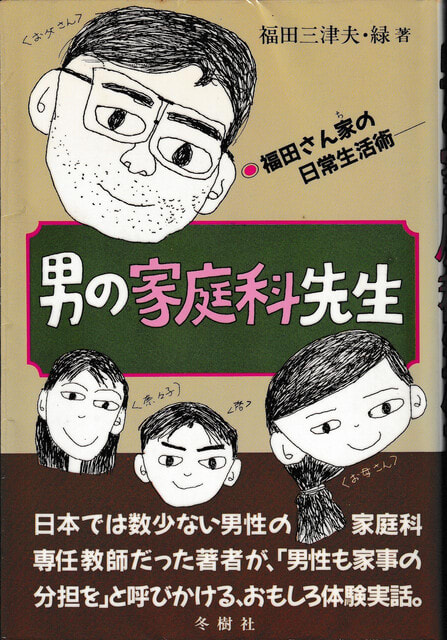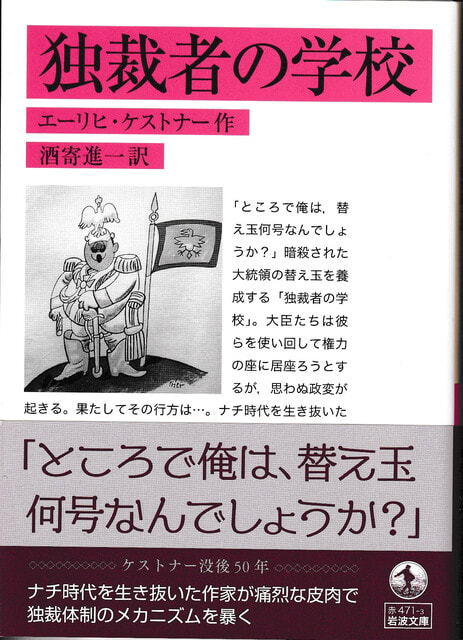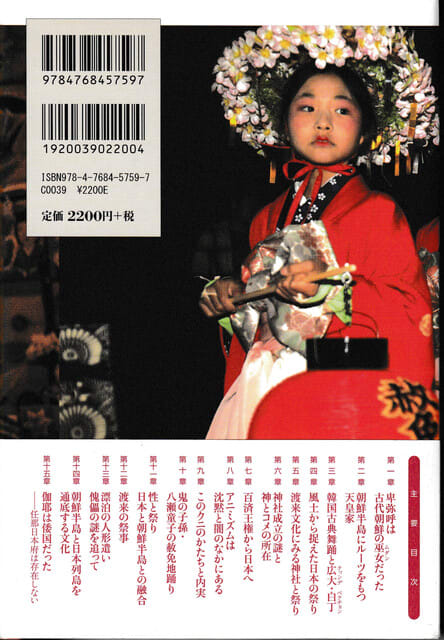読んでほしい雑誌を紹介しましょう。「週刊金曜日」と「生活と自治」です。



まずは「週刊金曜日」から。久し振りに「週刊金曜日」を購入しました。広告を掲載しない自立した「週刊金曜日」が創刊されたのは1980年代だったでしょうか。共に「演劇と教育」の編集をしていたある高校教師に勧められて、支援のためもあって数年購読を継続していたのでした。
いつのころか興味を持った教育などの特集号のみを購入するようになっていたのですが、書店に「週刊金曜日」を置くところも少なくなっていきました。嘆かわしいことに、最近では保守系の雑誌オンパレードで、リベラル系の「世界」「創」などを置く書店も珍しくなっています。しかし、私が時々行く秋津駅近くの書店は貴重な本屋です。そこで「週刊金曜日」を購入しました。
その理由は「ドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』何を問い、何が問われるのか」に心引かれたからです。性差別を受けた伊藤詩織さん自らの体験をドキュメントに描いた作品で、米アカデミー賞にノミネートされながら、許諾を得ていない映像・音声の使用を巡る問題で日本公開に到っていません。その顛末を知りたくての入手でした。
本人インタビューや伊藤さんの代理人のコメント、映画作家の想田和弘氏のコメントなど、丁寧にこの問題を扱っています。それにしても、伊藤さんと望月衣塑子記者の「応酬」には心痛めています。
様々な問題をクリヤーして日本公開を実現してもらいたいと切に願っています。
(追記)本日、2025年3月26日の朝日新聞朝刊に「ドキュメンタリー 力強さと危うさを」という記事が掲載されました。『Black Box Diaries』を巡っての原一男氏と中根若惠さんのコメントです。原氏は「ゆきゆきて、神軍」の映画監督です。タイムリーで興味深い記事でした。


「生活と自治」は生活クラブ事業連合生活協同組合連合会が発行するものです。生活クラブ、クラブ生協などと略称していますが、我が家でも以前から所属し、その品物を購入しています。扱う物品には定評があります。
「原発ゼロの社会にむけて」は多くの人に読んでもらいたい特集です。「生活と自治」は会員に送られてくるものですが、一般購入できないのがなんとしても残念なことです。
◆停戦
「停戦下」の空爆は戦争犯罪以外の何物でもない
師岡カリーマ(文筆家)
今月15日付、英ガーディアン紙の記事から。
「現在(イスラエルとハマス)両者は戦争への復帰を控えているが、
イスラエルはガザで一連の空爆を激化させ、数十人のパレスチナ人を
殺害している」。リベラルで人権重視のガーディアンにして、目を疑う
ようなこの矛盾。
空爆で数十人の死者を出しても「戦争行為は控えている」と表現され
るのだから。
いかに欧米メディアが不名誉な自己検閲を強いられているか想像でき
るが、印象操作の蓄積は犯罪幇助ではないか。
こうして「停戦状態」は、死体を積み上げた末の18日、死者400人超の
大規模空爆で崩壊、多くの子どもが死傷し、地上作戦も再開。
今年1月、イスラエルとハマスの停戦合意が発効した後も、イスラエ
ルは人道援助の搬入を遮断して故意に人道危機を悪化させ、ヨルダン川
西岸の占領地でも軍事攻撃を行うなど、パレスチナ人の生命と生活を破
壊し続けた。これ自体、報道用語では「国際法に違反する可能性があ
る」が、ここ数日の「停戦下」の空爆は、戦争犯罪以外の何物でもあ
るまい。
その空爆について、イスラエル政府が米トランプ政権に事前相談し、
了承を得ていたことを、ホワイトハウス高官が誇らしげに明かした。
ノーベル平和賞を狙っているというトランプ大統領が、個人的に戦争犯
罪に加担した証拠と見なされるべきであろう。
(3月22日「東京新聞」朝刊23「本音のコラム」より)
◆オウムの子は救えた
文部省は就学義務違反の保護者を
警察に刑事告発するよう指導すべきだった
前川喜平(現代教育行政研究会代表)
地下鉄サリン事件から 30年の20日付本紙に、オウム真理教への一斉強
制捜査で教団施設「サティアン」から救助された53人の子どもを保護し
た元児童相談所職員・保坂三雄氏へのインタビュー記事が載っていた。
サティアンでは、子どもたちは親から引き離され、勉強は1日1時
間。大半の時間が修行に充てられ、縛って逆さづりにするなどの虐待が
常態化していたという。
一斉強制捜査がなければ子どもたちは救い出せなかったのかという
と、そうではない。文部省(当時)には彼らを救い出す手段があった。
学齢期の子どもの保護者には、学校教育法により子どもを学校に通わ
せる義務(就学義務)があ」り、その不履行には刑事罰が科されること
になっている。学齢期の子には必ずどこかの学校に学籍があったはずだ。
文部省は、子どもたちの在籍校を所管する教育委員会に対し、就学義
務違反の保護者を警察に刑事告発するよう指導すべきだった。そうすれ
ばもっと早く子どもたちを救い出せただろう。
しかし文部省は何もしなかった。
就学義務違反の取り締まりは、当時から全く行われておらず、不登校
と区別しにくくなっていたのも事実だ。
しかし明らかな虐待の疑いがある場合には、伝家の宝刀を抜くべき
だったのだ。文部科学省が猛反省し教訓とすべきことである。
(3月23日「東京新聞」朝刊21面「本音のコラム」より)