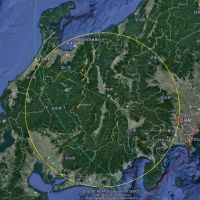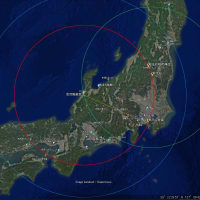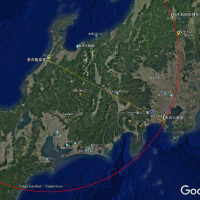神戸新聞杯のオルフェーヴルは強かったですね。スローをピッタリと折り合い、成長した馬体から繰り出されるフットワークの力強さ。フレールジャックが力んで追走した向正面で既に勝負がありました。返す返すも凱旋門賞に挑戦して欲しかった。ウインバリアシオンは本番睨みで余裕残し。本格化はもう少し先かもしれませんが、菊花賞ではチャンスがあります。
さて、椿大神社からツバキとは何だろうと考えました。調べてみると、椿は奈良の平群(へぐり)町に椿井(つばい)があり、桜井市の海柘榴市(つばいち)もツバイです。『記紀』によると、ツバキは唾吐きによる霊力、すなわち掃(はら)う神として描かれます→こちら。「掃う」は「祓(はら)い」と同じです。
実は、唾によって奇跡を起こすシーンは新約聖書にしばしば登場します。イエスが唾と土を混ぜて泥を作り、盲人の目に塗って目を開かせたとか。椿はラテン系でカメリアですが、これはフィリピンから椿を持ち帰った宣教師の名前カメルから。従って、聖書の舞台のパレスティナやエジプトには椿はありませんでした。
聖書との関わりで言うなら、むしろ石榴(ざくろ)のほうが頻繁に登場します。豊穣のシンボルとして、ギリシャ彫刻では『石榴を持つ少女』などが遺されています。『出エジプト記』28-33にはこうあります。
“そのすそには青糸、紫糸、緋糸で、ざくろを作り、そのすその周囲につけ、また周囲に金の鈴をざくろの間々につけなければならない。”
このように、石榴は祭司の衣服に縫い付けられたシンボルであり、赤い色から「海を渡ってきた石榴」という意味で海柘榴と書かれた椿。椿には、イエスの奇跡の唾と、祭司のシンボルの一つとしての石榴という二つの意味が込められていたのです。
椿を分解すると「三人の日の木」。要するに、太陽神イエスを含む天の三神と、イエスの掛けられた木を表しているのです。伊勢の猿田彦神社の額に刻まれる周は、マタイの口をヒントにしろというメッセージ。マタイの口とは『マタイによる福音書』にほかならず、この書を読めば、マタイとマグダラのマリアの血統が分かるという仕組みになっています。
猿田彦神社の額は、田と彦が合体して体を成し、猿の文字が烏帽子をかぶった人の頭になっています。サルはスペイン語で塩。塩の音読みのエンは、サルの音読みと同じ。エンは死海の沿岸のエンであり、塩のエンであり、そして日本の円に繋がるように、エンはイスラエルの祭司レビに付帯する言葉なのです。
猿田彦の田は、以前にデンマークで説明したように、デンと読んでダンと共にダン族を指す言葉。伝統とはもともと、ソロモン神殿を作ったダン族の技術継承を指すのです。天鈿女命にも田が付いているのはそのためです。鈿はテンやデンと読んで、意味は簪(かんざし)。聖書学的には、そろそろダン族がその正体を表す次期なのでしょうね。そういえば、凱旋門賞を勝ったのはデインドリーム(DANEDREAM)で、意味は「ダン族の夢」でした。
エフライム工房 平御幸
さて、椿大神社からツバキとは何だろうと考えました。調べてみると、椿は奈良の平群(へぐり)町に椿井(つばい)があり、桜井市の海柘榴市(つばいち)もツバイです。『記紀』によると、ツバキは唾吐きによる霊力、すなわち掃(はら)う神として描かれます→こちら。「掃う」は「祓(はら)い」と同じです。
実は、唾によって奇跡を起こすシーンは新約聖書にしばしば登場します。イエスが唾と土を混ぜて泥を作り、盲人の目に塗って目を開かせたとか。椿はラテン系でカメリアですが、これはフィリピンから椿を持ち帰った宣教師の名前カメルから。従って、聖書の舞台のパレスティナやエジプトには椿はありませんでした。
聖書との関わりで言うなら、むしろ石榴(ざくろ)のほうが頻繁に登場します。豊穣のシンボルとして、ギリシャ彫刻では『石榴を持つ少女』などが遺されています。『出エジプト記』28-33にはこうあります。
“そのすそには青糸、紫糸、緋糸で、ざくろを作り、そのすその周囲につけ、また周囲に金の鈴をざくろの間々につけなければならない。”
このように、石榴は祭司の衣服に縫い付けられたシンボルであり、赤い色から「海を渡ってきた石榴」という意味で海柘榴と書かれた椿。椿には、イエスの奇跡の唾と、祭司のシンボルの一つとしての石榴という二つの意味が込められていたのです。
椿を分解すると「三人の日の木」。要するに、太陽神イエスを含む天の三神と、イエスの掛けられた木を表しているのです。伊勢の猿田彦神社の額に刻まれる周は、マタイの口をヒントにしろというメッセージ。マタイの口とは『マタイによる福音書』にほかならず、この書を読めば、マタイとマグダラのマリアの血統が分かるという仕組みになっています。
猿田彦神社の額は、田と彦が合体して体を成し、猿の文字が烏帽子をかぶった人の頭になっています。サルはスペイン語で塩。塩の音読みのエンは、サルの音読みと同じ。エンは死海の沿岸のエンであり、塩のエンであり、そして日本の円に繋がるように、エンはイスラエルの祭司レビに付帯する言葉なのです。
猿田彦の田は、以前にデンマークで説明したように、デンと読んでダンと共にダン族を指す言葉。伝統とはもともと、ソロモン神殿を作ったダン族の技術継承を指すのです。天鈿女命にも田が付いているのはそのためです。鈿はテンやデンと読んで、意味は簪(かんざし)。聖書学的には、そろそろダン族がその正体を表す次期なのでしょうね。そういえば、凱旋門賞を勝ったのはデインドリーム(DANEDREAM)で、意味は「ダン族の夢」でした。
エフライム工房 平御幸