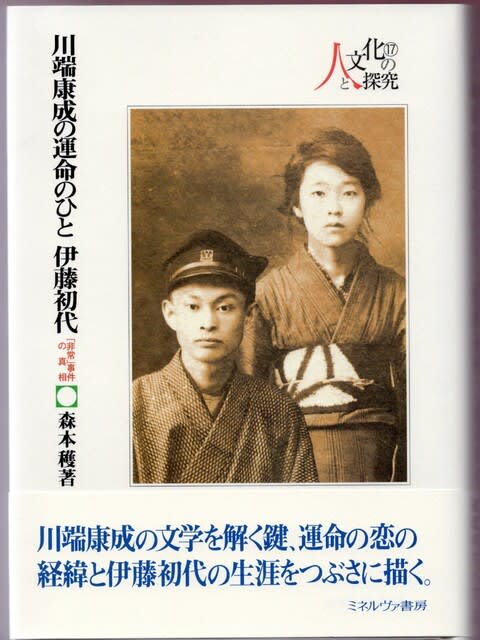昨日の神戸新聞夕刊の記事です。
神戸新聞さん、拝借お許しを。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
神戸出身の推理作家、横溝正史の草稿が発見されたとの記事。
わたしが所蔵する横溝の直筆署名です。

ところで、今読んでいる『星新一』ですが、興味深いページがいっぱい出てきます。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
これは、星新一が世に出るのを大いに助けた矢野徹と宮崎翁のこと。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
この記事に関連しての拙著『触媒のうた』の中のページです。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。
常盤新平さんの名前も出てきますが、常盤さんからはわたし何度かおハガキを頂きました。その一枚。

ほかにも何人もの馴染みの人の名前が出てきて興味が尽きません。
神戸新聞さん、拝借お許しを。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。神戸出身の推理作家、横溝正史の草稿が発見されたとの記事。
わたしが所蔵する横溝の直筆署名です。

ところで、今読んでいる『星新一』ですが、興味深いページがいっぱい出てきます。

 ←二段階クリック。
←二段階クリック。これは、星新一が世に出るのを大いに助けた矢野徹と宮崎翁のこと。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。この記事に関連しての拙著『触媒のうた』の中のページです。
 ←二段階クリック。
←二段階クリック。常盤新平さんの名前も出てきますが、常盤さんからはわたし何度かおハガキを頂きました。その一枚。

ほかにも何人もの馴染みの人の名前が出てきて興味が尽きません。