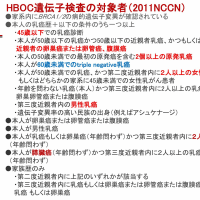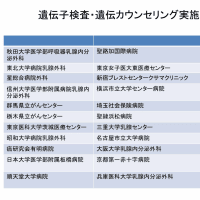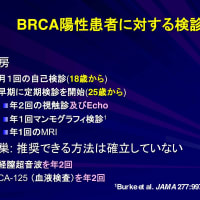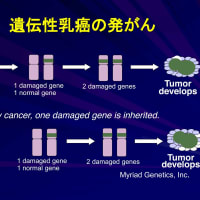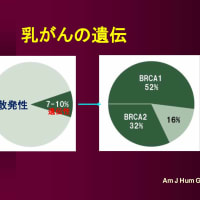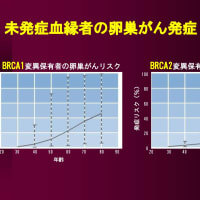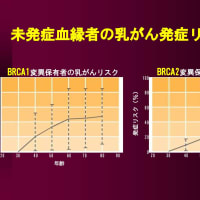自分が速効で寝付けるタイプなので、なかなか寝付けないという人の気分がいまひとつわからずにいました。
で、これがどんなに苦しいものなのか、理解できたのは家人の看取りがきっかけです。
あの頃は毎日、一寸先も読めず、家人も私もどうなっていくのかと思うと、大きな不安の濁流に飲み込まれた気分でした。体は激疲れのはずが、病院からの呼び出しがあるかもしれないと、全く眠りにつけなくて。
一睡もできず、でも眠くもならず、、、これが数日続きました。初めての体験でしたので、とても怖かったです。で、何とかこの事態から逃れようと、市販の睡眠導入薬を飲んだのですが。。。
きっかり3時間寝れました。が、、、ぜんっぜん爽やかな寝起きとはならず(T▽T)。薬を飲む前の、頭は疲れ思考は回らず、神経は過敏になった状態のつづきが待っていただけでした。ものすごーくがっかりしました。
というわけで、この時、うつ病からくる不眠で苦しむ人の気持ちが、始めてわかったのでした。睡眠薬を飲んでも、症状は改善しないんだなあと、身をもって知りました。
----------
【「眠れない」とはどういうことか?――人は毎日生きて、毎日死ぬ】
――自分が本当は何がしたいのかわからない。
「なかなか寝つけない」「寝ても眠りが浅くて、疲れがとれない」「寝よう寝ようと思うと、よけい眠れなくなってしまう」
このような不眠症状は、「うつ」状態においてはもちろんのこと、精神的なバランスが乱れた場合に生じてくる、かなりポピュラーなものです。
通常の治療では、「うつ」などの原疾患に対する治療薬とともに、その不眠の性質に応じて睡眠導入剤が処方される対症療法が行なわれます。
しかしながら、不眠がかなり深刻になってくると、強力な睡眠剤を複数組み合わせて用いても「眠れる時には眠れるけれど、やっぱり眠れない時には薬を飲んでも眠れない」という状態に陥るケースも珍しくありません。何が何でも眠れるようにとさらに薬を増強していくと、強い眠気や脱力が長時間持ち越されてしまい、翌日が使い物にならなくなってしまったりします。
今回は、このように通常行なわれている薬物療法で見落とされがちなポイントについて、つまり、不眠という状態をどう捉えるべきなのか、不眠という症状からどんなメッセージが受け取れるのかといったことを考えてみたいと思います。
「眠れない」とは?
まずは、「眠れない」ということについて、よく吟味してみましょう。
「眠れない」とは、「眠りたいのに眠れない」「眠るべきなのに眠れない」ということを省略した言い方であろうと思われます。
「頭」は本来「~すべき」、つまりmustやshouldの系列の言葉を用いる場所です。一方の「心」は「~したい」、つまりwant toの系列の言葉を発します。
「心」と「身体」は矛盾なく一心同体につながっていますが、理性や意志の場である「頭」は、「心」(=「身体」)に対してコントロールをかけたがる性質があって、「心」との通路を閉ざして一方的な独裁体制を敷きがちです。それは「頭」が「心」との間の蓋を閉めてしまった状態で、人間は「頭」vs.「心」(=「身体」)と分断されてしまい、両者は対立の様相を呈することになります。
さて、この仕組みから考えますと、「眠るべき(頭)なのに眠れない(身体)」は蓋が閉まっている状態として理解できますが、「眠りたい(心)のに眠れない(身体)」ということはあり得ないことになります。さてこれは、どういうことなのでしょうか。
眠りは「心」=「身体」のもの
―「頭」に命令されてたまるか!
これは、「頭」による偽装工作の結果だと考えると、簡単に説明がつきます。
つまり、「眠るべき」を「頭」が「眠りたい」に偽装したということです。この種の偽装は「頭」がしばしば行なうもので、「学校に行くべき」を「学校に行きたい」にすり替えたり、「会社に行くべき」を「会社に行きたい」にすり替えたりするのです。
偽装というのは大げさに響くかも知れませんが、別の表現で言うならば、「心」(=「身体」)の声を無視して「頭」の意志が一方的に作り出した「~したい」であったということです。
少々回り道をしましたが、ここで整理しておきますと、「眠りたいのに眠れない」という言い方も、実はその正体は「眠るべきなのに眠れない」だったということなのです。
つまり「眠れない」という状態は、「眠れ!」と高圧的に指令する「頭」と、「意地でも眠るものか!」と反発する「心」(=「身体」)の対立の構図で理解できるということです。
なぜ「心」(=「身体」)は、
「眠るまい」と反発するのか?
「眠るまい」と「心」(=「身体」)が反発するのには、いくつかの理由が考えられます。
1つは、そもそも眠りは「心」(=「身体」)の側が自然に行なうはずのものであって、「頭」によって指示される筋合いのものではないということです。
「頭」に相当する部分を持たず「心」(=「身体」)だけでできている自然界の動物においては、睡眠は自然な欲求であり、葛藤なく実現されています。ですから、「心」(=「身体」)にしてみれば、「頭」が睡眠に口を差し挟んでくることは越権行為であり、それに反発を覚えるのも当然のことでしょう。
現代人の生活は、案外歴史の浅い、時計仕掛けの硬直化した時間によって毎日の生活が規制されています。
季節が変わっても、天候がどうであれ、体調や気分がどんなでも、決まった時間に起床し出勤しなければなりません。そこから逆算して、睡眠を○○時間とるべきだから何時には寝るべきである、と「頭」が計算し、きちんと実行できることが「規則正しい」ことだとして奨励されています。
日々刻々と変わる生き物としては、必要とする睡眠の長さが日によって違ったり、眠くなる時間が変動したりすることはごく自然なことなのですが、しかしこれも現代の常識からすれば、「不規則な睡眠」として異常視されてしまう状況なのです。また、「うつ」状態においてよく見られる昼夜逆転の状態も、その意味が熟慮されずに、はなから病的なものと捉えられてしまう残念な傾向もあります。
フランスの啓蒙思想家ルソーは、代表作『エミール』の中で次のように述べています。
食事と睡眠の時間をあまり正確にきめておくと、一定の時間ののちにそれが必要になる。やがては欲求がもはや必要から生じないで、習慣から生じることになる。というより、自然の欲求のほかに習慣による新しい欲求が生じてくる。そんなことにならないようにしなければいけない。
子供につけさせてもいいただ一つの習慣は、どんな習慣にもなじまないということだ。(今野一雄訳、岩波文庫より)
1日を一生と捉えて毎日の死を迎える
「心」(=「身体」)が「眠るまい」とするもう1つの理由として、今日1日の幕を引く気になれないということが考えられます。
メメント・モリ(memento mori「死を想え」「死を忘れるな」という意味)という古いラテン語の格言があります。これは、「死」というものを想うことによって、ともすれば浪費されがちな「生」の有限性とはかなさを知らしめる警句です。
「よく死ぬ」ためには「よく生きなければ」なりません。ここで言う「よく生きる」とは、自分に生来与えられた固有の資質を存分に開花させ、自分らしい「生」を享受する生き方のことです。
これを1日の単位で考えてみても、同様のことが言えるのです。
1日を締めくくる眠りを、いわば「毎日の死」として捉えてみると、今日1日を「よく生きて」いなければ、「よく死ねない」。つまり、「死ぬに死ねない」がゆえに不眠になってしまうわけです。
1日をどう締めくくるか
もちろん、1日は限りある短い時間ですから、欲張ってあれもこれもすることはできません。しかしながら、1日の中でたとえわずかでもその人らしい時間を持つことができたか否かは、その日の眠りを大きく左右します。
よく「身体を動かして疲れれば眠くなるものだ」と言われたりしますが、これは「身体を動かす」ことがその人らしい過ごし方である場合に限って有効なものであって、そうでないタイプの人がいくら身体を動かしても、「身体は疲れているのに、頭だけが冴えてしまって眠れない」ということになってしまいます。
静かに読書したり、音楽を聴いたり、日記をつけて自分との対話を行なったりすることがその人にとって大切な「自分らしい時間」であるならば、たとえ30分でもそんな時間を持つことによって、自分の奥底で何かが充足し納得するので、眠気も自然に訪れやすくなるでしょう。
どのように過ごすことが「自分らしい時間」になるのか、それは各人各様ですから、自分自身で試行錯誤しながら見つけていく必要があります。
おびただしい「すべきこと」に追い立てられ日々を過ごさざるを得ない私たちにとって、ここで述べたようなことを実行することは、なかなか容易ではないかも知れません。しかし、何が自然で何が不自然なことなのか、日々の生活に何が欠けているのかということに無自覚であるよりは、せめて問題の所在に気づいているだけでも大きな違いなのです。
また、薬物療法を要するような不眠に苦しんでいる方であっても、社会化された「頭」が、内なる自然(「心」=「身体」)に向かって力ずくで睡眠剤という爆弾を投下し「あるべき睡眠」を強要するようなイメージではなく、時間に制約された状況に生きているがゆえに薬を使わざるを得ないことを、自分の「心」(=「身体」)に詫びつつ、「これで少しでもお休みください」とお願いするような気持ちで薬を使用することが大切だと思うのです。
----------
ここでは、「眠りたいのに眠れない」という言い方は、その正体は「眠るべきなのに眠れない」だったということになっていますね。
で、現代人の生活は、歴史の浅い、時計仕掛けの硬直化した時間によって毎日の生活が規制されている。
で、ルソーの作品から引用し、眠れないと言う人は、体の必要性からくる欲求より、習慣による欲求に支配されているのではないかと指摘しています。
「自分らしい時間」を過ごすことが、眠りにつく鍵としていますが、、、確かにこれを探すのは難しそうですね。だって、「自分さがし」って言葉がはやるほど、自分が何者なのかわからん人は一杯いるでしょうから。
私は寝しなに、数学の問題をやったり、哲学書みたいな難解な本を読み出すと、とたんに眠くなります。そういえばリカ子は、数学の問題を解きだすと、頭が冴え、シャキっとすると言っていました。
「自分らしい時間」、私にとって数学とか哲学は違うみたいです。
自分の奥底で何かが充足し納得するという「自分らしい時間」、、、私のそれは、ネットオークションです! これをやりだすと、リカ子と同様、頭が冴え、興奮し、眠りに、、、あれっ、眠りにつけないよ!
え“、何、このオチ?と思った人、 <ここをクリックよろしくね~ >

This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)
で、これがどんなに苦しいものなのか、理解できたのは家人の看取りがきっかけです。
あの頃は毎日、一寸先も読めず、家人も私もどうなっていくのかと思うと、大きな不安の濁流に飲み込まれた気分でした。体は激疲れのはずが、病院からの呼び出しがあるかもしれないと、全く眠りにつけなくて。
一睡もできず、でも眠くもならず、、、これが数日続きました。初めての体験でしたので、とても怖かったです。で、何とかこの事態から逃れようと、市販の睡眠導入薬を飲んだのですが。。。
きっかり3時間寝れました。が、、、ぜんっぜん爽やかな寝起きとはならず(T▽T)。薬を飲む前の、頭は疲れ思考は回らず、神経は過敏になった状態のつづきが待っていただけでした。ものすごーくがっかりしました。
というわけで、この時、うつ病からくる不眠で苦しむ人の気持ちが、始めてわかったのでした。睡眠薬を飲んでも、症状は改善しないんだなあと、身をもって知りました。
----------
【「眠れない」とはどういうことか?――人は毎日生きて、毎日死ぬ】
――自分が本当は何がしたいのかわからない。
「なかなか寝つけない」「寝ても眠りが浅くて、疲れがとれない」「寝よう寝ようと思うと、よけい眠れなくなってしまう」
このような不眠症状は、「うつ」状態においてはもちろんのこと、精神的なバランスが乱れた場合に生じてくる、かなりポピュラーなものです。
通常の治療では、「うつ」などの原疾患に対する治療薬とともに、その不眠の性質に応じて睡眠導入剤が処方される対症療法が行なわれます。
しかしながら、不眠がかなり深刻になってくると、強力な睡眠剤を複数組み合わせて用いても「眠れる時には眠れるけれど、やっぱり眠れない時には薬を飲んでも眠れない」という状態に陥るケースも珍しくありません。何が何でも眠れるようにとさらに薬を増強していくと、強い眠気や脱力が長時間持ち越されてしまい、翌日が使い物にならなくなってしまったりします。
今回は、このように通常行なわれている薬物療法で見落とされがちなポイントについて、つまり、不眠という状態をどう捉えるべきなのか、不眠という症状からどんなメッセージが受け取れるのかといったことを考えてみたいと思います。
「眠れない」とは?
まずは、「眠れない」ということについて、よく吟味してみましょう。
「眠れない」とは、「眠りたいのに眠れない」「眠るべきなのに眠れない」ということを省略した言い方であろうと思われます。
「頭」は本来「~すべき」、つまりmustやshouldの系列の言葉を用いる場所です。一方の「心」は「~したい」、つまりwant toの系列の言葉を発します。
「心」と「身体」は矛盾なく一心同体につながっていますが、理性や意志の場である「頭」は、「心」(=「身体」)に対してコントロールをかけたがる性質があって、「心」との通路を閉ざして一方的な独裁体制を敷きがちです。それは「頭」が「心」との間の蓋を閉めてしまった状態で、人間は「頭」vs.「心」(=「身体」)と分断されてしまい、両者は対立の様相を呈することになります。
さて、この仕組みから考えますと、「眠るべき(頭)なのに眠れない(身体)」は蓋が閉まっている状態として理解できますが、「眠りたい(心)のに眠れない(身体)」ということはあり得ないことになります。さてこれは、どういうことなのでしょうか。
眠りは「心」=「身体」のもの
―「頭」に命令されてたまるか!
これは、「頭」による偽装工作の結果だと考えると、簡単に説明がつきます。
つまり、「眠るべき」を「頭」が「眠りたい」に偽装したということです。この種の偽装は「頭」がしばしば行なうもので、「学校に行くべき」を「学校に行きたい」にすり替えたり、「会社に行くべき」を「会社に行きたい」にすり替えたりするのです。
偽装というのは大げさに響くかも知れませんが、別の表現で言うならば、「心」(=「身体」)の声を無視して「頭」の意志が一方的に作り出した「~したい」であったということです。
少々回り道をしましたが、ここで整理しておきますと、「眠りたいのに眠れない」という言い方も、実はその正体は「眠るべきなのに眠れない」だったということなのです。
つまり「眠れない」という状態は、「眠れ!」と高圧的に指令する「頭」と、「意地でも眠るものか!」と反発する「心」(=「身体」)の対立の構図で理解できるということです。
なぜ「心」(=「身体」)は、
「眠るまい」と反発するのか?
「眠るまい」と「心」(=「身体」)が反発するのには、いくつかの理由が考えられます。
1つは、そもそも眠りは「心」(=「身体」)の側が自然に行なうはずのものであって、「頭」によって指示される筋合いのものではないということです。
「頭」に相当する部分を持たず「心」(=「身体」)だけでできている自然界の動物においては、睡眠は自然な欲求であり、葛藤なく実現されています。ですから、「心」(=「身体」)にしてみれば、「頭」が睡眠に口を差し挟んでくることは越権行為であり、それに反発を覚えるのも当然のことでしょう。
現代人の生活は、案外歴史の浅い、時計仕掛けの硬直化した時間によって毎日の生活が規制されています。
季節が変わっても、天候がどうであれ、体調や気分がどんなでも、決まった時間に起床し出勤しなければなりません。そこから逆算して、睡眠を○○時間とるべきだから何時には寝るべきである、と「頭」が計算し、きちんと実行できることが「規則正しい」ことだとして奨励されています。
日々刻々と変わる生き物としては、必要とする睡眠の長さが日によって違ったり、眠くなる時間が変動したりすることはごく自然なことなのですが、しかしこれも現代の常識からすれば、「不規則な睡眠」として異常視されてしまう状況なのです。また、「うつ」状態においてよく見られる昼夜逆転の状態も、その意味が熟慮されずに、はなから病的なものと捉えられてしまう残念な傾向もあります。
フランスの啓蒙思想家ルソーは、代表作『エミール』の中で次のように述べています。
食事と睡眠の時間をあまり正確にきめておくと、一定の時間ののちにそれが必要になる。やがては欲求がもはや必要から生じないで、習慣から生じることになる。というより、自然の欲求のほかに習慣による新しい欲求が生じてくる。そんなことにならないようにしなければいけない。
子供につけさせてもいいただ一つの習慣は、どんな習慣にもなじまないということだ。(今野一雄訳、岩波文庫より)
1日を一生と捉えて毎日の死を迎える
「心」(=「身体」)が「眠るまい」とするもう1つの理由として、今日1日の幕を引く気になれないということが考えられます。
メメント・モリ(memento mori「死を想え」「死を忘れるな」という意味)という古いラテン語の格言があります。これは、「死」というものを想うことによって、ともすれば浪費されがちな「生」の有限性とはかなさを知らしめる警句です。
「よく死ぬ」ためには「よく生きなければ」なりません。ここで言う「よく生きる」とは、自分に生来与えられた固有の資質を存分に開花させ、自分らしい「生」を享受する生き方のことです。
これを1日の単位で考えてみても、同様のことが言えるのです。
1日を締めくくる眠りを、いわば「毎日の死」として捉えてみると、今日1日を「よく生きて」いなければ、「よく死ねない」。つまり、「死ぬに死ねない」がゆえに不眠になってしまうわけです。
1日をどう締めくくるか
もちろん、1日は限りある短い時間ですから、欲張ってあれもこれもすることはできません。しかしながら、1日の中でたとえわずかでもその人らしい時間を持つことができたか否かは、その日の眠りを大きく左右します。
よく「身体を動かして疲れれば眠くなるものだ」と言われたりしますが、これは「身体を動かす」ことがその人らしい過ごし方である場合に限って有効なものであって、そうでないタイプの人がいくら身体を動かしても、「身体は疲れているのに、頭だけが冴えてしまって眠れない」ということになってしまいます。
静かに読書したり、音楽を聴いたり、日記をつけて自分との対話を行なったりすることがその人にとって大切な「自分らしい時間」であるならば、たとえ30分でもそんな時間を持つことによって、自分の奥底で何かが充足し納得するので、眠気も自然に訪れやすくなるでしょう。
どのように過ごすことが「自分らしい時間」になるのか、それは各人各様ですから、自分自身で試行錯誤しながら見つけていく必要があります。
おびただしい「すべきこと」に追い立てられ日々を過ごさざるを得ない私たちにとって、ここで述べたようなことを実行することは、なかなか容易ではないかも知れません。しかし、何が自然で何が不自然なことなのか、日々の生活に何が欠けているのかということに無自覚であるよりは、せめて問題の所在に気づいているだけでも大きな違いなのです。
また、薬物療法を要するような不眠に苦しんでいる方であっても、社会化された「頭」が、内なる自然(「心」=「身体」)に向かって力ずくで睡眠剤という爆弾を投下し「あるべき睡眠」を強要するようなイメージではなく、時間に制約された状況に生きているがゆえに薬を使わざるを得ないことを、自分の「心」(=「身体」)に詫びつつ、「これで少しでもお休みください」とお願いするような気持ちで薬を使用することが大切だと思うのです。
----------
ここでは、「眠りたいのに眠れない」という言い方は、その正体は「眠るべきなのに眠れない」だったということになっていますね。
で、現代人の生活は、歴史の浅い、時計仕掛けの硬直化した時間によって毎日の生活が規制されている。
で、ルソーの作品から引用し、眠れないと言う人は、体の必要性からくる欲求より、習慣による欲求に支配されているのではないかと指摘しています。
「自分らしい時間」を過ごすことが、眠りにつく鍵としていますが、、、確かにこれを探すのは難しそうですね。だって、「自分さがし」って言葉がはやるほど、自分が何者なのかわからん人は一杯いるでしょうから。
私は寝しなに、数学の問題をやったり、哲学書みたいな難解な本を読み出すと、とたんに眠くなります。そういえばリカ子は、数学の問題を解きだすと、頭が冴え、シャキっとすると言っていました。
「自分らしい時間」、私にとって数学とか哲学は違うみたいです。
自分の奥底で何かが充足し納得するという「自分らしい時間」、、、私のそれは、ネットオークションです! これをやりだすと、リカ子と同様、頭が冴え、興奮し、眠りに、、、あれっ、眠りにつけないよ!
え“、何、このオチ?と思った人、 <ここをクリックよろしくね~ >
This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)