入院中のことを少し書いておきましょう。
入院生活で私が一番困るのは、他人のいびきです。
寝る時は真っ暗、一人でないと寝られない私です。普段の生活では、その環境だと朝までノンストップ8時間睡眠はいけます。しかし、4人部屋だと誰かがいびきをかき、トイレに行き、そして看護師だって見回りに来ます。
というわけで、デリケートな私は、必ず眠れなくなります。今回もそうでした。
睡眠不足は折り込み済みです。仕方ないから同部屋の人の寝言なんぞを聞いて過ごしていました。寝言は、何を言っているのか不明瞭なのが救いですね。明瞭だと、どんどん興味が湧いて聞き入ってしまいますから(笑)。
ある晩のことです。お隣の病室へ移ってきたおばあちゃんが、、、
「助けて~、誰か来て~」
何事ぞっ!って、思いますよね。
でも私は両足を手術しているし、周りの人たちだって似たようなもの。看護師が来るのをじっと待つだけ。
しかし看護師は来ない。おばあちゃんは叫んではいるものの、ナースコールを押していない様子。その後、おばあちゃんと同室の人によると、「助けて~」は彼女の口癖なんだそうな。
以後、毎日、何度もおばあちゃんの「助けて~」が聞こえることとなったのであります。
これが「○○に惚れとるで~」とか「○○を食べさせろ~」とかなら、生暖かい目でスルーできるのですが。。。
このおばあちゃん、誰かに助けを求めなくてはならぬ人生を送ってきたというのか??
などと、私の妄想は脹らむ一方で、
聞くのが精神的に辛くなってしまいました。
昨年末に怪我をして以来、周りの助けを借りて生活を続ける私です。親切な友人の助けなしには,ご飯だって食べられなかった。役所や病院にも行けなかったのです。私こそ「助けて~、誰か来て~」と叫び続けていた張本人なのであります。
自分も80歳を超えてなお、助けてと叫ぶ生活を送るようになるんじゃないか、、、と想像すると、暗くなってしまって。叫ぶの、もうやめてと、彼女に苛立ちを感じるようになっていったのです。
毎日この口癖を聞き、憂鬱になっていたら、ある夜のことです。同室の84歳のおばあちゃんが寝言で「早くやらなくちゃ~」。
彼女は翌朝、仕事をしていた夢を見たと話してくれました。このおばあちゃんは50歳の時、夫を亡くし、夫の会社の社長となり、従業員を養うために身を粉にして働いたそうです。従業員のご飯まで作っていたというから、朝から寝るまで働き詰めだったのでしょう。昔の話ですから、今よりずっと労働はきついはずです。
夢の中でも働き続けるおばあちゃん。この方は相当、頑張って生きてきたんじゃないかと。
80歳を超えた時、私はこんな格好いいおばあちゃんになっていたい。
尊敬できるおばあちゃんの出現に、私も頑張らなくっちゃと、自分に活を入れたのであります。
----------
【ネット依存】
治療目標は「節度ある使用に戻すこと」
インターネット上のゲームやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に没頭し、日常生活での心身状態や対人関係などに弊害が生じる状態をネット依存(インターネット嗜癖)と呼ぶ。2004年ごろから韓国などで注目を集め始め、長時間、同じ姿勢でインターネットを利用することで深部静脈血栓症を発症した例や、ネット依存との関連が疑われる自殺例などが問題となっている。
ネット依存は米国精神医学会によるDSM-4分類には含まれておらず、疾患として認定されていない。そのため、統一された診断基準はまだない。現在、診断の参考として主に使われているのが、米セント・ボナベンチャー大のキンバリー・ヤング氏が考案した「Internet Addiction Test(IAT)」と、韓国の情報社会振興院(National Information Society Agency)が開発した「Kスケール」だ。
どちらも「配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがあるか」「睡眠時間を削り、深夜までインターネットをすることがあるか」といった複数の質問項目を設け、回答項目ごとに設定された得点の合計で判定する。IATでは20問の設問があり、100点満点中40~69点をネット依存傾向、70~100点をネット依存の疑いとしている。
日本では11年7月、国立病院機構久里浜医療センターが国内初のネット依存治療部門を開設した。同センターはそれに先立つ08年に、20歳以上の男女4123人を対象としてIATによるネット依存傾向の調査を実施。回答を得た4090人のうち、2%に当たる82人が40点以上だった。
この結果から同センターの心理療法士の三原聡子氏は、国内の成人のネット依存傾向者(IAT40点以上)は約270万人と推計。ただし、「当センターに来院する患者の7割が大学生までの若年層であるため、調査対象に20歳未満も含めれば、より多くの依存者の存在が明らかになるのではないか」と推測する。
治療は、薬剤をほとんど使わず、生活習慣の改善を目的に個人精神療法などが行われる。同センターの精神科医の中山秀紀氏は「アルコールや麻薬と違い、インターネットは人々の生活に必要不可欠なものとなっており、節度ある使用に戻すことが治療目標となる。治療が困難な患者には根気強くアプローチをし、利用時間を制限していくことが重要となる」と語る。
現時点では、明確に効果が得られる治療法がないのが実情だ。三原氏は、「開設してから昨年12月までに121人の患者がネット依存を主訴に来院しているが、継続的に通院できている患者は3~4割。治療に難渋する患者の中には、うつ病や注意欠陥・多動性障害(ADHD)が背景にあるケースもある」と話す。
最近では患者に週1回、朝から夕方まで院内で過ごしてもらい、インターネットを使えない時間を設けるなどの取り組みを始めているという。「今後は、アルコール依存の治療に使われているグループ療法などの導入も検討していきたい」と中山氏は話している。
----------
入院中、私が一番懸念したのはこの問題です。私も1日中、ネット接続生活なので、それがいきなり遮断されたら、私は我慢できるのだろうかと。
結果は、全く問題なしでした♩
というか、ネットショッピングとかオークションとか、無駄に時間を使っていたことがよくわかりました。ネットショッピングで品物を買うことより、どんな品があるのかに興味があるだけだったんです。知ってためになるのか? なりませんね(苦笑)。
人気ブログランキングに参加中、<ここをクリックよろしくね~ >

This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)
入院生活で私が一番困るのは、他人のいびきです。
寝る時は真っ暗、一人でないと寝られない私です。普段の生活では、その環境だと朝までノンストップ8時間睡眠はいけます。しかし、4人部屋だと誰かがいびきをかき、トイレに行き、そして看護師だって見回りに来ます。
というわけで、デリケートな私は、必ず眠れなくなります。今回もそうでした。
睡眠不足は折り込み済みです。仕方ないから同部屋の人の寝言なんぞを聞いて過ごしていました。寝言は、何を言っているのか不明瞭なのが救いですね。明瞭だと、どんどん興味が湧いて聞き入ってしまいますから(笑)。
ある晩のことです。お隣の病室へ移ってきたおばあちゃんが、、、
「助けて~、誰か来て~」
何事ぞっ!って、思いますよね。
でも私は両足を手術しているし、周りの人たちだって似たようなもの。看護師が来るのをじっと待つだけ。
しかし看護師は来ない。おばあちゃんは叫んではいるものの、ナースコールを押していない様子。その後、おばあちゃんと同室の人によると、「助けて~」は彼女の口癖なんだそうな。
以後、毎日、何度もおばあちゃんの「助けて~」が聞こえることとなったのであります。
これが「○○に惚れとるで~」とか「○○を食べさせろ~」とかなら、生暖かい目でスルーできるのですが。。。
このおばあちゃん、誰かに助けを求めなくてはならぬ人生を送ってきたというのか??
などと、私の妄想は脹らむ一方で、
聞くのが精神的に辛くなってしまいました。
昨年末に怪我をして以来、周りの助けを借りて生活を続ける私です。親切な友人の助けなしには,ご飯だって食べられなかった。役所や病院にも行けなかったのです。私こそ「助けて~、誰か来て~」と叫び続けていた張本人なのであります。
自分も80歳を超えてなお、助けてと叫ぶ生活を送るようになるんじゃないか、、、と想像すると、暗くなってしまって。叫ぶの、もうやめてと、彼女に苛立ちを感じるようになっていったのです。
毎日この口癖を聞き、憂鬱になっていたら、ある夜のことです。同室の84歳のおばあちゃんが寝言で「早くやらなくちゃ~」。
彼女は翌朝、仕事をしていた夢を見たと話してくれました。このおばあちゃんは50歳の時、夫を亡くし、夫の会社の社長となり、従業員を養うために身を粉にして働いたそうです。従業員のご飯まで作っていたというから、朝から寝るまで働き詰めだったのでしょう。昔の話ですから、今よりずっと労働はきついはずです。
夢の中でも働き続けるおばあちゃん。この方は相当、頑張って生きてきたんじゃないかと。
80歳を超えた時、私はこんな格好いいおばあちゃんになっていたい。
尊敬できるおばあちゃんの出現に、私も頑張らなくっちゃと、自分に活を入れたのであります。
----------
【ネット依存】
治療目標は「節度ある使用に戻すこと」
インターネット上のゲームやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に没頭し、日常生活での心身状態や対人関係などに弊害が生じる状態をネット依存(インターネット嗜癖)と呼ぶ。2004年ごろから韓国などで注目を集め始め、長時間、同じ姿勢でインターネットを利用することで深部静脈血栓症を発症した例や、ネット依存との関連が疑われる自殺例などが問題となっている。
ネット依存は米国精神医学会によるDSM-4分類には含まれておらず、疾患として認定されていない。そのため、統一された診断基準はまだない。現在、診断の参考として主に使われているのが、米セント・ボナベンチャー大のキンバリー・ヤング氏が考案した「Internet Addiction Test(IAT)」と、韓国の情報社会振興院(National Information Society Agency)が開発した「Kスケール」だ。
どちらも「配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがあるか」「睡眠時間を削り、深夜までインターネットをすることがあるか」といった複数の質問項目を設け、回答項目ごとに設定された得点の合計で判定する。IATでは20問の設問があり、100点満点中40~69点をネット依存傾向、70~100点をネット依存の疑いとしている。
日本では11年7月、国立病院機構久里浜医療センターが国内初のネット依存治療部門を開設した。同センターはそれに先立つ08年に、20歳以上の男女4123人を対象としてIATによるネット依存傾向の調査を実施。回答を得た4090人のうち、2%に当たる82人が40点以上だった。
この結果から同センターの心理療法士の三原聡子氏は、国内の成人のネット依存傾向者(IAT40点以上)は約270万人と推計。ただし、「当センターに来院する患者の7割が大学生までの若年層であるため、調査対象に20歳未満も含めれば、より多くの依存者の存在が明らかになるのではないか」と推測する。
治療は、薬剤をほとんど使わず、生活習慣の改善を目的に個人精神療法などが行われる。同センターの精神科医の中山秀紀氏は「アルコールや麻薬と違い、インターネットは人々の生活に必要不可欠なものとなっており、節度ある使用に戻すことが治療目標となる。治療が困難な患者には根気強くアプローチをし、利用時間を制限していくことが重要となる」と語る。
現時点では、明確に効果が得られる治療法がないのが実情だ。三原氏は、「開設してから昨年12月までに121人の患者がネット依存を主訴に来院しているが、継続的に通院できている患者は3~4割。治療に難渋する患者の中には、うつ病や注意欠陥・多動性障害(ADHD)が背景にあるケースもある」と話す。
最近では患者に週1回、朝から夕方まで院内で過ごしてもらい、インターネットを使えない時間を設けるなどの取り組みを始めているという。「今後は、アルコール依存の治療に使われているグループ療法などの導入も検討していきたい」と中山氏は話している。
----------
入院中、私が一番懸念したのはこの問題です。私も1日中、ネット接続生活なので、それがいきなり遮断されたら、私は我慢できるのだろうかと。
結果は、全く問題なしでした♩
というか、ネットショッピングとかオークションとか、無駄に時間を使っていたことがよくわかりました。ネットショッピングで品物を買うことより、どんな品があるのかに興味があるだけだったんです。知ってためになるのか? なりませんね(苦笑)。
人気ブログランキングに参加中、<ここをクリックよろしくね~ >
This blog “The salon of breast cancer women authored by Noe:l” is able to read in Japanese:-)










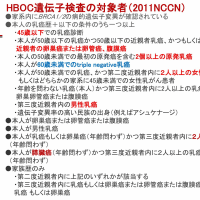
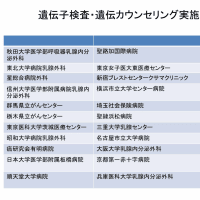
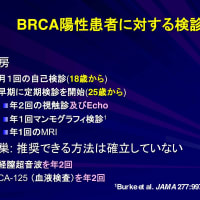
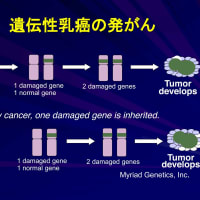
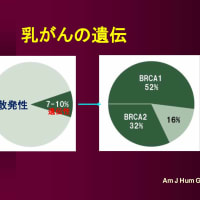
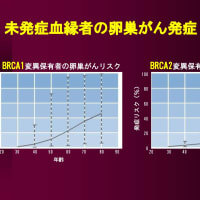
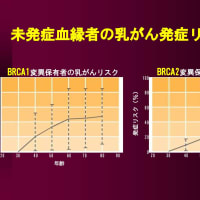



私は、病院の方針で術後2~3日は、必ず2人部屋で、お行儀もよいお方との同室だったため、幸運でした。
が、産婦人科への入院だったので、たまに夜中のお産とかで、助産師や医師が、廊下をパタパタ小走りしたり、付き添われた家族の方のひそひそ声で目が覚めたことがありました。(あと乳児の夜泣きとかw)
でも、命の誕生なので、ああ、産まれたんだなぁって、素直に安心して寝ちゃいましたけどw
病棟によって違うのかもしれませんね。
インターネット、あればはまってしまうけれど、なければ、散歩と読書で案外過ごせました。
あ、あと、痛みが引いたとたん、売店で珈琲を飲む楽しみも♪持っていた小銭は、ほとんど珈琲代に消えました~
流産した知人は、出産した患者さんたちと同室にされ、とっても辛かったと言っていました。病状から考えると流産も出産も似たようなものかもしれませんが、こりゃ厳しいですわな。
ネットのない生活、私も大丈夫なことがわかってちょっと安心です。
実はかなり心配でした(^///^)。