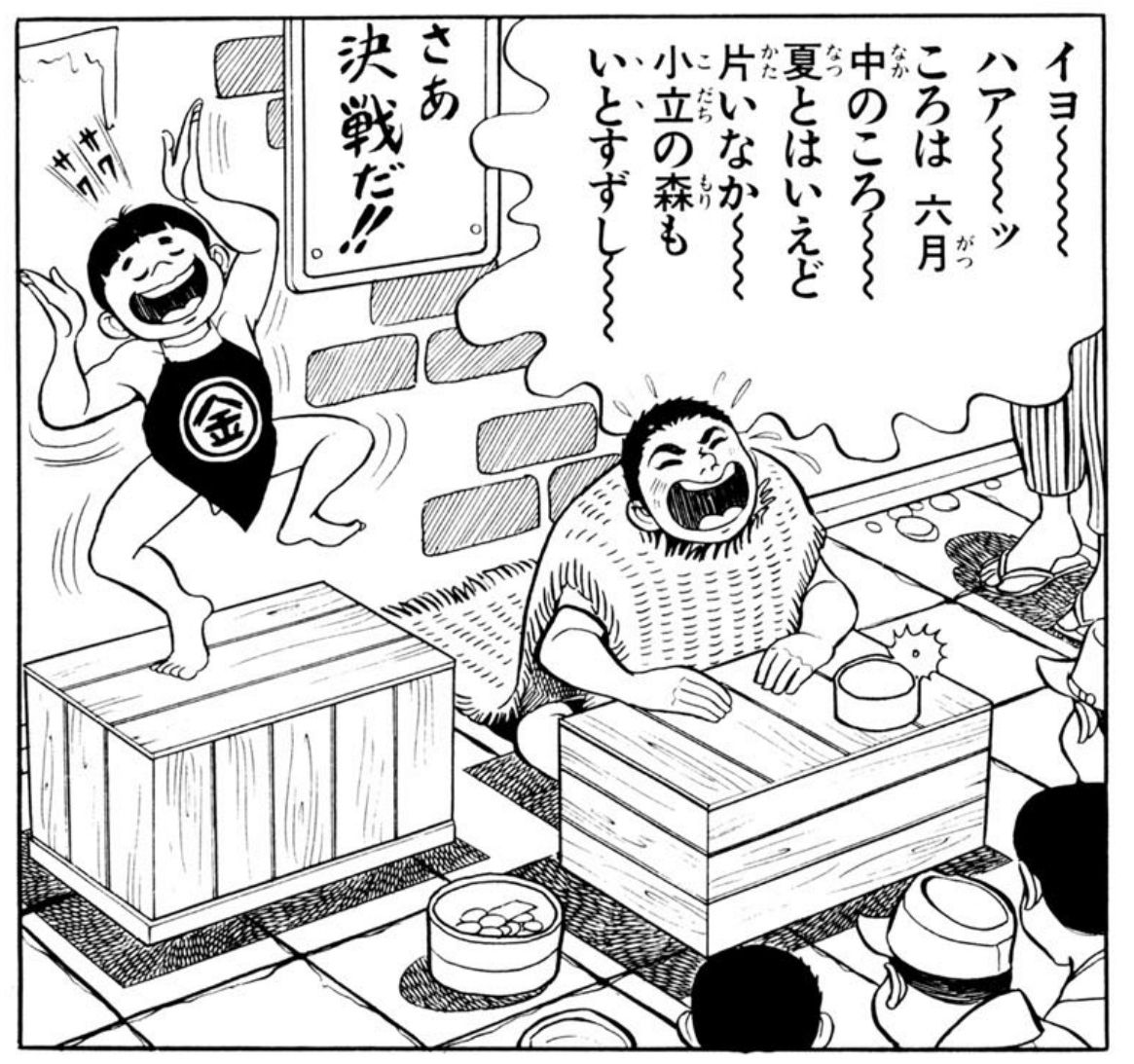スノーボール 改訂版中 アリス・シュローダー P107
<
だが、バフェットと長時間いっしょにいると、つむじ風のようにほとばしるエネルギーに閉口することがあった。”飽くことを知らない”と人々はささやいた。バフェットの注意がそれると、うしろめたく思いつつほっとする。バフェットは相手が興味を持つと思われる切り抜きや資料を山ほど友人に送りつける。さりげない会話のようでも、じつはそうではない。どんなに漠然としていても、バフェットの話にはつねになにかの目的があり、相手を試していることもあった。一件納期そうな態度に見えるが、バフェットは内面の緊張で細かく振動している。
>
同前P128
<
バフェットは心の底から「どうか遊びに来てください、お待ちしています」というのだが、そのうちにそういう相手がやってくると、彼らがいることだけで満足したかのように、新聞を読みふけった。逆に延々と話しつづけて、相手がぐったりして帰ってしまうこともたまにあった。
>
<
だが、バフェットと長時間いっしょにいると、つむじ風のようにほとばしるエネルギーに閉口することがあった。”飽くことを知らない”と人々はささやいた。バフェットの注意がそれると、うしろめたく思いつつほっとする。バフェットは相手が興味を持つと思われる切り抜きや資料を山ほど友人に送りつける。さりげない会話のようでも、じつはそうではない。どんなに漠然としていても、バフェットの話にはつねになにかの目的があり、相手を試していることもあった。一件納期そうな態度に見えるが、バフェットは内面の緊張で細かく振動している。
>
同前P128
<
バフェットは心の底から「どうか遊びに来てください、お待ちしています」というのだが、そのうちにそういう相手がやってくると、彼らがいることだけで満足したかのように、新聞を読みふけった。逆に延々と話しつづけて、相手がぐったりして帰ってしまうこともたまにあった。
>