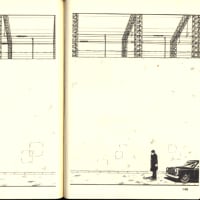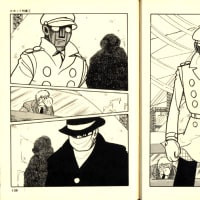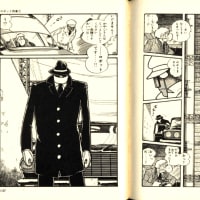陸の孤島であったかつてのインカ帝国では金の流通はあまりなく、加工できる便利な金属程度の認識で、市場は布の交換などによって成り立っていた。
このようにブランドでの価値と言うものについては古今東西通底するものではなく、時と場所によってはそれが成り立たないものとなる。
かつてのDCブランドは、それはもう鳴りをひそめた。
ブランドものでギラギラとしている様と言うのは現代社会で敬遠され、高級品でさえ素朴路線を描いている。
尚、高級品路線を狙うのは間違いではない。大塚家具と匠大塚でどちらが成功したのかというのは一目瞭然であろう。
ただ、マクロ経済の衰退と、それに伴うミクロ経済の縮小においては、その購買層において財布の紐の空き口の幅も短くすることを余儀なくされたと言うのは間違いない。
それがベースとなって、ブランド品が衰退したとも言える。
2019年においての自動車販売で一番売れているのが軽自動車であると言うのもその象徴である。
だが、一方において現在は1台20万円もするスマートフォンが売れているのも事実である。
要は、ブランド嗜好と言う人間の特性は変わっていない。従来産業におけるブランドと捉えられていたもの、衣服、車、腕時計と言うものが、別のものへと変遷したのだ。
ここで言うブランド嗜好は何かというのを社会哲理の観点からおさらいしてみると、ブランド嗜好とは個人の地位やステータスとしての個の外的表現をするための所有品や装飾品と言うことになる。
幼稚園児/保育園児にしてもそうで、アンパンマンから仮面ライダーに乗り換えるのは「あいつアンパンマンなんて見ているよ」と言う年相応におけるステータスの下降を防ぐために仮面ライダーやらウルトラマンやら戦隊モノに乗り換えるのではないかと私は予想している。
それが20年前は衣服であり、車であり、腕時計であり、靴であり、宝石であり、学歴であったわけだが、現代社会ではスマートフォンに変化した。
この「変遷し続けるトレンド」と言うのは10〜20年スパンでおそらく継続し続ける。
このスマホについてもいずれは「どうでもいい」と扱われ、別の何かが個人の見栄とステータスを象徴するものとして誕生するのではないかと考える。そこにビジネスチャンスがある。
80年ほど前は日本海軍がある種のブランドであったわけであるが、今の日本人はそういう意識をあまり持っていない。
持っていても少数派であろう。
このようにブランドでの価値と言うものについては古今東西通底するものではなく、時と場所によってはそれが成り立たないものとなる。
かつてのDCブランドは、それはもう鳴りをひそめた。
ブランドものでギラギラとしている様と言うのは現代社会で敬遠され、高級品でさえ素朴路線を描いている。
尚、高級品路線を狙うのは間違いではない。大塚家具と匠大塚でどちらが成功したのかというのは一目瞭然であろう。
ただ、マクロ経済の衰退と、それに伴うミクロ経済の縮小においては、その購買層において財布の紐の空き口の幅も短くすることを余儀なくされたと言うのは間違いない。
それがベースとなって、ブランド品が衰退したとも言える。
2019年においての自動車販売で一番売れているのが軽自動車であると言うのもその象徴である。
だが、一方において現在は1台20万円もするスマートフォンが売れているのも事実である。
要は、ブランド嗜好と言う人間の特性は変わっていない。従来産業におけるブランドと捉えられていたもの、衣服、車、腕時計と言うものが、別のものへと変遷したのだ。
ここで言うブランド嗜好は何かというのを社会哲理の観点からおさらいしてみると、ブランド嗜好とは個人の地位やステータスとしての個の外的表現をするための所有品や装飾品と言うことになる。
幼稚園児/保育園児にしてもそうで、アンパンマンから仮面ライダーに乗り換えるのは「あいつアンパンマンなんて見ているよ」と言う年相応におけるステータスの下降を防ぐために仮面ライダーやらウルトラマンやら戦隊モノに乗り換えるのではないかと私は予想している。
それが20年前は衣服であり、車であり、腕時計であり、靴であり、宝石であり、学歴であったわけだが、現代社会ではスマートフォンに変化した。
この「変遷し続けるトレンド」と言うのは10〜20年スパンでおそらく継続し続ける。
このスマホについてもいずれは「どうでもいい」と扱われ、別の何かが個人の見栄とステータスを象徴するものとして誕生するのではないかと考える。そこにビジネスチャンスがある。
80年ほど前は日本海軍がある種のブランドであったわけであるが、今の日本人はそういう意識をあまり持っていない。
持っていても少数派であろう。