集英社新書による「上司は思いつきでものを言う」、「『わからない』という方法」の続編。第一章/乱世と勝ち組み、第二章/たった一つの価値観に抗する、第三章/悲しき経済、第四章/どう生きていったらいいんだろう?、おまけの一章/「世襲制度」について。
橋本氏は、「勝ち組・負け組」という二分法の危険性を問う。「勝敗の結果」に依っているこの二分法が、実は「勝ち・負け」を言われる競争の当事者の外側にいる人達、投資家やエコノミストによってジャッジされているに過ぎないことを明らかにする。
「バブルがはじけた」と言われた後の時代は、乱世です、と言いきる。「我々の考えることは、『勝ち組みのあり方』ではなくて、『我々の視点で見る』なのです。そういう簡単なことが忘れられてしまっているからこそ、現在は『混迷の中にある』ということになってしまうのです」という。
そして、「エコノミストにとっての『乱世』は、『世界経済が破綻した後の状態』なのでしょうが、私にとっての『乱世』は、”世界経済を破綻させないように”として、エコノミストが絶対の権限を握ってしまった危機状態』のことです」という。
「事態の打開にはいろいろな方向性があるにもかかわらず、どうして現代では、”たった一つの方向性”だけが浮かび上がってしまうのか」と問いかける。
「経済」の語源、「経世済民」の本来の意味である「世を治め、民の生活を安定させること」、「民政」を示す。「これは、国民の利益・幸福を図るということをする、政治の一部門である。こういう考え方が近代以前にあって、そこに『ECONOMY』がやって来た。だから『経世済民』という大概念の中に「経済」として位置付けられた」と解説する。
橋本氏は、「我々が幸福であるようなあり方を模索する」がイコール「経済」であってもいい、「経済」とは、「その具体的な方策の一つ」であってしかるべきとする。世界でうごめく「欲望」に対する「我慢」、「ただ『我慢ができない」だけの人間は愚か者である」し、このことが、「この現実をなんとかする」につながると締めくくる。
橋本氏は、「勝ち組・負け組」という二分法の危険性を問う。「勝敗の結果」に依っているこの二分法が、実は「勝ち・負け」を言われる競争の当事者の外側にいる人達、投資家やエコノミストによってジャッジされているに過ぎないことを明らかにする。
「バブルがはじけた」と言われた後の時代は、乱世です、と言いきる。「我々の考えることは、『勝ち組みのあり方』ではなくて、『我々の視点で見る』なのです。そういう簡単なことが忘れられてしまっているからこそ、現在は『混迷の中にある』ということになってしまうのです」という。
そして、「エコノミストにとっての『乱世』は、『世界経済が破綻した後の状態』なのでしょうが、私にとっての『乱世』は、”世界経済を破綻させないように”として、エコノミストが絶対の権限を握ってしまった危機状態』のことです」という。
「事態の打開にはいろいろな方向性があるにもかかわらず、どうして現代では、”たった一つの方向性”だけが浮かび上がってしまうのか」と問いかける。
「経済」の語源、「経世済民」の本来の意味である「世を治め、民の生活を安定させること」、「民政」を示す。「これは、国民の利益・幸福を図るということをする、政治の一部門である。こういう考え方が近代以前にあって、そこに『ECONOMY』がやって来た。だから『経世済民』という大概念の中に「経済」として位置付けられた」と解説する。
橋本氏は、「我々が幸福であるようなあり方を模索する」がイコール「経済」であってもいい、「経済」とは、「その具体的な方策の一つ」であってしかるべきとする。世界でうごめく「欲望」に対する「我慢」、「ただ『我慢ができない」だけの人間は愚か者である」し、このことが、「この現実をなんとかする」につながると締めくくる。










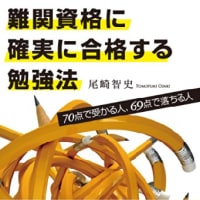
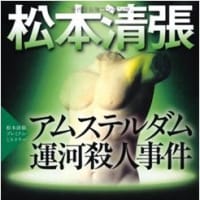
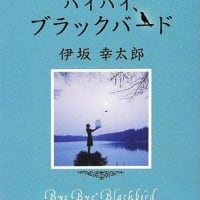

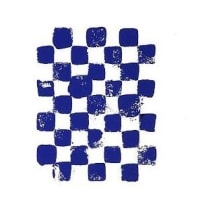
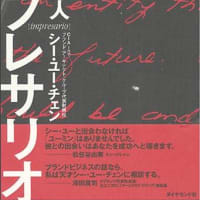



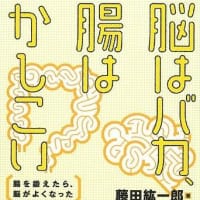
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます