
<目次>
序章 ものすごく小さくて大きな世界
第1章 宇宙は何でできているのか
第2章 究極の素粒子を探せ!
第3章「4つの力」の謎を解く――重力、電磁気力
第4章 湯川理論から、小林・益川、南部理論へ――強い力、弱い力
第5章 暗黒物質、消えた反物質、暗黒エネルギーの謎
先日、理化学研究所が「iPS細胞」を、目の網膜の再生に応用する、世界初の臨床研究を国に申請したことが報じられましたね。いよいよ山中教授の研究成果が臨床の場に移され、実証の段階に入りました。大いに期待したいところです。
何で本書を買ったのかよく覚えていませんが、理系オンチの私が読んでも少し理解ができました。そんな私が、本書について最も関心を持ったのは、「宇宙は何でできているのか」という物理学上の命題に対して、日本人物理学者が湯川秀樹さん以来、世界の先端でずっと理論的なリーダシップの一角を担っているということでした。
<ノーベル物理学賞>
1949年の湯川秀樹さんの「中間子の存在の予想」
1965年の朝永振一郎さんの「量子電気力学分野での基礎的研究」
2008年の小林誠さん、益川敏英さんの「林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見による素粒子物理学への貢献」、南部陽一郎さんの「素粒子物理学および原子核物理学における自発的対称性の破れの機構の発見」
これだけを書いても、一般の方にはチンプンカンプンな内容ですが、要は、この宇宙を構成する原子の最小要素が何であるか、という命題に対して、60年以上も前にそれを世界的に先駆な形で理論的に仮説を立て、それが実証されてきた、ということなんですね。
また、この理論物理学の仮説に対して、一連の実証に一役買ったのが、2002年にノーベル賞を受賞した小柴昌俊さんの「宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献」。
2009年11月、「事業仕分け人」蓮舫議員が次世代スーパーコンピュータ開発の予算に関して、その要求予算の妥当性についての説明を求めた「世界一になる理由は何があるんでしょうか?2位じゃダメなんでしょうか?」という質問に対して当時、賛否両論の話題になりましたね。
今振り返ると、この極めて簡素な質問に対して、単刀直入に応えられなかった文科省の担当者に問題があったんだと思います。基礎研究の各分野で世界一になることの重要性は、言わずもがな、のことです。日本政府はこうした研究に対し、恒久的に十分な支援を続けるべきですね。
また、本書の執筆者である村山斉さんのような伝道師役的研究者が各分野に必要ですね。

湯川 秀樹(1907年1月23日 - 1981年9月8日)日本の理論物理学者。
原子核内部において、陽子や中性子を互いに結合させる強い相互作用の媒介となる中間子の存在を1935年に理論的に予言した。1947年、イギリスの物理学者セシル・パウエルが宇宙線の中からパイ中間子を発見したことにより湯川理論の正しさが証明され、これにより1949年(昭和24年)、日本人として初めてノーベル賞を受賞した。

朝永 振一郎(1906年3月31日 - 1979年7月8日)日本の物理学者。
相対論的に共変でなかった場の量子論を超多時間論で共変な形にして場の演算子を形成し、場の量子論を一新した。超多時間論をもとにくりこみ理論の手法を発明し量子電磁力学の発展に寄与した功績によって、1965年にジュリアン・シュウィンガー、リチャード・ファインマンと共同でノーベル物理学賞を受賞した。


自然界においてクォークが少なくとも三世代以上存在することを予言する、対称性の破れの起源の発見。「小林・益川理論」。両者はこの論文の中で、もしクォークが3世代(6種類)以上存在し、クォークの質量項として世代間の混合を許すもっとも一般的なものを考えるならば、既にK中間子の崩壊の観測で確認されていたCP対称性の破れを理論的に説明できることを示した。

南部 陽一郎(1921年1月18日 - )日本生まれのアメリカ人理論物理学者。
1952年に渡米。1960年代に量子色力学と自発的対称性の破れの分野において先駆的な研究を行ったほか、弦理論の創始者の一人としても知られ、現在の素粒子物理学の基礎をなす様々な領域に多大な貢献をなした。とくに自発的対称性の破れの発見により、2008年にノーベル物理学賞を受賞した。

小柴 昌俊(1926年9月19日 - )は、日本の物理学者。
1987年、自らが設計を指導・監督したカミオカンデによって史上初めて自然に発生したニュートリノの観測に成功したことにより、2002年にノーベル物理学賞を受賞した。
彼らの業績の源泉には、このお二人の存在がありました。

坂田 昌一(1911年1月18日 - 1970年10月16日)日本の物理学者。
元名古屋大学教授。湯川秀樹、朝永振一郎とともに日本の素粒子物理学をリードした。湯川の中間子論の第2から第4論文の共著者である。1955年、中性子・陽子・ラムダ粒子が最も基本的な粒子とし他のハドロンはこの3つの素粒子とそれらの反粒子で組み立てられるというハドロンの複合模型(坂田模型)を発表した。

仁科 芳雄(1890年12月6日 - 1951年1月10日)日本の物理学者。
日本に量子力学の拠点を作ることに尽くし、宇宙線関係、加速器関係の研究で業績をあげた。日本の現代物理学の父である。理化学研究所時代の弟子からは慕われ、「親方」と呼ばれた。ドイツ滞在中に励ましの書簡を送られた朝永振一郎は、仁科を「温かく親しみやすかった」と評している。また、湯川秀樹は新粒子予言のさいにボーアから批判を受けたが仁科はこれをかばい、後に湯川は「非常に鼓舞された」と語っている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E5%B1%B1%E6%96%89
<村山斉「宇宙になぜ我々が存在するのか」 - 現代ビジネス - isMedia>
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/34514










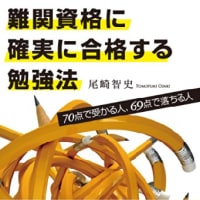
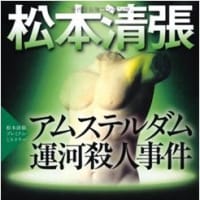
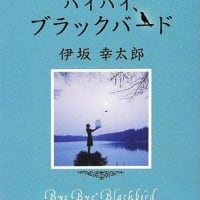

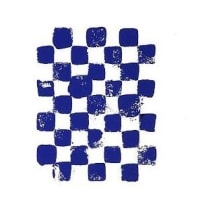
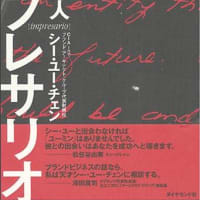



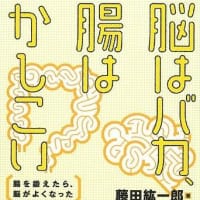
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます