■『彼岸過迄』を読了。岩波の新書判全集で読みました。旧カナは慣れると問題ないですけど、漱石の奔放な宛字が──漱石に限らず明治のものはそういうのが多いようですが──ちょっと読みにくく感じます。今はわたしも含めてたいていの日本人は漱石を文庫本で読むと思いますが、以前なんどか話題にしたように、文庫本では原典の漢字を一般的な用字に書き換えたりカナに開いたり平気でやりますからね。それにしてもわたし、『彼岸過迄』読んでなかったんですねえ。センター試験に出たところ、ぜんぜん記憶になかったので、こりゃいかんと思って、読みました。これは登場人物がやたら動き回る小説ですね。「須永の話」で敬太郎が須永をさそって「両国から汽車に乗つて鴻の台の下迄行」く話が出て来ますけど、漱石の小説で、東京より東のほうが出てくるのってほかになんかありましたっけ。あと、柴又、材木座、小坪、箕面、明石も出てくるでしょ。柴又の川甚て店は今も続く有名なところだそうですね。「二人は柴又の帝釈天の傍迄来て、川甚といふ家へ這入つて飯を食つた。其所で誂らへた鰻の蒲焼が甘垂るくて食へないと云つて、須永は又苦い顔をした。」とあります。川甚のウェブサイトにはこのうちの前半の文だけ、誇らしげに掲げてありました。
■それと、もちろん敬太郎の探偵物語ね。あそこは読んでて面白かったです。
■それと、もちろん敬太郎の探偵物語ね。あそこは読んでて面白かったです。










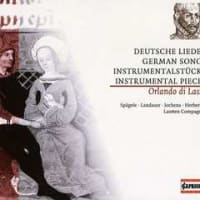
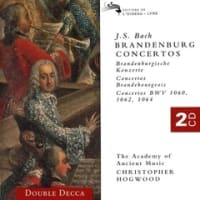
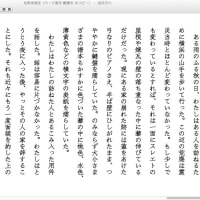
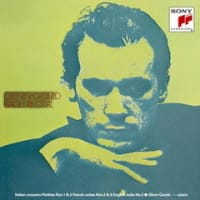




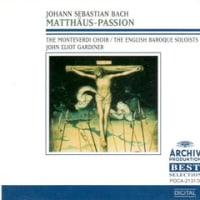





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます