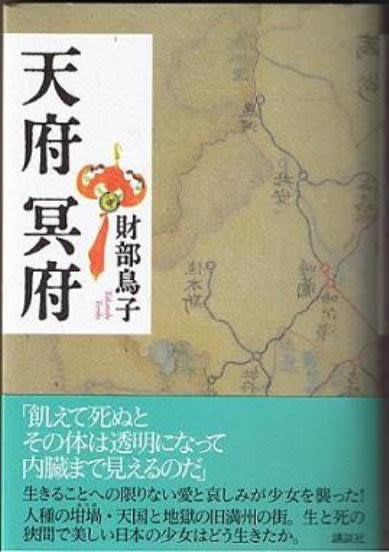
(2005年7月7日・講談社刊)
これはおそらく詩人財部鳥子の私小説と受け取ってよいのではないかと思います。この一冊には「天府」「冥府」と二編の小説が収録されています。旧満州ジャムスにおける生活を、主人公の少女「マス子」の視点から描かれた、占領下の街ジャムス「天府」と、敗戦後に難民となってからの街ジャムス「冥府」は続編と言えるでしょう。
【天府】
主人公は1933に新潟県に生まれましたが、生まれて間もなく父親は妻子を置いて渡満します。それを追うかたちで母親に負ぶわれて旧満州国に渡ることになります。この父親は多分「狭い日本住みあきた。」という、ある種のスローガンに影響された、旧満洲占領時代に大陸に渡った男たちのひとつの典型のように思われます。それに対して「大陸の花嫁」という言葉もありました。この小説は娘の視点で父母の姿が描かれていますが、そこに浮上してくるものは、夫の生き方に翻弄されながらも、言葉を覚えることから始まり、この新天地に必死に生きようとした女性の孤独と哀しみがわたしをとらえます。
しかし「天府」と名付けられたように、ここは日本人にとっては、この時期はある種の豊かさをもたらす土地でもあったわけです。我々日本人が「占領者」であることを知らなかった子供にとっては、この街の人々はみなやさしく、興味深い人々だったはずです。また大人にとっては、その当時の日本の風土のもっていた湿度の高い因習から放たれた人間の生き方が許される場所だったとも言えます。
その背景には「生」と「死」とがと親しく共存する場所であったという「前提」も忘れてはならないでしょう。また「土匪」の度重なる襲来によって疲弊していたジャムスは、多くの日本人を受け入れることを余儀なくされたのです。女の身でありながら母「雪江」は常時帯のなかに拳銃を携帯し、夫のいない夜には、子供をゆるく負ぶったまま眠るということもあったのです。また、夫の不在が多い生活のなかで、孤独な母にはロシア人の毛皮服商との恋もあった。このことには、わたしは少しも驚かないが、「雪江」の娘にとっては根強い記憶となったのだろうか。
私事だが、わたしの父も大学卒業後すぐに旧満州へ渡っている。そして母は「大陸の花嫁」として、父に嫁ぎ、三人の娘に恵まれた。末娘のわたしにはまったく記憶にない世界だが、わたしの母が「雪江」に重なる感覚は最後まで拭えなかった。わたしは「そのままでいい。」と思っている。否定も肯定もしない。
【冥府】
きみの耳なりは詩の音 死の音とよぶ
髪を刈られた極限の少女がすわりこんでいて
永遠にうごかない息をしている
(中略)
きみの心は犬の涙のようにおわっている
この「冥府」を読み終えて、一番はじめに思い出したのは、上記の財部鳥子の詩集「腐蝕と凍結・1968年・地球社刊」のなかの作品「詩の音」でした。わたしは財部鳥子の少女期の旧満州における体験は詩作品のなかでしか理解していなかったと思います。そこで読み取ったものは、凄惨な時代を見てしまった少女の癒しようのない心の傷であり、死んでいった者たちへの取り返しのつかない鎮魂でした。
しかし、この主人公の少女は否応なくではあったとしても、たくましく「冥府」の時代を生きたようです。理髪師の母にいがぐり頭にされて少年のように生きたのです。
『わたしはまたきっぱりと男子になって東亜(註:弟の名)や回復した宮脇青年や和田おばさんたちと稼ぎに出た。コークス拾い、空き家荒し、煙草売り、なんでもやる。』父を亡くし、母は病気から回復せず、長女の主人公は幾度もこうしてみずからに言い聞かせたのでしょう。そして戦後六十年の時期にこの体験を「冥府」と名付けて、潔く世に送った。そしてわたしはそれを一気に読みきったのです。最後はこのように結ばれています。『みんな冥府の情景だと思った。』と・・・・・・。









