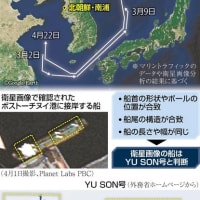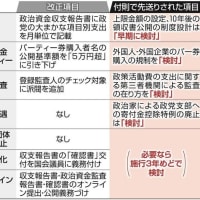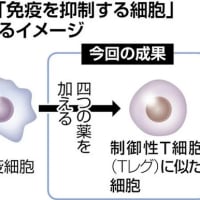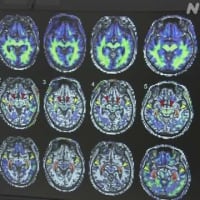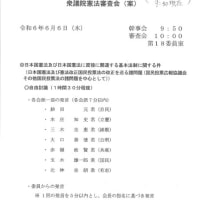©読売新聞
端末使った入試不正、デジタル機器の性能向上で巧妙化…不正対策は「受験生のモラル頼み」の現状 読売新聞 2024/05/17 01:16
早稲田大の入試問題流出事件では、撮影・通信機能を備えた最先端の電子機器「スマートグラス」が悪用された。偽計業務妨害容疑で16日に書類送検された東京都町田市の男子受験生(18)は、撮影した画像をスマートフォンに自動転送するアプリを使っていたほか、撮影時にシャッター音が鳴らないよう細工していたといい、入試不正対策の難しさが改めて浮き彫りになった。
通信端末を悪用した大学入試での不正行為は後を絶たず、大学や文部科学省は対応に苦慮している。
2011年2月には京都大の入試で男子予備校生(当時19歳)が試験問題をインターネット質問掲示板「ヤフー知恵袋」に投稿して解答を募る事件が起きた。携帯電話に問題文を打ち込む手口だったが、デジタル機器の性能向上に伴い、手口はさらに巧妙化した。
22年1月の大学入学共通テストでは、大阪府内の女子大学生(当時19歳)がスマートフォンで試験問題を動画撮影し、仲介役の男に動画を共有。男は静止画に加工し、通話アプリ「スカイプ」で外部の学生に送信して問題を解かせ、女子学生に解答を伝えていた。
事件を受け、大学入試センターはスマホの電波を遮断する装置を共通テストの全会場に設置することを検討したが、毎年約100億円の費用が必要と試算されたため、導入を見送った。
昨年の共通テストからは、試験開始前に監督者が受験生に対してスマホを机上に出すよう指示。電源を切ってかばんにしまわせている。
文科省は22年、全国の大学などに、不正行為は警察に届ける場合があることを受験生に周知するよう通知。巡視時には受験生の手の位置や目線などに注意するよう監督者らに求めている。
文科省幹部は「技術が進歩する中、不正の根絶は難しい。不正が発覚した場合には厳しく取り締まるということを各大学にはさらに徹底して周知してもらい、受験生のモラルに訴えていくしかない」と強調する。
都内の私立大の入試担当者(46)は「試験監督者に丁寧に受験生の様子を見てもらうしか不正防止策はないが、試験中の巡回を強化しすぎれば受験生からクレームが来かねないので難しい」と語った。
韓国では金属探知機での確認も
【ソウル=小池和樹】受験競争の激しい韓国では、日本の大学入学共通テストに相当する「大学修学能力試験」で厳しい不正対策が講じられている。
試験会場には、全ての電子機器の持ち込みが禁止され、監督官は金属探知機で学生による持ち込みの有無を確認することができる。試験会場周辺では外部の人物と不審な連携がないか警察が警戒にあたる。
韓国では2004年に同試験で携帯電話を使った大規模なカンニングが発覚し、対策が厳格化された。だが、21年実施の同試験でも計208件の不正があり、根絶には至っていない。