
(仏教総合雑誌大法輪6月号特集「知っておきたい仏教の常識」掲載)
日本仏教は、そのはじめから国家仏教であり、僧侶はもとから国の庇護と規制の下に置かれた。
七五七年、『僧尼令』二十七条が制定され、僧尼の出家には官の許可を要した。試経という試験に合格すると剃髪し、受戒(四分律二五〇戒)が行われた。律蔵に規定された通り「交淫、盗み、殺人、悟りを得たと詐称する事」が重く禁ぜられ、犯すと還俗しなければならなかったのである。
この時代にもまったく破戒僧がいなかった訳ではないだろう。しかし、官僧として大戒二五〇戒を受持する制約があった。
しかし、後に天台宗では、大乗梵網経にある十重四十八軽戒をもって僧侶の受戒と見なす大乗戒壇を比叡山に建立した。これにより大戒を受持せずとも官僧として遇されることとなった。
このことが、後生の僧侶に厳正な戒律に対する意識低下を助長することになったのである。
鎌倉時代以降、官僧を脱して自由に活動する僧侶が増えて一層戒律が軽視された。
僧兵が現れて不殺生戒を犯し、「末代には妻もたぬ上人年をおうて稀にこそ聞こえし」(沙石集)と記されるように、隠れて妻帯することも特別なことではなかったであろう。だからこそ、慚愧の念をもって公然と妻帯する僧侶も現れてくる。
江戸時代には、寺院僧侶は厳しく統制された。その一方で、幕府の官僚として人民の管理統制を担い、僧侶は堕落傲慢にふけり、社会の反発を招いた。
そして、それがために明治新政府の神道国教化政策により、一八七二年(明治五)
「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべきこと」と太政官布告があり、それまで僧尼令で定められた肉食妻帯の禁が解かれる。
これは国家が妻帯を認めたということではなく、国家が仏教との関わりを解く一環であったに過ぎない。しかし、これを国の意向と受け取り、妻帯に踏み切る僧侶が多く現れたのである。
僧侶の妻帯問題は、明治後期まで仏教界にとって誠に重大な問題であった。各宗宗議会で公認すべきか否かで議論紛糾したが、結局自然の成り行きに順じる方向で収束し、現在に至っているのである。
今日では、このことに何の痛痒も感じない僧侶を生む時代となっている。まさに破戒ではなく無戒の時代なのだと言えよう。
(↓よろしければ、クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

日本仏教は、そのはじめから国家仏教であり、僧侶はもとから国の庇護と規制の下に置かれた。
七五七年、『僧尼令』二十七条が制定され、僧尼の出家には官の許可を要した。試経という試験に合格すると剃髪し、受戒(四分律二五〇戒)が行われた。律蔵に規定された通り「交淫、盗み、殺人、悟りを得たと詐称する事」が重く禁ぜられ、犯すと還俗しなければならなかったのである。
この時代にもまったく破戒僧がいなかった訳ではないだろう。しかし、官僧として大戒二五〇戒を受持する制約があった。
しかし、後に天台宗では、大乗梵網経にある十重四十八軽戒をもって僧侶の受戒と見なす大乗戒壇を比叡山に建立した。これにより大戒を受持せずとも官僧として遇されることとなった。
このことが、後生の僧侶に厳正な戒律に対する意識低下を助長することになったのである。
鎌倉時代以降、官僧を脱して自由に活動する僧侶が増えて一層戒律が軽視された。
僧兵が現れて不殺生戒を犯し、「末代には妻もたぬ上人年をおうて稀にこそ聞こえし」(沙石集)と記されるように、隠れて妻帯することも特別なことではなかったであろう。だからこそ、慚愧の念をもって公然と妻帯する僧侶も現れてくる。
江戸時代には、寺院僧侶は厳しく統制された。その一方で、幕府の官僚として人民の管理統制を担い、僧侶は堕落傲慢にふけり、社会の反発を招いた。
そして、それがために明治新政府の神道国教化政策により、一八七二年(明治五)
「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべきこと」と太政官布告があり、それまで僧尼令で定められた肉食妻帯の禁が解かれる。
これは国家が妻帯を認めたということではなく、国家が仏教との関わりを解く一環であったに過ぎない。しかし、これを国の意向と受け取り、妻帯に踏み切る僧侶が多く現れたのである。
僧侶の妻帯問題は、明治後期まで仏教界にとって誠に重大な問題であった。各宗宗議会で公認すべきか否かで議論紛糾したが、結局自然の成り行きに順じる方向で収束し、現在に至っているのである。
今日では、このことに何の痛痒も感じない僧侶を生む時代となっている。まさに破戒ではなく無戒の時代なのだと言えよう。
(↓よろしければ、クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)















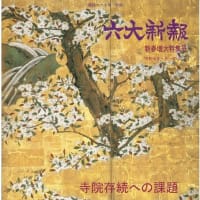









破戒?無戒?
個人的な見解や批判を書いた文章ではありません。そのような受け取り方をされたのであれば本意ではありません。
当然のことですが、自戒を込めて書いたものでもあります。仏教徒として、自己批判は必要なことではないでしょうか。自らを見つめることから仏教があり、出家の根本の戒律を犯していることを考えれば、本来この問題について看過することなく大いに議論されるべきではないでしょうか。
本山要職者には現状をふまえた僧制の改正について検討するべきことを上申いたしました。あなた様はこの問題についてどのような見解をお持ちでしょうか。是非、ご教示下さいますことをお願い申し上げます。
あなたが僧侶になるまでそして僧侶になった後も大変なご努力をされたのはこのアーカイブを紐解くと伝わってきます。
ただ肝心要な戒を破り妻帯に踏み切ったあたりの事が何処にも書かれていない。これでは説得力がないですよ。
戒定慧は仏教の根幹であることを考えれば、日本仏教なるものも意味をなさないことになります。その意味において日本仏教いかにあるべきかという議論がなされるべきではないかと考えております。
私個人についての身の振りについてはここでも何度か触れているかとは思いますが、今生での自分自身の人生の意味、役割というものを考えたときにこのような選択がよかろうと思ったとしか言いようがありません。
どなたの人生においても、理想通りに人生を歩める人はありません。期待通りに道は開けません。理想と現実の中で誰しもだじろぎ、思い通りにならない自分に、忸怩たる思いを重ねていくものなのではないでしょうか。
関心をお持ち下さりありがたいことだと思います。少しあなたのことを教えてください。どうしてこのブログを熱心にご覧下さり、なぜこの記事に強く思いを寄せコメントされたのか。仏教に何を求めておられますか。
私は単純になぜ肉食妻帯にいたったかを聞いているだけです。
よほど痛いところをつかれたのか文章に怒りを感じます。
答えにもなってません。
このブログにも仏教にも大した興味はありません。
たまたま見つけたお題が僧侶の妻帯というテーマだからコメントした次第です。
タバコを吸いながらタバコの害を話す医者。
陰ではとんでもない事をしているのに厚い顔無知な教師。
オフは平気で法に背く行為をしているのに人様を取締る警察。
そして自分の事はさておいて人の道を説く坊主。
等々
権力やそれに準ずるものに守られた偽聖職者(やそれに近いもの)が許せないだけです。
答えになっていますか?
そろそろあなたのシンパが応援の横やりコメントが入る頃ですかね。
出来ればご遠慮したいものです。
私は自分の至らなさを常に思い、事あるごとに皆様にお話しもしております。破戒のこの状態をたちまちいかになしたらよろしいのでしょうか。皆様のお知恵を拝借したいところです。
いろいろとお教え下さいまして、ありがとうございました。どうぞお元気に、お幸せにお過ごし下さい。
そもそも悟りを求めて僧侶になる人が日本にはほとんど居ないかと思います。
坊主の顔をしていない坊主が最近は増えましたね。
前述されてらっしゃる方がいってますが
欲を配すべき存在がただの一つの職業に収まっていると考えていたのですがそういう傾向もやはりあるみたいですね。お墓や寺に関して否が応でも関わるこの自国の風習とはいえ外国の宗教のように現実的に思えない理由がわかりました。神信仰を押し付けるイメージがあまりないだけましでしたが、やはり妻帯者の寺は信用できそうにないですね。
>七五七年、『僧尼令』二十七条が制定され、僧尼の出家には官の許可を要した。試経という試験に合格すると剃髪し、受戒(四分律二五〇戒)が行われた。
と言う記載がありますね。
当時は僧尼と言うのは、官の決めた身分であったかと思います。
その身分には、色々の戒律があり、それを守らなかったら還俗せねばならない決まりがあったというのは、
時の政府 官が僧尼を官の推し進める宗教(仏教)の伝道師と思ってたからなのではないでしょうか?
つまり官は、国家の事業として仏教を広めていたので、
仏教の伝道師僧尼が世間からうしろ指を指されるようなことは、絶対に避けたいと言う気持から、僧侶にいろいろな戒律を定めたのだと思います。
(そんなことがあったら官の威信にかかわることですから)
だからこれらの戒律は、信仰上に必要なものであるからではなく、官の体面を傷つける恐れを排除するためであったと思います。
あれ程仏教にご熱心であられた聖武天皇が、皇后と生涯を共にされたのも、妻帯が信仰に関わるものではないと思っておられたからだと思います。
戒律があるから、破壊と言う言葉も出来るのであって、戒律がないところに破壊と言う言葉はありえませんし。
お釈迦様も、苦行は悟りの因にあらずと仰ったそうですし、肉食妻帯したからと言って、貞節を守り、肉食でも命をつなぐための食事で、節度を守ったものであるなら、それらをどうして禁じなければならないのでしょう。
宗教と言うのは生き方を教えてくださるものであると言うことを考えたなら、
宗祖の教えを奉じながらも、普通人と同じ生活をしておられる方が、よほど世情が分かった素晴らしい指導が出来られるのではないでしょうか?
私の家は浄土真宗ですが、宗祖親鸞上人はそのお師匠さんの法然上人から、妻帯したほうが悟りに届き易い者は妻帯すればよいし、妻帯しないほうが悟りに近づき易い者はしないほうが良いと言われ、
貴方は妻帯したほうが良かろうと、妻帯を薦められて、当時としては珍しい妻帯の僧侶として、一生を添い遂げられたと聞いています。
ですから、今のお坊さんが妻帯しておられようと妻帯しておられまいと、そんなことで,宗教家としての値打ちは上がりもしなければ下がりもしないと、私は思っています。
宗教家の絶対に必要な条件は、本当の悟りを得ておられるかどうかであるのですから。