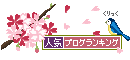はい、というわけで本日2本目のブログはちょっぴり問題提起を。
昨日レッスンに行った学校で、レッスン後に音楽室をお借りしまして。
するってーと、琴なんか置いてありまして。
「わー、先生!お琴もやるんですね?!」
「そうなんですよー。私が教えてるんですよー。と言ってもさくらさくらくらいですけど。教えなきゃいけなくて、、、自分が習ったことないモノも教えなきゃならないから、大変ですよ!」
「わー、そうですよねぇ、、、」
「私は初任の学校に師範の免許持ってた先生がたまたまいたんで、ランチご馳走するからーって教えてもらえたんですけど。」
「そういう人がいなかったら大変ですねー」
「なんかお琴の方に怒られそうで。適当なこと教えてんじゃないよって。」
ってな会話をですねしたわけです。
でも、これってよーく考えるといろんな問題はらんでますよね?!
楽器って、そのものに「出会う」ってだけでももちろん価値はあると思うけど、「どう」出会うかも大事な気もします。
学校でやるのはあくまで入口だから、全然やったことない人が教えても良い、、、かもしれません。
でも、例えば自分の身近に置き換えて、、、それがトランペットだとして、
やったことない人が教えてたら、オイオイ!!と思う気もします。
さりとて、現状はといえば、吹奏楽部の顧問の先生なんだと、楽器の専門の先生じゃない先生も多いんじゃないかな?!
その人はどうよ?となって、専門じゃないとダメ!となれば、もう成り立ちませんよね。
課外活動は良いではないか?!
そうかもしれません。
授業で取り上げるもの、、、
こういうものについて、全然扱い知らないってのだったら、ほんと辛いでしょうし、習う方も信じてたのにあとから全然デタラメとかツライですよね。
こういうのって、研修ないのかなー??
昨日の先生の話っぷりだと、研修とかなさそうてすよね?地域によるのかなー??
んで、じゃあ全部ちゃんとできるように!ってなったらそりゃーそれでツライ。そんなにいろいろできんわい!!
音楽の先生になるにも、教員養成課程からくる人と、いわゆる音大出て教員免許を取る人とじゃー、これまた用意されてる講座なんかにも微妙に違いが。
広く浅く、「教えるための知識」などを身につけるか、狭く深く、「自分自身の技能」を高めるか。
どちらもいい面もあるし、足りない面もあるよね。
先生になるんだとして、
できたら大学では、薄っすらとでもいいから、いろんな楽器の専門家から扱いや奏法やその音色感なんかを習っておきたい。
弦、木管、金管、打楽器、和楽器、そしてリコーダーやなんかも。
音大で教員免許取って先生になる人は、これらを学んでくるシステム自体が足りないかもしれない。
ん?
もしかして今は和楽器とかも単位として必須??
それって、ちょっと上の世代の人だけの問題??
そこ、分からんけど、
でね、ほらほら、あの無駄とも思える、「教員免許の更新システム」。こういうやつの変化形で、授業で必要な技能なんかを短期間、大学の授業の聴講なんかで補充できたりなんかするとよくなーい??
現状も教員免許の更新には1単位6000円とか取られる訳じゃん?
そんな感じでちょいと有料でもいいから、知りたいことを知りたいときに!!っていうフレキシブルな環境があったら、先生のストレスも減るだろうし、習う方もありがたいし。
良くね??
何か、教育が良くなるような方法こそ、考えるべきだよね。
先生の質の低下→先生の質を良くするために→免許更新、、、って安直だよね。
習ってないようなことを、文科省の役人が思い付き(失礼!)でこれも良いねみたいな感じで無責任に入れちゃったり、やっと波に乗ってきたら、やめちゃったり、一貫性とか、何のためにかとかが決まってないからいかんのじゃよ。
給料安いし、労働時間長いし、余計な仕事多すぎるし。
そりゃー大変だよぉ。
親も口出ししまくるか、丸投げかどっちかの人が多いみたちだしね。
それば!!また!!ちょっとした問題提起をしてみましたー。
昨日レッスンに行った学校で、レッスン後に音楽室をお借りしまして。
するってーと、琴なんか置いてありまして。
「わー、先生!お琴もやるんですね?!」
「そうなんですよー。私が教えてるんですよー。と言ってもさくらさくらくらいですけど。教えなきゃいけなくて、、、自分が習ったことないモノも教えなきゃならないから、大変ですよ!」
「わー、そうですよねぇ、、、」
「私は初任の学校に師範の免許持ってた先生がたまたまいたんで、ランチご馳走するからーって教えてもらえたんですけど。」
「そういう人がいなかったら大変ですねー」
「なんかお琴の方に怒られそうで。適当なこと教えてんじゃないよって。」
ってな会話をですねしたわけです。
でも、これってよーく考えるといろんな問題はらんでますよね?!
楽器って、そのものに「出会う」ってだけでももちろん価値はあると思うけど、「どう」出会うかも大事な気もします。
学校でやるのはあくまで入口だから、全然やったことない人が教えても良い、、、かもしれません。
でも、例えば自分の身近に置き換えて、、、それがトランペットだとして、
やったことない人が教えてたら、オイオイ!!と思う気もします。
さりとて、現状はといえば、吹奏楽部の顧問の先生なんだと、楽器の専門の先生じゃない先生も多いんじゃないかな?!
その人はどうよ?となって、専門じゃないとダメ!となれば、もう成り立ちませんよね。
課外活動は良いではないか?!
そうかもしれません。
授業で取り上げるもの、、、
こういうものについて、全然扱い知らないってのだったら、ほんと辛いでしょうし、習う方も信じてたのにあとから全然デタラメとかツライですよね。
こういうのって、研修ないのかなー??
昨日の先生の話っぷりだと、研修とかなさそうてすよね?地域によるのかなー??
んで、じゃあ全部ちゃんとできるように!ってなったらそりゃーそれでツライ。そんなにいろいろできんわい!!
音楽の先生になるにも、教員養成課程からくる人と、いわゆる音大出て教員免許を取る人とじゃー、これまた用意されてる講座なんかにも微妙に違いが。
広く浅く、「教えるための知識」などを身につけるか、狭く深く、「自分自身の技能」を高めるか。
どちらもいい面もあるし、足りない面もあるよね。
先生になるんだとして、
できたら大学では、薄っすらとでもいいから、いろんな楽器の専門家から扱いや奏法やその音色感なんかを習っておきたい。
弦、木管、金管、打楽器、和楽器、そしてリコーダーやなんかも。
音大で教員免許取って先生になる人は、これらを学んでくるシステム自体が足りないかもしれない。
ん?
もしかして今は和楽器とかも単位として必須??
それって、ちょっと上の世代の人だけの問題??
そこ、分からんけど、
でね、ほらほら、あの無駄とも思える、「教員免許の更新システム」。こういうやつの変化形で、授業で必要な技能なんかを短期間、大学の授業の聴講なんかで補充できたりなんかするとよくなーい??
現状も教員免許の更新には1単位6000円とか取られる訳じゃん?
そんな感じでちょいと有料でもいいから、知りたいことを知りたいときに!!っていうフレキシブルな環境があったら、先生のストレスも減るだろうし、習う方もありがたいし。
良くね??
何か、教育が良くなるような方法こそ、考えるべきだよね。
先生の質の低下→先生の質を良くするために→免許更新、、、って安直だよね。
習ってないようなことを、文科省の役人が思い付き(失礼!)でこれも良いねみたいな感じで無責任に入れちゃったり、やっと波に乗ってきたら、やめちゃったり、一貫性とか、何のためにかとかが決まってないからいかんのじゃよ。
給料安いし、労働時間長いし、余計な仕事多すぎるし。
そりゃー大変だよぉ。
親も口出ししまくるか、丸投げかどっちかの人が多いみたちだしね。
それば!!また!!ちょっとした問題提起をしてみましたー。