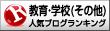「神ではなく」7月4日
反橋希美記者が、『心の中の「佐々木さん」』という表題でコラムを書かれていました。その中で反橋氏は、元東レ取締役佐々木常夫氏の思い出について書き、『一番印象に残ったのは「育児は自己実現の感触を得にくいもの」という一言だった』と述べられています。
その理由について反橋氏は、『そう言ってしまってもいいんだと思った。当時の私は「母たるもの育児に喜びを感じねば」という重圧にがんじがらめだった』と語られています。私は育児の経験がないうえに、女性ではないので「母親」というものに対する重圧を十分には理解できていませんが、我が国にはまだそうした、あるべき母親像、母性神話のようなものが根深くあることは理解しているつもりです。
同じようなことが、教員についても言えるのではないでしょうか。教員は授業や子供の指導に喜びを感じるべき、という考え方が、教員にとって重荷となっている現状があるのではないかということです。
教え子の成長を実感できたとき、確かに喜びを感じます。熱量の低い教員であった私にもそうした瞬間はありました。しかし、他の仕事でもそうでしょうが、喜びややりがい、充実感や達成感を感じる瞬間があると同時に、その何倍ものボリュームで、辛い、嫌だ、腹が立つ、怒りすら覚えるといったマイナスの感情に支配されることがあるのも事実です。それも、校長や副校長といった上司、同僚の教員、保護者、教委の職員といった対大人関係ではなく、教え子と向き合っているときにも、そうしたマイナスの感情に支配されるときがあったのです。
思い出は過去を美化する、ということがあります。私も教職を離れ、過去の教え子たちとのあれこれを思い出すとき、「美しい思い出」が多くなっていますが、じっくりと当時のことを思い返すと、私は不機嫌で、その感情のために意地悪な教員であった場面が浮かび上がってきます。
先程、私は熱量の低い教員だったと書きました。正直、マイナスの感情もあまり強くない方だったのかもしれません。また、教員聖職論とは早くから距離を置いており、子供の喜び=自分の喜びというような感覚自体が少なかったと思います。飾らずに言えば、サラリーマン教員、デモシカ教員的な面が強かったということかもしれません。それでも、負の感情と縁を切ることはできなかったのです。
ですから、私とは違うタイプ、教職を天職と考え、教員は子供の成長を最大の喜びとすべきという固定概念に囚われ、自らを理想の教師像に近づけようと必死に努力し続けていた教員、彼らは、反橋氏と同じように、理想と現実の食い違いに苦しんでいたのではないかと想像するのです。
教員専門職論の立場をとる私は、現役の若い教員に、「子供との触れ合いに喜びを感じるのが理想の教員」などという迷信は捨てなさいと言いたいです。必要なのは、子供を成長させる責任感と、その責任感に裏打ちされた専門職としての研鑚だと。