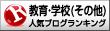「教えないこと」12月28日
茶道裏千家元家元千宋室氏が、インタビューに答えていました。千氏は、軍隊で特攻部隊に属していたそうです。その軍隊経験に基づいた一言が印象に残りました。『この家を継ぐ者は、千家の菩提寺の大徳寺で禅の修行をしなければならない。僧堂に入ったら、軍隊の方が楽でした。軍隊は何をすべきか殴ってでも教えてくれます。お寺では、自分の修行なので誰も教えてくれない』というものです。
重い真理が含まれているように思います。一般的に世間の多くの人には、無理矢理教え込まれることを「苦行」とし、自由に考えてよいと言われる方が楽だという思い込みがあります。学校においても同じです。強制的に教え込むことは悪であり、教育的ではないという考え方です。そして、それが、「教員は教えすぎてはいけない」「子供に自由に考えさせる教育が真の教育だ」という発想につながり、考えるために必要な最低限の知識すらもってはいない子供に対して、「自由に考えなさい」と指示するという残酷な仕打ちを強いていながら、それを自覚していない教員を生みだしてしまったのです。
千氏は、長い月日継続されてきた名門の跡継ぎとして、子供時代からその重圧と格闘し、特攻部隊という極限状態の中で、自分の生について考え続けていたことでしょう。しかもこのとき、既に20代の半ばという年齢に達していました。それでもなおかつ、「教えられない」ことに苦しんでいたのです。千氏に比ぶべくもない幼い子供たちにとって、「教えられないこと」が、どれくらい厳しいことか、少し考えれば分かることです。
ですから、教員は、強制的に教え込むことを躊躇ってはいけないと思います。誤解のないように補足しておきますが、「殴ってでも叩き込め」とか「罰や褒美や競争で教え込め」と言っているのではありません。それらは方法論にすぎません。そうではなく、教育の基本的な考え方として、考える上で欠かせない知識を与えたり、良き市民として必要な習慣を身につけさせたりするのは教育者の使命であり、自主性を隠れ蓑に、それらを教える努力を怠ってはならないということです。難しいのは、教えすぎてもいけないという点です。
教育の専門家として教員に求められるのは、教えることと考えさせることを見極める能力と、そのことを子供の内発的な興味に基づいてどのように獲得させるかという技術なのです。ヘレンケラーの恩師であるサリバンさんは、ものには固有の名前があるということはどうしても教えなくてはならないと考え、水に触らせ掌にwaterと書くという方法を工夫したのです。自主性や主体性の陰に逃げ込んではいけないのです。
茶道裏千家元家元千宋室氏が、インタビューに答えていました。千氏は、軍隊で特攻部隊に属していたそうです。その軍隊経験に基づいた一言が印象に残りました。『この家を継ぐ者は、千家の菩提寺の大徳寺で禅の修行をしなければならない。僧堂に入ったら、軍隊の方が楽でした。軍隊は何をすべきか殴ってでも教えてくれます。お寺では、自分の修行なので誰も教えてくれない』というものです。
重い真理が含まれているように思います。一般的に世間の多くの人には、無理矢理教え込まれることを「苦行」とし、自由に考えてよいと言われる方が楽だという思い込みがあります。学校においても同じです。強制的に教え込むことは悪であり、教育的ではないという考え方です。そして、それが、「教員は教えすぎてはいけない」「子供に自由に考えさせる教育が真の教育だ」という発想につながり、考えるために必要な最低限の知識すらもってはいない子供に対して、「自由に考えなさい」と指示するという残酷な仕打ちを強いていながら、それを自覚していない教員を生みだしてしまったのです。
千氏は、長い月日継続されてきた名門の跡継ぎとして、子供時代からその重圧と格闘し、特攻部隊という極限状態の中で、自分の生について考え続けていたことでしょう。しかもこのとき、既に20代の半ばという年齢に達していました。それでもなおかつ、「教えられない」ことに苦しんでいたのです。千氏に比ぶべくもない幼い子供たちにとって、「教えられないこと」が、どれくらい厳しいことか、少し考えれば分かることです。
ですから、教員は、強制的に教え込むことを躊躇ってはいけないと思います。誤解のないように補足しておきますが、「殴ってでも叩き込め」とか「罰や褒美や競争で教え込め」と言っているのではありません。それらは方法論にすぎません。そうではなく、教育の基本的な考え方として、考える上で欠かせない知識を与えたり、良き市民として必要な習慣を身につけさせたりするのは教育者の使命であり、自主性を隠れ蓑に、それらを教える努力を怠ってはならないということです。難しいのは、教えすぎてもいけないという点です。
教育の専門家として教員に求められるのは、教えることと考えさせることを見極める能力と、そのことを子供の内発的な興味に基づいてどのように獲得させるかという技術なのです。ヘレンケラーの恩師であるサリバンさんは、ものには固有の名前があるということはどうしても教えなくてはならないと考え、水に触らせ掌にwaterと書くという方法を工夫したのです。自主性や主体性の陰に逃げ込んではいけないのです。