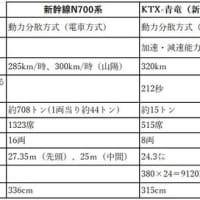天気予報をする人は2種類の人がいるようです。
その一つは気象予報士、もう一つは二十四節季(気)解説士が本業で、副業で気象予報士をやっている人。
二十四節季(気)解説士は聞きなれない言葉かもしれませんが、従来から居ます。この人たちは二十四節季(気)が来ると、例えばそれが「大雪(たいせつ)」なら
「今日は二十四節季(気)の一つ「大雪」で、「山岳だけでなく、平野にも降雪のある時節」と言われているように、暦通りに栃木県では今年初めて雪が降りました。」と判で押したように同じことを言います。特に「暦通り」という言葉が好きなようです。「暦が外れた」とは絶対に言いません。それは、日本のどこからか二十四節季(気)に当てはまる気象の地域を捜して来るからです。
二十四節季(気)解説士は、みんな同じようなことを言うので、どこかで養成しているのかもしれません。 私の推測では、気象予報では老舗の日本**協会当たりに秘密組織がありそうな気がする。ここには二十四節季(気)の好きな年寄も沢山居ると思います。
ところで、12月初旬に平年より早く雪が降り、しかも死者も出るような大雪になって、その大雪のピークを過ぎた12月7日に、ラジオで二十四節季(気)解説士(副業が気象予報士)が「今日12月7日は二十四節季(気)の一つ、大雪(たいせつ)で、暦通り栃木では今年初めての降雪になっています」と言っていました。
12月初旬の北陸や四国では既に大雪になって死者も出ているのに、わざわざ関東北部の降雪を持ち出して、「暦通り」と言うことはない!
前にも書きましたが、俳句をする人や一般人が暦の話をするのはどうってことはありませんが、天気予報をする人が、毎年固定している暦が当たった!当たった!と言うのは自己否定だと思います。職業人としての自覚が欠落しています。
2014.12.11