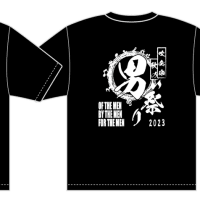吉祥寺シアターで、青年団の公演「眠れない夜なんてない」を観劇する。
昭和から平成に変わろうとしている時、マレーシアの日本人用リゾート地を舞台に描かれた作品。
定年を迎え完全に移住してきた老夫婦と、それを尋ねてくる娘たち。定年後の住処を探しに下見に来た夫婦。短期滞在でリゾートを満喫しようとしている若めの夫婦、娘と二人で暮らしている初老の男……。
平田オリザ演出なので、声もはらないし、セリフのリズム感も演劇チックではない。間違っても踊り出したりはしない。なんでもないやりとり、ごく自然な会話のやりとりが積み重ねられていくうちに、登場人物それぞれが抱える事情や屈託があきらかになっていき、人の居場所のふたしかさや、人間関係のもろさなどをじわじわと感じさせられる。
演劇は表現を見るという受け身の行為ではなく、自己を相対化する行為だ……、的な文章を評論の演習で読んだ記憶がある。
青年団のお芝居は、開演前から必ず舞台に誰かがいて、ふつうに本を読んだり片付けしたりしてる。もう一人の人が入ってきて軽く会話もする。
これも本編の芝居のうちかなと思って物販で台本を買ってみると、開場時間の段階から、舞台でこうこうするようにとの指示がある。もはや開場時間が開演に近い。そうか、「男祭り」で開演の前に、教員バンドで15分演奏してしまったのもOKではないか。
ディズニーランドは、舞浜から入場ゲートの間にもすでにちょっとした趣向が凝らされているのとも本質は似ているかもしれない。ディズニーランドと青年団とでは、そのベクトルの量は似ていて向きは反対だ。
そして芝居が終わったあと、実は向きも同じなのかもしれないとも思う。
日常を極力そのまま描こうとするかのように見えたかの芝居は、見ている人をいつのまにか非日常へ連れて行く。日常の自分とまったく異なる方向にいる自分を感じさせてくれるという意味で。
超高級料亭の出汁みたいな味わいといえるかもしれない。
一口すすって、味薄くない? と一瞬感じ、いや、ちがう、すごい深い! 何これ? と感じるような。
料理本に出ている一番出汁のひき方なんて、絶対もったいなくてできるわけないじゃん、という日常を過ごしているのに、じわじわと非日常にカラダを侵食されていくような感覚。
芝居がはじまった瞬間に、いきなりステーキを口の中にほおりこんでくるようなお芝居もあるけど、青年団はまさに料亭の味わいだ。とすると、埼玉芸術劇場でやってるシェークスピアはフレンチ、キャラメルボックスは洋食屋、梅棒は得たいのしれないアジアン、歌舞伎は高級天ぷら……、みたいなものか。
食事処にもピンからキリまであるように、お芝居にもあるが、食事のピンに比べたらお芝居は安い。
静かな演劇の最高峰である青年団は4000円。藤原竜也の出るフレンチの最高峰も1万円ぐらいなのだから。もういっかい食べてみようかしら。
昭和から平成に変わろうとしている時、マレーシアの日本人用リゾート地を舞台に描かれた作品。
定年を迎え完全に移住してきた老夫婦と、それを尋ねてくる娘たち。定年後の住処を探しに下見に来た夫婦。短期滞在でリゾートを満喫しようとしている若めの夫婦、娘と二人で暮らしている初老の男……。
平田オリザ演出なので、声もはらないし、セリフのリズム感も演劇チックではない。間違っても踊り出したりはしない。なんでもないやりとり、ごく自然な会話のやりとりが積み重ねられていくうちに、登場人物それぞれが抱える事情や屈託があきらかになっていき、人の居場所のふたしかさや、人間関係のもろさなどをじわじわと感じさせられる。
演劇は表現を見るという受け身の行為ではなく、自己を相対化する行為だ……、的な文章を評論の演習で読んだ記憶がある。
青年団のお芝居は、開演前から必ず舞台に誰かがいて、ふつうに本を読んだり片付けしたりしてる。もう一人の人が入ってきて軽く会話もする。
これも本編の芝居のうちかなと思って物販で台本を買ってみると、開場時間の段階から、舞台でこうこうするようにとの指示がある。もはや開場時間が開演に近い。そうか、「男祭り」で開演の前に、教員バンドで15分演奏してしまったのもOKではないか。
ディズニーランドは、舞浜から入場ゲートの間にもすでにちょっとした趣向が凝らされているのとも本質は似ているかもしれない。ディズニーランドと青年団とでは、そのベクトルの量は似ていて向きは反対だ。
そして芝居が終わったあと、実は向きも同じなのかもしれないとも思う。
日常を極力そのまま描こうとするかのように見えたかの芝居は、見ている人をいつのまにか非日常へ連れて行く。日常の自分とまったく異なる方向にいる自分を感じさせてくれるという意味で。
超高級料亭の出汁みたいな味わいといえるかもしれない。
一口すすって、味薄くない? と一瞬感じ、いや、ちがう、すごい深い! 何これ? と感じるような。
料理本に出ている一番出汁のひき方なんて、絶対もったいなくてできるわけないじゃん、という日常を過ごしているのに、じわじわと非日常にカラダを侵食されていくような感覚。
芝居がはじまった瞬間に、いきなりステーキを口の中にほおりこんでくるようなお芝居もあるけど、青年団はまさに料亭の味わいだ。とすると、埼玉芸術劇場でやってるシェークスピアはフレンチ、キャラメルボックスは洋食屋、梅棒は得たいのしれないアジアン、歌舞伎は高級天ぷら……、みたいなものか。
食事処にもピンからキリまであるように、お芝居にもあるが、食事のピンに比べたらお芝居は安い。
静かな演劇の最高峰である青年団は4000円。藤原竜也の出るフレンチの最高峰も1万円ぐらいなのだから。もういっかい食べてみようかしら。