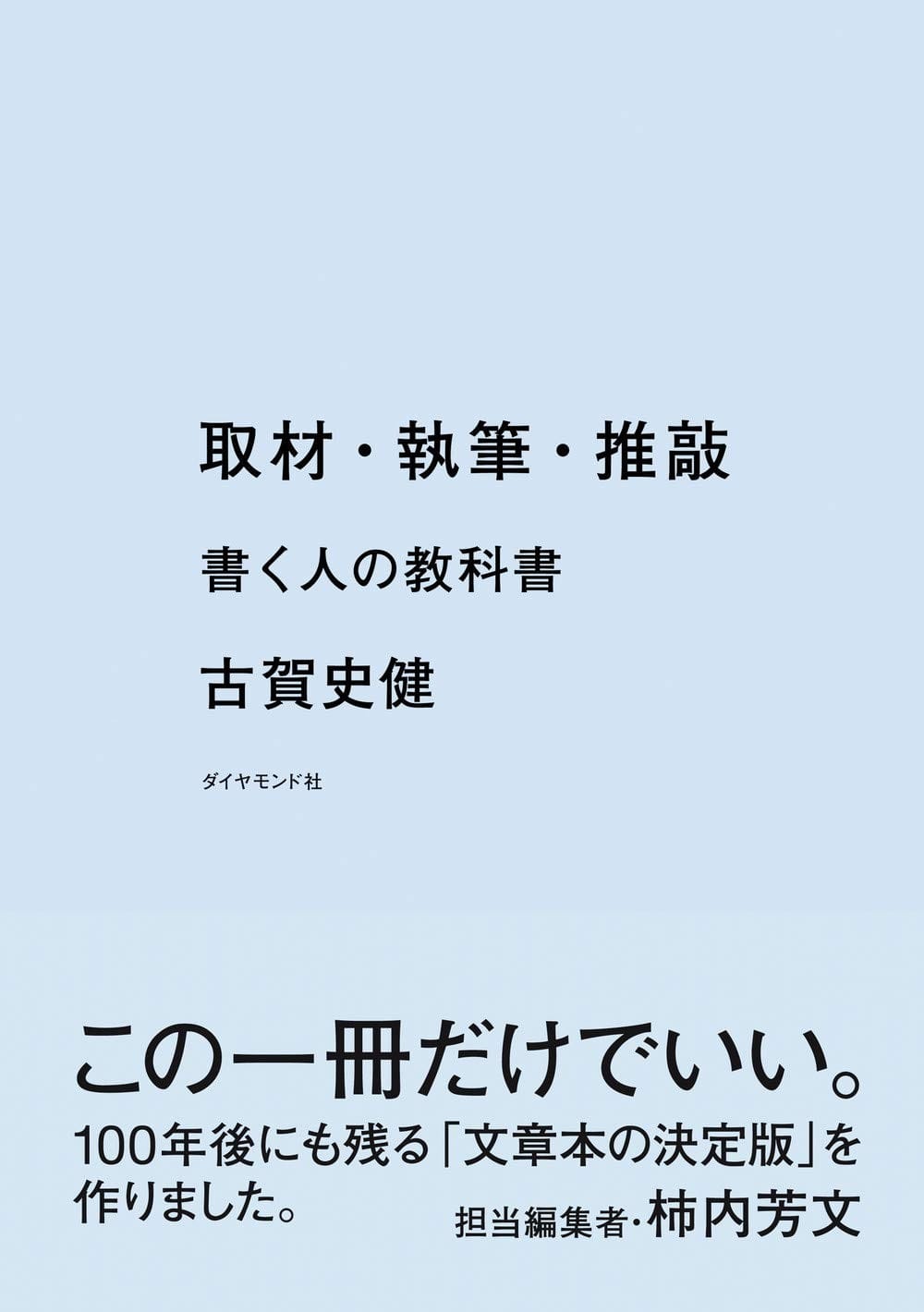
プロフェッショナルな文章の書き方を勉強したいと思って購入した、最近話題の書である。著者は「嫌われる勇気」の共著者だ。著者がそうとう気合を入れて3年かかって書いた本で、476ページあって内容は盛りだくさんであるが、文章は平易で読みやすかった。どれだけ頭に入るだろうかという不安はあるが、記憶をサポートするために、ここにこうしてノートとしてまとめておきたい。
[ガイダンス]
・著者は、書く人(ライター)である以前に、つくる人(クリエイター)であるとの自己認識を持っている。ライターは、ただ文章を書いているのではない。書くことを通じで、コンテンツをつくっている。コンテンツとは、「エンターテイン(お客さんをたのしませること)を目的につくられたもの」としている。
・本を作るうえで、編集者がいる。「誰が、なにを、どう語るか」を編集するのが編集者である。一方、原稿そのものを編集していくのは、作家であり、ライターである。ライターは、編集という武器を手に入れ、「書く人」から「つくる人」にならなければならない。
・価値あるコンテンツを生まれるのは、「情報の希少性」「課題の鏡面性(自分ごととして感じられること)」「構造の頑強性(精緻なロジックによる構成力)」の3つが揃ったときである。
[取材]
・悪文とは、技術的に未熟な文章を指すのではないし、そこに投じられた時間も関係ない。ただただ「雑に書かれた文章」はすべて悪文である。悪文に厳しい読者になれば、自分の書く文章に対しても厳しくなれる。
・悪文と同じく、「嫌いな文章」も大切に読んでほしい。ある文章について、自分が抱いた嫌悪感をことばにしていく。自分の「嫌い」に向き合い、掘り進めていくと、私という人間が見えてくる。わたしがどうありたいのかが、理解できる。
・取材で能動的に聴くことができるのは、①相手の話がおもしろい、②相手のことが大好きである、③自分にとってものすごく大切な話をしている、の条件の2つ以上を満たしているときである。①はこちらでコントロールできない。一方、②③は、自分次第でどうにでもコントロール可能な要素だ。そのために、取材前に入念に下調べをする。
・質問力をつけるのには、接続詞「つなぎことば」を使うことだ。接続詞を置くと、「でも、○○じゃないですか」「ということは、○○なのですか?」と質問が出てくる。ほかにも、「そうすると」「だとしたら」「とはいえ」「それにしても」などと言うと、いい質問につながっていく。
・プロのライターでも筆が乗っていないと、わかりにくい文章を書くことがある。わかりにくい文章とは、書き手自身が「わかっていない」文章である。
・優秀なライターたちはみな、「ほんとうに言いたいことなど、なにもない」と語る。なにかを書くことは好きかもしれないが、自己表現欲や創作欲、自己顕示欲はほとんど持っていない。ではなぜライターは書くのかというと、「言いたいこと」を持たなかったのに、取材を通じて「どうしても伝えたいこと」を手にしてしまうからだという。
[執筆]
・ライターの職業的役割、機能は、「録音機」「拡声器」「翻訳機」である。世のなかには、声のおおきな人と、声のちいさな人がいる。研究者、経営者、社会活動家、アスリート、政治家、アーティスト、そして市井の人びと。それぞれの専門領域ではすばらしい活動を続けながらも、ただ「声がちいさい=発信力に乏しい」というだけで世間に知られていなかったり、誤解されていたりする人びとがいる。もしも遠くにまで届けられれば、世界を変えるかもしれない大事な声が、そこにとどまっている。ライターは、そんな声に寄り添う「拡声器」だ。
・論理的文章は、上から主張、理由、事実の三層構造になっていて、下が上を支えている。この事実のパートは、データ、数値、実例、類例を論拠とする。誰もが膝を打つような類例ー見事な「たとえ」ーを論拠にできてこそ、ライターである。
・日本人に馴染み深い作文構造は起承転結で、展開のおもしろさがある。一方、アメリカの教育現場で叩き込まれる小論文の構造は、「序論」「本論」「結論」の三部構成で、論理的である。著者が提案するのは、それぞれのいいとこ取りである、起転承結である。価値あるコンテンツの条件として「課題の鏡面性」=「課題共有」があった。読者との「課題共有」のために、「起転承結」の「転」が使える。世間で常識とされていること(起)を、いきなりひっくり返してみずからの主張を述べる(転)。驚いた読者は、「どういうことか、説明してみろ」と身を乗り出して聴く姿勢ができる。課題はここで、共有される。
・原稿の構成を考えるにあたって指針になるのが、ガイダンスで述べられたコンテンツの三角形「情報の希少性」「課題の鏡面性」「構造の頑強性」である。それによって、集められた素材から原稿の構成を選択できる。
・本の構成において、章立てを設計するにあたって著者が提案しているのが、百貨店の設計である。百貨店の各フロアには「コンテンツ」が配置されている。本とはおおきな建造物であり、コンテンツの百貨店である。具体的に並べていく。1F(化粧品、ハイブランド)=世界観の提示=はじめに・第1章。2F(レディース)=本論=第2章。3F(カジュアル、ユニセックス)=具体の展開=第3章。4F(メンズ、フォーマル)=視点の転換=第4章。5F(専門店、インテリア)=専門的議論=第5章。6F(レストラン)=反芻と達成=第6章。屋上=絶景の提供=あとがき。
・本は、立ち読みを入口とするメディアだ。導入で「おもしろくない」と判定されれば、そこで試合終了である。だから、何かを論じる本は、導入ー上記の第1章から第2章までーが勝負である。
・本は雑誌と違って、賞味期限の長い、この先何年、何十年と読まれる、普遍的なコンテンツをつくらなければならない。多くの人は、これから先、10年後の読者をイメージして、どんなコンテンツをつくるべきかを考える。しかし、未来のことなんてわかるわけがないのだ。見るべきは「未来」ではなく「過去」である。古典とされる作品群は、先駆的だったわけでも進歩的だったわけでもなく、ただただ「普遍的」だったのだ。著者は、2013年に上梓した「嫌われる勇気」の執筆にあたって、これを古典にしたいと考えた。具体的にどうしたかというと、100年前の読者をイメージしたのだ。だからこの本には、コンピューターもインターネットもテレビでさえも登場しない。そして、世界中で読まれることを想定して、日本社会特有の悩み、受験や就活、儒教的な価値観などはあえて避けた。その結果というわけではないものの、同書は現在、世界数十ヵ国で翻訳されて読まれている。人間の根源的な悩みを探った、普遍性を意識したコンテンツだったのである。
・どのような文章が、原稿のエンターテインを生み出し、読者の満足につながるのかという文章表現レベルに特化して考えると、ポイントは文章の「リズム」「レトリック(とくに比喩)」「ストーリー」である。
・文章の「リズム」を自習するのに、音読するのはいちばんの自学習慣であるが、自分の書いた文章については客観性が保ちにくい。そこで、筆写が推奨される。「自分が気持ちいいと思う文章」を読むだけでなく、ひと文字ずつ正確に筆写していく。書き写すことで、読点の位置に驚いたり、語尾や文末表現のゆたかさに驚くだろう。
・小説や映画の世界であれば、「起伏」も重要であるが、論文的ストーリーの鍵は、導入から結末までの「距離」である。その展開の妙にこそ、論文的ストーリーのおもしろさが宿る。結末からなるべく遠いところ、本論とはおよそ無関係に思えるようなところから、語りはじめるのである。
[推敲]
・他人が書いた文章については、客観的に読むことができる。しかし、自分が書いた文章は「客観」がむずかしい。自分の原稿を読み返すとき、大切なのは距離の置き方である。距離のつくり方には、「時間的な距離」「物理的な距離」「精神的な距離」の3つがある。
・時間的な距離の取り方は、書き終えた原稿をひと晩寝かせて、翌日にフレッシュな目とあたまでもう一度読み返す。物理的な距離の取り方は、原稿の見た目を変えることだ。たとえば著者は、原稿をスクリブナーというワープロソフトを使って「横書き」の「明朝体」で書いている。そして、ざっと読み返す際には、ワードに書き出して「縦書き」の「ゴシック体」で表示させる。そして最終的には紙にプリントアウトし、赤ペンでチェックする。精神的な距離の取り方は、推敲前の原稿を、編集者や家族、友だちに送って読んでもらい、もう自分ひとりのものじゃないという既成事実をつくることで、精神的な距離を生んでいく。
・原稿について迷ったら捨てる。あんなに苦労して書いたのに、あれだけ調べてまわったのに、あんなに時間をかけて考えたのに、と考えてしまうが、読者はあなたの「苦労」を読むのではない。読者はただ「おもしろいコンテンツ」を読みたいのだ。
・立ち位置として、実際に書くことをしない編集者はロマンチストであり、それを書くライターリアリストであるべきだ。編集者とは無責任な大ボラ吹きであり、ライターは嘘を禁じられた人間だ。そんな両者が手を結ぶからこそ、いいコンテンツが生まれるのだ。
・推敲は、どこまで行けば終わるのか。それは、原稿から「わたし」の跡が消えたとき、「最初からこのかたちで存在していたとしか思えない文章」になったときだ。苦しんで書いた跡、迷いながら書いた跡、自信のないまま書いた跡、強引につないだ跡、いかにも自分っぽい手癖の跡などがすべて消え、むしろ「これ、ほんとにおれが書いたんだっけ?」と思える姿になったとき、ようやく推敲は終わる。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます