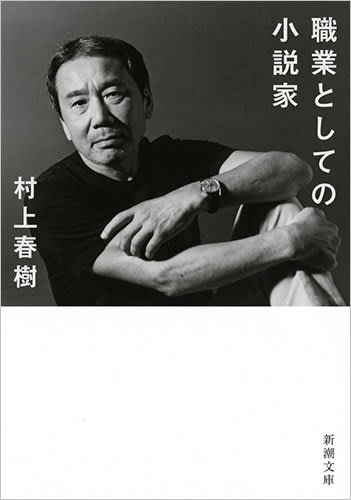
同時代を生きる稀代の小説家、村上春樹が自らの小説作成方法を明かした貴重な書だと思う。小説を書くときに彼の頭の中では何が起きているのかをくわしく教えてくれている。それは次のようである。
小説を書くのはそんなに難しいことではないが、小説を長く書き続けていくことは至難の業だという。それは、普通の人間にはまずできないことで、ある種の「資格」のようなものが求められる。それはもともと備わっている人もいれば、後天的に苦労して身につける人もいる。(だれでも人生でなにか特別な経験をしているから、それをネタに一つや二つくらいは小説が書けそうだが、小説を何本も書き続けるとなるとネタ切れして書けなくなってしまうだろうことは容易に想像される。)
小説を書くというのは効率の悪い作業で、それは「たとえば」を繰り返す作業である。一つ個人的なテーマがあったとすると、それを別の文脈に置き換えて、「それはね、たとえばこういうことなんですよ」と延々と続けていくことだ。最初のテーマがすんなりと明確に知的に言語化できない、そういう回りくどいところにこそ真実・真理が潜んでいると小説家は考える。
1978年4月のある晴れた日の午後、大好きなヤクルトの広島戦の野球を神宮球場で見ていた時、突然啓示のように何の脈絡・根拠もなく「そうだ、僕にも小説が書けるかもしれない」と思ったことが、村上が小説家になろうとしたきっかけである。それで最初に「風の歌を聴け」を書いたが、そのときはうまくかけずに満足もできなかったと述べている。
毎日朝早く机の前に座り、「さお、これから何を書こうか」と考えを巡らせる瞬間は本当に幸福である。ものを書くことを苦痛だと感じたことは一度もない。小説が書けなくて苦労したという経験もない。
毎年、ノーベル文学賞受賞を期待されている村上だが、2016年度ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランについてはその受賞前から、自己革新力を具えたクリエーターだと評価する。
どういう小説を書きたいか、その概略は最初からかなりはっきりいていた。今はまだうまく書けないけれど、先になって実力がついたら書きたい小説のあるべき姿が頭の中にあった。
小説家になるために重要な訓練なり習慣としては、たくさん本を読むことで小説はどういう成り立ちなのか基本から体感として理解すること、そして自分が目にする事物や事象をその是非や価値を判断せずに子細に観察する習慣をつけること。そうした観察の結果、頭の中には大きなキャビネットが備え付けられていて、その一つ一つの抽斗の中には様々な記憶が情報として詰まっている。小説を書きながら、必要に応じてこれと思う抽斗を開け、中にあるマテリアルを取り出し、それを物語の一部として使用する。
小説を書く上で心がけたのは、「説明しない」ということ。(私も村上の小説を読んで、なんでもかんでも説明をしない、謎を謎としてそのまま残しておくことが、意図した執筆法だろうと感じていた。)それよりいろんな断片的なエピソードやイメージや光景や言葉をどんどん放り込んで立体的に組み合わせていく。それは音楽を演奏することに似ている。とくにジャズ。リズムのキープと和音とフリー・インプロビゼーションが大切で、そこには無限の可能性、自由がある。「書くべきことが何もない」というところから出発する場合、エンジンがかかるまでは大変だが、いったん前に進み始めると、あとはかえって楽になる。「何だって自由に書ける」ということを意味しているからだ。その人の持つマテリアルが軽くて量が限られていても、その組み合わせ方のマジックを会得しその作業に熟達すれば、いくらでも物語を立ち上げていくことができる。「自分は小説を書くために必要なマテリアルを持ち合わせていない」と思っている人もあきらめる必要はない。マテリアルはあなたのまわりにいくらでも転がっている。そこで大事なことは、「健全な野心を失わない」ことだ。
長い歳月にわたって創作活動を続けることを可能にする持続力を持つために必要なことは、基礎体力を身につけること。逞しくしぶといフィジカルな力を獲得すること、自分の身体を味方につけること。
小説に登場するキャラクターは、話の流れの中で自然に形成される。キャラクターを立ち上げるのは、脳内キャビネットからほとんど無意識的に情報の断片を引き出し、それを組み合わせている。その自動的な作用を個人的に、「オートマこびと」と名付けている。そうやって書いたものは後日何度も書き直される。そういう書き直し作業は自動的というより、意識的にロジカルにおこなわれる。
登場人物をこしらえるのは作者だが、本当の意味で生きた登場人物は、ある時点から作者の手を離れ、自立的に行動し始める。それは多くのフィクション作家が認めている。小説がうまく軌道に乗ってくると、登場人物たちがひとりでに動きだし、ストーリーが勝手に進行し、その結果、小説家はただ目の前で進行していることをそのまま書き写せばいいという、きわめて幸福な状況が現出する。物語は架空のものであり、夢の中で起こっているというのと同じことである。それが眠りながら見ている夢であれ、目ざめながら見ている夢であれ、自分に選択の余地はない。
以上のように、村上にとって物語を紡ぐという作業はかなりの部分、無意識というか自動思考によって勝手に進んでいくようである。シュルレアリスムの自動手記のようである。それを書き直し作業によって意識的に調整していく。だから、その無意識から物語を引っ張り出してくる能力、つまりは脳のはたらかせ方なんだろうが、そこに極めて長けているということなのだろう。




























