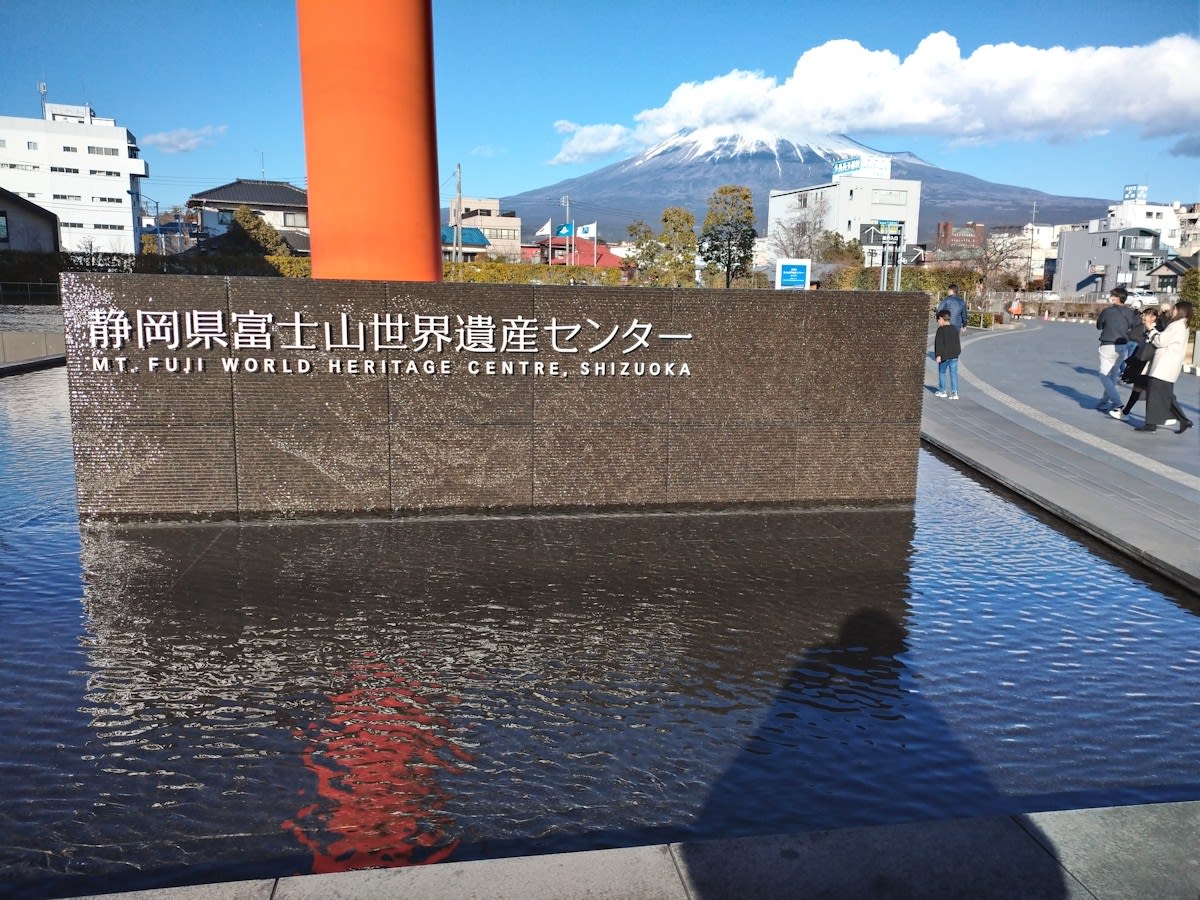1泊2日で大学同窓会の旅に行ってきました(2025年4月19・20日)。1日目は愛知県の知多半島と篠島行きです。
私が在籍した大学の学科は1学年20名の定員でしたが、辞めた人、留年して出ていった人、留年して入ってきた人も多く、全部合わせると25名くらいになります。その中で、今回の同窓会に集まったのは、2日間の参加が6名、2日目だけ来た人が1名でした。9年ぶりの同窓会です。今回の幹事の1人が名古屋市在住なので、このような場所に行くことになったのです。

新横浜駅から新幹線で名古屋駅に行き、在来線に乗り換えて金山駅で下車、駅から歩いて10分くらいのレンタカー屋で集合しました。5人でレンタカーに乗って移動です。知多半島の南端の師崎に向かいます。中間地点の半田市で少し、観光しました。写真に写っているのは、旧カブトビール工場の看板。

明治時代に建てられたという旧カブトビール工場(半田赤レンガ建物)の中を見学しました。それなりに大きなビール会社だったそうですが、政府の方針で廃止になったみたいです。

運転手以外で、復刻されたカブトビールの2種類を飲んでみました。コクのある味でしたね。

ミツカングループのミツカン・ミュージアムを見学しました。工場がすべて黒塗りで、江戸風なのかスタイリッシュなのです。

ミツカンといえばお酢の製造で有名です。写真は本物か模型かよくわかりませんが、昔のお酢醸造の様子で、表面を覆っている白い糸のようなものが、アルコールから酢酸を作る酢酸菌だそうです。

ミツカン工場の前を流れるのは半田運河で、海からも近いです。

ちょうど祭をやっていて、山車が4台集まっていました。海の町だけあって祭が派手だし、ヤンキーもたくさん集まっていました。このあと、名鉄知多半田駅で1人をピックアップして、知多半島南端に移動しました。

知多半島南端の師崎の駐車場に車を預け、高速船に乗ります。

目的地の篠島が見えてきました。

篠島の「漁師の宿おかだ」に泊ったのですが、夕食の料理がすごかったです。リーズナブルな価格で、海の幸がふんだんにふるまわれました。これは、特大級のタイのお造り。

はじめて見る巨大な二枚貝。タイラギというそうで、ややコリコリした食感でした。

イセエビ。手前には、1人分の生シラスが写っています。

タコを丸ごとボイルしたものが出てきて、自分たちでハサミで切って食べました。

タイは、1人1匹ずつ焼魚も頂きました。

カキは、生だったか焼だったか、忘れてしまいました。厚い身のフグの入ったヒレ酒を飲んで酔っぱらったせいかもしれません。もっと早い時期だったらフグ料理が出たそうです。
豪快な漁師料理を堪能しながら、お互いにみんなの近況を聞き合ったのでした。