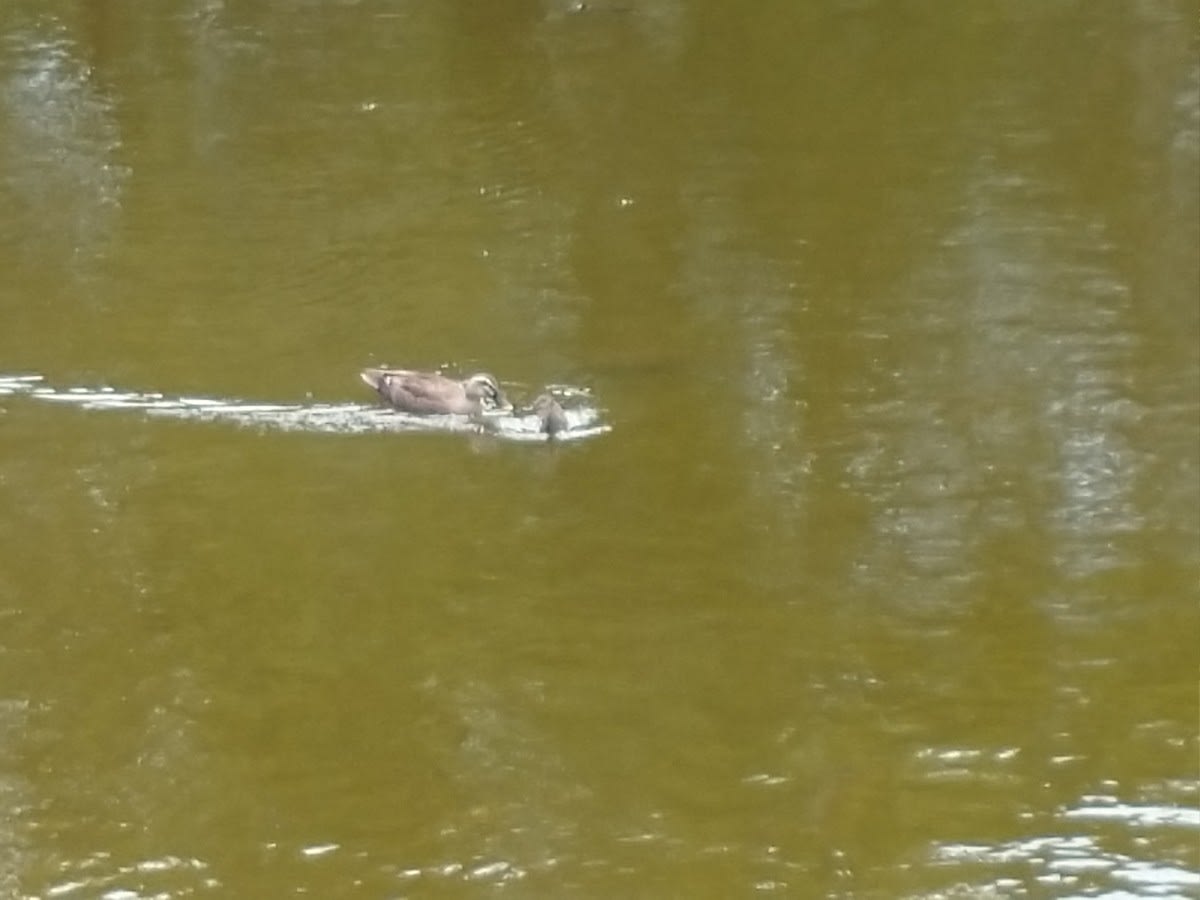入江川や馬場花木園を歩いていたら、コサギを何度も見る日でした(2025年3月9日)。

いつもの散歩コースの一つ、入江川を上流に向かって歩きます。約2.4 kmの短い川で、横浜港に注いでいます。写真は入江川の中流域、コサギがエサを採っています。

入江川上流域のせせらぎ緑道にもコサギがいました。コサギはわりと人慣れしていて、人が静かに近づいたくらいでは逃げたりしません。スマホのカメラなので、あまり精細な写真は撮れませんが。

カルガモのつがいかな。

馬場花木園に来ました。小規模ながら、近場ではいちばんいい感じの手入れのとどいた公園。

白梅はもう咲き終わりそうでしたが、紅梅はいまが満開でした。

池と日本家屋と裏山からなるこのバランスはなかなかのもんだと思いませんか?

昭和30年代前半の写真では、このあたりが林に囲まれた田んぼだったことがわかります。現在の馬場花木園の景観は、周りの林を活かしながら人為的に作られたものなのですが、都会の人工物とはまったく異質な、つよく自然を感じさせるものになっています。

この池にもコサギがいました。やっぱりエサを探しています。小エビや小魚など、動物性のものを採っているようです。

水辺を感じさせるネコヤナギ。

あずまやには、吊るしびなが飾られていました。

裏山はちっさいんですが、けっこう山っぽいのです。

竹林もあります。

帰りに入江川せせらぎ緑道の支流を通ったら、ここにもコサギがいて、エサ探しに集中していました。この日見たコサギはぜんぶで4羽。こんなに多く見たのははじめてです。もうすぐ繁殖の時期になるから、その前にいっしょうけんめい体に栄養をつけようとしているのだと思います。